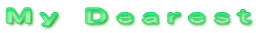
2.
「いやあ〜、お父さん、ご安心ください。このクソガキなんかには任せませんから。純はこの俺がちゃんと幸せにします。自分で言うのもナンですがね、包容力、経済力、精力、どれをとってもこのガキとは比べ物にならねえ。まあ今は二人でイチャイチャやってますが、遅かれ早かれ純は俺と一緒になって、末永く仲良く暮しますんで」
「おお、何と心強いお言葉。そこまで想ってもらえてこの子も幸せだ。尭村先生、よろしくお願いします」
「先生、だなんて水臭い。名前で呼んでくださいよ、お父さん」
「そうかい、では貴仁くん。息子をよろしく頼むよ」
「お任せください、お父さん」
そして肩を叩き合いながら笑う二人。尭村と純は怒りをこらえた表情で睨みつけ、
「ふざけんなよ……なんだよこの猿芝居はっ」
「そうです、二人ともいい加減にしてくださいっ」
しかし上機嫌の(馬鹿)親父たちにその怒りは通じず、猶も笑って酒を酌み交わす。
「よおっし、これを開けるか。コニャックですが、イギリスの方ならスコッチの方がいいのかな」
「おおっ、これはロール・ド・マーテル。マーテルコニャックの最高級品ではないですかっ。よろしいんですか?」
「もっちろん。こういうめでたい時に開けなくては、一生お蔵入りだ。さあさあ」
琥珀色の液体をグラスに注いで、縁同士をチン、と合わせる。
「純の幸せな未来に乾杯!」
超高級ブランデーをぐいぐい流し込む二人を、その息子たちは呆れて眺めるばかりだった。
「おっ、そうだ。ぜひお父さんにお見せしたいものがある」
暫くの間、ブランデーをあおりながら取り留めのない会話に興じていた二人だったが、何かを思いついたのか貴仁が突然立ち上がった。
「ほう、何ですか?」
「この世に二つとない芸術作品。今持ってきますんで、ちょっとお待ちを」
貴仁は浮かれた調子で部屋を出ると、革張りの箱を大事そうに抱えて戻ってきた。
「これです。さあどうぞ。但し、汚さないでくださいよ、大事なものだから」
聡は神妙に頷いて箱を開けた。途端に目を大きく見開き、震える手で中身を取り出して見つめた。
「こ、これは…素晴らしい……」
「でしょう? 見れば見るほど惹き込まれてゆく」
貴仁がそこまで言うほどの作品なら、きっと傑作に違いない。興味を引かれた純は近寄って手元を覗き込んだ。が―――
「な、なななななななにこれっ。何でこんなものがッ」
「どうした、純っ」
顔から火を吹いて悲鳴を上げる純に、尭村は慌てて駆け寄った。聡の手の中にあったのは―――
「なんで親父がこんな写真持ってんだよッ」
深い紫色の浴衣を着て、恥ずかしそうな上目使いでこちらに視線を送る純の写真。しかもマニアックなことに、背後から項を写したものまである。ほんのり色づいた華奢な項が、匂い立つような色気を漂わせた写真。
「貸せっ、俺が没収するッ」
腕を伸ばして奪い取ろうとしたが、背後から貴仁に羽交い絞めにされて引き剥がされる。
「くっそぉ、離せ、離せぇっ」
力任せに暴れまくる息子を余裕綽々で押さえ付けて、にこにこ笑いながら「他にも色々ありますよ」と言い放つ。
「どれどれ……おおっ、これはエプロンじゃないかっ」
「あっ、だめぇ、見ちゃだめっ」
浴衣の次に出てきたのは白いエプロン姿の純。もちろん裸エプロンではない。必死で奪い返そうとする純をさらりとかわして、聡は次々と写真を取り出す。
メイド姿で、やっぱり恥ずかしそうな上目使いのとか、無理やり着せられたのか、バニーサンタの格好でむーっと膨れているやつとか―――
「どれもこれも可愛くて、目移りしてしまうなあ。はっはっはっは……」
頬を緩めためろめろの表情で、だらしない笑いをこぼす聡。秘書の西城が見たら、即、辞表を提出してくるに違いない。
「もおやだぁっ、ばかぁ」
「親父っ、いつの間にあんな写真撮ったんだよっ」
「色んなルートがあるんだよ。俺をなめんじゃねえぞ」
妙なところで父親の威厳を誇示する貴仁。その時、聡が突然泣き出した。
「どっ、どうしたの、お父さ―――」
「ああ、純くん……どうしてパパを呼んでくれなかったんだ。花嫁の父として傍にいたかったのに………」
純ははっとして聡が持っている写真をひったくる。それは紛れもなく、ウェディングドレスを着た自分で―――
「純っ、まさかウェディングドレスか?」
純は涙目でこくこくと頷く。貴仁はどーだと言わんばかりに胸を張って、
「そのドレスは俺と成仁が二人で選んだんですよ。似合ってるでしょう?」
「ええ、ええ…。まるで、たった今この下界に降臨した天使のようだ。それに、やっぱりウェディングドレスはシンプルでスタンダードなのが一番萌えますねっ」
「おおっ、あなたとは趣味が合う。やたら丈が短いのとか、ピンクだなんだとカラフルなのが流行っているようですが、やっぱりコレでしょう。ねえ?」
「当然です。純白のドレスにベールは外せませんね。ああ、純くんお願いだ。もう一度パパのために着てくれぇ……」
「い、やッ」
純は口を大きく開けて拒絶を叩き付けると、尭村の許にぱたぱたと駆け寄った。そしてぎゅっと抱きつくと、目尻を下げて写真を眺めている二人に向かって厳しい声で、
「もう、二人とも変なことばっかりゆって、嫌いですっ」
純の「嫌い」宣言に少なからずショックを受けた聡と貴仁は、呆然と立ち尽くす。尭村はふっと嗤って、
「当然だ。純、俺の部屋へ行こうぜ」
見せ付けるように肩を抱いて、二人を置き去りにして部屋を出ていった。

「尭村さん、ホントにごめんなさい。父さんが―――」
部屋に入るなり、純は肩をすぼめてこわごわ謝った。尭村はソファに座るよう促して、そっと腰を抱き寄せ、
「気にするな。っつうか、親父に関しては俺も人のこと言えねえし。とにかくあの写真については、俺がどんな手を使ってでも奪い返しておくから安心しろ」
純は何かを言いかけたが一瞬ためらった。しかし自分を鼓舞するようにふっと息を吐くと、
「写真のこともあるけど…。ね、さっき……父さんが変なこと言ったでしょ?」
「変なこと? 何のことだ」
純は腿の上に揃えた手をきゅっと握り締めて、
「幸せに……してやってくれ、とか……。ごめんね、自分の勝手な都合だけで言うから……相手の迷惑も考えずに」
「迷惑、ねえ……」
呆れたような呟きをどう誤解したのか、純はますます萎縮して固まった。尭村は少し乱暴にその身体を抱き上げると、自分の膝の上に座らせた。そして肩を強く掴み、
「いい加減にしろよ。何で迷惑なんだよ。もしかして、迷惑だ、縛られたくないって思っているのはお前の方じゃねえのか」
「ちっ、ちがう、僕は―――」
驚いて必死にすがる純を、尭村は冷たく追及する。
「僕は、何だよ」
「僕は、ずっと一緒にいたい、あなたのものになって、縛られて、離さないでほしい、って―――」
「俺も同じだ」
「あ………」
尭村のひと言で、純の心にかかっていた曇りは払われた。尭村は少し口調を和らげて、
「解ったか? あんな風に迷惑がってると誤解されるのがどんなに悲しいことか。お前も知っている通り、思わせぶりな言葉とか含みのある言葉でごまかすような芸当は俺にはできない。相手が親父さんだろうが何だろうが、嫌なことは嫌だとはっきり言う」
「尭村さん……」
「いつも言ってるだろ? 俺はお前のものだって。ぎりぎりに縛り付けてみろよ。望むところだ」
「うん……」
純は尭村の身体に両手を巻き付けて、ありったけの力を込めた。しかし尭村は笑って「まだまだだな」と軽くいなす。顎に手を添えて上を向かせ、
「純、俺の束縛はこんなもんじゃねえぞ。覚悟しとけよ」
そして純が答えるより早く、唇に噛み付く。柔らかくてほんの少し震えている唇を舌で丁寧に舐めてから、ゆっくり口腔に挿入した。待ち構えていた舌を絡め取って吸い上げると、背中に回された手が悶えるように爪を立てた。
「はぁ……ふ……ぅ…ぁ………」
いったん唇を離したが、追いすがるように伸びてきた純の舌に煽られて再び吸い付いた。熱い舌をこすり合わせて唾液を送ると、純は「ふぅん…」と可愛い吐息を漏らしつつ飲み干した。
そして、舌と舌を繋ぐ唾液の糸を吸い取ってようやく唇を離した。
とろんとした目付きでうっとりと自分を見上げてくる純。鳩尾の辺りがざわざわと騒ぎ始めたが、今日は我慢せねばなるまい。
「純…お前、親父さんに愛されてるな」
「え…?」
純が昔、幼い頃、父親に疎まれていたということは知っていたが、尭村は敢えて言葉を濁さず言った。過去は過去。そして今、純が父親に愛されていることは紛れもない事実なのだから。
何より大事なのは生きている今、この瞬間なのだ。
「お前を幸せにしてくれというあの言葉、あれは真剣だった。だから俺も真剣に答えたんだ」
純の瞳を、ゆっくりと涙の菲膜が覆い始めた。しかし涙に振り回されることなく、明晰な口調で想いを明かす。
「父さんはね、僕に負い目を感じているの。昔放っておいた分、今必死で愛してくれようとしてる。でも……僕どうしていいか分からなくて。嬉しいけれど戸惑ってしまう。だからつい、キツイことを言って突き放してしまったり………」
「それでいいじゃねえか」
晴れ晴れとした明るい声が降ってきて、思わず尭村の顔をじっと見つめた。
「胡散臭いホームドラマじゃあるまいし、そんな簡単に打ち解けられるわけねえよ。戸惑いながらでも徐々に歩み寄っていけばいい。何があっても、親子の縁が切れることはないんだからな」
「うん……尭村さんありがと。………だいすき」
涙が蒸発した後の笑顔は眩しいほどに輝いて、尭村の目を釘付けにした。
まぶたに、頬に、鼻の頭にちょんちょんとキスをして、そして唇へ向かおうとしたその時、突然尭村の表情が険しく凍った。
「ど、どしたの、尭村さん……」
「ちょっと待ってろ」
純をソファに残してずんずんと扉に向かい、ノブに手を掛けて勢いよく開ける。
「うひゃあ」
情けない悲鳴と共にどかどかとなだれ込んできたのは―――
「お、お父さんっ、せんせいっ」
床に手をついてへらへら照れ笑いを浮かべているのは聡。対して、床にどっかり座り込んだまま、わざとらしくあさっての方向を向いているのは貴仁。
「おまえら〜〜、いい年こいたおっさん二人が何やってんだよっ」
「てめえが純に悪さしねえか心配で、張ってたに決まってるじゃねえか。いいか成仁、可愛い娘を持った親父の気持ちってのはな―――」
「僕は娘じゃありませんっ。こんな、覗き見するなんて……やっぱりお父さんなんて嫌いっ」
「うう、じゅん〜〜、パパを許しておくれ。お前を愛するがゆえに―――」
半泣きで許しを乞う聡は英国紳士でも豪腕経営者でもなく、反抗期の子供の前でひたすらおろおろするただの父親だった。しかし純は膨れてそっぽを向いている。
そんな二人を眺めていた尭村親子は、「しょうがねえなあ」と同時に呟いた。

空港のVIPルームには、純たち親子と早紀に環、そして尭村がいた。帰国する聡を見送りに来た彼らは、取り留めのないお喋りをしつつ別れを惜しんでいたが、いよいよ搭乗時間が近付いてきた。
聡はゆっくり立ち上がると、少し淋しそうに微笑んで、
「では、そろそろ行くよ。早紀さん、環ちゃん、お見送りありがとう。これからも純くんのこと、よろしく頼みます。それから尭村くん」
尭村は挑みかかるかのような真剣な眼差しで聡を見つめ返した。百の言葉より雄弁な視線の交錯。やがて聡は静かに頷き、
「始めは少し心配だった。君には…女性を一瞬で虜にしてしまう暴力的ともいえる魅力が備わっているからね。これからも様々な誘惑に直面するだろう。しかし君の強さ、純粋さがあれば、一番大切なものを失わずに済むはずだ。どうか、僕のような過ちは犯さないでほしい」
尭村はただ黙って、力強く頷いた。やはり、あの日部屋で純と交わした会話を聞かれていたようだ。しかし怒りは湧かなかった。
貴仁の言う通り、きっと心配だったのだろう。心配して心配してうるさがられる。親ってのはなかなか大変なんだなと、しみじみ思った。
「尭村が、純粋ぃ〜〜?」
隙間もないほど棘の生えた声で異議を唱える環を氷の視線で突き刺して、尭村は純の手を取った。
「ほら純、ちゃんと親父さんに挨拶してこい」
「は、はい…」
環や早紀に言われたら、照れもあって渋ったかもしれない。しかし尭村の言葉には素直に頷いて、純はとことこと聡の許へ。
「お父さん、僕は今すごく幸せです。だから心配しないでね。それから……僕をこの世に送り出してくれてありがとう。感謝しています」
やはり気恥ずかしさは拭えないのか、顔を真っ赤にして俯いたまま想いを告げる。しかしそれは、聡にとって十分過ぎるほどの言葉だった。
込み上げる感情に喉が圧迫されて、掠れた声しか出てこない。それでも聡は必死に言葉を返した。
「純くん……お礼を言わねばならんのは僕の方だ。君の存在が、僕を強くしてくれる。君がいてくれて本当に良かった。生まれてきてくれてありがとう……僕は―――」
こらえ切れず、純の身体を引き寄せて強く掻き抱く。そして温もりを反芻してからそっと顔を覗き込んだ。紫色の瞳、アメジストの瞳、愛しいあの女性に生き写しの……。
しかし、以前のように彼女の顔と重なって見えることはなかった。ここにいるのはヴィヴィアンの息子、ではない。秋原純という一人の人間。
嘗ては自分勝手な感情から遠ざけ、死ぬより辛い苦しみを味わわせ、それでも尚、この不甲斐ない父親を愛そうとしてくれる心優しい天使。
「―――僕は、どんなに離れていても、いつも君のことを想っている。愛しているよ、純………」
まだ慣れない父親の抱擁だったが、そこから伝わる想いはきちんと受け止めることができた。純は何度も頷いて、僕も愛してる、と言おうとした。
その時―――
「失礼します。お客様、お届け物ですが……」
空港の係員が声を掛けてきた。気を利かせた環が素早く扉に駆け寄り、ほんの少し開けて届け物を受け取る。
「尭村様と仰る方からです」
「あ、はい…。ありがとうございます」
環は不審な表情を隠そうともせず、謎の届け物を受け取った。
それは、筒状に丸められた紙。かなりの大きさから、ポスターのようなものではないかと思われる。しかも送り主が尭村。環は首をひねりながら聡に差し出した。
「あのう、これ、尭村様からっていうことは―――」
「何だそれ? 俺は知らねえぞ。親父からか?」
途端に聡の顔色がさっと変わった。環から受け取ると、あたふたとコートを抱えて部屋を出ようとする。何かおかしいと感じた純は、厳しい声で、
「お父さん、それは何ですか? ちょっと見せてください」
「い、いや、何でもないんだよ。尭村先生からのちょっとした餞別だ」
「見せてくださいっ」
二人が言い合っている隙に、尭村がそのポスターらしき紙の筒をすっと抜き取った。そして「ああ〜っ」という聡の叫びを無視してくるくると開いてみると―――
「あんのクソ親父がぁ………」
こめかみにくっきりと浮き上がった血管が、びくびくと波打つ。それは、純のコスプレ写真をポスター大に引き伸ばしたものだったのだ。
ひらりと落ちたメモには、貴仁からの贈る言葉。
―――部屋に貼ってください。俺の絵より嬉しいでしょう? またゆっくり飲みましょう
「お……お父さん……これって…………」
「いや、待てっ、僕が頼んだわけじゃないっ。純くん、落ち着いて、落ち着いて」
「そうなんだ。じゃあもちろん、こんなもの持って帰らないよね……?」
「そ、それは……部屋に貼ろうかな、なぁんて………」
へらへら笑ってごまかそうとする聡に向かって、純は爆発した。
「やっぱり、やっぱりお父さんなんてだいっ嫌いっ」
聡はほとんど泣きながら、それでも純の特大写真はしっかり抱えて帰国の途についた。

「ったくふざけんなよ。家に帰ったらすぐに親父を締め上げてやるっ」
空港からの帰り、尭村は貴仁への怒りをぶちまけていた。しかし、
「あたし思うんだけど。そもそも純にあんな格好をさせた誰かが悪いんじゃないの?」
環の余りにごもっともな意見に一瞬返す言葉を失って、ぎりぎりと歯を噛み締める。が、ふてくされた子供が言い訳をするように、
「いいじゃねえか。コスプレは男のロマンなんだよ」
ぽつりと呟いて、さらに冷たい視線を浴びたのだった。(Fin)
BACK TOP INDEX