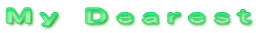
1.
その知らせは、突然訪れた。
「じゅんー、電話よお。早く早くっ」
いつになく浮かれた環の声に急かされて、純はぱたぱたと階下へ駆け下りた。
「誰から?」
「いいからっ。出れば分かるって。ほらほら」
「う、うん……」
そして受話器を取って耳に当て、探るような声で「もしもし、純です」と言うが早いか―――
『やあっ、純くんだね。パパだよん。ああ、やっぱり純くんの声は可愛いっ。最高だあ、パパ幸せ〜〜』
「………では、ごきげんよう」
純らしくもない低い声で冷たく言い放つと、受話器を置こうとした。すると何かを感じたのか、通話口から『待ってくれえ〜』という悲愴な叫び声が。純は渋々戻すと、
「もうっ、用件があるならちゃんと言ってくださいっ」
『うう……その前にお願い。お父さん、って呼んで。もちろんパパ、でも構わないよ』
「嫌っ。何でそんな改まって……」
『だってだって、こうやっておねだりしないと呼んでくれないじゃないか。パパさびしー』
純はふーっと苦い溜め息をついてから、すっと息を吸い込んで
「お父さん……」
『うっ……うぅ……ぁぁ………ブラヴォ………最高です…………(悶)』
受話器の向こう、遠いイギリスでは、父、秋原聡(そう)が悶えまくっているようだ。純はがっくりと、疲れたように肩を落とす。傍らでは環と早紀が、お腹を抱えて笑い転げていた。
純は時計をちらと見る。今2時過ぎだから、イギリスは…朝の5時。その時間ですでにこのテンションだ。太陽が昇りきった頃には一体どうなってしまうのか、想像しただけで疲労感が増す。
「で、用件は何なのですか?」
『ああ、そうだった。純くんの声があんまり可愛いからつい忘れるところだった。えとね、来週日本へ行く用事があるんだ。だから用事はとっとと済ませて、純くんに会いに行くからねー』
「ええっ? 来週って、そんな突然……」
あたふたする純に、聡は朗らかな声で
『大丈夫大丈夫。ホテルに泊まるから早紀さんたちにご迷惑は掛けないよ。直哉(なおや)くんは相変わらず宝探しだろ?』
直哉とは環の父親で、文化庁直属の研究室室長を務める考古学者。いったん発掘現場へ出向いてしまうと、半年くらいは音信不通になる。
早紀の口癖は「直哉さん生きてるかなあ」である。彼女でなかったら、疾うに離婚していてもおかしくないだろう。
「そういう問題じゃなくて、あの……」
『純くんが普段歩いている道とか、買い物をしている店とか、そんなところを一緒にぶらぶらしたいんだよ。それに、恋人も紹介してもらいたいしね』
「こっ、恋人なんて、そんな……」
『いない、とは言わせないよ。純くんみたいにキレイで可愛くて優しい天使が、放っておかれるはずがない。彼女でも彼でもノープロブレム。パパに会わせてね。それじゃあ、早紀さんと環ちゃんによろしく〜〜』
結局、高テンションのまま電話は一方的に切られた。純は呆然と受話器を見つめていたが、やがてはっと我に返り、
「たまきおねえちゃぁ〜〜ん」
電話でのやり取りから何となく状況が把握できた環は、すがり付いてきた純の頭をなでなでしつつ半笑いで宥めた。その傍で早紀はにこにこしながら、「聡さんてば相変わらずね〜」と暢気な感慨を漏らした。

「はーっ、やった、やったぞ……」
聡は重厚なマホガニーのデスクに突っ伏して、達成感に酔っていた。朝の5時過ぎだというのに、一分の隙もないスーツ姿。
その傍らに控えている秘書の西城もまた、主人に劣らぬ完璧な立ち姿で、柔和な笑みを浮かべていた。
「ご子息の許可は得られたようですね」
「いや、許可はもらっていない。恐くて訊けんよ。来ないで、なんて言われたらどうしようかと…。だから一方的に電話を切ってしまった」
肩をすぼめて、萎れた声で打ち明ける聡を、西城は驚きも露わに見つめた。
優雅な物腰と美貌で人を惹き付け、堅実かつ強権的な経営手腕で人を恐れさせる聡が、息子のことになると情けないほどの弱腰ぶりを発揮するのだ。
もちろんそれには相応の理由があるのだが、それでも普段の彼からは想像もつかぬこのヘタレぶりは、ずっと片腕として仕えてきた西城にはなかなか理解し難いものだった。
「もっと頻繁に会いに行かれたらいかがですか? その方が早く打ち解けるかと」
「君は秘書としては優秀だが、人の心の機微についてはまだまだだねえ」
聡はゆっくり立ち上がると、書棚に凭れて西城を見据えた。
「あの子は、日本でようやく自分の居場所を見つけたんだ。そこに僕がずかずか入り込んでいったらどうなると思う? そりゃあ僕だって会いたいさ。でも、自分の欲求を押し付けるだけでは、距離を縮めることはできない。昔は放っておいたくせに…と思われるのが関の山だよ」
西城は溜め息をついて、
「難しいものですね、子供というのは……。私はやはり、一生独り身でいいです」
「確かに難しい、しかし素晴らしいものだよ、子供というのは。僕は今、最高に幸せだ」
その言葉通り、聡は瞳を輝かせてうっとりと微笑んだ。

その日、弓月家の車寄せに黒塗りのハイヤーが停まった。迎えに出た3人の前に颯爽と現れた聡は、文句の付けようのない英国紳士だった。
チャコールグレイの高級生地で、身体にフィットするように仕立てられたスーツを見事に着こなした長身は、人の上に立つ者がまとう虹色のオーラを放って暈然と輝いている。微かに灰色がかかった瞳は優しい光に潤って、じっと純を見つめた。
しかし立ち止まって近寄ろうとはしない。純は、隣の環に小突かれて、おそるおそる自分から近付いていった。
「あ、の……久しぶりだね、お…父さん……」
すると聡は端整な相貌をくしゃりと歪ませて、腕を広げて純に抱きついた。
「純くんっ、会いたかった、会いたかったよ……」
「わ……あの、お父さん、苦しいよ………」
抱き締める力が強いから苦しいのではない。切なくて、胸がどきどきして、うまく呼吸ができない。だから苦しいのだ。そう分かってはいたけれど、環たちの手前恥ずかしさもあり、純は身体をねじって拘束を逃れた。
しかし聡は、まだ離そうとはしない。純の頬を両手で包み込んで上から覗き込み、
「ああ……暫く見ない間にまた一段と綺麗になったね。どんな絶世の美女も君の前ではただの石ころだ。僕の可愛いアメジスト……」
「とっ、父さん!」
我慢できず、ついに純は叫んで身体を突き飛ばした。
「それが久しぶりに会った息子に言う言葉っ? 冗談はやめてよッ」
「おお、純。マイハニー。冗談なものか。僕の口は真実しか言わない。君の美しさはラファエロの天使をも凌ぎ―――」
「もおっ、いいかげんにしてッ」
ちょっと(かなり)異常な親子喧嘩を、環と早紀は呆れ半分喜び半分でじっと見守っていた。

「あそこが、お気に入りのパン屋さん。たまに学校を抜け出して直と買いに行くの。それから…あ、あの公園にたまに来る屋台の焼きたてメロンパンが美味しいんだ。それからあそこのお好み焼き屋もよく―――」
聡は笑いを噛み殺しながら、「食べ物ばっかりだねぇ」と素直な感想を言う。純はぷっくりふくれて「育ち盛りなのっ」とそっぽを向いた。すると、立ち止まってじっとこちらを見ている女性と目が合った。
女性は顔を赤くして、聡に見入っている。休日の午後ということで家族連れや若い夫婦、カップルなどが多かったが、女性はみな聡のことをうっとりと眺めて連れのことなど見向きもしない。
純はこの状態を喜ぶべきなのか厭うべきなのかよく分からず、はあと溜め息をついた。すると聡はうきうきした声で、
「ねえねえ純くん。周りの人たちみんな、純くんのことを見てるよ。あんまり綺麗なんでびっくりしてるんだねえ」
「なっ、なにゆってるの。そんなことあるはずない―――」
聡は気障な仕草で指を振って、
「純くんは鈍いからなあ。まあ、そんなとこも可愛いんだけどねっ。でもパパは心配だ。純くん、男は狼なんだからね。気を付けるんだよ」
そんなの知ってます、だっていつも狼さんに食べられてるもん、と心の中で言い返しつつ、純は黙って頷いた。

その時、森下は悪夢を見た。真っ昼間にもかかわらず、それは間違いなく悪夢の類いだった。そして今この場にいる自分を悔やみ、呪った。
テニスサークルの仲間を呼んでカラオケ大会やるんだからあんた邪魔よ、と言って家から追い出した母を呪った。だったら尭村を無理やり連れ出してぶらぶら暇潰しでもしよう、と安易な考えに飛びついた己れの軽率さを呪った。
そして何より、こんな街中で堂々と男連れで歩いている純を呪った。
「あっ、尭村、見ろよ。あんなところに中古レコード屋がっ」
「んあ? ずい分前からあるぜ。知らなかったのかよ」
尭村は面白くもなさそうに答えると、性懲りもなく寄ってくる女をうるさそうに追い払った。そして再び歩き出す。
「ああっ、待てっ。そっちじゃねえっ」
「はあ? 何言ってんだよ。公園の裏に、輸入もんの珍しいスピーカーばっか集めた店ができたからって誘ってきたのお前だろ」
森下は尭村の前に立ち塞がって、視界を遮った。そして冷や汗を拭いながら、
「い、いや、その、あっ、そうだ。あの店は確か今日定休日なんだよ。悪い悪い。ははははは………」
尭村の表情がだんだん険悪になってゆく。目の前でわざとらしい笑いにしがみつく友人を睨んで、
「森下、てめえ俺をおちょくってんのか? 邪魔だ、どけっ」
肩に手を掛けてぐいと横へどかす。森下は八百万(やおよろず)の神に祈った。秋原たちはもうおりませんように。
果たして、無神論者の祈りは届いたか。森下がそおっと顔を上げると、そこに神がいた。但し、鬼神だったが。
「……ざけんじゃねぇぞ………」
「あ、あああああああきむら、落ち着け、まだそうと決まったわけじゃ――」
眉だけでなく髪まで逆立って、ヤバいオーラを発している尭村に、お前はスーパーサイヤ人かッ、と突っ込む森下。どうやら相当に動揺しているらしい。
「あっ、待てよ、待てっておい!」
二人に向かってずんずん突き進む尭村に渾身の力で抱き付いて止めようとしたが、一撃で呆気なく吹っ飛ばされた。
腕を伸ばして足にすがり付こうかと思ったが、我に返ってやめた。これじゃあ、振った男に捨てないでとしがみつく往生際の悪い女みたいだ。何だか周囲からの視線も痛い。
―――お、俺は知らねえぞっ。秋原、お前も悪いんだからなっ
そして携帯電話を取り出して、すぐ救急車を呼べるようにスタンバイした。

「純………」
池を泳ぐアヒルたちに餌をあげていたら、背後から名前を呼ばれた。聞き覚えのある声だけど、余りに低く歪んでいるので誰か分からなかった。
が、ふと振り向いた先にいたのは―――
「あ、あきむらさんっ」
嬉しそうに笑って飛び付こうとする。しかし人目を、というか隣にいる父の目を気にして抑えた。尭村は剣呑この上ない目付きで聡を睨んで、
「純、こいつは誰だ。ずいぶん仲良さそうだな。ちゃんと紹介してもらおうじゃねえか」
「えっ? あ、はい……あの……えと………」
赤くなってもじもじする純の肩を、聡は愛おしげに目を細めてそっと抱いた。その時、尭村の怒りは沸点を迎えた。純が口を開くのがあと少し遅かったら、確実に聡をぶん殴っていただろう。
「僕の……父です」
「……………ちち?」
間抜けづらで単語をそのまま繰り返す尭村。まるで阿呆である。しかしそんなことを気にする余裕もないのか、拳を握り締めたままもう一度「父?」と訊き返す。純は頬を染めて頷いて、
「はい。ロンドンからね、僕に会いに来てくれたの……」
聡はにこやかに笑ってぬっと手を差し出し、
「秋原聡と言います。いつも純がお世話になっているようで」
「あ、ああ……こちらこそ」
固めていた拳を解いて、しっかり握手を交わした。そこへ森下がおそるおそる近付いて、
「あのぅ……どちらさんで?」
「純の親父さんだ」
森下は、驚きと安堵の余り気が抜けたのか、がっくりと肩を落として「よかったぁ〜」と息を吐く。尭村はじろりと睨んで、
「お前が妙な気を回すからだ」
「なっ、なんだよっ。俺は何も言ってねえぞ。お前が勝手に誤解して、すげえ形相で突進していくから止めたんじゃねえかッ」
「はん。別に誤解なんかしてねえぞ。俺は純を信じている」
「おまえはぁ〜〜」
二人が何を言い争っているのか分からない純は、きょとんとした表情で見つめるばかり。対して聡はにやにや笑いつつ、
「純くん、パパにも紹介してくれないかな。こちらの二人は学校の先輩かな?」
「あっ、うん、あの……あの………ね………」
純はまず、紹介しやすい方から始めた。
「こちらは森下先輩です。蒼薇学園の2年生。とても優しい先輩です」
「ほうほう。純の父です。これからもよろしくお願いします」
「こっ、こちらこそ」
そして尭村の方を向き、さらに頬を赤く染めてもじもじした挙句、
「こ、こちらは尭村先輩。同じ蒼薇の2年生で、それで………」
「それで?」
聡の追及に観念したのか、口ごもることなくはっきりした口調で、
「僕の…いちばん大好きでいちばん大切なひとです」
濁すことなく言い切ると、微かな不安を滲ませた表情で成り行きを見守っていた尭村に、ふわりと笑いかけた。一番大好きで一番大切な人に向ける笑顔で。
「あっ……あきむらさ―――」
気付いた時には、純の身体は胸の中にあった。尭村は我を忘れて抱き寄せ、休日の公園には似つかわしくない熱い抱擁を与えたのだ。
「あ、尭村さん、だめ……離してっ………」
「尭村ッ、おまえ、親父さんの前でっ」
はたと我に返った尭村は、せかせかと拘束を解いた。
「悪い、我慢できなかった」
「おまえはぁ〜〜」
俯いているため、聡の表情は判らない。しかしそのまま肩を震わせ始めたから、怒りを抑えているのかも―――
「ぅっ……ぅぅっ…………」
って、泣いてるし。聡は一人でうんうん頷きながら目をこすり、
「そうか……純くんにも大切な人ができたんだね。よかった……。パパは少し淋しいけど、でも嬉しいよ。愛村くんっ」
「尭村だっ」
思わず厳しい突っ込みを入れる尭村。が、そんなことはお構いなしで聡は続ける。
「僕みたいなダメ親父がこんなこと言う資格はないかもしれんが、どうかこの子を幸せにしてやってくれ。この子は……幸せにならねばならんのだ。頼むよ」
「お、お父さんっ。そんな……そんなこと押し付けちゃだめ。そんな、尭村さんを縛り付けるようなことは―――」
「分かりました。俺が必ず幸せにします」
純の抗議を遮るように、尭村は力強く言い置いた。そして純の肩をぎゅっと抱く。純は切なそうに眉をたわめて、尭村の腕の中で縮こまるばかり。
父の傍若無人な言動のせいで、尭村に迷惑を掛けているのではないかと……。消え入りそうな声で、
「尭村さん……、ごめんね」
「ん? なんだ?」
「ううん、何でもないの……。あ、森下先輩とどこか行くはずだったんでしょう? 引き止めてしまってすみません」
森下は慌てて首を振り、
「いや、大した用があったわけじゃねえし。ちょっとぶらぶらしてただけで。もう帰ろうって言ってたんだよ。こいつと一緒だと女がわんさか寄ってきてうぜえし――――痛ッ」
尭村に思い切り足を蹴られた森下。見れば純は「そっか、そうですよね…」と淋しそうに笑っている。
余計なこと言いやがってという眼差しで睨まれた森下は、小声で「すまん…」と謝った。
「それじゃ、僕たちももう帰りますね。尭村さん、先生によろしくお伝えくださ―――あっ、そうだ」
純はぱっと顔を上げて、少し明るさを取り戻した顔で聡に向き直り、
「そうそう、尭村さんのお父さんってね、画家の尭村貴仁先生なんだよ。好きでしょ? 尭村先生の絵」
そもそも、純が貴仁の作品を好きになったのは父親の影響だった。つまり、貴仁のファン歴は聡の方が長いのだ。
「ええっ、本当かい? それはすごい、すごいご縁だなあ。今度ぜひお会いしたいな」
「今日なら親父は家にいるが……。純、これから来るか?」
「で、でもご迷惑じゃ―――」
申し訳なさそうに窺う純を、聡ははしゃぎながら引っ張った。
「わ、行こう、行こう。せっかくのお誘いじゃないか。ほらほら、純くん」
「もおっ、お父さん。そんな勝手に………」
結局、聡の勢いに負けて二人で尭村家を訪問することになった。純は不安で仕方なかった。貴仁の仕事を邪魔したり、とんでもなく失礼なことを言って貴仁に不愉快な思いをさせてしまうのではないかと。
しかし、そんな心配が不要だったと気付くのに、そう時間はかからなかった。
INDEX TOP NEXT