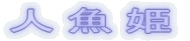
―70万ヒット記念SS―
1.
―――その時、僕は初めて恋を知ったのです。月明かりが射し込み青銀色に染まる海中をゆらゆらと沈みゆくあの方へ手を伸ばし、この胸にそっと抱き留めた時に……

海岸沿いに広がる豊かな海洋国家。その国の王子は、性格には多少問題ありと言われてはいたものの、容姿端麗、頭脳明晰、そして武術や剣の達人でもあり、国中のうら若き女性の憧れを一身に集めておりました。
国の女性だけではなく、隣国の貴族の娘なども、宴などで彼を見た途端のぼせ上がり、様々な策を弄して寵愛を得ようと奮闘はするものの、散々弄ばれた挙句冷たい拒絶を浴びせられ、傷心の余り身体を壊して寝込んでしまう始末。
大臣や教育係などからは、もう少し女性の扱い方に気を付けなさいとやんわり諭されるものの、本人は「うるせえな」と一蹴。今宵もまた一人、二人と泣かせては、夜空を見上げて虚しさを噛み締めるのでした。
彼の名は成仁。しかしそんな彼にも、たった一人気になる人がいたのです。顔も覚えていない、言葉を交わしたこともない、果たして実在するのかも怪しい人。
それは、海で嵐に遭い、船から投げ出された自分を浜辺で介抱してくれた人でした。朦朧とする意識に微かに刻み込まれた、肌の温もりと可愛らしい声。
その人は「どうか死なないで」と繰り返しながら、必死に身体をこすったり、ぎゅっと抱き締めて温めたりしてくれたのです。
成仁の意識はそのまま遠のき、気が付いた時には救出され、寝台の上に寝かされて手当てを受けていました。
医者の話によると、浜辺で発見された時の体温や呼吸は、長時間海中に浸かっていたとは思えぬほど正常で、気持ちよさそうに眠っているようにしか見えなかったということでした。
自分は夢を見ていたのかもしれない。死の危機に瀕した時、人間の脳は甘美な夢を生み出してその恐怖から逃れると聞いたことがある。
しかしあの、深い愛情の詰まった可愛らしい声だけはどうしても忘れることができず、自分が救出された国へ従者を遣わして密かに捜索させ、半ば諦めながらもよい知らせが来るのを心待ちにしていたのでした。
とはいえ大した結果も得られず、今日もまたその面影に想いを馳せながら、海辺を散策していました。
すると前方に、数人の男たちが群がっているのが見えました。成仁は馬より下りて駆け寄ります。
「何事だ」
「あ、これは成仁様。それが………」
男は言葉で説明するより早いだろうと、半歩ずれて下方を指さしました。そこには、海の泡より白く、百合のように嫋やかな裸体がうつ伏せで倒れています。
気を失っているのか、ぴくりとも動きません。成仁は足音を忍ばせて近付くと、その傍らに膝をついて手を伸ばし、髪に付いた砂をそっと払ってやりました。
何という美しさ、艶めかしさ。肩から腰、脚へと続くラインは優美この上なく、城が抱えている稀代の名工たちでも、この美を再現することは不可能に違いない。そして肌の光沢と肌理は真珠そのもの。
成仁は吸い付きたい衝動に駆られ、思わず唇を近付けました。しかし人目があるのを慮って、息があるかどうか確かめるふりをして顔を上げたのでした。
「まだ息はある。素性は分からぬが、とにかく城へ連れ帰って医者に診せることが先だ。異存はないな?」
そして答えを聞くまでもなく、その美しい漂流物を抱えて城へ戻ったのでした。

―――優しいお姉様、ごめんなさい。僕のわがままを許して。僕はどうしてもあの方にお会いしたいの。そしてできれば、ずっとお傍にいたいの………
「気が付いたようだな。よかった」
薄く目を開けてぼんやりと辺りを見回していた純の耳に届いた声。
それは―――
「俺はこの国の王子で、名は成仁という。ここは城の中だ。何も心配する必要はない」
これまで自分を優しく育んでくれたもの全てを失ってもいいから会いたい、そう願って再会を夢見ていたその人がすぐ傍にいる。純は歓喜に身を震わせつつ、ゆっくり起き上がって愛しい人へ手を伸ばしました。
成仁は驚きこそしたものの、その仕草に込められた想いの深さに打たれて何も言わずその手を取りました。そして寝台の端に腰かけ、そのまま手を引いて抱き寄せます。
すると得も言われぬ甘い芳香がたちのぼって、鼻孔を優しく慰撫してくれました。成仁は蕩けそうな意識を叱咤して、問い掛けます。
「お前、名は何という」
純は唇を震わせて答えようとしましたが、出てきたのは小さな小さな吐息だけ。その事実に今改めて気付いたようにはっと息を呑むと、喉を押さえて項垂れました。
「お前、声が……口が利けないのか?」
純は淋しげに、しかし少し誇らしげに微笑みつつ頷きました。そして成仁の手を取って、その手のひらに指を滑らせます。
「じゅん………それがお前の名前なんだな」
純は再び頷いて、“助けていただいてありがとうございます”と書きました。
「礼を言われるほど大したことはしてねえよ。それより純、お前の国はどこだ? 何故あんな所で―――」
純は首を振って、“何も覚えてないのです”と答えました。
「そうか……きっと事故に遭って、記憶を失ってしまったのだろう」
それは悲しむべきことなのに、何故か成仁の心は明るい光で満たされました。もちろん、自分でもその理由は分かっております。純をここへ置く理由ができたからです。
「ならば純、記憶が戻るまでここにいるといい。遠慮は要らん」
“でも、ご迷惑では”
「誰がそんなことを言った? これは命令だ。ここにいろ。ちょうど、身の回りの世話をする人間を探していたところだ。もちろん回復してからで構わないからな。頼んだぞ」
ずっとお傍にいれる―――純は嬉しさの余り成仁の胸にぎゅっと抱き付きました。すると、心臓の鼓動がとく、とく、と聞こえてきました。
生きている、成仁様は生きている。あの嵐の後の夜、死者のごとき蒼白い胸を必死でさすったことが思い出されます。
どうか死なないで―――願いより強い祈りを込め、時の経過も忘れて介抱し、気が付けば空は白々と明るんでいたのです。
人の気配が近付くのを察したため、純は泣く泣くその場を離れたのでした。微かに血色が蘇り始めた唇に、そっと自分の唇を押し当てて。
「純、どこにも行くな。俺の……傍にいるんだぞ」
純は温かな胸の中で、幾度も幾度も頷いたのでした。

さてその後、純の身体は順調に回復しました。しかし声だけは、城お抱えの名医でもどうすることもできず、原因すら分からないという始末。
医者たちの不甲斐なさに怒りを露わにし、「声を出そうと努力しないからだ」とまるで純が悪いかのごとく言い放つ外科医に本気で剣を抜こうとする成仁を、純はひたすら宥めるのでした。
“僕はへいきです。成仁様がお傍にいてくだされば”
怒りで震える拳を必死に開かせて、その手のひらに指を這わせ想いを伝える純。そしてその言葉を成仁の身内に浸透させるように上から唇を重ねると、見る者の身も心も蕩かすような微笑みを浮かべるのです。
成仁の荒く毛羽立った心はあっという間にしっとりと潤い、怒りも苛立ちも忘れて甘い抱擁を与えるのでした。
身体が回復すると、純は世話係として成仁に仕えるようになりました。とはいえ、城での生活は純が嘗ていた場所とは何もかも違っており、失敗ばかり。とても成仁の役に立っているとは言えませんでした。
それに、食事の作法なども知らぬ純は、恥をかいたり笑われたりすることが多く、そのたびに与えられた部屋の隅に縮こまって静かに涙を流しておりました。
でも、元いた世界、温かく優しい世界に戻りたいと思ったことは一度もありませんでした。何故なら―――
「純、またこんな所で泣いていたのか」
目をこしこし擦りながら振り返ると、そこには黒い瞳に慈しみを込めてこちらを見つめる愛しい人の姿が。ゆっくりと近付きながら、
「あんな奴らの言うことなんて気にするなと言っただろう」
純の存在ごと包み込むようにふわりと抱き締めると、髪に耳に額に、ついばむようなキスを降らせます。純はその身に余る贈り物をうっとりと受け取ると、手を取って言葉を連ねてゆきます。
“ごめんなさい。自分がなさけなくて……”
成仁はふっと微笑い、目尻に指を這わせて涙の痕を拭います。そして、
「馬鹿だな。自分を責める必要がどこにある? 記憶を失ったお前が、生活に戸惑うのは当然だろう。それに―――」
成仁は言葉を断つように口を閉じました。彼はこう言おうとしたのです
―――みんな、お前を嫉んでいるんだ。お前の美しさを……
しかし成仁には分かっていました。そんな醜い感情など、純には理解できるはずもないと。
この無垢なる魂には、嫉妬、嫉み、怨みなど負の牽引力を持つ感情は未知の領域、想像もつかないに違いない。だから口を噤んで、ただ温かな抱擁を与えるだけにしたのでした。それこそが、純の悲しみを癒すことができると信じて。
―――成仁様、ありがとう………だいすき
純は心の中に閉じ込めている想いを、指先に託して伝えました。ただし、手のひらにではなく背中に。
いつかちゃんと伝えられる日が来ますようにと願いながら、背中に回した手でそっと書いたのでした。

「純、まだ恐いか?」
馬上で成仁の胸にしがみつきながらも、首を振る純。成仁は苦笑を漏らしつつ純の顎に手を掛けてそっと上を向かせます。
純の全快を祝って二人きりで遠乗りに出たのはいいのですが、初めて馬に乗った純は怯えるばかりで、周りの景色に目を向けることもできなかったのです。
「俺に掴まったままでいいから、周りを見てみろ」
どんなに恐くても、成仁の言い付けに背くことなど考えられない純は、言われた通りこわごわ頭を巡らせて、周囲を見回しました。
―――なんて、きれい………
遠くの山々は緑に煙り、稜線は暈然と輝いています。まるで、神々の絵筆に彩られたよう。
目の前に広がる草原では、青く柔らかそうな草が風にそよいで漣のように揺れ、頭上では木漏れ日がちかちか瞬いています。そこに二羽の小鳥が舞い降りて、キスを交わすかのように嘴を合わせました。
これまで暮していた世界が全てだと思っていた純の目の前に開けた、この豊饒、美しさ、神秘。純は込み上げる悦びと感動を味わいながら、うっとりと景色に見入っていました。
そして、そんな純を見つめる成仁の心も浮き立っておりました。嬉しそうに瞳をきらきらさせて周囲を見回す純が、愛しくて仕方ありません。
「あの木蔭で休むとするか」
成仁は、純の静かな感動を乱さぬよう小さな声で囁くと、木蔭に馬を進めてまず自分が先に下り、そして純を抱き下ろしました。
すると純は何を思ったのか、サンダルを脱ぎ捨てて裸足になると、草の中へ駆け出したのです。
成仁は驚きましたが、すぐに肩を竦めて笑いました。純がそうしたくなる気持ちがよく解りました。柔らかな緑に覆われた草原は、まるで遠浅の海のようだったから。
純は波打ち際で遊ぶ子供のように、草の中でくるくると回ったり、飛び跳ねたりしています。その無邪気で優雅なダンスを暫し堪能した成仁は、純に声を掛けました。
「こら。一人で遠くへ行くな。俺の傍にいろ」
すると純は裸足のままぱたぱたと駆け寄って、成仁の胸にぴたっとくっつきました。そして嬉しそうに頷きます。
行きません、どこにも行きません。ずっとお傍にいます―――
「純……」
何かを考えるより早く、成仁の手は純の腰に回っていました。そしてもう片方の手で頭を支え、そのまま顔を近付けて唇を重ねました。
純の唇は想像より柔らかくて、妄想より甘くて、空想より温かい。これまで数え切れないほどの女性と関係してきたはずなのに、たった一度の口付けでこれほどの悦びが得られるとは―――
その時、成仁の記憶の片隅に微かな電流が走りました。
しかしそれが何なのか追究する間もなく、唇はゆっくりと離れました。ちゅぷ、という可愛らしい音を弾かせて。
「少し休んだら、奥へ行ってみよう。もっと違う景色が見られるぞ」
純は真っ赤に染まった頬を胸に押し付けて、小さく頷きました。
その後二人はしっかり手を繋いで、氾濫する緑の中を散策しました。
見るもの全てが珍しい純は、きょろきょろと視線を巡らせておりましたが、そのせいで足許が疎かになっていたようです。大きく盛り上がった木の根に躓いて、転んでしまいました。
「純っ、大丈夫か?」
平気なことを伝えようと元気よく立ち上がろうとしたのですが、足にちくりと痛みが走って思わず顔をしかめてしまいました。そっと衣の裾をめくってみると、ふくらはぎに血が滲んでいます。
「ああ、木の根ですりむいたな。すぐ消毒しないと」
成仁は純の身体を軽々と抱き上げて草原へ戻り、草の上に寝かせて水筒を取り出しました。そして裾を大きくめくって患部に水を注ぎ、綺麗に洗い清めます。
「純、沁みるか?」
唇を噛み締めて耐える純に、心配そうに訊ねる成仁。純は正直に頷きます。すると――
「…………っ」
純は思わず息を呑みました。成仁が患部に吸い付いて、舌を這わせて舐め始めたのです。
純は首を振り、成仁の肩を叩いて止めさせようとしました。そんな、傷を舐めるなんてだめです。成仁様のようなお方が―――
しかし純の抵抗になど構わず、成仁は傷を丁寧に舐めると、そのまま衣を捲り上げて純の脚全体を露わにしました。
青い草の上にすらりと伸びる真っ白な脚は眩しすぎて、成仁は一瞬目を逸らしそうになりました。しかし挑むように凝視すると、太ももの内側に顔を寄せて吸い付きました。
伸ばした舌の上に、滑らかでとろける肉の感触を写し取り、うっとりと反芻します。薄い皮膚をざらざらと舐め上げるたびに脚がびくびくと震え、純の呼吸が荒くなってゆくのが分かりました。
成仁はゆっくり顔を上げ、純の股間に指を滑らせました。純は驚きの余り顔を引きつらせて、成仁の不埒な手を引き剥がそうとします。しかし呆気なく払われ、押さえ付けられてしまいました。
「大人しくしてるんだ」
これまで聞いたことのない低く険しい声で命令されて、純の身体は凍りつきました。それをいいことに、成仁は襟に手を掛けてずり下ろし、雪原のごとき胸を露わにします。
ピンク色に潤んで勃ち上がるあどけない突起は、純の呼吸に合わせてぷるぷる揺れておりました。その愛らしいことといったら。
成仁は迷わず口に含んで、舌先でころころ転がしながらそのぷにぷにした肉の実を存分に味わいました。もちろん、股間に滑らせた手でペニスを嬲るのも忘れてはおりません。
始めは萎縮して項垂れていた半身も、成仁の手の中で次第に熱を帯び、やんわりと勃ち上がり始めていました。
成仁は名残り惜しそうに胸の果実を解放すると、荒い息を隠そうともせず純の脚を大きく広げ、組み敷こうとしました。
とその時、濃厚な怯えに彩られた昏い瞳で見上げられて、情欲の虜となっていた成仁は我に返ったのでした。
「純、お前……処女か?」
純は何を訊ねられているのかも分からず、涙を浮かべてただ首を振るばかり。しかしそれだけで十分でした。純が男を知らないことは明らか。
成仁は純の上から身をどかして乱した衣を直してやると、「驚かせて済まなかった」とひと言詫びて、濡れた目尻に唇を寄せようとしました。
が、すっかり怯えきった純はびくんと震えて顔を背けてしまったのです。成仁は、非は自分にあると分かっていながらも、苛立ちを隠すことができませんでした。
「薬を塗ったらもう帰るぞ。大事な用を思い出した」
冷たい声で嘘を吐き、事務的な手つきで純の脚に消毒薬を塗りつけてさっさと立ち上がってしまったのでした。
純は、自分の怯えが成仁の怒りを呼んでしまったのだと思い、どうしてよいか分からず途方に暮れるばかりでした。
INDEX TOP NEXT