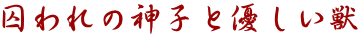
<神威紅──16歳と11カ月13日>・II
「お邪魔します……」
リビングに案内された紅は、小声で囁いたきり部屋の隅に立ち尽くした。ソファに座ろうともしない。
「何してんだ。ぼーっと突っ立ってないで座れ」
御剣が不審をにじませた声でそう言うと、紅は真剣な顔で見返し、
「どこに座ったらいい?」
「は…?」
「あ、いや。友だちの家とか遊びに行ったことないから、こういう時どうしていいか分からなくてさ」
呆れられたと思ったのか、紅は小さくなって弁解するように答えた。その華奢な身体は、広いリビングの陰影の中に今にも埋もれて消えてしまいそうで、御剣は思わず目を逸らした。
あれを自分のものにしたいという欲求が、二人きりの私的な空間にいると余計に高まってしまう。御剣は、心身を切り刻む痛みに意識を向けることで、その不穏な兆しを抑えた。そしてソファの真ん中を指差した。
紅は素直に頷いて、ぽすんと腰を下ろす。そして暫しためらった挙げ句、自分の横をぽんぽん叩いて、
「御剣、ここに座れよ」
照れ隠しなのか拒絶されるのが怖いのか、俯いたまま誘う。髪の隙間からちらと覗く耳たぶは真っ赤に染まって、御剣をたまらない気持ちにさせた。が、もちろんそんな危うい感情を露呈するわけにはいかない。普段通りの態度で、
「ちょっと待て。今、何か飲み物を……」
「いらない。起きてるのもつらそうな怪我人に、そんなことさせられるか。少し話したら、すぐ帰るから」
紅はきっぱりとそう言って、まだ赤い顔のまま御剣を見上げた。安易な接近は、自分にとっても紅にとっても危険だと分かってはいた。しかし今この状況で紅と距離を保てるほど、御剣の理性は強靭ではなかった。
御剣は黙って隣に座り、紅の眼鏡に手を伸ばした。紅はびくんと身じろいで俯いたものの、前回のように抵抗することなく、御剣の手が眼鏡を外すのを黙認した。しかし、膝の上でぎゅっと握られた拳が緊張を物語っている。
「……紅、こっちを向け」
もっと優しく促すべきだったのかもしれない。人と接するのに慣れていない紅が今、どれほどの勇気を振り絞ってここにいるか察してやるべきだったと。御剣がそんな反省に沈んでいると、紅がそろそろと顔を上げた。
御剣は冷たい命令口調の埋め合わせをするかのように、指先で紅の頬を撫でた。甘く、じれったい愛撫。そして、顔にかかる前髪に指を挿し込んで、絹麻にようにひんやりと滑らかな感触を愉しみつつかき上げた。
黒い帳の奥処に秘された美(うる)わしの花。これまで誰からも愛でられることなく、己の美しさにも気づかず、ただひっそりと咲き続けてきたのだ。
肌は白く透き通っているが陶器のように無機質ではなく、朝露を浴びた百合もかくやと思わせる瑞々しさがあった。触れた指先がしっとりと吸いついて離れない。
睫毛は長いが幾分下向きに生えているため、そっとまぶたを伏せただけで表情に蒼い憂いが落ちる。潤みがちの大きな黒瞳は、光の加減によっては紫黒にも黝(あおぐろ)にも見えた。不安と緊張を持て余しているくせに眼差しの力は強く、見つめ合っているとふっと吸い込まれそうになる。不思議な魅力に満ちた瞳だった。
それに加え、愛らしい小鼻もややぷっくりとした珊瑚色の唇も、全ての細部が繊細で詩情に富み、御剣の心を掴んで離さなかった。
これでよく自分を『醜い』などと言えたものだと、御剣は怒りすら覚えた。孤独によって荒んだ心が、目まで曇らせてしまったとしか思えない。あるいは、兄に対する賛美や憧れが、己の価値を無意識のうちに貶めているのだろうか。
「紅、俺が怖いか?」
紅の前世を考えれば、男と二人きりというこの状況に恐怖を覚えぬはずはない。しかし、
「別に。怖くない」
その証立てをするように、紅は挑むように即答を返した。負けん気剥き出しの態度に御剣は思わず苦笑を漏らし、
「無理するな」
「無理してない。本当に、お前なんかちっとも怖くない」
紅は幾分棒読み口調でそう言うと、ぎこちない動きで御剣にそっともたれかかった。色気は皆無だったが、その甘え慣れていない動きが妙に可愛い。それに、初めて紅の方から近づいてくれたという嬉しさが、御剣を浮つかせた。
思わず肩を抱こうと手を伸ばしたが慌てて引っ込め、指先に残った感触を追うだけに留めた。これ以上の触れ合いは危険だと、額の奥で警報が鳴っている。
「もうひとつ、聞いていいか? さっき俺の夢を見たと言っていたな。それ以外にも、俺らしき人物が登場する夢は見ていないか?」
紅はかすかに眉根を寄せて黙り込んだ。やがて困惑を隠さず、
「ん、ああ。御剣なのかは分からないんだけど……全身に黒い毛が生えてて、真っ赤な目をした『カイ』っていう人間と獣のハーフみたいなのが出てきた」
「なん、だと……」
この瞬間、御剣は感情に引きずられ紅と接触を持ってしまったことを悔やんだ。やはり、遠くから見守るべきだったのだ。自分と接触したことで、紅の前世記憶が刺激されたことは疑いようがない。
紅が夢で見たのは間違いなく、前世の御剣の姿だ。このまま交流を続けていれば、記憶に嵌められた枷がさらに緩んでしまうかもしれない。
御剣は荒れる内心を抑え込み、できるだけ自然に応じた。
「はは、人と獣のハーフか。お前、俺のことを野獣みたいなヤツだと思ってたのか」
「ち、違うって。そんなんじゃなくて───」
「分かった分かった。ま、俺は見ての通りごく普通の人間だ。化け物じゃない。なんなら脱いでみせようか?」
すると紅は、予想通りの反応を返した。噛み付きそうな勢いで、
「誰が見るか! そんなものっ」
「そんなものとは失礼なヤツだな。ま、お前なんかに見せたって面白くもなんともねえし。さあて、紅。そろそろ帰れ。暗くなってきた」
「言われなくたって帰るっ」
がばと立ち上がった紅ににやけた作り笑いを向けながら、御剣は疼く心を宥めていた。これでいい。今はとにかく離れて、これ以上紅が前世を思い出さないよう配慮せねば。
御剣は素早く上着を羽織った。まだ外出できる状態ではもちろんない。今朝は病院のベッドで目覚めて、最低でも一週間の入院が必要だと告げられた。それを強引に振り切って戻ってきたのだ。
「ほら、行くぞ。送っていく」
御剣の申し出に、紅は目を剥いて首を振り、
「冗談だろ。怪我人は大人しく寝てろ」
「冗談だろはこっちの台詞だ。この辺りは人通りも少ない上、薄暗い。一人で帰すなんてできるか」
御剣は立ち上がって、さっさと玄関へ向かった。そして慌てて追いかけてきた紅に、
「明日は登校する。だから心配するな。分かったな?」
そう言って紅の返事を待たず、靴を履いて部屋を出た。
生まれたての闇はどこか生ぬるく、肌にまとわりつくような独特の湿り気があった。まだそれほど遅い時間ではないのに、家路を急ぐ学生や勤め人の姿もない。ブロック塀に挟まれた狭い道はしんと静まり返って、御剣と紅の足音だけが響く。
御剣は焦っていた。一刻も早くこの暗い道を通り抜けたい。充満する生臭い闇を隠れ蓑にして、そこかしこで黒い思惑が蠢いているような気がするのだ。それは予感よりもっと曖昧な胸騒ぎだったが、歩みを進めるごとに増幅していった。
しかし、傷を負った身体には今のペースが精いっぱいだった。紅が来る前に飲んでいた痛み止めは効き目が薄く、間断ない痛みが御剣の歩みを遅らせていた。
隣を歩く紅は、そんな御剣のペースに合わせながら、時折心配そうに視線を送ってきた。紅を守るつもりが、これでは立場が逆だなと苦い自嘲を噛み潰し、御剣はひたすら夜道を急いだ。
そして、細い十字路に差し掛かった時だった。根拠のない胸騒ぎは確信となり、そしてすぐに現実のものとなった。十字路の左右から音もなく現れた四つの人影。顔は隠しているが、暁の者であることは気配で分かった。
彼らの目的は何なのか、邪魔な御剣を闇に紛れて亡き者にすることなのか、あるいはもっと別の企みがあるのか。狙いは分からなかったが、それを探っている余裕はない。負傷して身体が思うように動かないこの不利な状況を覆すには、こちらから先に仕掛けるしかないだろう。
御剣は素早く地を蹴って、黒衣の人影に飛びかかった。比較的ダメージの少ない左手には、きつめにテーピングを施してある。唯一の武器であるこの硬い拳を顎や鳩尾に打ち込み、あっという間に二人を昏倒させた。
残るは二人。相手は怪我人と見くびっていたようで、御剣の攻撃力に明らかに動揺していた。そのわずかな隙を逃さず、第三打を繰り出そうとした時、後ろから紅の悲鳴が聞こえた。
「紅っ?!」
暁の者がまさか紅に危害を加えるとは思わず、背後は完全に無防備の状態だった。焦って振り向くと、御剣を襲った者同様、黒服に身を包んだ男三人が紅をまさに拘束せんとしていた。
「くそっ」
御剣はすぐに駆け付けようとしたが、それは能わなかった。ぐわんと響く重い衝撃が立て続けに頭と背中を襲い、膝からくずおれる。
「がっ……」
激痛に呻きつつも、御剣はなおも立ち上がろうとした。しかしその悲壮な意志を嘲笑うように再び殴打が襲いかかり、御剣はその場に倒れ込んだ。
「呪われた終夜一族には、地べたを這い回る姿がお似合いだ」
嗤いを含んだ声が頭上から降り、硬い靴底が頭を踏みにじる。それでも御剣は地面に爪を立て、紅の元へ行こうとする。
「こ……う……」
紅はすでに、男たちの腕の中で気を失っていた。助けなければ、助けなければ。気ばかりが先に立ち、身体が思うように動かない。
「こいつ、しぶといな」
「まあ、ここまで痛めつけておけば大丈夫だろう。それより、長居は無用だ。行くぞ」
号令とともに、男たちは去っていった。だらりと弛緩した紅の身体を抱えて。
「紅っ……」
御剣はよろめきつつ立ち上がると、早く追いかけたいと逸る心を宥めて呼吸を整え、感覚を研ぎ澄ませた。そして、男たちの気配を探る。彼らがどこへ向かっているのか、すぐに見当がついた。
「学校だな。よし」
御剣は唇に付着した血を無造作に拭い、男たちの後を追った。
「んっ……」
こんな不快な目覚めは初めてだった。全身がだるくて、うまく思考が繋がらない。僕は何をしているんだろう、どこにいるんだろう。確かさっきまで───
「……御剣っ」
起き上がろうとしたら、頭の芯に鈍痛がともった。紅は思わず眉をしかめ、痛みのさざ波が引くのを待った。
「お、目ぇ覚めたぁ?」
生理的な嫌悪感を湧かせるねっとりとした声に、紅はぞくりと震えた。天井から吊るされた裸電球が投げかける陰影は毒々しく、この空間自体が出来の悪い悪夢のようだった。
「な、なんだお前らは」
何とか起き上がって周囲を見回すと、五人の若い男がにやついていた。紅は本能的に危険を察知したが、逃げ出そうにも足に力が入らない。それに、彼らの中にはどこか見覚えのある者もいた。紅は恐怖を押し殺して平静を装い、
「ここはどこだ」
「ここか? 学校の倉庫だよ。もっとも、今は使われてないけどな」
その答えでようやく気づいた。彼らは明神学園の生徒だ。見覚えがあるのも当然だ。
「なんでこんなことを……」
彼らの目的は何なのか。紅は必死に頭を巡らせたが見当もつかなかった。自分みたいな人間を掴まえたところで、何の得があるというのか。そんな紅の困惑を見透かすように、一人がにたりと笑い、
「お前の言った通りだな。こいつ、眼鏡外したらかなりイケるじゃねえか」
「だろ? けっこう楽しめるぜ、きっと」
そして男たちは、獲物を追い詰める過程を愉しむ残酷な獣のように、ゆっくりと紅との間を縮めてきた。紅は叫んで制止しようとしたが、舌が張り付いて声も出せない。そうする間にも男たちに囲まれ、複数の腕に身体を押さえつけられた。
「やッ……やめ……」
触手のように何本も伸びてきた手が上着を脱がせ、制服のシャツを引き裂いた。露わになった胸の白さ滑らかさを直接味わいたいと、男たちは挙って手のひらを這わせる。さらにあどけない膨らみを見せる突起をつまんで弄び、吸い付いて歯を立てた。
紅は目を見開いて天井を凝視したまま、時折喉の奥から「ひぃ、ひぃ」と痛ましく引きつった喘鳴を漏らすだけ。心の処理能力を超えた恐怖に、全身の神経や筋肉、声帯までもが竦んで抵抗らしい抵抗は不可能だった。
「へえ、ここも可愛いな。見ろよ」
いつの間にか下穿きも全て脱がされ、下半身が剥き出しになっていた。完全に萎えきった薄桃色の性器が、これから訪れる陵辱に怯えるように細かく震えている。男はそれを無造作に掴んで、ぐにぐにと揉み始めた。
「ぅぁ、ぁ、ぁ……」
瞬きも忘れ黒い虚(うろ)と化した眼窩からとめどない涙が溢れたが、紅には泣いているという意識はなかった。半ば壊死しかけた心はあらゆる感情を締め出し、無感覚になることで自己防衛しようとしていたのだ。
「なんだ? こいつ。もうマグロかよ。つまんねえの」
男はからかうように紅の腰を叩くと、脚を掴んで広げ陰部をさらした。すると、別の男が自分の隆起した股間を指差して淫笑を浮かべ、
「これから順番に、こいつをぶち込んでやるから。最初は痛いかもしれねえけど、すぐに気持ちよくなるさ。たぶんな」
そう言って紅の上に覆いかぶさってきた。電球の陰になり、男の顔は暗がりに沈む。目も鼻も口も表情もない、ひとつの不穏な黒いシルエットとなった。
その時、紅の脳裏に青白い閃光が走った。
「あ……あ……」
それはまるで、闇夜を裂く稲妻のごとく。いや、裂いているのは紅の記憶の闇だった。ちかり、ちかりと瞬くたびに、光の彼方に何かが見える。泣き叫ぶ自分と、それを力づくで押さえつけている───
(イヤダ、ヤメテ)
声にならぬ声を上げたのは、果たして現実の自分なのか脳裏に棲む自分なのか。
「そら、力抜けよ」
力を抜け。でないと怪我をするぞ───そうだ、確かに『彼』はそう言った。そして僕を、僕の身体を……。
(ドウシテ? ドウシテコンナコト)
僕の身体を無理やり押さえつけて……それで……
(信ジテタノニ。アナタノ優シサヲ信ジテタノニ!!)
「うわあああああーーーーーーッ」
頭の中で何かが破裂し、抑え込まれていたものが怒涛のように溢れる感覚。紅の口から迸る叫びは、その苛烈さを物語っていた。
「あ……ああああ……僕は……僕はっ……」
丁寧に積み上げてきた平凡な日常という名の積み木細工が、音をたてて崩れてゆく。その残骸の中にそびえるのは、生々しい前世の記憶。愛した人に裏切られ、その挙げ句に全てを失ったという哀しみの末路だった。
「紅っ、大丈夫か!」
叫びながら駆け込んできたのは、顔や服に血の痕をこびりつかせた御剣だった。そのまま紅に近づこうとしたがぴたりと足を止め、倉庫内の惨状に愕然とする。紅を連れ去った男たちは壁まで飛ばされ、血まみれのまま気を失っていた。
「これは……一体……」
「僕がやったんだ」
紅は冷然と答え、御剣を見つめた。
「お前が……やっただと?」
「そうだよ。この男たちは僕を、暁の神子を辱めようとした。だから制裁を与えたんだ」
紅の言葉に、御剣の顔が歪んだ。鉄錆色の唇が、苦しげに問う。
「紅、お前まさか……思い出したのか」
紅は冷ややかな笑みを浮かべる。が、次の瞬間カッと目を見開いて激情のまま叫んだ。
それが、答えだった。
「御剣戒。僕はお前を絶対に許さない!!」
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT