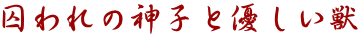
<前世哀話>・I
本当は、思い出したくなんかなかった。何も知らないまま、御剣戒、君のぶっきらぼうな優しさに浸っていたかった。
でも、前世の因縁を思い出してしまった以上、もう僕は君の誠意を信じることはできない。君を許すことはできない。なぜなら君は、僕を裏切ったからだ。君を心から慕い、そして愛した僕を……。
そう、あれは遠い昔。人が神の実在を当然の事実と受け入れ、神の声を聞くことのできた神代の世。僕たちは出会った。それが、悲劇の始まりだったんだ────
遥か昔。『暁』の姓を頂く一族が、大和の国で権勢を誇っていた。
彼らは特殊な神霊力を操ることができた上、国つ神である暁天之命(あかつきのあまのみこと)を護り神とした。そしてその庇護のもと、繁栄を謳歌していたのだ。
しかし恩恵には代償が付きもの。暁一族は代々、選ばれし神子の血肉を暁天之命に捧げ、その見返りとしてただひとつ願いが聞き届けられた。ある時は政敵の破滅を祈願し、ある時は侵略戦争の勝利を祈願する。そうすることで着々と勢力を拡大してきたのだ。
一族繁栄の命運を握る神子は『暁の乙女』と呼ばれ、身体のどこかに暁の星と呼ばれるしるしを持っていた。そして神子はみな、名の通り暁の明星と並び称されるほどの、輝くばかりの美貌の持ち主だった。
もちろん、待ち受ける宿命について本人には秘匿された。そして十七の誕生日を迎えるその時まで、一族の者から蝶よ花よとそれはそれは大事に育てられた。
いずれ訪れる血なまぐさい供犠のことも、一族が優しい笑顔の下に隠している思惑も、何も知らぬまま───
「紅様! お待ちください。お一人でそのような……」
「へいきへいき! 僕ももう十六歳だよ。たまには一人で出かけさせて」
「でも、長に怒られます。決して紅様を一人にするなと」
「だったら黙ってればいい。ほら、ばあやはそこで昼寝でもしてて。毎日僕のお守りで大変だろ? 遠くへは行かないし、日が傾く前には必ず戻ってくるから」
紅はそう言って、幼いころから身の回りの世話をしてくれているばあやを半ば強引に大木の根元に座らせた。そしてにっこり笑い、
「じゃ、行ってくるね。紫涙草が取れたら、ばあやにも分けてあげるから」
紫涙草とは、読んで字のごとく紫色の涙を流す花。涙の正体は蜜で、花弁から滴るほどの紫の蜜は非常に美味だった。紅はそれを集めて、ばあやも含め普段世話になっている使用人たちに贈ってあげたいと考えたのだ。
「えっと、確かもう少し行ったところに泉があって……」
事前に集めた情報をおさらいしつつ、どんどん森の奥へ進んでゆく。しかし道標となるはずの泉は見つからず、そろそろ引き返した方がいいか、もうちょっと進んでみようか迷っていると、突然足に鋭い痛みが走った。
思わず膝をつくと、前方の木に矢じりのようなものが突き刺さっているのが見えた。恐らく、これが後方から飛来して足首をかすめたのだろう。ということは……。
「おおっと、悪かったなあ。手が滑っちまってよぉ」
慌てて背後を振り返ると、顔じゅう髭で覆われた大男たちがにやにやしつつこちらを見下ろしていた。時折、手にした得物を誇示するように揺らしながら。
「あ、あなたたちは盗賊ですか?」
紅の問いに、男たちは一斉に吹き出した。まさか正面きって盗賊かと聞かれるとは思ってもいなかったのだろう。
「分かっているなら話は早い。身ぐるみ置いてきな」
紅はまず闘うという選択肢を捨てた。到底現実的ではない。そして逃げるという選択肢を考えたが、足に受けた傷は思いのほか深く、まだじんじん疼いている。とても逃げ切れる自信はなかった。結局、男たちの言う通り脇差しを置き、外套と袴を脱いだ。しかし、
「まだ残ってるぞ。それも脱げ」
絹綾の薄物一枚になった紅は、思わず後ずさる。すると盗賊らは素早く紅を取り囲み、
「こんな美形、都でもお目にかかれないぜ」
「ああ。久しぶりに楽しめそうだ」
「たっぷり可愛がってやろうぜ」
翡翠が埋め込まれた高価な脇差しや、金糸が織り込まれた外套には目もくれない盗賊らが一体何を欲しているのか、紅には分からない。しかし分からないながらも全身に悪寒が走り、甲高い悲鳴を上げた。
「チッ、わめくな」
一人が紅の口を塞ぎ、もう一人が薄物に手を掛けた時だった。明らかに風の流れが変わった。空気の粒子ひとつひとつが怯えるようにざわめき、それが周囲の木々にも伝播したのか枝が尋常でない震え方をする。
まさに、森全体が戦慄していたのだ。
「なっ、なんだありゃあ。化け物か」
森が何を畏れているのかすぐに分かった。こちらへ真っ直ぐ近づいてくる異形の者。人か物の怪か、あるいは未知の猛禽か。
盗賊たちよりさらに頭三つ分ほど大きい巨躯は、黒い鞣革の長衣で覆われ、顔の下半分には黒い包帯のようなものが巻かれている。その上には赫々と燃える緋色の瞳。腰まで届く漆黒の蓬髪は、まるでそれ自体が意思を持っているかのようにざわざわと波打っていた。
そして何よりその姿を異形たらしめていたのは、長衣の袖口や裾から覗く手足。それは黒い剛毛に覆われ、肉食の獣と同じ鉤爪が生えていたのだ。
豪猾を絵に描いたような盗賊たちも度肝を抜かれ、一瞬後ずさった。しかしすぐに賢しく計算を働かせ、数で勝っている自分たちの方が優位にあると結論した。
「化け物の分際で、人間様の邪魔をしようってのか。面白え」
男たちは素早く得物を取り、黒き獣人に一斉に躍りかかった。すると獣人は、その体躯からは想像できないほど優雅な身のこなしを見せ、一人残らず返り討ちにした。
鉤爪の餌食となった盗賊らは生血を滴らせつつ、「覚えてやがれ」とお決まりの台詞を吐いて逃げ去った。獣人は後を追おうとはせず、紅をちらと一瞥しただけで背中を向け、黙ってその場を去ろうとした。
「ま、待って! 待ってくださ……あっ、っ………」
紅は慌てて後を追いかけたが、盗賊が放った矢じりによる傷のせいでうまく走れず、その場に倒れ込んだ。
「い、痛っ……」
足が灼けるように痛んだが、両手をついて何とか立ち上がろうとした。助けてくれたあの人にお礼を言わなければという、その一心で。その時、
「大丈夫か? 無理をするな」
かの獣人がすぐ傍で屈んで、紅の顔を覗き込んでいた。間近で見るその外見は、紛れもなく人の理から外れた化け物。しかしそのたったひと言に含まれた労りの響きは、他人から優しくされ甘やかされることに慣れているはずの紅の心に、これまでにない感動のさざ波を起こした。
紅はこくんと頷いて、手を差し出した。彼は、自分の畜生の手で触れていいものか迷っているようだったが、やがておずおずと掴んできた。紅は思わずふふっと笑い、
「手に生えた毛がくすぐったい」
「そうか。すまない」
「ううん、謝らないで。ありがとう」
紅はその手に支えられて立ち上がり、服をぱんぱんとはたいて砂や枯葉を落とした。すると黒毛の巨人は紅の足元にひざまずき、足首の傷に顔を近づけ、
「矢じりがかすったようだな。毒は塗られていないが、感染症を起こしたら厄介だ」
そう言って立ち上がり、長衣の懐中から黒塗りの薬籠を取り出した。
「傷口を清潔な水で洗って、これを塗るといい。俺が手当てしてやれなくてすまんな」
確かに、彼の手で患部に薬を塗るのは難しいだろう。彼は、自分が手当てしてやれないのを心底申し訳ないと思っているようで、顔を伏せたまま紅に薬籠を手渡すと、そのまま立ち去ろうとした。
「あのっ、待って。あなたも怪我してます。手当てしないと」
紅の言葉に、彼は心底驚いた様子で、
「俺の、手当て?」
「はい。左手に血がにじんでる。さっき、盗賊をやっつけた時に付けられたんですね。それに、助けてもらったお礼もしてません」
紅はそう言って、彼の腕をきゅっと掴んだ。このまま行かせないという意思を込めて。
「……お前、俺が怖くないのか? この身体、見て分かるだろう? 俺は呪われた終夜(よすがら)一族だ」
「終夜……」
終夜一族。特殊な呪法を駆使し、かつては暁一族と拮抗するほどの勢力を有していた闇の一族だ。
しかし遡ること百五十年前、暁一族の神子祈願が受け入れられ、暁天之命によって闇の眷属に相応しい半人半獣の身に落とされた。
以後、終夜一族は不浄の民として忌み嫌われあっという間に落魄した。今、紅の目の前にいるのは、その生き残りなのだろう。
「そうだ。お前、暁一族の者だろう? ならば知っているはずだ。終夜と暁一族はかつての仇敵同士だと」
「あなたは僕の恩人ですっ。助けてくれた人には、ちゃんとお礼をしないと。それとも、あなたは僕たち暁一族を怨んでるのですか? だからっ……」
「いや。過去の怨恨などもう引きずってはいない。強い者が生き残り弱い者は朽ち果てる、そんな動乱期の出来事だ。勝者がいれば敗者もいるのは当然の理。ただ……この醜い身体が怖くはないのか? 誰だって、俺みたいな半人半獣とは関わりたくないと思うはずだ」
紅はブンブン首を振って、全身で否定した。
「確かに、お姿を見た時はちょっとびっくりしたけど、でも僕を助けてくれました。それに、あなたはとても優しいお声をしてます。だからちっとも怖くありません」
「ははっ……ちっとも怖くない、か。俺だって、鏡を見るとぎょっとするというのに。変わったヤツだ。まさか暁の人間に恩人呼ばわりされるとはな」
地獄の業火を想わせる緋色の眼が、一瞬だが和らいだ。それはかすかな変化だったが、紅にはすぐ分かった。今、彼は笑ったのだと。
「あの、恩人さん。あなたのお名前を教えてくれませんか?」
「俺か? 俺の名は、カイだ」
「僕は紅といいます。あの……カイはこの森に住んでいるのですか? 家族は?」
次々と繰り出される問いに、カイは淡々と答えた。
「森に住んでいるわけではない。たまに食糧を調達に来るだけだ。家族はいない。俺は終夜一族の最後の生き残りだ」
「じゃあ……カイは独りぼっちなんですか?」
「独りぼっちか。ずいぶん感傷的な言葉だが、まあそういうことだ」
それを聞いた紅は深々と頭を下げ、
「カイ、僕の友だちになってください。お願いします」
「友だち、だと?」
カイと名乗った闇の生き残りは、話にならないと言わんばかりに首を振った。途端に、紅の目尻を熱い涙が縁取る。
「やっぱり……僕のこと、暁一族のこと嫌いなんですね……ぅ、ぅっ……」
頬を転がる涙を拭いもせず肩を震わせて泣く紅に、カイはその魁偉な容貌に似合わぬうろたえぶりを見せた。
「ち、ちょっと待て。そうじゃないと言っているだろう。俺みたいな化け物とは親しくならない方がいい。だいいち、お前の親兄弟が許すはずがない」
「家族には言いません。たまにこの森で会って、お話しするだけでいいんです。僕、友だちが一人もいないんです。勉強も遊ぶのもいつも一人。一族のみんなが僕のことを大事にしてくれてるのは分かってるんだけど、でも、さびしくて……」
これまで淋しさや孤独を言葉に表したことはなかった。紅は紅なりに、自分の立場というものを弁えていたから。
しかし一度口にするとそれをきっかけに、心の底に押し込めていた不定形の感情が輪郭を持ち、次から次へと湧き上がってきた。紅はあらためて思い知った。ああ、僕は本当に淋しかったんだ、と。
「カイ、お願い……んっ、く……」
膨張する想いに比例するように溢れる涙を手の甲で拭いつつ、紅は懇願を続けた。すると、
「俺が……普通の人間だったらな……」
その憂いを帯びた呟きは、紅の耳をじりじりと焼いた。この時初めて紅は、カイの葛藤に思いを致すことができたのだ。相手を無視して自分の都合ばかり押し付けようとしたことが、カイを少なからず苦しめてしまったと。
「ごめんなさい。僕、我がまま言って。カイを困らせちゃって……」
正面から見た火焔の瞳には、血に飢えた獣でも闇に棲む魔物でもない、正真正銘の人間の、繊細な情緒が息づいていた。紅はそおっと手を伸ばしてまぶたを撫で、
「そんな、苦しそうな目をしないで。もう我がまま言わないから」
カイははっと息を呑み、紅をじっと見返してきた。ややあって、
「お前も、独りぼっちなんだな?」
紅が頷くと、カイはすとんと肩を落とし、
「本当にたまにだぞ。家族や一族の者にばれたら、すぐに会うのをやめる。それでいいな?」
「は、はいっ」
紅は嬉しくて、カイの身体に抱きついた。
「本当にお前は……おかしなヤツだ」
カイは呆れたようにそう言いながらも、紅の背中を撫でてくれた。鋭い鉤爪が紅の肌を傷つけないよう、優しく、優しく。
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT