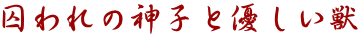
<神威紅──16歳と11カ月12日>・I
『お前、俺が怖くないのか? 俺は呪われた終夜(よすがら)一族の生き残りだぞ。見ての通りの化け物だ』
『あなたは僕の恩人です。助けてくれた人には、ちゃんとお礼をしないと』
『変わったヤツだ。まさか暁一族の人間に恩人呼ばわりされるとはな』
『恩人さん、あなたのお名前を教えてくれませんか』
『俺か? 俺の名前は、カイ───』
「カイ……」
まるでその名に導かれるように、紅は目を開けた。しばしぼぅっと天井を眺めていると、夢の断片がはらりはらりと脳裏からこぼれ落ちた。
夢の中で出会ったのは、神の悪意に満ちたいたずらとしか思えぬ恐ろしい姿をした人外のもの。二足歩行で人語も操るが、とても“人間”とは呼べぬ異形の姿をしていた。
それはまさに人と獣のキメラ。巨体は黒い剛毛にびっしり覆われ、手には猛禽の鉤爪。血走った瞳の中央では、緋色の瞳孔がぬらりと輝いていた。
しかし恐怖も嫌悪も感じなかったのは、こうして彼に“逢う”のは初めてではなかったからだ。昨日の白昼夢。脳内の幕間から覗き見た世界に、確かに彼はいた。そして、紅の手当てをしてくれた。その時は彼の名前は明かされなかったが、この夢で知ることができた。
「カイ……御剣、戒……」
無意識のうちにその名を呟いた紅だったが、すぐに我に返って自分に突っ込む。
「ち、ちょっと待て! 何言ってんだよ僕はっ」
声が似ているからつい重ね合わせてしまったが、そもそも外見は似ても似つかない。確かに態度は横柄で何を考えてるか分からない男だけど、あんな化け物と同一視するのはさすがに申し訳ない。
それにしても、昨日の今日でまた同じ夢を見るなんて、自分の思い込みの激しさには辟易してしまう。そんな己に活を入れるため、紅は両手でばん、と頬を叩いた。
「いって~~」
痛みで取り敢えず目は覚めたものの、顔の火照りは収まらない。紅はのそのそと起きて洗面所へ行き、冷水をぶっかけて豪快に顔を洗った。
「変な夢だったな。でもなんか……懐かしい」
思わず綻んだ唇から、ぽたりぽたりと水が滴る。紅はゆっくり顔を上げ、鏡に向かって呟いた。
「そういえば、昨日のお礼言ってなかったな……」
考えてみれば、これでもう三回も助けてもらっている。前の二回についても一応お礼らしきものは言っているが、ほとんど口げんかの延長、売り言葉に買い言葉で叩き付けたも同然だった。
「し、仕方ないなあ。ここらでちゃんとお礼しとくか」
さも嫌々と言わんばかりの口調でそう言う自分の顔は、言葉に反して嬉しそうに緩んでいた。
昼休み直前の四時限目。紅はカチコチに固まったまま、机の上に広げたテキストを凝視していた。
傍から見れば真面目に授業を受けている生徒だろうが、テキストの文字も教師の話も頭を素通りしているのは、全く違うページを開いていることから分かる。紅の頭の中はひたすら授業が終わるまでのカウントダウンをしていた。
あと三十分、あと二十五分、二十分───そのたびにどくんと心臓が跳ね、鞄に入った二人分の弁当がより重みを増していった。
やがて終了のベルが鳴ると、紅は机の上にぐったりと伏せてしまった。無理もない。今日は朝からずっと『昨日のお礼として御剣に手作り弁当を渡す』ことに神経を使い過ぎて、すでに消耗しきっていたのだ。
お前を嫌ってなどいない、御剣はそう言ったけれど、今朝の彼はこれまでと変わらず無愛想だった。昨日のお礼をあらためて言うつもりで近づいたら、すっと立ち上がってどこかへ行ってしまった。まるで、これ以上距離を縮めるなと言わんばかりに。
紅は行き場を失った感謝の言葉を呑み込んで、その場に立ち尽くした。そして何だよ、やっぱり嫌ってんじゃないかと独りごち、遠ざかる背中に恨みがましい視線を投げつけた。
『あんなやつに弁当渡すなんてやめろ』という声と、『受け取るかどうかは相手次第なのだから一応渡そう』という声が頭の中でぐるぐる渦巻いて、奇怪なマーブル模様を生み出す。結局、昼休みまで悶々と悩むことになったのだ。
しばし机に突っ伏していた紅は、自分の腹が鳴る音を聞いてのっそり起き出した。そして覚悟を決めて弁当の入った袋を手にしたのだが、
「あ、あれ? 御剣いない……」
御剣がいるはずの席は空だった。早々に学食へ行ってしまったのだろうか。紅が慌てて教室を飛び出すと、廊下の突き当たりに精悍な背中が見えた。
紅はそのまま追いかけたが、どう見ても悠然と歩いている御剣との距離はなかなか縮まらない。コンパスの差を痛感しつつ、何とか見失うことなく追いかけて屋上に出た。
ほんのちょっと走って階段を駆け上がっただけなのに、もう息が切れている自分が恨めしい。紅はぜーぜーと喘鳴を漏らし肩を上下させながら、日陰に腰を下ろし空を眺めている御剣に近づいた。
「何の用だ」
昨日の延長のような馴れ合いを続ける気はないと言わんばかりに、御剣はこちらを見もせずぴしゃりと叩き付けた。紅は足が竦むのを感じたが、手にした包みの重さに勇気を得て、
「これを渡しに来ただけだ」
「何だ、これは」
「昨日のお礼。あと謝罪も。なんか、兄さんがおかしな誤解したみたいで悪かった。ちょっと心配性なところがあるから」
御剣は何も言わず、差し出された包みを見つめるばかり。紅はひそかに深呼吸して、
「僕が作ったんだ。御剣って、お昼はいつも売店で買ったパンとかだろ? 僕が作ったものなんか食べたくないっていうなら、無理にとは言わないけど」
後半の口上は、拒絶された場合に備えたものだった。我ながら卑屈だとは思うが、やはり一生懸命作ったものを突っ返されるのは哀しい。このくらいの逃げ道は許されるだろう。
しばし包みを眺めていた御剣だったが、やがてふと目を細め、
「昨日のお礼、か。やっぱりお前は……変わってないな」
「えっ……?」
言葉の意味が分からず聞き返すと、御剣は「いや、何でもない」と言って手を伸ばしてきた。
「ありがたく食わせてもらう」
「お、おう!」
紅は素っ気なさを装って片手でぞんざいに差し出したものの、赤く染まった頬が隠し切れぬ嬉しさを暴露していた。
手に提げた袋には、もうひとつ自分の分の弁当が入っている。紅は駄目もとだと腹を括って、
「ここ、気持ちいいな。隣、邪魔してもいいか?」
御剣が無言のまま眉根を寄せるのを目にした紅は、ふいと横を向き、
「ちょっと言ってみただけだ。じゃ、僕は教室に───」
「座りたければ座れ。別に構わない」
紅は驚いて、思わず「嫌じゃないのか?」と訊く。すると御剣は軽く咎めるような視線を送り、
「昨日、嫌ってなどいないと言ったばかりだぞ」
「そりゃそうだけど……いつも一人で食べてるみたいだし」
「口を開けば教師の悪口、級友の陰口。あいつウザい、マジムカつく……そんな単語を浴びながら食ったら、せっかくの飯がまずくなる。だったら、こうして青空を見ながら一人で食った方がずっといいだろ?」
「そっか、うん。そりゃそうだ」
紅は素直に頷いて、隣にぺたんと座った。見れば、御剣はすでに弁当箱を開けて鶏肉の煮物をほおばっていた。紅も自分の包みをいそいそと開けて食べ始める。
「…………」
元々多弁ではない二人は、会話もせず黙々と食べ続けた。途中で御剣が「これ、旨いな」とぼそっと感想を伝えてきて、紅は思わず吹き出してしまった。
「何がおかしい」
不機嫌そうに睨む御剣に、紅は笑いの余韻をにじませつつ、
「ごめんごめん。あと、ありがと。でも言葉にしなくてもちゃんと伝わってるから」
どうやら御剣なりに気を使ってくれたようで、それが妙に可笑しくて嬉しかった。それからは再び無言の食事。傍からは気詰まりに見えるかもしれないが、少なくとも紅は、心地よい静けさに心神の安らぎを感じていた。
「……ごちそうさん。こんなまともな昼飯は久しぶりだった」
満足げな御剣の言葉に、紅は浮かれそうになる自分を何とか抑えて、「口に合ってよかった」と穏当な返事をした。
「弁当箱は洗って返す」
「いいよ。一つ洗うのも三つ洗うのも同じだから」
「三つ?……ああ」
なぜ三つなのか合点がいったらしく、御剣は大人しく空の弁当箱を返した。そしてゆったりと空を見上げたが、雲の流れではなく己の思考の流れを追っていることに紅は気づいた。
やがて御剣は、思いがけぬ問いを口にした。
「お前、どうしてそんな風に顔を隠しているんだ? 眼鏡が必要なほど目は悪くないだろう?」
「え? それは……兄さんの言い付けだから……」
歯切れの悪い返答に、御剣はちらと意味ありげな一瞥をくれて、
「ふ…ん。で、その理由は? まさか大した理由もなく、そんな酔狂な真似を可愛い弟に強いるわけないからな」
「理由は……」
紅は迷った。迷っていること自体が驚きだった。
これまで誰にも話したことのない過去。自分と兄だけが共有している記憶の疵。それをほんの十日前に知り合ったばかりの赤の他人に打ち明けるなんて、常識では考えられないことだ。
なのに、唇が自然と開いて言葉がするすると出てきた。
「ちょうど十年前のこと。僕は変質者に誘拐されかけたことがあるんだ。その時、両親は僕を助けようとして事故に遭い、死んでしまった。それ以来、年の離れた兄さんが親代わりになって僕を育ててくれた」
紅はいったん口を閉じ、傍らの御剣をちらと窺った。御剣はまだ空を見上げたままだったが、眉間には深い縦皺がくっきりと刻まれていた。その険しい表情の理由が分からぬまま、紅は話を続けた。
「兄さんが言うには、僕は女の子みたいな顔をしているからそういう変質者に目を付けられやすい。だからせめて成人するまでは、眼鏡と前髪でなるべく顔を隠すようにしなさい、って」
「で、お前は馬鹿正直にその言いつけを守ってるってわけか」
それなりの覚悟をもって打ち明けたにもかかわらず、揶揄するように軽くあしらわれ、紅はムッとした。何か言い返そうとしたが、それに先んじて御剣は正面から向かい合い、背筋がひやりとするほど真剣な声で信じられない問いを発した。
「あの神威蒼というのは、本当にお前の兄なのか?」
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT