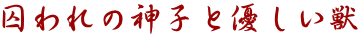
<神威紅───16歳と11カ月11日>・II
足首がじりじり痛むが、今はそれどころではなかった。
「下ろせよっ、自分で歩ける!」
御剣にいわゆる『お姫さまだっこ』された紅は、お姫さまにはおよそ相応しくない勇ましさで暴れた。しかし御剣は時折「うるさい」「大人しくしてろ」と言うだけで、平然と廊下を歩く。
紅は顔を真っ赤にして歯噛みしつつも、抱き上げられたまま子供みたいに駄々を捏ねる方が実は恥ずかしいのだと気づいてからは、むっつり黙り込んで身体を預けた。
医務室までの道のりは紅には長く感じられたが、実際にはほんの数分だった。しかし紅がほっと息をついたのも束の間、室内には誰もいなかった。
「なんだ、保健医いないじゃねえか。ったく……」
御剣は小さく舌打ちしつつ、紅を白い長椅子に座らせた。そしてスツールの上に足を乗せ、ズボンの裾をまくり上げて患部を観察する。やがて、
「……軽い火傷だな。痕が残るほどじゃない」
「ほんと?」
「ああ。よかった」
そう言う声には、心からの安堵がにじんでいた。ここまで心配してくれる彼に対し、感謝と喜びを感じるべき時だと分かってはいるのだが、戸惑いが先行してしまう。どうして彼はここまで僕のことを……。
「簡単に処置をしておく。あとで、一応医者に見せた方がいい。分かったな?」
「うん」
節々のしっかりした骨っぽい手が、その外見に反した繊細な動きで手当てをしてくれる。紅がそれをぼうっと眺めていると、脳裏に突然亀裂が走った。そして驚く間もなく、まるで幕の隙間から舞台を覗き見るように、全く違う景色が現れた。
『大丈夫か? 無理をするな』
『うん、ありがとう』
『矢じりがかすったようだな。毒は塗られていないが、感染症を起こしたら大変だ』
───えっ? なんだこれ……
紅はただ呆然と、脳内で展開する光景を眺めた。夢かうつつか幻か。いや、そのどれでもないと直感が囁く。これは『記憶』だ。魂に刻み込まれた遠い記憶が、何かに触発されて剥がれ落ちてきたのだ。
どうやら記憶世界の紅も足を怪我しており、手当てをしてもらっているようだ。しかしその相手は、異様な風体をしていた。
人なのか獣なのか分からない。いや、黒い剛毛に覆われたその身体は、人でも獣でもなかった。まさに人外の化け物。しかし、
『傷口を清潔な水で洗って、これを塗るといい』
この声。間違いない。この低く深みのある声の主は───
「終わったぞ。このままゆっくり歩いて戻れ。いいな?」
御剣の呼びかけに、紅は現実に引き戻された。と同時に、もうひとつの世界は幕を閉じた。しかし声の余韻はまだ耳の奥に凝っている。
「……どうした? 紅」
立ち上がる気配もなくぼぅっと見上げるばかりの紅に、御剣は不審げに訊ねた。紅はまだ白昼夢を引きずっているかのような覚束ない口調で、
「ああ……いや。ずっと前にも、御剣にこうして手当てしてもらったことがあったような気がして……」
その瞬間、御剣はかすかに身じろいだ。が、すぐに鼻で笑い、
「んなことあるわけねえだろ。お前のドジに付き合わされるのはこれが初めてだ」
「ドジって言うな! ていうか、さっきのは僕のせいじゃない。アルコールランプに点火したら、いきなり爆発したんだ」
「なるほど。アルコールランプも人を見るんだな」
「どういう意味だよそれはっ」
紅が詰め寄ると、御剣は笑いながら立ち上がり、
「冗談だ。それより紅、気をつけるんだぞ。脅すつもりはないが、アルコールランプの爆発もさっきの階段に落ちていたサインペンも、誰かのたちの悪いいたずらという可能性もある。もちろん、お前を狙ったというわけじゃなく、不特定多数の──」
「気を使う必要はないさ。僕個人を狙った嫌がらせだとしても別に驚かないし、今さら怒りも湧かない。僕がクラス中から嫌われていることはとうに分かってる。不気味な眼鏡妖怪、ってね」
御剣の言葉を遮ってぴしゃりと叩き付けるようにそう言った紅は、ぐいと胸を張って御剣を見返した。嫌われていることについて自分は何とも思っていない、痛くも痒くもないということを示すために。しかし、
「俺は違う。俺はお前を嫌ってなどいない」
淡々としながらも誠心のこもった御剣の言葉に、紅はうろたえた。つい声を荒らげ、
「嘘つくな! 転校してきた時、僕の隣に座るの避けたじゃないか。どうせ、あんな暗そうなヤツの隣なんてご免だって思ったんだろ」
「あ、いや、あれは……」
今度は御剣がうろたえ視線を泳がせる。いつもふてぶてしいほどの落ち着きを見せる彼が、こんな動揺をさらすのは珍しいことだったが、そこから何かを汲み取るには紅は自分の感情にのめり込みすぎていた。
「分かってるさ、僕なんか……でも……」
人に嫌われ避けられるのは慣れている。哀しいとか淋しいとかつらいとか、そんな繊細な感傷はとうに麻痺しているはずだった。
この先もずっと、友人や恋人と呼べる人が現れることはないだろうけど、自分には兄さんさえいてくれればいい。そんな甘い諦念を輩(ともがら)に、痛みのない日常を送ってきたのだ。なのに、
───ああ、そうか。僕は彼に避けられたあの時、少なからず傷ついていたんだ。
誰かに見てもらいたい、誰かに必要とされたい。そんな心の深層でくすぶっていた欲求を、この美しい転校生は刺激した。それは紅自身が気づかぬ間に、じわじわと心神を侵食していたのだ。
───今さら気づくなんてバカだなあ。
紅は笑おうとしたが、心の奥に生じた鈍い痛みが脊髄を伝って脳裏に浸透し、涙腺を揺さぶった。慌てて腹の底に力を入れたが間に合わず、潤んだ目尻から涙がひと粒こぼれ落ちる。せめて嗚咽はこらえねばと、紅は歯を食いしばって耐えた。
「うっ、く……ぅ……」
いきなり目の前で泣かれて、御剣はさぞ迷惑していることだろう。こんな醜態をさらしてしまった自分が情けなかったし恥ずかしかったが、もうどうにでもなれという不思議な解放感もあった。こうして感情をさらけ出すのは、本当に久しぶりだったのだ。
その時、喉に絡んだような低い声で名前を呼ばれた。
「紅……」
耳がこれまでにない甘さを感知し、紅は自分の感情にばかり向いていた意識を外へ向けた。と同時に、御剣の指が眼鏡のフレームに触れる。
「あっ」
紅が抵抗する間もなく、顔を覆っていた眼鏡が外された。
「かっ、返せ……」
御剣の手にあるそれを取り返そうと伸ばした指は、御剣の大きな手にふわりと包み込まれた。
「やっと、直接目が合ったな」
高貴な黒豹のような男の一体どこに、こんな優しい声を出す器官が備わっているのだろう。いや、優しいだけじゃない。感情と本能が支配する心の最も感じやすい部分を酔わせる媚薬のような、危険な魅力をも孕んでいる。
「もう一度言う。俺はお前を嫌ってなどいない」
その言葉の証立てをするように、御剣の無骨な、それでいて愛情に溢れた指先が涙を拭う。まるで、涙に閉じ込められた悲哀まで拭い去るかのように。
「嘘つくな。そんなのっ……」
「嘘じゃねえよ。あの時お前を避けたのは……自分を抑える自信がなかったからだ。お前に逢えたことでのぼせたここを冷ますためにも、取り敢えず離れる必要があった」
御剣はそう言って、自分のこめかみをトン、と指で叩いた。紅は涙越しに睨み、
「わけ分からないこと言うな」
「今は分からなくていい。でも、いずれ……」
珍しく続きをためらった御剣が再び口を開こうとした時、医務室の戸が勢いよく開いた。そして息を切らせて蒼が飛び込んできた。
「何やってるんだ!」
蒼は普段決して見せない険しい形相で紅を庇うように立ち、御剣の手から眼鏡をひったくった。兄の剣幕に驚いた紅は、自分の前に立ちはだかった背中をただ見上げるしかできない。
「何って見れば分かるだろ。火傷の手当てをしていた」
「……紅は泣いているじゃないか」
紅は慌ててごしごしと涙を拭い、目の前の怒りに強張った背中にそっと触れた。
「に、兄さんっ。違うんだ、彼は何も──」
「何もされていないのに泣いたのか? おまけに眼鏡まで取られて」
「あの、それは……」
何と説明してよいか分からず口ごもると、蒼は疑わしげな視線を送ってきた。紅はいたたまれず、肩をすぼめてちぢこまる。すると御剣がすっと立ち上がり、
「化学の実験中、なぜかこいつのアルコールランプが爆発して、軽傷とはいえ火傷を負った。驚きと恐怖から感情がコントロールできなくなって当然だろ。眼鏡を取ったのは涙を拭くためだ。そんなに目くじら立てるようなことか?」
そしてゆっくり出口まで向かうと、肩越しに振り向いて、
「それにしても、大事な弟が怪我したっていうのに『大丈夫か』のひと言もないんだな。傷の具合より眼鏡の方が気になるとは、お優しい兄上様だ」
こってりとした皮肉を叩き付けて出ていった。
「兄さん、あの……」
冷たく尖った視線を御剣が去った戸口に注ぐ蒼の横顔は、どこか禍々しさを感じる青黒い翳に沈んでいた。紅は戦慄を覚え、しばし声を掛けることができなかった。
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT