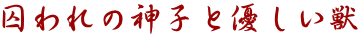
<神威紅──16歳と11カ月11日>・I
「ああ、神威さん。ちょっと頼まれてくれるかな」
授業の合間の短い休み時間。教室前の廊下で化学を教える香西に声を掛けられた。蒼の次に人気のある彼は、細いフレームの眼鏡をかけ、すらりとした長身に白衣が似合う、いかにも理系なインテリジェンスをまとった美青年だった。
普段から、自分が生徒たちに人気があることを十分意識した振る舞いを見せる彼が、紅は何となく苦手だった。ひがみなどではなく、その強い自意識に息苦しくなってしまうのだ。とはいえ、それを態度に出すようなことはもちろんしないが。
「はい。何でしょうか」
「これ、次の授業で使う資料なんだけど、実験室に運んでおいてほしいんだ」
香西はそう言って、両手で抱えていた大きな段ボール箱を紅に渡した。さほど重くはないが、嵩があるため華奢な紅が抱えると足元も前方もほとんど見えない。
「分かりました。えと、第一実験室ですよね」
「そう。北階段を使うと近道だよ。気をつけてね」
続けて「頼んだよ」と言いつつ、香西は紅の肩に手を伸ばした。おそらく肩を叩こうとしたのだろう。ありがちな軽いスキンシップだが、紅は「ひっ」と小さな悲鳴を上げて後ずさった。当然ながら香西は眉根を寄せ、
「神威さん? どうしたんだい?」
「い、いえ。なんでもありません。変な声出してすみませんでした」
額にうっすら汗をかきながら謝罪する紅を、香西は探るような目つきで見つめる。が、やがてふっと目を細め、
「なんでもないならいいんだ。それじゃ、よろしく」
そう言って、白衣の裾を閃かせて去っていった。紅は見送りながら、ほっと溜め息をつく。
───なんで、こんなに男性が怖いんだろ。やっぱりあのせいなのか……。
紅は子供のころ、ある事件で被害者となった。そのせいで、男性に対する恐怖が無意識下に植え込まれてしまったと考えるのが妥当のように思えたが、納得しきれない部分もあった。
もっと根深い何かが、そこには潜んでいるような気がして……。
「あ、こんな考え込んでる場合じゃない。第一実験室だよな」
それにしても、香西のような人気教師が自分に頼むなんて珍しい。彼の頼みなら何でも喜んで引き受ける取り巻きの生徒がたくさんいるのにと首を傾げつつも、紅は言われた通り北階段へ向かった。
日当たりの悪い北階段は晴天の昼間でも薄暗く、何となく湿っているような気がする。抱えた荷物のせいで足元の段は見えないけれど、毎日上り下りしている学校の階段だから問題はないはずだった。が、
「あっ」
階段を真ん中辺りまで上ったところで、急にぐらりとよろめいた。何か丸いものを踏んでしまったと気づいた時にはすでに、身体が後ろにのけぞっていた。両手が塞がっているから手すりを掴むこともできず、バランスを崩したままふわりと足が浮いた。
ああ落ちる、そう思った瞬間、周囲の景色がスローモーションで前に流れた。悲鳴を上げる間もなく、紅は反射的にぎゅっと目をつむった。その時、
「紅っ!」
名前を呼ばれ、はっと目を開ける。と同時に、身体が温かく力強いものに受け止められた。自分の身に何が起きたのか分からず、遥か上方の踊り場をただ呆然と見つめる。そこに白い人影の残像を見たような気がしたが、
「怪我はないな?」
背後から問う声の主に気づいた紅は、階段から落ちかけた恐怖も忘れて息を呑んだ。そして慌てて振り向き、「どうして……」と疑問をそのまま口にする。
「どうして、じゃねえだろ。お前が階段を踏み外して落ちてきたんだ。それを俺が偶然受け止めた。それだけだ」
御剣は呆れたと言わんばかりに答えた。その厳しい眼差しに気圧され、紅はそれ以上質問を重ねることができず黙り込む。すると御剣はちらと肩を竦め、
「昨日の威勢はどうしたんだよ。また果たし状叩き付けるみたいな勢いで礼を言ってくるかと楽しみにしてたのに」
「ち、ちょっとびっくりしただけだ」
「ああ、怖くて声も出せなかったのか」
馬鹿にしたような言葉にカチンときたものの、ここで声を荒げて反論してもどうせ『うるさい』と一蹴されるだけだと思い、紅はぐっとこらえた。そして「どうもありがと」とぼそっと告げる。
我ながらふてくされた子供みたいな態度だと思っていたら、御剣にしっかり指摘された。
「なんだよ、そのおたふくみたいなツラは」
「生まれつきだよっ。どうせ不気味な眼鏡妖怪だ。笑いたきゃ笑えよ」
すると御剣は紅のかすかに赤らんだ頬を手のひらで撫でた。そして、
───あ、笑った……。
いかなる曲線も悉く拒む意志が感じられる真一文字の唇が、かすかに緩んだ。それはつい見落としてしまいそうなほどささやかな揺らぎだったが、笑みであることに変わりはない。しかし、笑いたきゃ笑えと挑んだ紅が想像していたものとは、全く質の異なる微笑みだった。
紅はどう反応してよいか分からず、ただ見つめ返すばかり。そんな視線の交錯は長くは続かず、御剣は落ちた段ボールを拾い上げ無言のまま階段を上り始めた。
「ま、待てよ、ちょっと──」
紅は慌てて後を追おうとしたが、背中を向けたまま「お前は教室に戻ってろ」と言われ足を止めた。そして、自分が頼まれた仕事なのに彼にやらせていいものか迷っていると、さっき紅がバランスを崩した辺りで御剣が立ち止まった。
「これか」
そう言ってコツンと爪先で蹴ったのは、サインペンだった。誰かがまとめて落としたのだろう、数本が階段に散らばっていた。さっきはこれに気づかず、その上に足を乗せたせいでよろけてしまったのだ。
「……御剣?」
御剣は何やら考え込んでいる様子だったが、すぐに歩みを再開した。紅のことを振り返ろうともしない。一転して冷ややかな態度を見せる御剣だったが、その背中から伝わるのはぶっきらぼうな優しさだった。
「変なヤツ……」
遠ざかる背中を見送りながら紅は、男性の御剣に触れられたのに恐怖も怯えも湧かなかったことに気づいた。むしろ、触れ合った頬や背中が甘く疼くのを感じて、そんな自分に戸惑いを覚えた。
「それでは、班ごとに実験を開始してください」
香西の号令に従って、各々が自分の役割を果たすべく動き出した。器具を操作して実験を行う者、その経過を観察する者、結果を記録する者。
これまで紅は、どのグループに入っても何もさせてもらえず、一歩下がって成り行きを眺めているばかりだった。しかし、
「神威もぼーっとしてないで手伝えよ」
クラス内でリーダー格の進藤が、苛立ちを隠そうともせずアルコールランプを紅の前に押し出した。
「あ、ああ」
仕事を与えてもらえるとは思っていなかった紅は、ほんとにいいのかなとためらいつつもランプを引き寄せ、マッチを擦って芯に近づけた。次の瞬間、
「うわぁっ」
ほの青い小さな炎がともるはずだった芯はぶわっと音をたてて赤く膨らみ、その熱気で紅の手を焼いた。
紅は慌ててランプを払い落としたが、それがまずかった。床に落ちたランプは割れ、中の液体がこぼれて炎の勢いと広がりが増す。赤く燃え上がる触手は、あっという間に紅のズボンの裾を捕らえた。
「何やってんだよ神威っ」
実験室には怒号や甲高い悲鳴が響き、香西も「誰か消火器を持ってこい!」と叫ぶ。紅は必死に手で叩いて火を消そうとしたが、なぜか一番傍にいる進藤は消火に手を貸そうともしない。まるで実験の経過を観察するかのように、冷徹な眼差しを注ぐばかり。その時、
「どけっ」
濡れた上着を手にした御剣が、進藤を突き飛ばして駆けつけた。転校して以来、ほとんど表情の変化を見せたことのない御剣の剣幕に、周囲は床に広がる炎を忘れて息を呑んだ。
「じっとしてろ、紅」
御剣は水の滴る上着を火にかぶせて、上から何度も叩いた。その効果はすぐに現れ、紅の制服に移った炎は消えた。
「神威君、大丈夫か」
心配そうに安否を訊ねる香西だったが、声や表情とは裏腹に目は凪いでいた。その静かすぎる双眸が、ちらと御剣を射抜く。しかしすぐに紅へ戻り、
「立てるか? 立てるようだったらすぐ医務室へ行こう。さ、僕の手に掴まって」
爆発のショックからようやく我に返った紅は、「大丈夫です」と硬い声で答えて立ち上がろうとした。すると御剣が素早く間に割り込み、紅の身体をふわりと抱き上げた。
「え、えっ?」
あまりのことに対処できず、紅は大人しく抱かれる。実験室内には、驚きとも感嘆ともつかぬ溜め息がさざ波のように広がった。
「医務室には俺が連れて行く」
そう言い置いて実験室を出ようとする御剣を、香西は慌てて追いかける。
「ま、待ちなさい。それは教師の役目だ。僕がちゃんと──」
御剣は、視線だけで香西を黙らせた。ややあって、
「教師の役目? その割にはあんた、叫んでただけで何もしなかったじゃねえか。化学教師のくせに火が怖かったのか、あるいは、」
視線はさらに尖り、相手の心奥まで貫くような鋭さを帯びた。御剣はかすかに口端を吊り上げて、嘲るように続けた。
「最初から、火を消す気なんてなかったのか」
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT