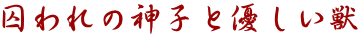
<神威紅──16歳最後の日>・III
紅が慌てて振り返ると、双眸に憤怒の炎を宿した蒼を先頭に、凶器を手にした一族の臣下たちが迫っていた。
灼けるような殺気に圧倒され、紅は思わず御剣にしがみついたが、御剣は焦りも恐れも見せず、悠然と問いを投げた。
「この期に及んで何をする気だ」
「決まっている。暁の乙女を神に捧げるのだ。供犠はまだ終わっていない」
蒼の答えが孕む矛盾を見透かすように、御剣は目を細めて首を振った。
「今の温かな光を見ただろう? 暁天之命はもはや、生贄を欲する野蛮な神ではない。それに」
御剣は思わせぶりな仕草で手首を指差し、
「時計を見てみろ。〇時をすでに五分過ぎている。紅は十七歳になった。もう神子の資格はない」
蒼は噛み付かんばかりの勢いで腕時計を確認した。そしてカッと目を見開き、無情な文字盤を凝視する。
「そんな馬鹿なっ……」
ようよう口から出た呟きは、濃厚な敗北に彩られていた。しかし御剣は勝ち誇った様子もなく、淡々と言葉を続ける。
「神霊の御光の中で時間の感覚が麻痺するのはよくあることだ。これも、暁の神の思し召しと考えればいい」
しかし、御剣の言葉が届いていないのは明らかだった。蒼は瘧にかかったように震えつつ、「馬鹿な馬鹿な」と否定の言葉を繰り返すばかり。御剣はもうひとつの決定的な事実を示すため、紅の衿元をそっとめくり、
「見ろ。神子の証である緋の六芒星が消えている。これでもまだ認めないか?」
蒼は紅の首筋にのろのろと焦点を合わせると、喉の奥で低く笑った。それは哄笑の前兆めいて不気味に引きつっていたが、平静を取り戻すのは早かった。
「暁一族再興の悲願は潰えた。その責任は、長である僕の隙と甘さにある。皆、済まなかった」
蒼は詫びるや否や懐から短刀を取り出し、素早く鞘を払って己の喉に突き立てようとした。予想だにしなかった蒼の行動に、紅は唇を悲鳴の形に開けたまま固まった。短刀は柄にまで赤い血を滴らせぬらりと光ったが、それは蒼の血ではなく───
「やめろ。そんなことをして何になる」
刀身をじかに掴んだ御剣は、刃が手のひらを斬り付けるのも構わず蒼の自害を止めた。そして空いた片手で蒼の手首をはたき、刀を手放させた。蒼は毒気を抜かれ、ただ呆然と血に塗れた御剣の手を見つめる。ややあって、
「なぜ……だ……」
お前は僕を、暁一族を憎んでいるのではなかったか───そんな深刻な問いと戸惑いが凝縮されたひと言に、御剣は明快な言葉で答えた。
「確かに俺はあんたの敵だが、同時に感謝してもいる。あんたはこの十年間、歪んだ目的のためとはいえ紅を大事に育て守ってくれた。どんな裏事情があったとしても、紅にとって神威蒼が優しい兄だったこと、そして二人で暮らしていた間、紅が幸せだったことは事実なんだ。そうだろ? 紅」
振り向いて穏やかに訊ねる御剣に、紅はひと筋の涙とともに何度も頷いた。
「そうだよ。僕は幸せだった。兄さんがいてくれたから、僕は孤独にならずに済んだんだ」
あの優しさが偽物だったとしても、これから二度と『兄さん』と呼べないとしても、蒼と二人で暮らしてきた十年間を否定することは、紅にはできなかった。そして、そんな紅の想いをきちんと汲み取って蒼を救ってくれた御剣に、紅は深い感謝と敬意を抱いた。
御剣は満足げに目を細めて再び蒼に向かい、
「本人がああ言ってるんだから間違いない。それにもうひとつ。ここであんたが死んだら、これまであんたを信じてついてきた一族の人間はどうなる。路頭に迷わせる気か?」
その問いに弾かれるように、蒼の背後に控えていた臣下たちが一斉に声を上げた。
「長! 我々は長一人に責任を負わせようなどとは思っていません」
「神を失っても、我らには長がいます」
「これからもどうか一族をお導きください!」
その声を背中で受け止めた蒼は、小刻みに震え出した。御剣は小さく頷き、奪い取った短刀を遠くへ投げ捨て、
「神の世はとうの昔に終わった。これからはあんたが指導者となって、一族を守るんだ。ただし、紅は別だ。紅は……俺が守る」
そう言って渡さないとばかりに紅の肩を抱く御剣に、蒼は不敵な笑みを向け、
「勝手にしろ。その者にもう用はない。お前にもな」
そしてくるりと身を翻し、すがるような眼差しを注ぐ臣下たちにひと言「行くぞ」と言い置いてゆっくり歩み去った。その後を追いかける彼らの顔は、決して暗くなかった。
去りゆく者たちを見送りながら、紅の唇は自然と感謝の言葉を紡いでいた。
「御剣、ありがとう」
「ん? ありがとうって、何がだ?」
「何がって……その色々と、だ。たくさんありすぎて分からない」
紅は正直に答えると、ぐいと涙を拭って笑った。しかし、血がこびりついた御剣の手を見た途端に笑顔は凍った。
「まだ血が出てる。止血しないと……」
包帯の代わりになるものを探した紅は、着物の腰紐がぴったりだと気づいた。すぐさまほどいたのだが───
「うわっ」
腰紐を解いた着物は当然ながら前がだらりとはだけ、胸から腰、股間に到るまでその素肌を露わにした。紅は慌てて前を掻き合わせて隠す。御剣は不審げに眉をひそめ、
「なんだ、誘ってるのか? こんなところで」
「誰が! 止血しようと思ったんだっ」
「ならちゃんと手当てしてくれ。ほら」
ずいと手を突き出され紅は「うっ」と詰まる。ちらと見上げた御剣の顔には揶揄めいた笑いが浮かんでいたが、未だ血を流す傷口を無視するわけにはいかなかった。
紅は顔を真っ赤に火照らせて、しっかと掴んでいた前衿を離した。すると再び着物ははだけ、素肌はもちろん局部までもが露わになる。しかし紅は澄まし顔を装って、丁寧に腰紐を巻き始めた。本当は爆発しそうなほど恥ずかしかったけれど。
すると溜め息混じりの「仕方ねえな」が頭上から降ってきた。
「ほら、これならいいだろ」
御剣は無傷の方の手で着物を押さえ、ちらと肩を竦めた。紅は頬を染めつつ「ありがと…」と小声で礼を言って、止血の処置を終えた。
「できたよ、御剣………ぁ、んッ」
いきなり抱き寄せられた紅は、着物の裾を閃かせつつ御剣の胸に倒れ込んだ。驚きに呼吸が止まり、一拍おいて深く息をつくと同時に唇を塞がれた。
「ふっ、ふぅっ、ん……んっ……」
初めてのキスは果物の味がするらしいとどこかで聞いたけど、御剣の唇は血の味がした。甘い口づけには相応しくないかもしれないが、それは紅を守るために闘った証なのだ。
紅は拙い舌使いでそれを舐め取り、御剣への感謝とともに記憶の表層へ刻み込んだ。すると伸ばした舌に突然甘い痺れが走り、紅は思わず腰を揺らす。舌先を軽くかじられたのだと気づいた時にはすでに、口の中にじゅわっと唾液が溢れていた。
御剣はそれを待ち構えていたかのように、舌を潜り込ませてすくい上げた。その動きの大胆さ淫らさに紅は眩暈を覚えつつ、口内が蹂躙されるに任せた。
「はぁっ、ふ、ぅ……ん……」
重ねた唇の隙間からこぼれるあえかな喘ぎは、とろりとろりと濡れた質感をもって首筋を伝ってゆく。交わる舌がくちゅくちゅと水音を奏でれば、喉の奥からさざ波のような官能がざわざわと這い上がる。
───も……だめ……だ……
喉の奥まで犯すような深い口づけに半ば朦朧となった紅は、御剣の胸にきゅっと爪立てることで、何とか意識を繋ぎ止めようとした。
そこで御剣もようやく紅の状態を察したようで、今にも溶け合ってしまいそうなほど密着していた唇を離し、唾液を滴らせつつ舌先をほどいた。
「みつるぎ……おまえに、たのみがあるんだ」
さんざん吸われ弄られた舌はうまく動かす、とろんとふやけた幼い声しか出せない。こんな声で大事なことを言うのも気が引けたが、これまで守られるばかりで一人前になりきれていないお子様な自分にはぴったりだと思い、そのまま続けた。
「僕の、そばにいてほしい。これからも、ずっと……」
我ながら色気も艶もない告白だったが、核にある想いはきちんと伝わったようだ。御剣はいつも冷静沈着な彼からは想像もできないほどの狼狽と、赤くなった顔を隠そうともせず、それでも最後の砦なのかぶっきらぼうに言い放った。
「頼まれなくても傍にいるさ。これからは俺が保護者だからな」
確かに、これまでの御剣は紅の保護者だった。けれど、紅が望む関係はそうではない。これからの二人に相応しいのは───
「一方的に守ってくれるだけの保護者はいらないよ。僕はこれから、御剣とは対等な関係でありたい。守られたり依存するのではなく、共に歩む恋人同士に」
自分の想いを告げた紅は、黙って御剣の答えを待った。御剣は一瞬固まったのち頭をぐしゃぐしゃっと掻いて、紅を乱暴に抱き寄せた。
「お前には敵わねえな」
「な、なんだよ突然……」
「何でもない。保護者っていうのは俺の卑怯なごまかしだ。悪かった。だいたい、あんなキスをしといて保護者もクソもねえよな」
御剣の言葉に先刻交わした口づけの余韻が再燃し、意思に反して身体が火照ってゆく。紅はたまらず深呼吸をして、体内に滞留する淫靡な熱を吐き出した。それに導かれ、素直な欲求が口をついて出る。
「ああいうの……またしてほしい」
すると濃厚な沈黙を経て、御剣がぽつりと呟いた。
「本当に……お前には敵わねえ」
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT