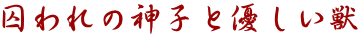
<神威紅──16歳と11カ月20日>
「神威君、君は無理せず休んでいてください」
生徒から怖がられている鬼の体育教師に敬語を使われ、ああこの人も暁一族の生まれ変わりなのかと知る。
前世の記憶を取り戻して以降、一部の教師や生徒らの自分に対する態度が明らかに変わった。みな敬意と礼節をもって接してくる。まるで自分が石ころから宝石になったみたいだと呟き、紅は自嘲を浮かべた。僕自身は何も変わってないのに、と。
教師の言葉に甘えて、紅は体育館の隅に腰を下ろした。コート内では、鋭い笛の音とともにバスケの試合が始まった。それを漫然と眺めていると、嫌でもあの時のことを思い出してしまう。初めて御剣に助けてもらった時のことを。
ふざけた同級生が、紅の頭目がけてボールを投げつけた。それを寸前で受け止めてくれた御剣。思えばあれから、何度御剣に助けられただろう。
あのぶっきらぼうな優しさは全て嘘だったのか。ただ暁一族への復讐のため、紅に近づいただけなのか。それとも───
『俺はただお前を助けたい。それだけなんだ』
深手を負いながらも紅の元に駆けつけ、必死に諭そうとした。あの声、表情、眼差し、そして抱き締められた時の温もり。全てが紅の心に問いを投げかけてくる。本当にあれを嘘だと思うのか? 神子祈願を妨害するための罠だったと思うのか? と。
「分からない、分からないよ、そんなの……」
あれ以来、御剣は学校に全く来なくなった。御剣君はバイクの事故で怪我をしたため、しばらく欠席することになりました、そう淡々と説明した担任も、おそらく暁の者だろう。
あの怪我は事故によるものではなかったのだと、今になって気づいた。彼の動きを封じるために暁が送った刺客にやられたのだろうと。
たぶん彼は二度とこの学校には来ない。神子祈願の妨害が失敗した今となっては、学校へ来る理由も紅に会う理由もないはずだ。そう思うと哀しくて虚しくて、御剣の部屋に押しかけたくなってしまう。
実際、それを行動に移そうとしたこともあった。学校からの帰り道、ちょっと寄り道するだけ、といったさりげなさを装って御剣のマンションに向かったのだが、どこからともなく暁の人間が現れて、真っ直ぐご自宅にお戻りくださいと諭される。
言葉遣いこそ丁寧だったが態度は強硬で、紅は自分が籠の中の鳥であることを思い知らされたのだ。
「身体、大丈夫なのかな。ひどい怪我だったからな……」
抱き締められた時に感じた尋常でない体温、荒い呼吸、薬品の匂い、そしてかすかな血臭が、今でもふと脳裡に蘇る。そのたびに紅は涙腺に疼きを覚え、慌てて目をこすってごまかした。そして自分に言い聞かせる。もう彼のことは忘れろと。
自分は御剣にさよならを告げて蒼の手を取ったのだ。暁一族の神子として生きる道を選んだのだ。
───僕を必要としてくれる人がいる。その人たちのために、前世でできなかった神子の務めを果たすんだ。
紅は何度も自分に言い聞かせ、そのたびに苦い溜め息をついた。
<神威紅──16歳最後の日>・I
通行人も対向車も街灯もない夜の山道を走り続け、その場所に着いたのは夜十時五十分。あと一時間と少しで日付が変わり、紅の十七歳の誕生日が訪れる。
結局、あれから御剣と会うことはなくこの日を迎えてしまった。彼は一度も登校せず、見舞いに行ったという女子生徒の話によれば、どうやら自宅にもいないようだった。
どこで何をしているのか、怪我は回復したのか気になったが、彼のことは忘れると決めた以上、その名を口にすることは決してしなかった。それに、儀式の作法や祝詞も覚えねばならず、よそごとに気を向ける余裕もなかったのだ。
───やっぱり、復讐が失敗したからもう僕に用はないってことなのか……。
それでもいいから最後にひと目会いたかったなと呟き、紅は慌てて首を振った。今はそんな感傷に浸っている時ではない。これから神子として最初の、そして最も重要なお務めが控えているのだ。
「どうした? 紅。何を考えている?」
蒼に問いを振られ、紅ははっと我に返った。
「あ、うん。頭の中で作法のおさらいをしてた」
「そうか。紅は真面目だからな。でもそんなに神経質にならなくても大丈夫だよ。基本的に、神子はいるだけでいいんだ。作法や祝詞は、あくまで儀礼的なものだ」
「そうなんだ。ちょっと安心したよ。それより兄さん、ここは一体……」
紅は辺りをぐるりと見回した。車を降りてから蒼の案内に従って歩いていたが、どこまで行っても周囲は鬱蒼とした森が広がるばかりで、さすがに不安になってきたのだ。
「ここかい? 紅は懐かしくないか? この辺り一帯は、かつて暁一族の領土だった場所だ」
蒼の答えに、紅の胸はとくんと高鳴った。ということはつまり、この森のどこかで前世の自分はカイに出会ったのだ。そう思った途端、そこかしこに魔が潜んでいそうな神秘の森に親しみが湧いてきた。
「さあ、あの石段を上れば神籬(ひもろぎ)がある。少し急ごう」
蒼の促しに頷きを返したが、紅の視線はまだ森に向いていた。木々の間に、黒い毛に覆われ緋色の瞳を持つ半人半獣が佇んでいるような気がして。
「ここが……神域……」
目の前に広がる光景に畏怖を覚え、紅は思わず後ずさった。断崖絶壁に挟まれた細い小道が真っ直ぐ伸び、その行き当たりにはまるでタールを塗り込めたかのようにぬらりと黒光りする巨岩がそびえていた。
「ここから先は神籬、つまり神をお招きする聖域だ。そしてあの巨岩は御霊代(みたましろ)。あそこに暁天之命は降臨する」
場の発する霊気にあてられ、蒼の説明にもほとんど上の空で頷いた。手や足の指先が痺れているのは、さっき近くの清流で身を清めたからだろう。さらに白無垢の着物を着せられ、裸足になるよう命じられた。
神子なのだから、神社の巫女さんのような赤袴を着けるのだろうと漠然と思っていたので、白無垢とは意外だった。それを何気なく蒼に伝えると、すっと目を細め「紅は神の花嫁だから」と言われた。
なるほど花嫁衣装かと納得はしたのだが、そういえば白無垢って死に装束でもあったなと思い、紅は慌ててその不吉な考えを打ち消した。
「これから始まる神降ろしの儀式には、僕は付き添うことはできない。ここからは祭司の真田と二人で行きなさい」
「兄さんは……来てくれないんだ?」
「僕は神域に立ち入ることはできない。でも安心なさい。ちゃんとここから見届けるよ。最後までね」
蒼の言葉に、なぜかうなじがぞわりと総毛立った。紅はすがるような目で蒼を見つめたが、蒼は構うことなく背中を向けて去っていった。
「さ、参りましょう」
真田に促され、紅は仕方なく視線を前方へ向けた。そして御霊代へゆっくり歩みを進めてゆく。
ほぼ垂直に切り立った崖に左右を挟まれ、紅は言いようのない息苦しさを感じた。一歩一歩進むたびに、崖が迫り来るような錯覚に襲われる。
───嫌だ、進みたくない。あそこに行きたくない。
最初は、この場所が持つ霊気に圧倒されただけだと思っていた。全身の血と肉が嫌だ嫌だと喚いているのは。だがそれは、もっと深い魂の暗部、無意識の領域から湧き上がる叫びだと気づいた。
そう、紅の身体に受け継がれた神子の『血』が、この場所に拒絶反応を起こしているのだ。それはまるで、こう言っているかのようだった。一刻も早くこの場から逃げなさい、と。
しかしもう遅い。気づけば紅は巨岩の前に跪き、恭しく頭を垂れていた。真田は低く通る声で祝詞を唱えながら、白い布で紅に目隠しをした。
視界を遮られた紅の脳裡を、『生贄』『供犠』『首を刎ねる』という血なまぐさい単語が飛び交う。しかし紅は必死に打ち消した。違う! そんなことあるはずがない。兄さんが僕をそんな目に遭わせるなんて絶対に───
「き、貴様っ! くそっ……」
紅が恐怖や疑念と闘っていると、真田の鋭い罵声と激しく揉み合う物音が聞こえた。それはやがて苦しげな呻き声へ変わり、ややあって静寂が訪れた。
何が起きたのか分からず、紅はただ困惑する。目隠しが外され、倒れた真田の傍らに立つ者を見ても、困惑は深まるばかりだった。
「御剣……どうしてここに……」
真田との格闘は、未だ傷の癒えぬ身体に大きな負担となったのか、御剣は肩を上下させて荒い呼吸を繰り返していた。
しかし紅を真っ直ぐ射抜く眼差しの強さには、いささかの衰えもない。御剣は紅を見据えたまま傍らに膝をついてその手を取り、
「大事なことを言い忘れていた。紅、俺はお前を愛している。前世からずっと、変わらず愛している」
言葉から溢れる真(まこと)の情は媚薬のごとく、紅の心身を酔い惑わせた。
「御剣……」
しかしそんな紅とは対照的に、御剣は己の言葉にも感情にも高揚した様子はなく、むしろ冷ややかな自嘲を含んだ声で続ける。
「愛のひと言で全てを水に流してもらおうなんて気は元よりない。前世でお前を犯し、挙げ句死へ追いやった罪が赦されるなんて甘いことは考えちゃいない」
御剣は紅の手を離し、咎人のごとく頭を垂れた。
「本当は、生まれ変わってまた出逢えたら、俺がこの手で幸せにするつもりだった。神子の宿命から解放し、愛していると告げて抱き締め、二度と離さないつもりだった。けれど、前世の罪が明らかになった以上、それはできない。ならばせめて、生贄などという野蛮で残酷な因襲からお前を救いたい。それが俺の、偽りなき本心だ」
そう言って立ち上がった御剣は、紅に向かって手を差し出し、
「頼む、今だけでいい。この手を取ってくれ。俺と一緒にこの血塗られた祭壇から逃げてくれ」
その真摯な訴えには、容易に抗えぬ磁力があった。
「でも僕は……」
それは口先だけの戸惑い。その証拠に、紅の右手は引き寄せられるように上がっていった。御剣の元へ。そして互いを求め合う指先が、今にも触れ合おうとしたその時だった。
「聖なる領域を穢す不届きな輩、呪われた闇の者よ、今すぐ去れ」
憤怒と憎悪でどろりと凝った声が、紅の右手を止めた。強張った指先は御剣のそれに届かず、虚しく宙を掻いてだらりと下ろされた。
一族の臣下を従えた蒼は、赤黒く爆ぜる殺気を隠そうともせず近づいてくる。しかし御剣は臆した様子もなく、紅を庇うように立ちはだかる。
「もうこんなことはやめろ。神の力で得た繁栄など長続きしないのは、歴史が証明している。神代は終わった。これからは過去の亡霊にすがるのではなく、自らの手で未来を築くべきだ。違うか?」
「過去の亡霊だと? 神の力とはすなわち天の理。それを軽んじて人の手だけで未来を築くだなど、不遜も甚だしい」
「思い上がっているのはどっちだ。お前たちは、自分が何の能力もないただの人間に生まれたという現実を認めたくないだけだ。前世の、支配者としての輝かしい記憶が忘れられず、こんなはずじゃないとガキみたいに地団駄を踏んでいる。前世の記憶を持って生まれてしまったのは不幸だったと同情はする。そのせいで野心という怪物に心を食われちまったんだからな。しかし紅を犠牲にして力を得ようとするのを、黙って見ているわけにはいかない」
御剣の声には確かに、わずかながら同情の響きがあった。紅はそこに前世のカイから連なる御剣の優しさを見たが、蒼たち暁一族にとっては屈辱以外の何ものでもなかった。
「光に見放された不浄の者が我らを見下すか! 貴様ごときが今さら何をしようが、運命は変えられん」
蒼が挑むようにそう言うと同時に、紅の身体は意識を取り戻した真田に荒っぽく抱き上げられた。そして御霊代である巨大な御影岩の前に下ろされる。
「紅ッ!」
素早く身を翻して紅を取り戻そうとした御剣は、飛びかかってきた蒼とその臣下に拘束され苦痛の生々しい呻きを漏らした。
「御剣っ……」
紅は慌てて戻ろうとしたが、真田の厳しい言葉が重い枷のごとく四肢に絡まった。
「紅様、儀式の続きを。我らの命運はあなたにかかっているのです!」
血走った眼を向けて懇願した真田は、紅の返答を聞かぬうちに祝詞の詠唱を始めた。
「謹而奉勧請(つつしみてかんじょうしたてまつる) 御社(みやしろ)なき磐境(このところ)へ降臨鎮座仕給(かうりんちんざしたま)ひて 神祇(じんぎ)の祓(はらい)可寿可寿(かずかず)を平(たいら)けく康(やす)らけく聞食(きこしめし)て───」
鬼気迫る真田の祝詞は紅の体内を侵食し、身体の自由を奪っていった。紅は意志に反して御剣に背を向け、その場に跪く。
いや、意志そのものが無に帰そうとしていた。
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT