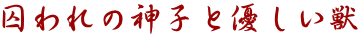
<前世哀話>・IV
「カ、カイ、やめて、やめて……」
涙声で何度懇願してもカイにそれをやめる気配はなかった。荒々しい動作で紅を裸に剥いたカイは、さらに両手を括って自由を奪うと、膝を割って脚を大きく開かせた。
赤ん坊のころ以来したことのない格好を強いられた紅は、羞恥に耐えられず目を閉じて現実から逃避した。
しかし、視覚を封じたことで他の感覚がいっそう鋭敏になり、剥き出しの局部にかかるカイの吐息や、内股を押さえている手のひらの熱さ、動くたびにカイの髪が奏でる霊妙なせせらぎなどが痛いほど感じられた。
それでも目をぎゅっと閉じて耐えていると、生温かく濡れたものがぬるりぬるりと股間を這い回り始めた。紅は「ひっ」と声を上げ、おそるおそる目を開けて視線を移した。すると薄い下生えのさらに奥処に、カイが舌を這わせているのが見えた。
「やだあっ……ああああッ」
分からない、カイが何をしようとしているのか分からない。激しい衝撃と混乱のただ中にありながら、紅はまだカイを信じる気持ちを捨てられないでいた。どんなに怖がっているか一生懸命に訴えればきっと分かってくれる。きっとやめてくれる。
「カイ、お願いだから、もうやめて。こんなことやめて。僕、怖い、怖いよ」
しかし、紅の希望は無残に粉砕された。必死の懇願に対するカイの反応は、
「うるさい。大人しくしてろ」
その言葉には微塵の優しさも労りもない。あるのはひりつくような凶暴性と苛立ち、そして焦り。その瞬間、紅の目の前は真っ暗になった。絶望という黒き帳が、視界を覆い尽くしたのだ。
舌でたっぷり濡らされたそこを、何かがゆっくりと撫で回した。それがカイの指だと気づくと同時に、ぬちっと音をたてて入り込んできた。
「くふぅっ……ぅぅっ……」
紅はかぶりを振り、腰をよじって恐るべき侵入者に抵抗しようとした。しかしそれを嘲笑うかのように、指は粘膜の筒をぬるぬると行き来する。そのたびに甘美なさざ波がざぁっと背筋を駆け上がったが、すぐに恐怖と羞恥が追いかけて上書きした。
「いやだぁ、もうやだぁ……」
紅はついに泣き出したが、とめどなく溢れる涙もカイの淫らな指遣いを鈍らせることはなかった。二本に増やした指を内部でばらばらに動かし、硬く強張った筒肉をとろかそうとする。しかし掻き回せば掻き回すほど紅のそこは頑なになり、カイの指を拒んでねちねちと軋んだ。
「力を抜け。でないと怪我するぞ」
それは非情な命令だった。心が極度の緊張に見舞われているのに、身体だけ力を抜くなんて器用な真似が紅にできるはずがない。紅は涙をまき散らして「やだ、やだ」と繰り返し、指を咥え込まされた入り口を締め付ける。
「紅、頼む。力を抜いてくれ。でないと……」
カイの口調が変わったが、そこに込められた労りや苦悩が紅の心に届くことはもはやなかった。恐怖と哀しみに支配されぼろぼろになった心は、カイに対し完全に扉を閉ざしていた。
その時、部屋の外で爆音が轟いた。それはまだ遠かったが、確実に何かが迫っている気配があった。それは、「くそっ、もう来たか」というカイの呟きからも感じられた。
カイはぎりぎりと奥歯を噛み締めたがやがて指を引き抜き、紅の膝を高く持ち上げた。そして自身の腰帯を解いて、長衣の前合わせをはだける。紅は涙の膜に覆われた瞳で、そんなカイの一挙手一投足を見つめていた。
もう何をされても何を言われても驚かない。漠然とそう思っていた紅は、次の瞬間目を剥き四肢を引きつらせた。ついさっきまでカイの容赦ない指に弄られていたその場所に、灼熱の塊が押し当てられるのを感じたのだ。
ぞわっと肌が粟立ち、唇が悲鳴の形に歪む。身体は本能的に知っていたのかもしれない。これからどんな痛みがどんな屈辱が、この身体を貫くことになるのかを。
「いっ、やああああああっーーーー!」
メリメリッと生々しい音がして身体が裂ける。それが恐怖が生んだ錯誤だと分かったからといって、恐慌が収まるわけはない。大きく広げられた脚の付け根、緩やかな曲線を描く谷間に突き立てられたものはまさに凶器めいて、生々しい威圧感を放っていた。
カイはさらに腰を進め、どっしりと太い根元までぐぶぐぶと沈めていった。
雄の欲望も本能も猛りも知らず、谷間の奥でひっそり蕾んでいた紅のそこは、ひくひくと痙攣しながら狂おしく咲いていた。
「ひっ、ひぃぃ」
壊れかけた声帯から、引きつった悲鳴が自然と滴る。尻の奥がカイの形に押し広げられるだけでなく、動きに連動して内部をずるんとこすられる感触には、未知のおぞましさがあった。
中の膜がぐちゃぐちゃにもつれ合って、引きずり出されたり押し込まれたりするたび、灼けるような痛みとともに、無数の蟲が皮膚の上を這い回るような甘美な悪寒に襲われた。
「痛いっ、痛いぃ……カイ、たすけて、カイ……」
痛みを与えている張本人に、つい助けを求めてしまう自分が哀しかった。惨めだった。まだカイを信じようとしているのか、ただ目の前にいるからすがってしまうだけなのか分からない。それでも紅はカイの名を呼び、その合間に苦しげな嗚咽を漏らした。
「カイ……ぇっ、ぇぇっ……」
するとカイはかすかに身じろいだ。それにつられ紅はふと目線を上げたが、のしかかるカイの大きな身体が光源を遮って逆光になっているため、その顔は黒く塗り潰されて表情は判別できない。
その『無』表情は、カイの心に巣食う底知れぬ何かを、奈落へと繋がる虚無を反映しているようで、紅はぞくりと慄えた。
とその時、紅の頬に温かな雫がぽつぽつと降りかかった。それが何なのか、どこから生まれたものなのか考える間もなく、カイは今のわずかな停滞を払拭するように激しく動き出した。
まるで紅の魂ごと食らい尽くすような勢いで腰を打ちつけ、紅のうぶな粘膜をえぐる。そのたびに結合部から漏れ出るぬちゃ、ぐちゅ、という淫音に、鼓膜が腐ってゆくような気がする。
紅は必死に頭を振って、その音を寄せ付けまいとした。もちろん、無駄な足掻きに過ぎなかったが。
そうしてカイの激しい抽挿に身も心も翻弄された紅は、徐々に正気を手放しつつあった。下半身は鈍い痛みに支配され、重くだるい。カイが深く突き刺すたびに、奥に甘ったるい疼きがじゅわっと広がったが、それは媚薬のように神経を麻痺させた。
「あっ、あぅ、ぅ、ぅぅっ」
いつの間にか、唇からこぼれるものが濡れた母音に変わっていた。カイの動きに合わせて自然と揺れる腰は、まるでもっと深く突いてとねだっているかのようだ。
そんな己の変化に、紅は戸惑いと怯えを覚えた。何がどうなってしまったのか分からない。けれど、けれど───
「あっ、あん、ああっ、」
ついさっきまで不遜な侵入者を頑なに拒んでいた内部(なか)が、まるで歓迎するようにとろんととろけて妖しく蠢くのが分かる。カイが動くたびにぎちぎちと軋んでいた入り口もほどけ、ぬるぬる滑って程よい摩擦を生じさせていた。やがて、
「やあっ、やだぁ、ん、あんっ」
甘えたような『やだ』に、拒絶の色は皆無だった。紅は自分が何を求めているのか分からぬまま、腰を跳ね上げつつ「やだ、やだ」を繰り返す。やがて視界は白くけぶり───
「あ、やっ、ん、深…い、やだぁ! あっ、あん!」
入ってきた時より容積を増したカイの性器が、腹の中でぐんと反り返りさらに膨れた。その先端が、これまで物欲しげにうねりつつも放置されていた奥座をこすり上げた瞬間、紅は浮遊と落下を同時に味わった。
「あああっ、あっ、あああーーーー!」
そして凄まじい勢いで尻の中に溢れる熱い液体に溺れながら、紅はゆっくりと白い闇の中に堕ちていった。
完全に意識を手放す直前、苦しげに哀しげに紅の名を呟く声と、近づきつつある破壊を知らせる爆音を聞いたような気がした。
目が覚めて最初に見たものは、黒く汚れた天井だった。ねえ、カイ、ここはどこ? 紅は強張った舌を動かそうとしたがやめた。カイはここにはいない、もう二度と会えないと直感で悟ったからだ。
起き上がろうと力を入れたが、全身が鉛を流し込まれたように重い。それでも何とか両手をついて身体を起こすと、暗い部屋の隅によく見知った顔を見つけた。
「ばあや……。あの、手を貸してもらっていい?」
紅が幼い時からあれこれ世話を焼いてくれたばあやはしかし、紅のささやかな頼みに怒りと軽蔑の視線で応じた。
「ばあや、どうし───」
「お前さんはもう、神子じゃない。暁一族が滅んだらお前さんのせいだ」
紅は言葉を失い、呆然と見返すばかり。すると錆びた蝶番がこすれる嫌な音がして、部屋の扉が開いた。現れたのは暁の長と、全てを見通す『目』の役割も果たす祭祀長、そして長の腹心の三人だった。
一族から慕われ崇敬されている長は、いつも笑顔を絶やさぬ美青年だった。しかし今は、笑みの欠片すら見当たらない。青ざめ凍りついた面ては、ばあやの視線にあったのと同じ感情が広がっていた。すなわち、怒りと侮蔑が。
「お前の軽率な行いにより、我々一族は暁天之命の守護を喪った」
淡々とした口調だからこそ、そこに凝縮された感情の激しさが際立った。紅はこくんと喉を鳴らし、
「そ、それは……どういう意味ですか?」
「お前は終夜の男に騙され、神子の資格を奪われた」
紅は何か言おうとしたが、舌が上あごに張り付いて動かない。
「神子はすなわち神の花嫁。それは処女でなくてはならない。当然だ。他の男の種に汚された不浄の者を、神が受け入れるはずもない。我らはお前を清らかな身体のまま神に嫁がせるため、これまで大事に守ってきたのだ。なのにお前は自ら終夜のけだものに近づき、気を許し、挙げ句犯され辱められた。終夜一族の復讐に、まんまと利用されたのだ」
違う、そうじゃない。だってカイははっきり言ってた。過去の怨恨など引きずってはいないと。暁一族を嫌ってはいないと。でも、でも───
「カイは、カイは……」
紅は否定しようとしたが、頭の中でもうひとつの声が響く。忘れたのか? 僕が神子だと分かった途端、カイは僕を連れ去り、十七の誕生日が過ぎるまで屋敷には帰さないと言った。それは紛れもなく、神子祈願を妨害するため。暁一族の繁栄を阻むため。
それに、俺を憎みたければ憎め、カイははっきりそう言ったではないか。神子の証である緋の六芒星に、憎悪の視線を注いでいたではないか。
「終夜一族の怨みを晴らすため、僕を……」
神子祈願の日が過ぎるまで監禁しておくつもりだったが、暁一族に居場所が知られてしまった。だから神子の身体を穢すことで、神の花嫁たる資格を奪った。全て辻褄が合う。
「そんな……そんなっ……」
最初からそのつもりで近づいてきたのかは分からない。いや、そんなことはどうでもいい。明らかなのは、カイに裏切られたということ。あの優しさは紅を懐柔するための手管だったということ。そしてカイのせいで、暁一族が窮地に立たされることになったということだ。
「お前はもはや神子ではない。その証拠に、緋の六芒星が身体から消えてしまった。今後は己の愚かさを噛み締め、穢れた身体と一族を裏切った罪を背負いながら生きていくがいい」
長の冷ややかな宣告が、紅の心を貫いた。紅は何も応えられぬまま、三人が部屋を出ていくのを呆然と見送った。
「これ以上、生き恥をさらす気かい?」
ばあやの言葉は、紅の耳に託宣のごとく響いた。それこそが、自分に残されたただひとつの道だった。紅が静かに首を振ると、ばあやは「よっこらしょ」と言って立ち上がり、部屋を出ていった。
一人になった紅は、狭い室内をぐるりと見回す。そして窓辺に近づいて外を見た。
「いいお天気……」
青空が近い。遠方には鬱蒼とした森が見える。カイと出会った森。
「カイ……」
一族から見捨てられたことより、神子の資格を失ったことより、カイに裏切られたことが哀しかった。紅は今、はっきり自覚したのだ。自分はカイを愛していたのだと。
紅は窓を開け放ち、窓枠に身を乗り出した。ここは、一族の破戒者を監禁する北の塔。暁一族は死刑を禁じている。“だから”、塔の窓は内側から開けることができた。
───次は……神子じゃなく普通の人間に生まれたいな……。
紅は平凡な来世に思いを馳せつつ、青空に向かって静かに身を投じた。
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT