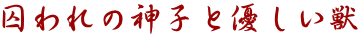
<前世哀話>・III
それから、時は穏やかに過ぎていった。意思に反して監禁されている状態なのに、紅は自分でも驚くほどすんなりとこの状況を受け入れてしまった。
家に帰りたくないと言えば嘘になる。今ごろきっと、一族のみんなは血眼になって捜しているに違いないと思うと、胸が締め付けられて苦しくなる。
それでも、カイのいない隙を見てここから脱出しようとまでは思わない。それをしてしまったら、もう二度とカイには会えないだろうと分かっていたから。
そしてもうひとつ、紅が現状を冷静に受け入れている理由。それは、十七歳の誕生日が過ぎたら解放するというカイとの約束があったからだ。
暁天之命への神子祈願という最初の大事なお務めはできないけれど、その後も神子としての仕事はたくさんあるはずだから、それをきちんとこなすことができれば問題ないと考えたのだ。
かくして紅は、カイとの生活を楽しむようになった。紅に逃げる気がないと知ると、カイは外に出ることを許した。廃墟を取り囲む森を、以前のように二人でのんびり散策する。木の実を採り、花を摘み、魚を釣る。
カイは時々、「信じられない」と呟いた。あんなことを仕出かした俺が、またこうしてお前と一緒に森を歩けるなんて、と。そのたびに紅はいたずらっぽく微笑んで、「あんなことって、カイはどんな悪いことをしたんだ?」とからかったのだった。
そして十日が過ぎた。その夜は、完全な闇夜だった。空は一縷の月明かりも許さないほどの分厚い雲に覆われ、灯火がなければ己の身体の輪郭すら分からないほどの晦冥に支配されていた。
暁一族は、太陽と光明を好み闇を厭う。紅も例外ではなく、呼吸するたびに濃密な闇が体内に侵入するような錯覚に息苦しさを覚え、明かりをつけてそっと寝床を後にした。カイの部屋へ行くためだ。
これまでも何度か、眠れぬ夜にカイの部屋を訪れた。紅に用意されたふかふかの布団とは対照的に、カイの寝床は粗末な藁敷きだった。
それでも紅は、カイの傍にいる方がぐっすり眠れたのだ。抱き締めてもらえるわけでもなく、ただ隣に寝ているだけなのに、カイの呼吸と気配を感じているだけで不思議と心が安らぐのだ。しかし、
「カイ、入るよ。また一緒に寝───」
「待て。今夜は駄目だ」
細く開けた扉の隙間から届いた断固たる拒絶に、紅は驚きを隠せない。こんな風に厳しくはね付けられたのは初めてだ。詰問も自然と涙声になってしまう。
「どうしてっ? どうしてだめなんだよ」
「光の届かぬ完全な夜だからだ」
もちろん紅にはその言葉が理解できず、扉を大きく開けて室内に踏み込む。そしてもう一度ちゃんと理由を質すため、カイの元に近づこうとした。が───
「……あなたは、誰?」
妖しく揺れる燭影を背景に悠然と立つは、高貴な夜と妖艶な闇の申し子とも言うべき美青年。我を忘れてその圧倒的な美に耽溺した紅は、やがてぶるっと頭を振って、
「あなたは……カイ? カイなんだね?」
「……ああ」
姿形は変わっても、ぶっきらぼうな返答はそのままだった。それが妙に可笑しくて、嬉しくて、紅は弾む心そのままぴょんぴょん跳ねつつ駆け寄った。そして正面から凝視する。
血に飢えた緋色の眼は、闇が凝結した黒水晶の瞳に。ざんばらの蓬髪は、肩口からさらりと流れる翠翹の髪に。獣毛に覆われていた手足は、しなやかな皮膚と逞しい筋肉をまとった伸びやかな四肢に。何もかもが鑑賞に値するほど美しい。
「これが、カイの本当の姿なんだね」
暁一族の神子祈願により半人半獣の姿に落とされた終夜一族の生き残り。その本来の姿を、紅は今目にしているのだ。
しかしカイは首を振ってはっきり否定した。
「いや、違う。お前の知っている半人半獣が、本当の俺の姿だ。今宵は月明かりも届かぬ完全な闇夜。この時ばかりは、暁天之命の神霊力も効力を失うから人間の姿になるが、日が昇ればまた元通り。あの醜い化け物に戻る。ぬか喜びさせて悪かったな」
その時紅は、なぜカイがこの姿を見られるのを嫌がったのか分かったような気がした。紅はこみ上げる切なさを怒ったような表情で隠してカイに詰め寄り、
「ぬか喜びだなんてなに言ってるんだよ。あの赤い目をした毛むくじゃらのカイも僕は大好きなんだよ。姿形は変わっても、中身は変わらない。どっちのカイも、僕にとっては優しくて強くてかっこいいカイなんだ。分かった?」
驚きを隠さずじっと見返すばかりのカイに、紅はぐいと顔を近づけ、
「返事はっ?」
「あ、ああ」
間の抜けた返事をするカイに紅は「よし」と言って頷き、腕を引いた。
「そうだ、今夜は僕の布団で一緒に寝ようよ。せっかくその姿なんだから」
「ち、ちょっと待て。それは……」
激しく狼狽するカイを部屋に引っ張り込むと、紅はさっさと布団に潜り込んだ。そして「早くぅ」と甘えた声を出して隣をぽんぽんと叩く。
カイは困ったような怒ったような複雑な表情でしばし見下ろしていたが、やがて小さな溜め息をついて紅の隣に身体を滑り込ませた。
「それじゃ、おやすみなさい」
紅が挨拶すると、「ああ」と神妙な相槌が返ってきた。
───なんだか、今夜はぐっすり眠れそう。
紅は胸の奥にくすぐったいものを感じつつ、幸せな眠りに沈み込んでいった。
それからまた、十日が過ぎた。カイは敢えて指摘せず紅も何も言わなかったが、十七歳の誕生日が明後日に迫っていた。しかし二人の生活に目立った変化はなく、順調、平穏そのものだった。
そんな日常でたったひとつ、紅が気になるカイの振る舞いがあった。カイは時折、紅の首筋にともった六芒星をじっと見つめることがあったのだ。
その険のある眼差しに攻撃的な熱を感じ取った紅は、カイの赤い瞳が誘発する錯覚だと分かっていても、肌が灼かれるような痛みを覚えずにはいられなかった。
やはりカイは暁一族を怨んでいるのだ、一族に繁栄をもたらす神子を憎んでいるのだ。しかし紅はそれを口にすることはしなかった。できなかった。今のこの平穏が、危うい均衡の上に成り立っていることを分かっていたからだ。余計なことを言って、カイとの良好な関係を崩したくなかった。
いずれにせよあと二日で自分は十七歳になる。そうすればカイは約束通り、自分を一族の元へ返してくれるだろう。その後は神子としての務めを果たしつつ、また以前のように森でカイと魚釣りをしたり花を摘んだりすればいい。
大丈夫、きっと全てうまくいく。紅は自分にそう言い聞かせ、もやもやとした不安の雲を追い払ったのだ。
そして夜が訪れた。その夜は新月で、夜空は全き闇に包まれていた。天の理は暁天之命の呪縛を一時的に解き、カイは再び美しい青年の姿に変じて紅と晩餐を楽しんでいた。
「う、うん。なかなか美味しいね。この苦味が何とも……」
「無理するな。頬が引きつってるぞ」
カイに痛い指摘をされ、紅はむっつり黙って手にしていた杯を睨んだ。
たまにカイが晩酌しているのを見ていた紅は、自分も飲んでみたいと駄々を捏ねた。そのたびにお子様は駄目だと一蹴されたのだが、しつこくねばってようやく今夜、芳醇な酒気を漂わせる液体をほんの少し分けてもらった。
そしてうきうきしつつ口に入れたのだが、途端に舌はぴりぴりするし、鼻は痛くなるし、味は苦いだけだし、調子に乗って大人ぶったことをひたすら後悔した。
しかしまずいと言えば、酒の味も分からぬお子様扱いされるに違いない。それは悔しかったから、再び杯に口をつけ、
「こういうのは、じっくり味わうものなんだよ」
なんて言いつつ、舌先でちろちろ舐めるようにして飲んだ。カイは笑いをこらえているようだったが、気にせずちびりちびりと進める。そうするうちに鳩尾の辺りが熱くなって、頭がふわふわしてきた。
「カイ~、なんか頭がふわふわしてきた」
そのまま正直に告げると、カイはやれやれと言わんばかりに肩をすくめ、
「たったこれしきの酒で酔うとはな。ほら、もう寝ろ」
「酔ってないっ」
「分かった分かった。でももういい時間だ。俺もそろそろ休む。さ、お前も──」
カイはそう言って手を伸ばしてきたが、途中でぴたりと止まった。
「カイ? どうしたの?」
宙で静止したままの手には太い筋が浮かび上がって、尋常ならざる緊張を伝えていた。わけが分からぬながらも、紅の身体もつられて強張ってしまう。しかし、
「……結界の森に何か触れたようだ」
この隠れ処の周囲には、方向感覚を狂わせる強力な磁場の結界がカイによって張り巡らされていた。だから、盗賊などに見つかることはなかったのだが───
「誰かが入ってきたということ?」
「いや……おそらく獣が迷い込んだのだろう。ごくまれにだが、死に場所を求めた手負いの獣が入り込んでくることがある」
そう言うカイの声はひどく張り詰めて、表情も険しさを増していった。手負いの獣が迷い込んだだけにしては、反応が過剰だった。紅は言葉にならぬ不安を覚え、すがるようにカイの顔を見上げた。するとカイは淡く笑って紅の頭を撫で、
「お前は先に寝ていろ。俺は様子を見てくる」
「一人で大丈夫?」
「ああ。ちゃんと武器を持っていくから安心しろ。俺がいない隙に酒を飲むんじゃないぞ。お子様はいい子で寝てろ」
からかいを含んだ軽口は、紅の不安を払拭するためのものだと分かっていた。だから紅は敢えて膨れっ面をしてみせた。
「なんだ、そのおたふくみたいなツラは」
「生まれつきですっ」
「はは、そうか。じゃ、行ってくる」
そう言って、カイは闇に溶けるように出ていった。遠ざかる背中は、ひどく強張っているように見えた。
「カイ、早く戻ってきて……」
紅は弱々しい声で呟くと、布団に潜り込んで不安を身体ごと覆い隠した。
「んっ……カイ……?」
短い眠りからふと目を覚ました紅は、闇がこれまでにない異質なざわめきを伝えていることに気づいた。のそのそと身体を起こして周囲を見回したが、特に変わったところはない。部屋は変わらず静寂に満たされていた。
しかし、静寂を脅かす何かが潜んでいることを否定することはできなかった。部屋の外、感覚の届かぬ遠くでそれは蠢いている。
紅は不安に耐えられず、もう一度カイの名を呼んだ。すると部屋の奥に凝固した闇がゆっくり溶け出すように黒い影が動き、やがて優雅なシルエットを結んだ。
紅はようやくほっと安堵の息をつき、見慣れた半人半獣の巨体とは異なるもう一人のカイに手を差し伸べた。
その手は、優しく握ってもらえるはずだった。大きな手でふわりと包み込み、安心感と温もりを与えてくれるはずだった。しかし安息を求めた手は放置され、虚しく宙を彷徨う。その時ようやく紅は、目の前にいるカイがいつもと違う空気をまとっていることに気づいた。
「カイ、どうしたの?」
寝床の傍らには、全き闇を嫌う紅のために小さな常夜灯がともしてある。その儚い光に照らされたカイの顔を覗き込んだ瞬間、紅の背筋はざわりと総毛立った。
悠久の星空を想わせる煌きを湛えた美しい黒瞳は、まるで奈落の底に繋がっているかのように底知れぬ闇を孕んでこちらを見下ろしている。対象物をことごとくただの“物”へと貶める絶対零度の視線を浴びた紅は、言葉を失いただ呆然と見返すしかできなかった。
これは、本当にカイなのだろうか。誰もが怖れ怯える醜怪な半人半獣の姿をしている時でさえ、こんな戦慄を覚えたことはなかった。血の色をした人ならざる双眸にも、温かな人間性を感じ取ることができたのだ。なのに今は───
「カイ? な、なにを……」
不毛な自問自答は、半ば暴力的に断ち切られた。カイの手に肩を掴まれ、そのまま布団の上に押し付けられる。
カイがこれから何をしようとしているのか分からない。しかし紅はその瞬間、これまで築いてきた大事なものが崩壊する音を、確かに聞いたのだった。
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT