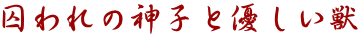
<前世哀話>・II
それから、二人のささやかな交流が始まった。紅は何かと理由を作っては森を訪れ、カイと会った。カイは森を熟知しており、紫涙草はもちろん、もっと珍しい草花やキノコ、木の実を見つけては紅に贈ってくれた。また、時には川で釣りをして、獲れた魚をその場で炙って一緒に食べたりもした。
カイは自分の方から親しげに近づくそぶりは見せず、相変わらずぶっきらぼうで寡黙だった。だから会話といっても紅が一方的に話すだけで、カイは聞き役専門。とはいえ、紅の言葉を疎かにすることは決してなかった。
時折ぽつりと挟む意見は実に思慮深く、示唆に富んでおり、彼が該博な知識と教養の持ち主であることは明らかだった。
と同時に、カイはとても優しかった。それも、これまで紅が家族や一族の人間から毎日のように浴びせられてきた“見える”優しさとは違う、もっと奥床しい優しさだった。
紅の周りにいる一族の者たちは、紅が何を欲しているか訊ねて、それを実現することで優しさを表そうとする。しかしカイは、紅の気持ちを静かに汲み取ってそれにただ寄り添おうとする。紅の喜びや痛み、哀しみ、孤独などあらゆる心の動きに共感しようとしてくれるのだ。
それは、カイ自身が豊かな情感と深い思い遣りの持ち主だからこそできること。紅の言葉にじっと耳を傾け、あの魔棲の双眸で『お前の気持ちはよく解るよ』と伝える。それだけで紅は救われたような気持ちになった。
そして紅は、自分がカイに惹かれ始めていることに気づいた。心のどこかでずっと一緒にいたいと思いつつ、それは叶わぬ望みであることも知っていた。打ち明ければ間違いなく、カイを困らせ苦しめることになることも。
だから紅は、この気持ちを恋と呼ぶべきなのか愛と呼ぶべきなのか、それとも一時的な気の迷いに過ぎないのか自分でも答えが出せぬまま、心の奥底に閉じ込めて鍵を掛けたのだった。
「来月から、しばらく会えなくなっちゃうんだ」
二人が親しく会うようになって、もうすぐ三月が経とうという頃だった。いつものように森を散策して、ばあやに作らせた弁当を二人仲良く分けて食べた。
そして食事の後の寛いだひととき。紅はさらりと打ち明けた。自分の言葉がどれほど重大な意味を持つのか知らぬまま。
「一族の大事な大事な儀式があってね。その準備で、今からみんな大騒ぎなんだよ」
「そうか。お前も手伝わなくていいのか? こんなところで呑気に遊んでいて」
カイの問いに、紅はちょんと胸を張り、
「僕はいいんだ。儀式当日まで、ちゃんと体調さえ整えておけば」
「……どういうことだ?」
「だって、僕は神子だもん。儀式上の作法は小さい頃から何度も教わってるし。だからちゃんと───」
「神子……だと?」
カイの声色が変わった。顔に巻かれた黒い布のせいで表情が分からない分、その声や口調から心情の変化を推し量ることができるようになっていた。紅は続く言葉を呑み込んで頷き、
「う、うん。そっか、カイには言ってなかったっけ。僕、一族の神子なんだ」
「まさかお前が『暁の乙女』なのか? しかし、神子は代々女性が務めていたはずでは」
「そう、ほとんどが女性だったけど、男の神子も数は少ないけどいたみたいだよ。ほら見て。ここに神子のしるし、六芒星の痣があるだろ? 僕はれっきとした神子なんだ」
襟元を大きくはだけて、首の付け根にある『暁の星』をカイに見せた。きっと、これで信じてくれるはずだ。
果たしてカイは、ごうごうと音が聞こえそうなほど灼然と瞳を燃え上がらせて、紅の白く滑らかな首筋を、そこに刻まれた赤い六芒星を凝視し続けた。
「そんな……バカな……」
「カイ? どうしたの?」
「そんなことが……まさかそんなことがっ……」
身体の奥から湧き上がる感情に突き動かされるように、カイは勢いよく立ち上がった。紅は驚いてその巨躯を見上げたが、カイは自分の思考に没頭しきっているようで、爛々と輝く双眸を中空に据えたまま微動だにしない。時折「まさか、そんな」と呟くだけで。やがて、
「紅、ひとつ教えてくれ。お前は来月で十七歳になるんだな?」
「え? うん、そうだよ。やっと神子として一族の役に立てるんだ」
「……そうか、分かった。紅、すまない。大事な用を思い出した。今日はこれで帰らせてもらう」
カイのこんな切羽詰まった声を聞くのは初めてだった。色々質したいこともあったし、何よりもう少し一緒にいたかったのだが、我がままは控えねばと自戒した。
自分は大事な神子として、一族から甘やかされているという自覚はあった。それと同じ感覚で我を通したら、カイに呆れられてしまう。
「そか。用事があるなら仕方ないね。でも、あの、また会ってくれるよね?」
なぜだか分からないが、聞かずにはいられなかった。紅の懇願にも似た問いかけに、カイはまだ思考に沈んだ様子で虚ろに頷いた。そして紅の方を見もせずに帰っていった。
その二日後。紅はいつものように森へ行く準備をしていた。もちろん、カイに会うためだ。しかし、これまでにないほど厳しい顔をしたばあやが、まるで行く手を阻むかのように紅の前に立った。
「紅様。そろそろお一人で森をうろつくのはおやめになってくださいまし。来月には、大事な儀式が控えているのでございますよ。お屋敷の中で静かに瞑想などを───」
「ばあや、どいて。瞑想なら森の中でやってるから。前も言っただろう? 森の呼吸を感じながらの方が無になれるんだ。儀式の準備でざわついてる屋敷より、ずっと落ち着ける」
紅のもっともな言い分に対し、ばあやは声をさらに低めて、
「まさかとは思いますが、森で誰かに会っているのではないでしょうね」
「な、なに言ってるんだ。そんなことあるはずないだろ。とにかく、神子としての務めはちゃんと果たすから。儀式が終わってからも、森通いは続けるからねっ」
紅は強い口調でそう言って、ばあやの身体を押しのけた。そして屋敷を後にする。ばあやはその背中を見つめながら、薄笑いを浮かべた。
「儀式が終わったら、何もかも終わるのですよ、紅様……」
「あっ、カイ! もう来てたんだ」
森の入り口から少し入ったところにカイの姿が見えた。前回の別れ際の尋常でない様子から、ちゃんと来てくれるか不安があっただけに、紅は心底嬉しかった。ぱたぱたと足音も軽く駆け寄り、すでに見慣れたその巨躯に飛びついた。
「ねえねえ、今日は久しぶりに川釣りをしようよ。それから───」
無邪気にじゃれつく紅の肩に、カイの大きな毛むくじゃらの手が置かれた。その時、
「終夜の悪鬼め! 紅様から離れろ!」
怒りと憎悪に満ちた鋭い叫びが背中に突き刺さった。紅が驚いて振り返ると、森の入り口に剣を構えた複数の男がいた。みな暁一族の私兵だ。
紅は「どうして…」と呟いたものの、ばあやに誰かと会っていることを勘付かれたに違いないとすぐに察した。屋敷を出た時から、後を付けられていたのだろう。
紅は思わずカイにすがりついた。それが、屋敷には戻りたくない、カイと一緒にいたいという意思表示だったのかは自分でも分からない。
いや、恐らくそうではないだろう。こちらに向けられた剣の切っ先や、男たちの憎悪にぎらつく顔がただ怖かっただけ。暁一族よりカイを選ぶとか、そんな大それたことは考えてもいなかった。しかし、
「紅、俺にしっかり掴まっていろ」
その命令がどんな思惑に基づくものなのか分からぬまま、紅は頷いてカイの身体にぎゅっと抱きついた。次の瞬間、
「あっ、待て! 追えっ、早く追え!!」
男たちの焦りを含んだ怒号が、あっという間に遠のいてゆく。紅は目をつむり、ひたすらカイにしがみついた。全身に受ける風と味わったことのない浮遊感から、カイが超人的な飛翔を繰り返し森を駆け抜けていることが分かった。
初めは何がなんだか分からず全てをカイに委ねていた紅だったが、徐々に不安が湧き上がってきた。果たしてこれでよかったのだろうか。さっきの私兵は、自分を助けに来たのだ。それは分かりきったこと。暁の者が、神子を害するはずがない。
ならば自分は今、何から逃げているのだろうか───
「紅、着いたぞ」
カイの言葉で我に返ると、確かに両足がしっかり地に着いていた。しかし安堵の溜め息など出るはずもない。
紅の眼前にそびえるのは朽ちかけた廃墟。かつては要塞か領主の居城だったのか、大砲の筒が空に向かっていくつも口を開けていた。むろん、今は使い物にならないだろうが。
「ね、カイ。ここは……どこ?」
紅の当然の疑問を無言の背中で跳ね返し、カイはさっさと中に入っていった。紅は慌ててその後を追う。廃虚の中は広く複雑で、迷路さながらに紅を幻惑した。
「ここは俺の棲家だ。見かけはこんなだが、中はそこそこ快適だ」
さっきの質問に答えたカイは、重厚な石造りの扉を開けた。確かに中は広くて快適そうだった。床には毛足の長い絨毯が敷かれ、作りつけの薪ストーブもある。
紅は「うわあ」と声を上げ、室内をぐるりと見回した。漠然とだが、カイはもっと野性的な塒(ねぐら)に住んでいると思っていたのだ。
「すてきなお家だね、カイ」
紅が振り向いてそう言うと同時に、扉がゴォンと重低音を響かせつつ閉められた。その瞬間、世界から切り離されたような感覚に囚われ、薄れかけていた不安が再び頭をもたげた。
紅は身体が震えるのを抑えることができず、ただ呆然と扉を見つめる。ややあって、
「カイ……ここから出して」
カイはこれまで、紅の望みを全て叶えてくれた。甘いものが食べたいと言えば、舌がとろけるような木の実を採ってきてくれた。眠いと言えば柔らかな叢で一緒に昼寝をしてくれた。お気に入りのブローチを失くしたと言えば、石を磨いて新しいものを作ってくれた。
なのに───
「駄目だ。お前は暫くここにいろ」
「どっ、どういうこと?! 暫くっていつまで?!」
「お前の十七の誕生日が過ぎるまでだ」
「そんなっ……僕は十七の誕生日に神子として、暁天之命をお迎えするという大役を果たさなければならないんだ! 帰して、僕を今すぐ帰して!」
紅の必死の懇願にも、心を動かされた気配はない。カイは黙って身を翻し、奥の部屋へ行こうとした。紅は追いかけようとしたが、足が竦んで動けない。予想だにしなかった展開に、神経回路が混乱をきたしてしまったようだ。
「やっぱり……やっぱりカイは僕たち暁一族を怨んでるんだ! だからこんなことをして、暁天之命への祈願をさせまいと……」
涙ながらの告発を、カイは真正面から受け入れた。
「ああ。そう思ってくれて構わない。俺を憎みたければ憎め、紅」
そう言って奥の続き部屋へ行ってしまったカイの残影に、紅はぽつりと話しかけた。
「せめて否定しろよぉ、カイのばか……」
その夜、紅は泣き明かした。知らない場所に独りぼっちの淋しさや不安ももちろんあったが、何よりカイに裏切られたことの方が哀しかった。
そして空が白み始めたころ、泣き疲れてようやく寝入り、目が覚めると朝食の用意がしてあった。食事には、美しい白百合の花が添えられていた。
「カイ……」
いつだったか、カイが摘んできてくれたことがあった。鋭い鉤爪で花を傷つけないよう、苦心しつつ抱えている姿が何だか可愛くて、愛おしくて、胸の奥が温かくなったのを思い出す。紅は白百合を手にすると奥の扉へ近づき、ノックをした。
「カイ、いる?」
返事はなかったが、紅は構わず続けた。
「あの、お花ありがとう。それから、一人で食べるの淋しいからこっちに来て」
扉の向こうから、濃厚な戸惑いが伝わってくる。やがて、扉が開いた。そこから現れたカイは、力なく項垂れていた。こんなに消耗しきった彼は初めて見る。
紅は思わず駆け寄って「具合が悪い?」と訊ね、うんと背伸びをして額に手を当てた。が、
「う~ん……毛むくじゃらで熱があるかどうかわかんないや」
そんな無邪気すぎる紅にカイは驚きを隠さず、困惑に揺れる灼熱の瞳で見つめ、
「お前、俺が憎くないのか?」
「正直分からない。裏切られたのは哀しいし家に帰りたいけれど、それとカイが憎いという気持ちがどうしても繋がらない」
紅は素直に答えると、もう一度「この花ありがとう」と言って微笑った。カイはふいと顔を背けたが、
「何か……足りないものや欲しいものがあったら遠慮なく言え。いいな?」
その言葉は限りなく優しく、そしてかすかに震えていた。
BACK TOP 囚われの神子INDEX NEXT