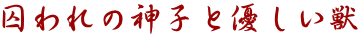
誰かが、僕の名前を呼んでいる。
───紅、紅……
その姿は闇に沈んで見えない。けれど僕は“彼”を知っている。そんな根拠のない確信に、僕の胸はざわざわと騒いだ。
───紅、気をつけろ。お前は十七歳の誕生日に……
続く言葉が耳に届くより先に、僕は眠りの浅瀬からゆっくりと浮上した。
目が覚めてもなお、“彼”の甘くかすれたテノールが、耳の奥処に漂っているような気がした。
一話 <神威紅──16歳と11カ月3日>
「……また、あの夢だ」
神威紅(かむい・こう)はのっそりと起き上がり、やつれたため息をひとつ、吐いた。いつごろからだろう、数日おきに同じ夢を見ては、その忠告めいた内容にもやもやした鉛色の不安を感じるようになったのは。
夢の声には、聞き覚えがあった。にもかかわらず、声と一致する人物の顔は思い浮かばない。紅の周りにいる人間、これまで会ったことのある人間の中に、その声の持ち主を見つけることはできなかった。それが、さらに不安を濃くする原因ともなっていた。
しかし紅はぶるっと頭を振り、「気にするな」と自分に言い聞かせた。たかが夢じゃないか、と。
夢の声はいつも、十七歳の誕生日に何かが起きるとほのめかしていたけれど、その日はたぶん、兄と行き付けのイタリアンレストランで食事しているだろう。紅の誕生日は毎年、そうやって過ごしてきたのだ。
唯一の肉親であり、誰よりも紅を大事にしてくれる優しい兄、神威蒼(かむい・そう)。そんな彼と兄弟水入らずで過ごすひとときに、物騒なことが起きるとは思えない。紅は勢いよくカーテンを開けて澄んだ朝日に身を浸し、不安の残滓を払った。
「げっ、もうこんな時間!」
時計を確認すると同時に紅は声を上げ、ベッドから飛び下りてばたばたと着替えを始めた。制服と格闘すること数分。紅は何とか身支度を整え、朝食と弁当をこしらえるため部屋を出てキッチンへ向かう。
部屋の机には最近の流行には程遠い大きくて不恰好な眼鏡が置きっぱなしになっているが、これは視力を矯正するためではなく、紅の“顔を隠す”ためのものだから、掛けなくても別段不自由はなかった。
成績は中の中、これといった特技や才能もない紅が唯一得意なのが料理だ。朝晩の食事はもちろん、自分と兄の分の弁当を作る。
兄はいつも、紅の料理を少し大げさなくらい褒めてくれた。その賛辞には、家事のほとんどを引き受けている紅に対する感謝の念が上乗せされていると分かってはいたが、微笑みとともに「すごくおいしいよ、紅」と言われれば、やはり嬉しさを感じずにはいられない。
そしてまた、「おいしいよ」の一言が聞きたくて、紅は早起きして食事作りに精を出すのだ。
「おはよう、紅。ああ、いい匂いだなあ。朝から元気が出るよ」
「おはよ、兄さん。ちょっと寝坊しちゃったけど、何とか間に合わせるから」
寝起きに慌てて制服と格闘していた人間とは思えないほど落ち着いた手際で、紅は弁当箱に色とりどりのおかずを詰める。すると蒼はゆっくりと近づき、その髪を撫で、
「寝癖、取れてないぞ」
「あ、うん。時間がなくて」
朝日を浴びて琥珀色に煌く蒼の髪や瞳が眩しくて、紅は目を細めつつも見入ってしまう。墨を刷いたような黒髪黒瞳(こくどう)の紅にとって、色彩と光輝に溢れた兄の容姿は憧憬の的だった。
兄、神威蒼は二十八歳。両親を幼いころに亡くした紅を、親に代わって育ててくれた。彼は紅が通う明神学園高校で、日本史を教えている。爽やかな笑顔に涼やかな美貌。加えて人柄は温和、講義は熱心とくれば、生徒に人気が出ない方がおかしい。
そんな蒼はいつも、人の輪の中心にいた。肉親のひいき目かもしれないけれど、紅には兄が惑星に取り囲まれた太陽のように見えた。つまりは、自慢の兄というわけだ。
「そら、綺麗に直ったぞ」
取り留めのない思考を巡らせている間に、蒼が濡れたタオルで寝癖を直してくれた。紅は一応お礼を言ったが、顔に掛かる長い前髪の隙間から兄を見上げて肩をすくめ、
「僕の寝癖なんて直したって意味ないよ。どうせ、誰も見てないし」
「こら。また『どうせ』と言う。その口癖はやめなさいと言ったはずだぞ」
「でも事実だから。クラスメートも、僕を見ると気が滅入るってさ。あれで神威先生の弟なんて信じられない、だって。ま、確かに。僕と兄さん、ぜんぜん似てないもんな」
紅が自虐的に笑い飛ばすと、蒼はうっすら目を細めて、
「僕は、紅が弟で本当によかったと思っている。本当に」
本心からのものと分かる深みのある声でそう言った。
「おはよう」「連休何してたぁ?」「バイト先の友達とね……」───休み明けの校内に、生徒らの明るい声が交錯する。しかしその声は、紅の元までは届かない。まるで見えない壁に囲まれているかのように、全て紅を避けて通っていった。
蒼の存在が歯止めになっているのだろう、積極的ないじめがあるわけではなかった。あるのは完全な無視。さらに遠回しの嗤笑や蔑み、他愛もない陰口。それらが常に紅の周囲に滞留していた。
学校という集団生活において、『暗い』というレッテルが発揮する負の効果は計り知れない。暗いやつ、ノリが悪いやつ、面白くないやつは早々に見限られ、友人関係の網目からふるい落とされてしまう。紅に、親しく言葉を交わす友人は一人もいなかった。
それも仕方ないよな、と紅はまるで他人事のように考えていた。不細工な黒縁眼鏡と長い前髪で隠された顔が、笑みを浮かべることはまずない。しかも、休み時間はずっと本を読んでいるのだから、声を掛けようという気も起こらないだろう。結果、紅の周囲には喧騒を寄せ付けぬエアポケットのような空間が出来上がった。
それはそれで構わないと、紅はとうに割り切っていた。どうせ、高校時代の友人関係なんて一過性のもの。集団の中で孤立するのが怖いから一緒にいるだけで、卒業してしまえば連絡も取らなくなるだろう。
最初から一人でいることを選択してしまえば、あとは余計な人間関係に煩わされなくて済む。信じて裏切られ、傷つくという経験をしなくて済む。
そう、紅はなぜか昔から他人を信用することができず、特に男性に対する猜疑心が強かった。
思い出す限り、信頼していた人に手酷く裏切られた記憶はなかったが、なぜかちょっとでも優しくされると身構えてしまうのだ。この人もきっと、僕を裏切るに違いない、と。
他人と心を通わすことのできない自分には、情緒的な何かが欠けているのではないか、いや、ただの自意識過剰なのかと思い悩んだこともかつてはあった。親友と呼べる人間がいないことに、淋しさを感じたこともあった。しかし兄と暮らす日々が、そんな紅のささくれ立った心を穏やかに均してくれたのだ。
そして今では、兄さえいてくれればいいと思えるようになった。友だちもいらない。まして恋人なんて。他人は裏切るけれど、兄は裏切らないのだから。絶対に。
「ねえねえ、聞いた? うちのクラスに転校生が来るって」
興奮で上ずった声に、紅のモノローグは断ち切られた。もちろん、紅への問いかけではない。周囲の会話が耳に入ってきただけだ。
「へえ。男? 女?」
「男だって。こんな時期に珍しいよね。でもちょっと楽しみ───」
すぐに興味を失った紅は、窓の外に目を向けた。クラスに転校生がやってくる。誰もがわくわくするような出来事なのだろうが、紅には何の関係もない───はずだった。
「ベルはとっくに鳴ってるぞ。席に着きなさい」
担任が教室に入ってくると、転校生に対する期待感はさらに高まった。大抵の期待は裏切られるものと相場が決まっているのに、それでもみな懲りもせず勝手に期待を重ね、勝手に幻滅するのだ。
期待される方はいい迷惑だよな、と見ず知らずの転校生につい同情してしまうのは、これまで紅もそういった経験を嫌というほどしてきたからだ。神威蒼の弟は、兄に似て爽やかな美少年に違いないという期待が、幻滅に変わる瞬間を何度も目の当たりにしてきたのだ。
しかし、そんな同情は不要だったと紅はすぐに思い知ることになる。ごく稀にだが、現実が期待を超えることがあるのだ。そう、ちょうど今この瞬間のように。
「今日からみんなの新しい仲間になった、転校生の御剣君だ」
担任の紹介に導かれるように、彼が教室に入ってきた。教室中の視線が集中する。と同時に、好奇心と高揚感で波打っていた室内の空気がすーっと凪いだ。
教師は驚いた様子で室内を見渡す。おそらく、女子の甲高い嬌声を覚悟していたのだろう。なのに、嬌声はおろか囁きすら聞こえない。不気味なほどの静寂が支配したが、そこには危うい熱気が淀んでいた。ちょっとしたきっかけで暴走する、感情の熱が。
「御剣戒(みつるぎ・かい)です」
教卓の傍らでそっけない自己紹介をした転校生、御剣戒は、神の鑿で丹念に彫られた彫刻を想わせる美形だった。クラス中が息を呑み、その鑑賞に没頭する。それがゆえの静寂だった。
それは紅も同じだったが、外見以外にもうひとつ、その声にも心惹かれるものがあった。そう、転校生の声は、紅の夢で忠告を繰り返す声に似ていたのだ。
もちろん、だからといって二つの声をイコールで結ぶような単純な思考回路はしていない。甘くかすかに毛羽立った極上のテノールという共通項が、耳を惑わせただけ。紅は軽く頭を振って感覚をリセットしてから、再び転校生、御剣戒を眺めた。
すらりとした長身に、濃紺のブレザーがよく似合う。引き締まった身体は、制服の上からでもしなやかな筋肉の躍動が想像できた。黒髪黒瞳は紅と同じだが、夜の上にさらに闇を重ねたような純黒のそれはただ美しく、『黒』が持つ禍々しさと高貴さを兼ね備えていた。
名前を名乗った後はひと言も発していないのに、その圧倒的な存在感は百万の言葉を費やすより雄弁だった。
長めの前髪が落とす影は妖しく、神秘的でありながらどこか獰猛さも感じさせる。まるで黒豹のようだ、と紅は思った。そう、群れなす動物たちを高みから見下ろす孤高の黒豹そのものだった。
ようやく鑑賞を終えた女子生徒たちが一斉に騒ぎ出した。しかし御剣当人は我関せずで微動だにしない。あくまで悠然と構えていたが、不動を保ちつつも切れ長の目だけは、何かを捜すようにゆっくり左右に動いていることに紅はふと気づいた。
───何を……捜しているんだろう。
俯いたまま髪の隙間から御剣を窺っていた紅だったが、好奇心から顔を上げて真っ直ぐ視線を向けた。すると、左右に揺らいでいた御剣の瞳がぴたりと止まった。
「え……?」
目と目が合った瞬間、教室内の喧噪は遠のき背景は霞む。輪郭を失った世界の中で、ただ御剣だけが確かな存在感と鮮烈な色彩をまとって立っていた。
底知れぬ深みを孕んだ瞳の中に、瞬間的に燃え上がる緋色の感情を見た紅は、まるで皮膚が灼かれるかのような錯覚に襲われた。
───僕を捜していた……なんてことあるはずないよな。
突拍子もない妄想だと自嘲しつつも、心臓が跳ねてしまう。送り出された熱い血が全身に巡り、指先まで火照る。後から考えれば、見つめ合っていたのはほんの数秒だったろう。しかしそこに凝縮された何かが、玉響の時をひどく長いものに感じさせた。
「ええと、それじゃ取り敢えず御剣君はあの席に座ってもらおうかな」
御剣の視線が外されると同時に、教師の声が耳に届いた。視線の呪縛から解放された紅はほっと息をついたが、教師が示した席が自分の隣であることに気づき、再び身体を強張らせた。
───うわ、何か緊張する……。
しかし御剣は、そんな紅の緊張をさらりとかわすようにもうひとつの空席を指差し、
「あの一番後ろの席に座らせてください」
そして教師の許可を待たずさっさとそちらへ向かってしまった。もちろん、紅になど見向きもしない。
「当然よねえ」
「眼鏡妖怪の隣なんて、誰だって嫌だよな」
クラスメートたちの馬鹿にしたような囁きや忍び笑いには慣れている。紅はそれらに和するように、喉の奥でくくっと笑った。
───ちょっと目が合っただけなのに。何を期待してたんだ、僕は。
紅は小さく肩をすくめると、この美しい転校生のことを早々に頭の中から追い出した。
御剣の一途な視線が自分の背中に注がれていることに、もちろん気づくはずもなかった。
NOVEL INDEX TOP 囚われの神子INDEX NEXT