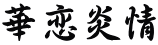
─KAREN ENJOU─
九、懊花の章
絢が受ける衝撃を見越していたのか、苑山は構わず話を進めた。
「乙耶は凛として雅やかな美しい青年だった。もともと儂の内弟子で、尭とも親しかったこともあり、両派の板ばさみのような状態になって苦しんでいた。その上両派からの引き抜きに遭って、乙耶は次第に……追い詰められていったのだ」
絢は膝の上で両手をぎゅっと握り締めた。柊二の恋人のことなど聞きたくないという感情的な拒絶と、全てを聞かねばならないという義務感がせめぎ合う。そんな絢の情態に気づいたのか、苑山はいったん乙耶から話を逸らした。
「しかし乙耶の心痛とは裏腹に両派の亀裂はいよいよ深まり、修復不可能な段階まで進んだ。そしてついに、尭が行動を起こした。いや、暴挙に出たと言うべきか。海外での個展準備のため儂が留守にしている間を狙って緊急の役員会を招集し、そこで儂の家元辞任と自身の十二代目就任を宣言。無理やり承認を得てしまったのだ」
「そんなっ……」
「あり得ないっ」
絢と幹は同時に声を上げた。苑山は二人の驚きももっともだと言わんばかりに重々しく頷き、
「儂自身はそれまで、両派の諍いに口出しはせず黙って俯瞰していた。尭に対しても、それについて敢えて苦言を呈することはしなかった。それゆえ、尭やその取り巻きたちは儂を与し易いと判断したのだろう。強引にことを進めて既成事実を作ってしまえば、あとはどうにでもなると」
それがどれほど甘い考えだったか、尭は間もなく身をもって知ることになる。息子の行動を知った苑山はついに激怒し、周囲の宥めにも耳を貸さず尭を破門。さらに勘当して家から追い出した。
そして、家元は当時九歳の絢と八歳の幹いずれかに継がせると宣言したのだ。
「この結末に最も衝撃を受け傷ついたのは、おそらく乙耶だったろう。あれは芯の強い青年だったから、自分が何とかせねばと思い詰め、挙げ句決定的な断絶を防げなかった自分を責めて、冬の海に飛び込んで死んでしまった。乙耶は身寄りがなかったから、身元確認は柊二が行った。その時の柊二の気持ちを考えると……」
「あ……あ……」
その時絢の脳裡に、石碑の前に生けられた真紅のグロリオーサが浮かび上がった。自殺者の魂を慰めるために柊二が生けた、艶やかな鎮魂の花───
───そう、か……あの花は死んだ恋人のために生けたものだったんだ。
絢は己の左胸に爪を立て、ぎゅっと掴んだ。苦しい、息ができない。喉は灼けるように熱く、頭の芯がずきずき疼く。
身体の中で何か途轍もないものが暴れ回っているのは分かるけれど、その正体が分からないのだ。絢は心を落ち着けて、感情を整理しようと努めた。
自分を責めて冷たい冬の海に身を投げた乙耶。そして恋人を突然喪うことになってしまった柊二。二人を襲った不幸に絢は心を痛め、同情し……。
───違う、違う! “これ”はそんな美しいものじゃない! 同情とか哀れみとか労わりもあるけれど、そんなきれいごとを遥かに凌いで燃え上がるこれは……。
絢は確かな答えを出せぬまま、祖父の言葉に耳を傾ける。
「愚かなことに、厳粛に故人を悼む場であるはずの葬儀でも、両派の人間は醜いいがみ合いをやめなかった。柊二はおそらくその時、紫月流に対する決定的な嫌悪に取り憑かれたのだろう。その直後に開催された本部展で、柊二は乙耶が好きだった妙蓮寺椿を生けた。しかしその作品を、儂は……認めることができなかった」
それは、観客の前で舞台に立って生ける客前装花だった。柊二は花切り鋏みで自らの皮膚を傷つけ、滴る血を花に浴びせる。まるで椿が血を流しているかのような、花にあって花に非ず、異形の何かが完成した。
その鬼気迫るパフォーマンスに、観客はもちろん流派の人間も一様に息を呑む。そんな彼らに柊二はひと言、「花の痛みを知れ」と言い放ったという。
この舞台はのちのち語り種になるほど見事なものだったが、苑山は「華道に非ず、禍道の如し」と断じ、柊二を破門したのだった。
「柊二は破門の宣告を淡々と受け入れた。おそらく、破門されなければ自ら流派を去るつもりだったろう。あれから十年。儂はずっと柊二を捜し続けていた。当時のことを謝罪し、できればもう一度流派に戻ってきてほしいと伝えたかったのだ。しかし」
苑山は弱々しく微笑んで肩を落とし、
「十年という年月は、全てを水に流すには十分ではなかったようだな。然もありなん。儂ら年寄りにとって十年は長いが、毎日を駆け足で生きている若者にとっては、十年などあっという間なのだろう」
「お祖父様……」
「苦悩を汲み取ろうともせず一方的に破門しておいて、今になって力を貸してほしいと願い出るなんて虫がよすぎたな」
苑山は自嘲混じりにそう言うと、哀しげに目を伏せた。その丸まった背中に、紫月流の伝統と未来という重々しいものがのしかかっているのを、絢ははっきり見た。
そしてそれを、いずれは自分と幹が背負わねばならないという事実に、初めて生々しい戦慄を覚えた。
翌日、絢は紫月流の東京本部を訪れた。資料室にある映像を見るためだ。
「一九九×年の本部展、オープニングセレモニーですよね。こちらのテープに収められていると思います」
「ありがとうございます」
絢は礼を言って受け取り、空いている部屋で早速再生してみた。しかし幹部や来賓の挨拶が延々と続き、柊二が登場する気配は一向になかった。
絢はいったんテープを停止し、深く息をつく。十年前の柊二を早く見たいと逸る気持ちもあるが、それ以上に躊躇が大きかった。
亡き恋人を想って血を流しながら生ける姿を見た時、自分は冷静でいられるだろうか。柊二の哀しみに共感し、清らかな涙を流すことができるだろうか……。
絢は躊躇を振り払って、再生ボタンを押した。再びセレモニーの様子がモニターに映し出される。やがて、何人目かの挨拶が終わったところで舞台が暗転した。そして次に照明がともされると、そこに深い藍色の着物を着た長身の男性が立っていた。
「柊二さんっ……」
映像はデジタル処理されていないのか、あまり鮮明ではなかった。しかし柊二のまとう鋭利な気は、不鮮明な画面を通して真っ直ぐ絢に届いた。それは鬼気と呼ぶに相応しい、凄惨で怜悧で、そしてどこか痛々しく哀しい翳を帯びていた。
舞台全体を収めるため遠くから撮影されており、柊二の表情までは分からない。ただ、その立ち姿から尋常でない何かが伝わってくる。
柊二はやや顔を伏せて仁王立ちしたまま、ぴくりとも動かない。さっきまでざわついていた客席はしんと静まり返り、しわぶきひとつ聞こえない。誰もが、柊二が放つ“静の気迫”に惹き込まれていた。
そして、それは唐突に始まった。柊二の客前装花。黒塗りの大きな花器に、枝ぶりの見事な妙蓮寺椿を生けてゆく。しかし、生けているのは花だけではなかった。
「ああっ……」
絢は思わず声を上げた。それと連動するかのように、映像の中の観客たちもざわつき始める。祖父が言っていた通り、柊二は花鋏みの先端で手の甲や腕を傷つけ、文字通り血の雨を降らせた。いや、血の華を咲かせたのだ。
カメラは撮影者の驚きを反映して小さく揺れたが、やがて戸惑いを振り切るかのように大胆にズームアップしてゆく。
画面には、血の滴る妙蓮寺椿。真紅の花弁に重ねられた血の色は、絢がこれまで見た赤の中で最も禍々しく美しかった。
「柊二さん、あなたはっ……」
恋人の好きだった花に、己の血を滴らせる。それは哀悼であると同時に、恋人との生々しい結合でもある。
そう、柊二は今、舞台上で亡き恋人を抱いているのだ。二度と逢うことのできない、愛しい愛しい恋人を───
「いや…だ……」
絢は、自分の声に戦慄を覚えた。なんて醜くおぞましい声。しかしすぐに気づいた。“これ”が今の自分に他ならないと。
「もう……やめて……」
柊二さん、柊二さん、こっちを見て。僕を見て。あなたの恋人は死んでしまったんです。もうどこにもいないんです。あなたがどんなに想いを込めて花を生けても、彼の元には届かないんです───絢の切実な訴えを無視して、柊二は椿を生け続ける。
能面の如き無表情で舞うように生ける彼の中に、椿より血より赤く爛れた愛執を見た絢は、たまらず声を嗄らして叫んだ。
「いやだ! 見たくないッ……」
そして再生機の電源を落とすと、視界はのっぺりとした黒一色に覆われた。しかし瞼裏(まなうら)に灼きついた血の滴る椿は消えることなく、より一層鮮やかに咲き誇って絢を苦しめる。一刻も早く記憶から消し去りたいのに、そんな絢の願望を嘲笑うかのように花は赫々と輝いていた。
その瞬間絢は、身体の奥がカッと燃え上がるのを感じた。と同時に、これまでぼんやりとその存在を感じていたもうひとつの心臓が、確かな鼓動を刻みつつ、黒くどろりとした熱いものを送り出す。それはあっという間に、絢の心と身体を支配してしまった。
その正体は───嫉妬。
「ああ……」
派閥争いを止められなかったことを悔いて、自ら命を絶った乙耶。そんな彼に同情するどころか嫉妬するとは、自分は何て醜い人間なのだろう。そう思いながらも、体内で赤黒く爆ぜる情念の炎を消すことができない。
「柊二さん……柊二さん……」
名前を呼ぶたびに、舌や唇がひりひり灼ける。それでも絢は口を閉ざさなかった。絢が今すがることのできる唯一のものは、柊二の名前だけだったから。
「柊二さぁん……」
苦しくて苦しくてたまらない。絢は身悶えしつつ、柊二と出会ってしまったことを恨んだ。彼に会わなければ、こんな苦しみを味わわずに済んだのに、と。しかし、
「いや、違う……」
絢はすぐに思い直した。それでも自分は、柊二と出会う運命を選んだだろう。たとえ傷つき涙を流し、嫉妬の炎に灼かれて苦しみ悶えたとしても、柊二のことを知らぬまま過ごす安穏とした毎日の方が幸せだったとは思えない。
喜びと苦しみは表裏一体。傷つくことを怖れていたら、魂が震えるような歓喜にも出会えない。そう、光ばかりを求めて闇から目を背けていたら、いずれ視覚は麻痺して何も見えなくなってしまうように。
『執着を持たないのは、失敗した時や認められなかった時に傷つかないための予防線だ』
耳の奥に蘇る柊二の言葉。その意味を、絢はようやく悟った。と同時に、自分に足りないものが何であるかも。
───僕が生ける花はただ綺麗なだけの、のっぺらぼうの花だった。それは、心の深層でどろどろと渦巻いているものから目を背けてきたからだ。
しかし苑山を初め歴代の家元たちはみな、そういった己の深い部分に正面から向き合ってきたのだ。
そして柊二も、恋人を喪った哀しみ、派閥争いを続ける人間たちへの怒りや憎しみ、何もできなかった自分への苛立ちといった決して美しくはない感情を、見事作品に昇華させた。
絢はぐっと奥歯を噛み締め、心の奥をまさぐった。そこから湧き上がってくるのは、剥き出しの欲望。
乙耶ではなく自分を見てほしい。乙耶ではなく自分を愛してほしい───
「は、ははっ……」
絢の唇から、冷めた自嘲がこぼれた。これが僕だ。このどろどろした願望、醜い嫉妬。どんなきれいごとで包み込んでも決して消えることのない情念。ならば、
「これを、花にぶつけてみよう」
絢は静かな決意を込めて呟いた。そして胸の内で続ける。美しい花にこの醜悪な情念をぶつけて、僕なりの『美と醜の弁証法』を完成させるんだ、と。
正直、怖い。不安もある。一体どんなものが出来上がるのが、自分でも予測がつかない。柊二はその卓越した技術と磨き抜かれた感性で、美と醜が渾然一体となった異形の傑作を作り上げることができたのだ。
けれど自分はまだまだ未熟。同じことをしても無惨な失敗に終わってしまうかもしれない。それでも、やらないよりはずっといい。絢は、そんな風に考えられる自分に驚きを覚えた。
花には、生けた人間のありのままが映し出される。ただ醜いだけの失敗作に終わったら、それが今の自分なのだということ。全て甘んじて受け入れよう、と。
絢は本部を出て、まだ自宅にいる祖父に会うため家路を急いだ。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT