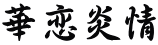
─KAREN ENJOU─
八、瞠花の章
「やっぱり、まだあの花屋に通ってたのか」
幹の刺々しい皮肉も、今は気にならなかった。それよりも、祖父の態度の方が気がかりだ。家を出てからずっと、己の世界に没頭するように黙り込んでいる。
こういう時の祖父には、たとえ側近中の側近であっても容易に話しかけることはできない。だから絢は、胸の奥で渦巻くもやもやを問いの形にして吐き出すこともできず、抱え込んだまま柊二の店に向かっていたのだ。
商店街は車両の乗り入れが禁止されているため、近くに留めてそこからは歩きだった。昨年喜寿を迎えた苑山だったが、その歩みに年齢相応の衰えは感じられない。
ぴんと伸びた背筋に、シャッシャッと空気のこすれる音がしそうなほどきびきびした足運び。そこには、年齢を超越した人間としての美しさが結晶していた。
「あ、あの花屋です」
絢が指差すと、苑山は一度だけ頷いてさらに歩みを速めた。夕刻の賑わいがひと段落ついた商店街は人影もまばらで、柊二の店にも客はいないようだ。
苑山は店の中に入ると、何も言わずただ柊二を見つめた。和装の厳めしい老人がいきなり現れて柊二はさぞ驚いているだろうと思い、絢は慌てて間に入って紹介しようとした。しかし、
「やはり、お前だったか……」
湧き上がる感慨を噛み締めるような苑山の呟きに、絢は驚き固まる。対して柊二は落ち着き払った声で、
「ご無沙汰しております」
「……うむ」
短い会話から、そのまま重苦しい沈黙へ。絢は何がどうなっているのか分からず、うろたえるばかりだった。その時、
「花屋のおじちゃーん」
店先から子供の声がした。買い物帰りの母親と一緒に、花を買いに来たようだ。柊二は「ちょっと失礼します」と頭を下げて苑山の横をすり抜け、どのミニブーケを買うか迷っている母子に普段と変わらぬ気さくな応対をする。絢はたまらず、祖父に質した。
「あの、お祖父様、これは一体……」
苑山は絢と幹に向き直り、
「彼は狩野柊二(かのう・しゅうじ)。かつて二十二歳の若さで紫月流の総師範にまで上りつめた男だ。あれを天才と言わずして、誰を天才と呼べようか」
「なっ……ん……」
絢も幹も驚愕のあまり絶句したが、より深い驚きに襲われたのはもちろん絢の方だった。
「だっ…て……僕には日向柊二って……」
「日向は母方の姓だ。おそらく絢が紫月の縁者だと察し、自分の素性が名前からばれないよう名乗ったのだろう。馬鹿者めが。名前など変えたところで、“手”を見ればすぐに分かるものを」
その言葉に偽りはない。苑山は絢の作品に加えられた柊二の“手”を見ただけで、すぐに気づいたのだ。
「二十二歳で総師範なんてあり得ないっ……」
幹は絢とは違う部分に驚きを感じているようだ。然もありなん。総師範とは、師範補、準師範、師範の上に位置する最上級の役職。流派に何十年と籍を置いて研鑽を積み、ようやく手が届くというレベルのものだ。二十代前半の青二才が到達できるはずがない。
しかし苑山は微笑を浮かべ、
「どこの世界にも、生まれながらの才能、天稟を持つ者はいる。我々凡人が百の努力をもって積み重ねたものを、ひらりと一足で飛び越えてしまう者がな」
絢も幹も言葉を失った。紫月流の歴代家元の中でも、実力人格ともに五指に入ると言われる祖父苑山が、自身を『凡人』と評したのだ。
裏を返せば、それだけ柊二の才能が凄まじいということだ。
「お待たせして申し訳ありません」
接客を終えた柊二がようやく戻ってきた。
「いや、こちらが押しかけてきたのだ。謝る必要はない」
苑山はさらりと返して店の中を見回し、
「花屋をやっていたとはな」
「はい。もう花の世界はこりごりだと思っていたのですが。あれから世界を旅するうち、花と無縁の生は私にとって死に等しいと思い知りました。まさに、花は業。この身と切り離すことはどうしてもできなかった」
柊二は搾り出すようにそう言って、苑山を真っ直ぐ見つめた。苑山も柊二に劣らぬ強い視線を返し、
「もう一度、紫月に戻ってくる気はないか」
「私は破門された身です」
淡々と返す柊二に、苑山は初めて表情を変えた。煮詰められた悔恨と自責が、顔に刻まれた皺に暗い陰翳を投げかける。
「儂も当時はあの騒動のせいで、神経が尖っていた。自らの動揺を抑え、流派を維持するので精いっぱいで、お前の気持ちも乙耶(おとや)の苦悩も汲んでやることができなんだ。乙耶には本当に……申し訳ないことをした」
事情は分からないながらも、苑山が心から詫びていることは絢にも伝わった。しかし柊二は黙って首を振り、背中を向けてしまった。
「……勝手なことを言ってしまったな」
無理強いはいけないと判断したのだろう。苑山は静かにそう言って絢と幹を促した。肩を落としたその姿に、絢が常から畏怖を抱いている厳格な師の面影はない。まるで、現世(うつしよ)に倦み疲れた老爺のようだった。
「絢、帰るぞ」
一向に立ち去る気配を見せない絢に、幹が苛立たしげに呼びかけた。しかし絢は「先に帰ってください」ときっぱり言い放つ。幹は眉をひそめたが、仕方ないと諦めたのか苑山とともに帰っていった。
それを見送ることなく、絢はこちらに向けられたままの広い背中に対峙した。
「……柊二さん」
呼びかければいつも、もしゃもしゃの髭づらで笑顔を返してくれた。なのに今は振り向いてもくれない。
「柊二さん、どうして黙っていたのですか?」
いけないと思いつつも、つい詰問口調になってしまう。対して柊二は、何の感情も窺えぬ淡々とした声で、
「俺はもう紫月の人間ではない。今さら言う必要もないだろう」
「で、でもっ……」
「本部展が近いのだろう? 早く帰りなさい」
絢は大きく首を振った。こんな強張った背中を向けられたままで帰れるはずがない。
「こっちを……向いてください」
柊二はかすかに身じろいだが、ややあってゆっくり振り向いた。相変わらずの熊みたいな髭づら。なのにいつもの親しみや安心感が湧くことはなく、皓々と輝く切れ長の瞳に見据えられて、絢は背筋にすっと冷たいものが走るのを感じた。
「もうひとつ……教えてください。乙耶さんというのは誰ですか?」
ちぢこまる舌を必死に動かして訊ねた絢に対し、柊二の答えは喉元に匕首を突きつけるかのように容赦なかった。
「君には関係ない」
その瞬間絢は、ぱりん、と何かが割れる秘めやかな音を聞いた。それが自分の心が折れた音だと気づいたけれどどうすることもできず、儚い光にすがるように問いかけた。
「また、ここに来てもいいんですよね……?」
この前のように、仕方ないなと笑って頷いてくれる、そんな期待は再びこちらに向けられた背中と、分厚い沈黙に跳ね返された。絢はぽっきり折れた心を抱え、店を飛び出すしかできなかった。
「ぅ、ぅっ……」
初めて向けられた冷たい眼差しと容赦ない拒絶の言葉が、心の傷口にじりじり沁みる。今になって分かった。もう店に来ない方がいいと言われた一度目の拒絶が、どれほどの優しさと労わりに満ちていたのか。本心からの拒絶が、どれほど冷たく残酷な力を揮うのか。
「関係なく……ないっ……」
どうして言い返せなかったのか。他ならぬあなたのことなのに、大好きなあなたのことなのに、関係ないはずないでしょう? と。
でもそうやって悔やみつつも、あの場で言い返すことなど自分にできないことは分かっていた。ただ、涙をこらえて立ち去るしか。
「苦し…い……」
身体の奥にともった得体の知れない何かが、もうひとつの心臓のようにドクドクと鼓動を刻み始めるのを、絢はその時確かに感じたのだった。
自宅に戻るとすぐ、絢は祖父の部屋を訪れた。もちろん、柊二について教えてもらうためだ。苑山は絢の来訪を予想していたのか、幹も部屋に呼ぶと、二人の孫を前に穏やかに口を開いた。
「いずれは、お前たちにも話さねばならんと思っていた。十年前、尭が流派を去るに至ったいきさつと、その後の痛ましい事件についてだ」
苑山はそんな重々しい前置きを導き手に、絢も幹もこれまで曖昧にしか知らされていなかった十年前の家元争いについて話し始めた。
「お前たちの父親で儂の息子でもある尭に対し、儂は幼いころから親としてではなく師として厳しく接した。いずれは儂の跡を継いで家元となる身。修業は早ければ早いに越したことはない。しかしあれはそんな儂に対し、ただ反発するばかりだった──」
絢も幹も背筋を伸ばし、祖父の言葉ひとつひとつを全身で受け止めた。ずっと知りたかったけれど、正面から質すのが憚られた父、尭のことが、初めて祖父の口から語られたのだ。
尭は長じてもなお父の厳しさを愛情と受け止めることができず、また古い理念に基づいた流派の運営方針にも不満を抱き、経営について何かと口を挟むことが多かったという。
そんな息子を苑山も疎むようになり、亀裂は修復不可能な深さに達した。流派の内部でも保守的な苑山派と進歩的な尭派に分裂。対立は全国に存在する支部にまで波及し、支部長や師範らは二派に別れることとなった。
「そこまで深刻な対立になってしまったなんて……」
絢の呟きに同調するように、幹も眉間に縦皺を刻んだ。苑山はやつれた自嘲を浮かべ、
「儂の不徳の致すところだ。それより絢は、当時の柊二について知りたいのだろう?」
艶めいた含蓄のある問いかけに、絢の頬は自然と赤らむ。それと連動するかのように幹の目尻は吊り上がったが、もちろん絢が気づくことはなかった。
「伝統も斬新もない、そこには美と独創があるばかり───これはある著名な評論家が柊二の生けた花を見て言った言葉だ。伝統をおろそかにして前衛に走っているのではない、かといって伝統の上に胡坐をかいているわけでもない。まさに温故知新。連綿と受け継がれた紫月の伝統を土壌に、自らの才能を開花させた恐るべき男だ」
型破りな発想、高度な技術、そして深甚なる知識。これらが三位一体となって生み出される柊二の花は、当時絶大な人気と高い評価を得た。一部の保守層からは異端児扱いもされたが、それすら彼の評判を押し上げる一要素となったのだ。
当時、彼が生けると一輪の花に狂気とドラマが生まれると評され、紫月流の総師範となった頃にはすでに、その端麗な容姿もあって流派内はもちろん他流派からも注目される、押しも押されもせぬ人気華道家だった。
「しかし柊二は己の才に溺れることなく、周囲の称賛に踊らされることもなく、常に真摯に花と向き合っていた。流派が分裂した時もそういった俗事には関わらぬとばかりに、どちらの派閥にも与せず中立を貫いていたのだ。しかし」
両派の対立が深まる中、弟子や生徒たちからの人気も高く世間的な知名度もある柊二を、苑山派も尭派も自らの陣営に引き入れようと画策を始めた。
流派の運営方針について決定権を持つ華務局の常任理事(トップ)にしてやる、ならばこちらは副理事の椅子を用意する、などの甘い餌をちらつかせたのだが……。
「柊二はどちらにもなびく気配を見せず、淡々と花を生け弟子を指導した」
「柊二さんらしい……」
絢は思わず唇を綻ばせた。流派内の地位とか名誉とか、そんなものは彼にとって煩わしいだけだったろう。ただ花に向かい、己に向かい、深い創造の世界に沈み込んでゆく。彼が唯一流派に求めていたのは、それができる環境だったに違いない。
しかし、絢の口元に浮かんだ微笑は、次に発せられた苑山の言葉で跡形もなく消え去った。
「柊二を直接取り込むことを諦めた両派が次に目を付けたのは、柊二の恋人である都筑乙耶(つづき・おとや)だった」
「恋……人……」
絢はその苦い単語を、ただ唇でなぞるしかできなかった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT