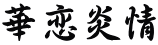
─KAREN ENJOU─
十、炎花の章
ここに立つといつも緊張する。祖父の部屋に通じる戸の前で、絢は深呼吸を繰り返した。そして床に膝をつき、声を掛ける。
「絢です。入ってもよろしいでしょうか」
すると一拍おいて、「入りなさい」と返ってきた。絢はほっと安堵の息をついた。まずは第一段階突破。大袈裟ではない。近親者でも一番の弟子でも、すげなく追い返されることは珍しくないのだ。
祖父は珍しく、ゆったりとした部屋着をまとっていた。顔色も余りよくないように見える。絢は思わず声を低め、
「お祖父様、具合がお悪いのですか?」
しかし、絢の杞憂だったようだ。苑山は鋭い輝きを宿した双眸で絢を射抜き、
「何か用事があって訪ねてきたのではないのか? つまらん会話で時間を無駄にしたくはない」
「はっ、はい。申し訳ありません」
絢は慌てて居住まいを改め、畳に両手をついて深く頭を下げた。そしてすっと息を吸い込み、
「お願いがあって参りました。どうか、本部展への出展をお許しください」
「…………」
返ってくるのは無言の静寂ばかり。それでも絢は、頭を下げ続けた。徐々に激しさを増す脈音が、鼓膜を内側から震わす。まるで、耳元で兵隊が行進しているかのようだ。
「出展は禁じると言ったはずだが」
聞く耳持たないとばかりに追い返されるかと怖れていたが、祖父の声は存外穏やかだった。だからといって安心は禁物だ。そういったわずかな気の緩みも、祖父の炯眼はあっさり見抜いてしまうに違いない。
絢は畳に爪を立て、己を鼓舞するように声を張って訴えた。
「承知しております。これまでの僕は形だけの稽古を積み、ただ安穏と毎日を過ごしておりました。花は人なり、人は情なり───この言葉の真意を掴むための努力もせず、どうせ自分は何をしても駄目だと卑屈に構えておりました。けれど」
脳裡を赤いものがよぎる。血に濡れた妙蓮寺椿。引き裂かれた恋人たちの嘆き───
「けれど柊二さんと乙耶さんのことを知り、お祖父様の苦悩を知り、自分は逃げているだけだったと気づきました。僕はこの本部展で、己の内深くにあるおぞましいものを花に託し、作品として昇華させたいのです。どうか、僕にチャンスをください。お願いいたします」
許可がもらえるまで何時間でも、絢はここで頭を下げ続けるつもりだった。しかし、
「……相分かった。本部展への出展を許可する」
「えっ?」
絢は思わず顔を上げ、素の状態で聞き返してしまった。祖父はもう絢の方を見てはおらず、書物に目を通している。
祖父がこんな簡単に前言を翻すはずない、でも確かに許可するって言った……と絢が困惑に沈んでいると、苑山は書物に目を留めたままひと言、
「精進しなさい」
「はっ、はい! ありがとうございます!」
許可がもらえたことをようやく察した絢は、ぴょこんとお辞儀するとばたばたと部屋を出ていった。
「まったく、騒々しい子だ」
そう言う苑山の口元には、かすかな笑みが漂っていた。
それから本部展まで、怒涛のように時間が過ぎていった。しかし絢はその流れに呑み込まれることなく、流れを遮るように両の足でしっかり立って、己との対話を深めていった。
───僕が表現したいもの、それは……
愛し愛されたいという欲望。身も心も灼き尽くす情念の炎。それらは決して“美しい”ものではない。しかし目を逸らさず立ち向かっていった時、ゆらめく炎の中に何かが見えるのではないか。
絢は出展の準備を進めるとともに、柊二への手紙をしたためた。
『柊二さんへ
僕は今、本部展への出展準備に追われています。お祖父様から許可をもらうことができたのです。思えばお祖父様は、僕の方から出させてくださいと申し出るのを待っていたのでしょう。お祖父様に見限られてしまったと思い込んでいた自分が情けなく、恥ずかしいです。
これまで、僕にとって花はきれいなもの、安らぎを与えてくれるものでした。花で自己を表現しようにも、その“自己”が一体何なのかも分かっていなかったのです。
でも柊二さん、あなたと出会ったことでようやく気付きました。それは己の内に潜む激しい情動。剥き出しの欲望。それに向き合うのはとてもつらく苦しいですが、いつだったかあなたは、ぬるま湯に浸って現実から目を背けるのは逃げだと仰いましたね。だから僕は逃げることなく、その醜い自己を花に託してみようと思います。
本部展の招待券を同封しました。柊二さんにとって紫月流は思い出したくない過去かもしれませんが、今の僕の全てをあなたに見てもらいたいのです。
会場でお待ちしております。
紫月 絢』
自宅の住所は分からないから、店宛てに送ることにした。ポストに投函した絢は、深く息を吐いて己に言い聞かせた。さあ、あとは作品制作に全神経を傾注するだけだ。余計なことは考えず、燃え上がる情念に全てを委ねればいい。
本部展は、三日後に迫っていた。
「江戸中期からの伝統を真摯に受け継ぎながらも、現代と向き合うことをおろそかにせず常に前進し続けた十一代家元、苑山氏は───」
壇上では、来賓の挨拶が続いている。しかし真面目に耳を傾けている者は少なく、招待客の多くは会場内を回遊しつつ、個々の作品に対する感想や批評をひそひそ囁き合っていた。
本部展初日。ついにこの日がやってきた。会場内は、流派の役員はもちろん、一般の招待客、文化庁や大使館関係者などの来賓で埋め尽くされていた。
絢は、準備に追われた昨日からの疲れを引きずりつつも、緊張のせいで頭は妙に冴えていた。感覚も鋭敏になっているのか、努めて耳に入れないようにしても、周囲の囁きが聞こえてしまう。
『これって、家元のお孫さんの……?』
『ええ、そうよ。確か兄の方ね』
『紫月流の枠からはみ出してない?』
『流派云々というより、何だか怖いわ。けれどなぜか見ずにはいられない』
『まさに異形の美ね。生命が燃やし尽くされる最後の瞬間を見ているよう』
『そう? 私には、これが美しいとは思えないわ』
この作品が賛否を呼ぶだろうことは、絢にも分かっていた。より洗練された形、より思索的なラインを好む紫月流の王道からは外れた作品であると。
だから何を言われても、今さら動揺することはない。紫月流の枠内に収まったままでは、心の内に潜む“怪物”を表現することはできないと覚悟を決めていたのだ。
絢は深呼吸して心に凪を呼び込むと、周囲でざわざわと渦巻く言葉を静かに掻き分けつつ、会場内でひときわ異彩を放つ自分の作品へ近づいた。
赫々と燃え上がる情念の華。その名も───『華恋炎情』。
使用した花材は二つだけ。妙蓮寺椿と孔雀葉牡丹。椿は全体をくねらせながら、天へ伸び上がるように枝を広げている。それに、細く鋭い葉が幾重にも重なった孔雀葉牡丹を、枝に絡みつくように生けてみせた。
葉牡丹は、限りなく赤に近い紫。それはまるで燃え盛る炎のごとく椿を包み、その存在ごと呑み込んでやると言わんばかりの勢いを露わにしている。
しかし椿は、ただ炎に侵食されるだけのか弱い存在ではなかった。生を謳歌するかのように枝を広げ、真紅のみずみずしい花弁を惜しげもなくさらす。
そう、これは自らの内から溢れ出る炎なのだ。炎が激しさを増せば増すほど、花はより艶やかに、歓喜と苦悶におののきつつ咲き誇る。
椿の枝に這うように絡みつく赤紫の葉牡丹は、決して美しくはない。下手をすれば、生理的な嫌悪感すら誘発するかもしれない。
しかし絢が表現したかったのは取り澄ました美ではなく、今の自分のありのままの姿だ。それが鑑賞者の目に醜悪、異形のものとして映るのならば仕方ない。甘んじて受け入れようと、とうに覚悟を決めていた。
「あ……」
展示ブースの手前で、絢は思わず足を止めた。来場者たちは、絢の作品から立ちのぼる瘴気を避けようとしているのか、周囲はエアポケットのようにぽっかり空いている。そこにどこからともなく幹が現れたのだ。
幹はじっと佇んだまま、作品に濃密な視線を送り続けている。絢は声をかけようとしたが、なぜか躊躇われ、弟が鑑賞し終えるのを待った。
やがて幹はゆっくりと振り向くと、絢に向かって深々と頭を下げた。そしてたったひと言、
「見事です」
絢は何も返せず立ち尽くす。頭を上げた幹は、これまで見たこともないような敬愛に満ちた微笑をさっと閃かすと、足早に立ち去っていった。
「……ありがとう」
人波に紛れあっという間に見えなくなった背中に、絢は心からの感謝を呟いた。弟の言葉や態度は厳しいものだが、それは流派の未来や華道そのものを真剣に考えているからこそなのだ。だからいい加減な人間や努力を怠る人間には手厳しい。
そんな弟からの賛辞がどれほど重いものか、絢に分からぬはずはなかった。理解してくれる人がこんな身近にいたというのに、自分は顔を背け逃げるばかりだったのだ。
絢は深く反省するとともに、表現することの喜び、伝えることの喜びがじわじわ湧き上がるのを感じた。しかし、
「柊二さん……やっぱり来てくれないんですね……」
会場をくまなく見渡しても、柊二らしき人物の影すらなかった。あの長身に髭づらなのだから、もし来ていたらすぐに見つけられるはず。幹に褒められた嬉しさも、言葉にできぬ寂寥であっという間に上書きされてしまった。
絢は肩を落として苦い溜め息をつき、オープニングセレモニーが続いているステージへ向かった。そろそろ式のクライマックス、家元による客前装花が始まる頃だろう。その時、
「絢! ちょっと来てくれ」
どんな場でも悠然と構えている幹が、動揺を隠さず駆け寄ってきた。血の気の失せた青い顔と眉間の縦皺には、不安と焦燥が色濃く漂っていた。
何か予想外の事態が起きてしまったのかもしれない。絢は素早く頷くと、鼓動が速まるのを意識しつつ幹の後についていった。
幹は会場を出て、人で溢れる廊下を走り控えの間に飛び込んだ。そこには、これから装花を行う祖父苑山が待機しているはずだ。
「お祖父様!」
その光景に、絢の口から悲鳴が漏れた。長椅子に力なく横たわった祖父は唇まで真っ白で、時折まぶたが痙攣めいた動きを見せる以外はぴくりとも動かない。絢はがくがくと震えそうになる膝を叱咤して幹を振り向き、
「救急車はっ?!」
「いや、それが……」
幹が困惑げに苑山へ視線を送ると、それに応えるように薄いまぶたが僅かに上がった。
「儂が呼ぶなと言った。ことを大きくしたくはない」
苑山の声は、思いのほかしっかりしていた。しかしいつもの迫力と張りはない。
「でもっ……」
「心配はいらん。ホテルに車を手配してもらった。これから葉山君と本嶋君に病院へ連れていってもらう。さすがにこの体調で客前装花はできん」
葉山と本嶋は苑山の付き人だ。二人に任せておけば大丈夫だろう。問題は……。
「絢、幹、あとは頼んだぞ」
言葉の意味を理解した瞬間、絢は臓腑がぎゅっと縮み上がるのを感じた。それは、幹も同じだったろう。
「苑山先生、お車の用意ができました。さ、どうぞ」
付き人二人はなるべく大仰に見えないよう、苑山を両脇からそっと支えた。そして控え室を後にする。残された絢と幹は、身体の震えが互いにばれないようにするので精いっぱいだった。
年一回の本部展、その初日。盛大なオープニングセレモニーの掉尾を飾る家元の客前装花は、言うまでもなく最も重要なイベントだった。その完成度は本部展の成否のみならず、流派全体の評価を決めると言っても過言ではない。
「む、無理だ……客の前で即興で生けたことなんてない」
幹は今にも消え入りそうなかすれ声で呟いた。その顔は、絢を呼びにきた時よりさらに青ざめている。隣にいると圧迫感すら覚える精悍な身体は、二回りほど小さく見えた。いきなりのしかかってきたプレッシャーに必死に耐えているのが、手に取るように分かる。
「駄目だっ、怖い……」
そう言って、身体の震えを抑えつけるように歯を食いしばる弟を見た瞬間、絢は決意した。自分がやろう、と。
絢は一歩踏み出て、力強く告げた。
「僕がやるよ。これまで僕は逃げてばかりで、紫月流宗家という重荷を幹一人に背負わせてきた。今度は僕が、その重圧を引き受ける番だ」
「兄さん……」
「僕が失敗しても、出来の悪い兄だから仕方ないって笑われるだけで、紫月流の評価が落ちるようなことはないさ。その時は幹、頼んだよ」
絢はそう言って、何とか笑ってみせた。頬がみっともなく引きつってしまったが、それは仕方ないだろう。力なく項垂れる弟の広い背中をぽん、と軽く叩いて、絢は控え室を後にした。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT