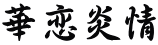
─KAREN ENJOU─
七、錬花の章
商店街を抜けて駅を越え、昔ながらの立派な門構えが立ち並ぶ高級住宅街へ。すでに明かりの消えている家も多く、辺りはひっそり静まり返っている。
二人の口も自然と閉ざされ、無言の散歩になったが、絢には心地よい沈黙だった。隣を歩く柊二の息遣いに耳を澄ませ、その横顔や吐き出される白い息を時折ちらと見つめる。それらは言葉以上の鮮やかな印象を絢に刻み込んだ。
幸せな時間は、早足で過ぎ去ってゆく。気がつけば、自宅はもうすぐそこだった。オレンジ色の門灯が、闇をぼぅっと照らしているのが見える。その途端、柊二の歩みが遅くなった。
「柊二さん?」
立ち止まって見上げる絢に、柊二は無理にこしらえたと分かる引きつった笑みを向けた。
「いや、何でもない。さあ、行こう」
とても“何でもない”ようには見えなかったのだが、絢が問いを重ねる前に柊二は歩みを速めた。絢は慌てて小走りになり追いつく。
門前に立った柊二は、その向こう、暗闇に浮かぶ屋敷のシルエットを目を細めてじっと見上げた。その表情は痛みをこらえているようでもあり、追憶に耽っているようでもあった。
やがてふっと短い息を吐いて絢に向かい、
「さ、行きなさい。手の消毒を怠らないように」
「は、はい。それであの……また明日、お店に伺ってもいいですか?」
「構わない。ただし、俺が言ったことを守るのなら、だが」
絢は大きく頷いた。
「守ります。お祖父様に認めてもらえるよう、お稽古に励みます」
決意を伝える絢に、柊二はいったん何か言いかけて口を噤んだ。やがてためらいがちに再び口を開き、
「生けていて分からないこと、迷うことがあったらいつでも力になる。俺は門外漢だが、その分客観的なアドバイスができるかもしれない」
もし祖父や幹だったら、花屋風情に教えを乞うなど紫月流の恥、と端から拒絶しただろう。しかし絢はすでに、柊二の研ぎ澄まされた感性や発想力、そしてそれを形にする卓越した技術の結晶を幾度も目にしている。
加えて絢には、たとえ門外漢だろうがいいものは吸収しようという、生来の素直さや柔軟さがあった。
「はい。よろしくお願いします」
絢はまるで師匠に対するように丁寧なお辞儀をすると、「おやすみなさい」と言った。しかし門をくぐる気配を見せないため、柊二が怪訝そうな顔をすると、はにかんだ笑みを浮かべ、
「どうぞ、行ってください。ここでお見送りしてます」
「あ、いや。それには及ばない。早く家に入りなさい」
笑顔から一転、しゅんとしおれる絢。するとおでこに優しくあやすようなキスが降ってきた。
「しようのない子だ。また明日。おやすみ」
柊二はそう言ってくるりと背を向け、足早に去っていった。絢はおでこに残る余韻を反芻しながら、見えなくなるまでその場に佇んでいた。
「……やっぱり、ひげがくすぐったかった」
思わず漏れた感想に自分でぷっと吹き出し、ふわふわと浮かれた足取りで部屋に戻ったのだった。
「まったく……」
柊二はぶつぶつ悪態をつきながら、歩いているとは思えぬスピードで夜の街を進んでいた。
「もうちょっと自覚を持ってくれ。自分がどれほど男を……」
言葉は途中で、苦い溜め息に掻き消された。花が自分の美しさを知らぬように、絢もまた己の美しさや妖艶さに気づいていない。だからあれほど無防備な振る舞いができてしまうのだろうが、受け止める側としては正直困ってしまう。
無意識のうちに振りまかれる媚態に煽られ、惹きつけられた挙げ句、思いもかけぬ方法で突き放される。そう、とろりと潤んだ瞳で見つめ、悩ましげに腰を揺らしながら身体が火照ってきたと訴え、泊まってもいいんですかと喜んだ挙げ句の───
「お泊りセット、か……ははっ……」
呆れたような呟きがつい漏れてしまうが、そんな無邪気さも彼の魅力なのだともちろん分かっている。分かっているからこそ、対応に困るのだ。
きっとこれまでも、本人が気づかぬまま甘い香りを振りまき、男を狂わせてきたのだろう。一体何人の男が、あの泣き黒子に舌を這わせたいと身悶えしたか。薄く感じやすい皮膚の下に息づく官能の熱に灼かれたいと妄想したか。
しかし今まで蕾が閉じたままだったのは、おそらく弟の努力があったからだろう。以前、自分の行動に弟がよく干渉してくると絢がこぼしたことがあったが、己の美貌に無頓着でかつ性善説を信じきっている呑気な兄を心配するあまり、いろいろ口出ししてしまうに違いない。その気持ちはよく分かる。
「絢、もう少し気をつけろ。でないと……俺のような男に引っかかってしまうぞ」
柊二は自虐的に呟いて、軽く頭を振った。紫月流の跡取りと関係を持つなんて暴挙以外の何ものでもないと、ちょっと考えれば分かる。
これからは、今夜のように絢から溢れ出る蜜に我を忘れて溺れることのないよう、己をしっかり制するのだと自分に言い聞かせながら、柊二は夜の街を歩き続けた。
絢は、柊二との約束を守った。家にいる時はいつも花と向き合い、と同時に己の心に問いかけた。自分は何を表現したいのか。何を創造したいのか。
美しいだけでは駄目だ。美の彼方にあるものを捉えて自分のものにしなくては、『華』にはならない。
お前が生けるのは華ではなくただの花だ───祖父の叱責が耳の奥に蘇り、鋏を持つ手がすくんでしまう。いつもの絢ならそこで項垂れ鋏を置いてしまったが、柊二の厳しくも優しい激励の言葉を思い出すと、自然と背筋が伸びて再び花に向かうことができた。
そうして生けた花を絢はさまざまな角度から撮影し、柊二に見せて感想を求めた。それに対し柊二は、絢も驚くほど鋭く的確な指摘を返した。短い言葉に凝縮されたそれは、もはや感想ではなく批評の域に達していた。
絢は全てを素直に受け入れ、家に帰って柊二のアドバイス通りに手を入れる。そしてあらためて、指摘の正しさにうなる。
ちょっとした角度の違いで、そのもの自体の造形はもちろん空間の表情まで変わってくるのだ。絢は今さらながら、生け花の奥深さに感嘆を禁じ得なかった。
やがて、本部展が一週間後に迫った。いくら出展を禁じられているとはいえ、絢にも紫月流の職員としての仕事がある。それを放り出して柊二の店に通うわけにはさすがにいかず、絢はしばらく顔を出せないと伝えた。柊二ももちろん心得ており、ちゃんと仕事するんだぞと言って頭をぽんぽんと撫でてくれた。
その日の帰り際、絢は昨日生けた花を柊二に見せた。
「梅と万年青(おもと)を生けてみたんです。どうでしょうか」
いつものように感想を乞うと、柊二はふむ、とうなってから床すれすれに伸びた梅の枝を指差し、
「悪くはないが、この辺りに雅致が欠けている。絢らしくない」
「僕らしくない……?」
「ああ。無骨だ」
絢は身体がかぁっと熱くなるのを感じた。確かにこの梅と万年青は、自分の個性に対する挑戦のつもりで生けたのだ。
敢えて“自分らしくない”ことをすることで、新たな景色が見えるかもしれないという色気があったことは否めない。それを柊二は、たった一枚の写真で見抜いてしまった。
「個性というのは、見方を変えれば檻であるとも言える。そこから飛び立とうとするのは決して悪いことではない」
絢の赤面に気づいたのか、柊二は声を和らげフォローしてくれた。絢は面目ないと言わんばかりに頷き、
「でも、やりすぎはいけないということですね」
「その通り。花自身にこう見られたいとかこう見せようという作意がない分、生ける側の思惑が如実に表れてしまう。ゆえに、新しいことをやる時は極力控え目に。そうしないと、あざとさばかりが目立つ卑しい作品に堕してしまう。想いをぶつけるのは構わないが、花との対話を忘れてはいけない。花あってこその己だということを、肝に銘じておくように」
柊二はそう言って、枝の長さや挿す角度などを細かく指導した。絢は一言一句聞き漏らすまいと脳裡に刻み、家に帰るとすぐに生け直した。
「ああ、すごい……」
これだ。これこそ自分が思い描いていた、優雅と壮健を兼ね備えた美。儚げで繊細な個性と言えば聞こえはいいが、絢が生けるとどこか弱々しく生気に乏しい花に見えてしまう。だからといって、ただ大胆に冒険すればいいというものでもない。
「花との対話……そうか、ただ自分を押しつけるだけでは駄目なんだ。花を“使って”表現するのではなく、花と“ともに”表現する……」
絢は、視界がかすかに明るくなったような気がした。努力し対話を重ねれば、花はちゃんと応えてくれる。そしてそれは、自己との対話を深めることにも繋がるのだ。
絢は迷った挙げ句、この梅と万年青を玄関脇の花台に置くことにした。
紫月家には、家元に見てもらいたい作品ができた時、それはすなわち自信のある作品ということだが、この花台に置くという暗黙のしきたりがあった。それは『裏披露目』と呼ばれ、伝統として紫月家に代々伝わっていた。
絢は三年前に初めて、悲壮な覚悟とともにその裏披露目をしたのだが、祖父に厳しい言葉を浴びせられ、それ以来一度も花台に載せることはなかった。
本部展への出展を禁じられている身でおこがましいとは思ったが、柊二の協力を得た自分が今できる精いっぱいのものを見てもらいたいという欲求に抗うことはできず、おそるおそる置いたのだ。
絢は自室で緊張しつつ祖父の帰りを待ったのだが、今は本部展前の一年で最も多忙な時期。さすがの祖父も裏披露目どころではないかもしれないと気づき、ほっと安堵するような少し淋しいような複雑な感慨に浸った。
やがて、祖父が帰宅した。その姿を見なくとも、使用人たちがいっせいに出迎える慌ただしい足音や、屋敷内の空気がきゅっと引き締まる感覚から分かる。
絢は騒ぐ心を落ち着かせるため深呼吸をした。一度、二度、そして三度目の息を吸い込もうとした時だった。突然部屋の扉が叩かれた。
「絢、開けるぞ」
こんな上ずった祖父の声は初めて聞く。絢が困惑しつつ「は、はい」と答えた時にはすでに扉は開けられ、祖父、苑山が興奮を抑えきれぬ様子で部屋に入っていた。
いつも冷たく凪いでいる灰色の眼は、宝物を見つけた少年のようにきらきら輝いている。苑山の背後に控えている幹も、普段と違う祖父に驚きを隠せないようだ。
「絢、あの花を生けたのはお前か?」
せかせかした前のめりの口調にも、祖父らしからぬ興奮がにじんでいた。“あの花”とはもちろん、花台に置かれた梅と万年青のことだろう。絢は勢いに呑まれつつも頷いた。しかしもうひとつの事実を付け加えるのも忘れなかった。
「確かに生けたのは僕ですが、ある人の助言に従って修正いたしました」
「それは誰だ」
「はい。懇意にさせていただいている花屋のご主人です」
答えてから絢は反射的に首をすくめた。花屋風情に教えを乞うとは何事かッ、と鞭でぴしりと叩くような叱責の言葉が飛んでくるに違いないと覚悟していたのだ。現に幹も険しく眉根を寄せ、怒りを露わにしている。しかし、
「……絢、今すぐ儂をその花屋へ連れて行ってくれ」
思いもかけぬ要求に、絢のみならず幹も呆気にとられた。そんな二人には構わず、苑山は「幹も一緒に来なさい」と促した。そしてさっさと歩き出す。
絢は慌てて上着を掴むと、その後を追いかけたのだった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT