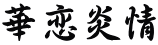
─KAREN ENJOU─
六、疼花の章
商店街から程近い三階建てアパートの一室が、柊二の住まいだった。ひと目で独身男の一人暮らしと分かる殺風景な部屋。決して広くはないが、物が少ないため広々として見える。
「救急箱を取ってくるから、待っていてくれ」
柊二はそう言って、いったん奥の部屋に消えた。絢はほぅっと息を吐いて、左の胸を押さえる。さっきから、激しい動悸が収まらない。
柊二にまた逢えたのはもちろん嬉しい、けれど迷惑がられているかもしれないと思うと、不安で泣き出したくなってしまう。そんな感情の乱高下に、絢の心は翻弄されっぱなしだった。
絢は気を落ち着かせるため、壁に無造作に留められた花の写真を眺めた。荒涼とした砂漠や険峻たる岩山、肉厚の葉が生い茂るジャングルなど背景はさまざまだが、どれも見たことのない花ばかりだ。
「珍しい花だろう?」
小さな救急箱を持って、柊二が戻ってきた。絢はこくりと頷き、
「どれも見たことがありません。この写真は柊二さんが?」
「ああ。数年間、世界を旅していた。その時に撮ったものだ」
「旅って、一人で?」
「もちろん。まあ旅と言えば聞こえはいいが、放浪だな」
では、たった一人でこの砂漠や岩山に立ったということか。淋しくなかったのだろうか、人恋しくならなかったのだろうか。当時の柊二の心象風景に思いを馳せようとした絢だったが、ずっと誰かの手に支えられ守られて生きてきた自分には想像もできないことだと諦めた。
経験の差、年齢の差といえばそれまでだが、絢はつくづく自分の幼さを痛感した。
「さ、消毒するから手を出して」
絢は言われた通り、赤く擦り切れた手を出した。柊二は消毒液の染み込んだ綿をピンセットでつまみ、患部にちょんちょんと当てては、息を吹きかけて乾かしてくれる。
「……っ、」
絢はとっさに唇を噛み締めた。すると柊二に「痛むか?」と訊かれ、かすれた声で「大丈夫です」と返す。しかし、大丈夫ではなかった。本当は、今にも涙が溢れてしまいそうだった。嬉しくて、切なくて。
何か特別なことをしてくれているわけではない。ただ傷の手当てをしているだけ。なのにひとつひとつの動作や息遣い、手の温もりには優しさが満ちていた。
大事にされることには慣れていた。紫月流宗家に生を受け、幼いころから何不自由なく育てられた。
芸事には厳しい祖父も、それ以外のことなら大抵の望みは叶えてくれた。流派の幹部や師範たちにも『坊ちゃん』と呼ばれ、腫れ物に触るような扱いを受けた。
なのに、柊二のなにげない優しさやちょっとした気遣いに、こんなに心揺さぶられてしまうなんて。
「よし、あとは雑菌が入らないようガーゼを当てておこう。家に帰ってガーゼを取る時、少しひりひりするかもしれないな。その時はぬるま湯につけてそっと──」
柊二は途中で言葉を呑み込んだ。そして困惑を隠さず、はらはら涙をこぼす絢の顔を覗き込む。
「どうした、そんなに痛むか?」
絢は小さく首を振り、涙にたわんだ睫毛の奥から柊二を見つめ、
「もう来るなって言われたのに……ごめんなさい。でも、会いたかったんです」
「絢……」
「柊二さんに、どうしても会いたかったんです、僕っ……」
決死の告白をしたにもかかわらず、柊二はふいと顔を背けてしまった。拒絶の仕草に絢の頭は真っ白になり、震える声で、
「ご迷惑……ですか?」
すると柊二は大きな溜め息をついて、がしがしと頭を掻いた。そして彼には珍しい探るような口調で、
「迷惑だと言ったら……どうする?」
頭で考えるより先に、口が勝手に動いていた。
「泣きます」
「今も泣いてるじゃないか」
「こんなものじゃありません。目が干からびるほどわあわあ泣いて哀しいのを吐き出して、それから……またお店に行きます。それで、今度こそバレないようこっそり覗き見します」
答えながら、これじゃまるでストーカー宣言じゃないかと自分に呆れた。柊二も苦笑いを隠さず、
「君のこっそりは当てにならない」
「きょ、今日はちょっと油断してたんです。今度はもっとうまくやります!」
一体何を力説しているのか、自分でもよく分からなくなってきた。
「柊二さんの視界に入らないよう気をつけます。ご迷惑はかけません」
「待ちなさい。俺は迷惑だとは言ってないぞ」
「え?」
拒絶されたのか受け入れてもらえたのかすぐには判断できず、絢は大きく目を瞬かせた。それからおずおずと、
「じ、じゃあ……また柊二さんのお店に行ってもいい……ですか?」
柊二はその問いには直接答えず、絢に真っ直ぐ向き直り、
「そもそも、俺はもう来るななんて言ってない。来ない方がいいと言っただけだ」
「同じじゃないですか!」
「違う。君にああ言ったのは、迷惑とか邪魔だとかいう俺の気持ち云々ではなく、君のためにはその方がいいと思ったからだ」
絢は思わず本心を口にしていた。
「柊二さん……ずるいです」
柊二は虚を衝かれたように固まったが、すぐに苦笑を浮かべ、
「確かに、そうかもしれないな」
「さっきの答え、まだもらってないです」
絢はそう言って柊二に詰め寄り、涙の残滓にけぶる瞳でじっと睨みつけた。ちゃんと答えてもらうんだという意気込みを隠さずに。
すると柊二は、今度は目を逸らすことなく絢の視線を真っ向から受け止めた。そのまま緊張を孕んだ沈黙が流れ、ややあってふっと空気が緩んだ。
「……仕方ない。またさっきのような目に遭われたら、俺にも責任があることになってしまうからな」
「じゃあ、いい…ですか?」
「ああ」
それを聞いた瞬間、勝手に身体が動いていた。絢は柊二に飛びついて、その胸にきゅっとしがみつく。自分がとんでもないことをしたと気づいたのは数秒後だったが、その時には柊二の腕が背中に回されていた。柊二はあやすようにぽんぽんと叩きながら、
「いいか、絢。君のためには来ない方がいいというのは、嘘ではない。たとえ家元を継がなくとも、紫月流宗家に生まれた君には果たすべき役割があるはずだ」
柊二の言葉が、直接身体に浸透してゆくのが分かる。絢は抱き着いたまま、小さく頷いた。
「だから来ても構わないが、その分稽古にも精を出すこと。あらゆる芸事は、たゆまぬ努力の積み重ねによって少しずつ磨かれてゆく。どうせ駄目だと立ち止まった時点で、全て終わってしまう」
「はい。努力します、お稽古もちゃんとします。だから……柊二さんのお傍にいさせてください」
絢は顔を上げ、直接目を見て訴えた。絢のひたむきな言葉に柊二は一瞬たじろいだようだったが、すぐに頷きを返してくれた。そして絢の濡れた目尻をそっと拭う。
その時初めて絢は、柊二の指が長くすらりとした造形美を持っていることに気づいた。いや、それだけではない。
──柊二さんの瞳、なんて綺麗……。
ぼさぼさの長い前髪の陰で煌く切れ長の瞳は、深い水底を想わせる藍がかった黒。鋭く澄んでいるのに、知性の輝きが幾重にも累なっているため底が見えない。眼差しの力は強く、じっと見つめているとその魔性に搦め捕られ身動きがとれなくなってしまう。
もっさりとした鈍重な外見とは対照的な、剣呑なまでに美しい個性に、絢はかすかな畏怖すら覚え視線を逸らした。すると目元にふっと温かな息がかかり、続いてちくちくしたものと柔らかなものが同時に目尻に触れた。
「ひゃっ?」
未知の感触に絢は間の抜けた悲鳴をあげたが、柊二から離れようとはしなかった。しがみついたままそろそろと見上げると、柊二はのそりと頭を下げ、
「驚かせてすまない」
粗相をした熊のような仕草がなんだか愛おしくて、絢は思わずくすりと笑った。
「ひげ、くすぐったかったです」
「あ、ああ、悪かった」
「でも、あの、唇はとっても柔らかかったです」
だからもう一回してほしい、そんな欲求を言葉にするのは、絢にはまだハードルが高かった。しかし口にしなくとも、その訴えかけるような雄弁な眼差しから想いを汲み取ることは難しくない。柊二は顔を近づけ、絢の目尻にぽつりとともった泣き黒子へ唇を押し付けた。
さっきの不意打ちとは違うしっとりとした感触に、絢はほぅっと熱い吐息を漏らす。すると、吐息の余韻が消えるより早く、柊二の唇がふわりと重ねられた。
「んっ……」
ああ、これがキスなんだ───絢にとって初めての触れ合いは、身体の奥がじんわり熱を帯びて濡れてゆくような、不思議な感覚をもたらした。
絢はそれを正直に伝えようと口を開く。その言葉に、どれほど淫らな含蓄があるか分からぬまま。
「柊二、さん……あの……」
「ん? どうした? 絢」
「身体が……変なんです。お腹の奥が熱くて、くすぐったくて……」
そして、見事に固まった柊二の胸に顔を押しつけ、熱っぽく湿った自問を吐き出す。
「僕……どうしちゃったんだろ、ああ……」
どうしてよいか分からず、絢は腰の辺りに溜まって疼く熱を散らそうと、ゆらゆらと揺らしてみた。しかし熱は静まるどころか、じわじわと全身に広がって指先まで火照らせる。
身体が熔けてしまいそう、そんな感慨をくゆらせていると、切羽詰まったかすれ声で名を呼ばれた。
「絢っ……」
はい、と律儀に答えようとしたが、身体が軋むほどの激しい抱擁に呑み込まれ答えるどころではなかった。呼吸が止まり、悦びと怖れのせめぎ合いに掻き乱される。気がつけば、柊二の手は絢の尻をやわやわと揉んでいた。
こんなことをされたのは初めてだが、不思議と嫌な気がしない。もっとしてほしいとさえ思う。そんな自分の感情にどこか淫靡なものを感じ、絢は小さくふるえた。
すると、それを合図にしたかのように柊二の手は離れた。
「……もう遅い。そろそろ帰らないとお祖父さんが心配する」
とってつけたようなよそよそしい口調に、絢の胸はしくんと痛んだ。眉間に浅い皺が寄るのを抑えきれず、柊二の胸に爪を立て、
「もう少し……ここにいたいです」
すると柊二はなぜか意地悪く口端を吊り上げ、
「なら、泊まっていくか?」
「えっ?! いいんですか?」
喜びに顔を輝かせて聞き返す絢を、柊二は呆然と見返すばかり。
「柊二……さん?」
「あ? ああ、いや。その、分かっているのか? 男の部屋に泊まるというのがどういうことなのか……」
困惑げに訊ねる柊二を見て、絢は自分の過ちにようやく気づいた。
「ごめんなさい。お泊りセットも持ってきてないのに、人の家に泊まろうなんて……」
「お泊り……セット?」
「はい。よその家に泊まる時、迷惑をかけないため持っていく必需品です」
絢の答えに、なぜか激しく脱力する柊二。絢は眉をたわめ、
「柊二さん、大丈夫ですか? 顔色が……」
「ああ、大丈夫だ。それより、やっぱりもう帰った方がいい。家の近くまで送るから。いいな?」
「はっ、はい!」
柊二と夜の散歩ができる。絢は嬉しさからぴょんと立ち上がり、「早く行きましょう」と急かした。柊二は「分かった分かった」と言って、苦笑を浮かべながらのっそり立ち上がった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT