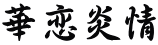
─KAREN ENJOU─
五、哀花の章
本部展が近づくにつれて、屋敷の中も慌ただしくなっていった。絢は与えられた仕事を淡々とこなし、それ以外は部屋にこもって過ごした。
出展作品の構想を練っていると思われているらしく、使用人たちはなるべく干渉しないようにと気を遣ってくれた。そう、意外なことに苑山は、絢の出展を禁じたことをまだ誰にも話していなかったのだ。
もし次代家元候補の一人が出展しないとなれば、大騒ぎになる。だから直前まで伏せておくことにしたのかなとぼんやり考えつつ、ちょっとでも気を抜くと心は柊二の方を向いてしまう。
もう店に来るなと言われてから一週間が経とうとしていたが、絢は未だにしがみついていた。柊二と一緒に過ごした日々の思い出に。
こんな風に何かに心奪われるのは初めてのことだった。柊二にも話した通り、絢はこれまで人にも物にも執着を持つことがなかった。恋愛に対して憧れめいたものはあったが、相手の裏切りや心変わりに悩んだり泣いたりしている人を見ると、何だか怖ろしいような気がして身が竦んでしまう。
情に乱されず心静かに美しい花を生ける、自分にはそんな穏やかな生活が合っているんだと考えるようになってからは、絢の恋愛に対する憧憬は薄れていったのだ。
なのに今、絢の心は平穏には程遠い状態だった。静寂も孤独も嫌いではなかったはずなのに、夜一人でいると淋しくて虚しくて、ふと気づけば泣いている。慌てていつものように口を拳で押さえるのだが、涙は止まるどころかどんどん溢れ、嗚咽まで漏れてくる。
仕方なく涙が流れるに任せ、ようやく涸れ果てたころにはぐったりと疲れてしまい、浅い眠りの波間でゆらゆらしているうちに夜が明ける、という有様だった。
幹も言いたいことを言ってすっきりしたのか、あるいは本部展前で出来の悪い兄に構っている暇がないのか、あれ以来絢に絡んでくることはなかった。
ほっとする反面、幾許かの淋しさもあり、これで本格的に見捨てられてしまったんだなあと、自虐的な感慨に耽ることもあった。
そしてまた今夜も、絢は何をするでもなく、自室で一人無為の時間を過ごしていた。おそらく打ち合わせなどのためだろう、夜になっても人の出入りは多く、部屋の外では慌ただしく人の行き交う音がする。
しかしそれは、もはや絢とは無縁の世界だった。この隔絶された空間の静謐を乱すことができる人物は、たった一人だけなのだ。
その時、ぱさ、ぱさ、と何かが落下するかすかな音がした。絢は振り向くと同時に、悲嘆の声をあげた。
「ああっ……」
ガラスの花器に生けていた、斑入りの赤いチューリップ。店を手伝ったお礼に柊二からもらった花だ。少しでも長く生かそうと丁寧に水切りをして、部屋の温度も温かくなりすぎないよう調節した。
その甲斐あって一週間以上もってくれたのだが、終わりは突然訪れた。残っていた二本とも、一度に全ての花弁が落ちてしまったのだ。
その瞬間に絢が感じたのは、これで柊二との繋がりが完全に絶たれてしまったというリアルな喪失感だった。それは哀しみを通り越して、恐怖を喚起した。
「い、いやだっ……」
絢は落ちた花びらを拾い上げた。それは瑞々しさも弾力もなく、指の間でくたりと伸びた。その上に、ぽつぽつと涙が降りかかる。
その時絢は、ようやく理解した。自分は柊二のことが好きなのだと。経験したことのない胸の痛み、感情の乱れ、そして涙。これらは全て、柊二への想いから派生しているのだ。
絢は立ち上がって部屋を飛び出した。誰とも顔を合わせることなく屋敷を出ることができたが、その幸運を喜ぶ余裕もなかった。夜の街を走り、通い慣れた商店街へ急ぐ。
ほとんどが店じまいをしており、人通りもない。絢は弾む息を抑え、足音を忍ばせて石畳を歩いた。やがて───
「柊二…さん……」
柊二は一人、閉店作業に精を出していた。店の陰に隠れてその様子を窺っていた絢は、何度も歩み出ようとしたのだが、黙々と働く柊二の姿には、安易な接近を許さぬ修行僧のような厳かさがあり、なかなか近づけない。
それを見ているうちに、絢は自分の感情的で甘えた行動が恥ずかしくなり、くるりと背を向けた。しかしこのまま帰るのは忍びなく、脇道に入ってカフェへ向かった。閉店時間を過ぎていることは分かっていたが、目的は柊二の生けた花を観ることだったから問題ない。
人気のない小路に、コツ、コツ、と自分の足音が響く。そういえば、こんな遅い時間に一人で出歩くのは初めてかもしれない。
しかし柊二のように、この時間まで働いている人はたくさんいる。そんな当たり前の事実に今さら思い当たり、絢は自分の幼さに思わず唇を噛み締めた。
やがて、薄闇の中にカフェの白い外観がぼんやり浮かび上がった。当然ながら照明は全て落とされ、ひっそり静まり返っている。石碑の前に生けられた柊二の花を観るため、絢はテラス側に回った。その時、
「あんだよこれ、邪魔くせぇ!」
明らかに酔っていることが分かる怪しげな呂律の怒鳴り声が聞こえた。絢はびくっと飛び上がり、反射的に物陰に身を潜めた。
「こんなとこに花なんか飾ってんじゃねえよ。通れねえだろ!」
喚いているのは、三人組の若い男だった。そのうちの一人の服に、柊二が生けたつるそけいの枝が引っかかってしまったようだ。
もちろん、通行人の邪魔になるような生け方はしていない。三人とも酔いが足にきているようで、道から外れてふらふらよろめいている。そのせいだった。
「ったく、邪魔なんだよ!」
一人が枝を無造作に引き抜いて、地面に叩き付けた。つるそけいの黄色い花弁が無惨に散るのが目に入ると同時に、絢は飛び出していた。
「やめてください!!」
叫びながら男たちを押しのけて駆け寄り、花をかばうように腕を広げる。そしてキッと見上げ、
「こ、この花は自殺者を供養するため供えられたものです。乱暴なことはしないでくださいっ」
必死の訴えは、男たちの酔いただれた頭には何の効果もなかった。いや、それどころか──
「なんだぁ? てめえ。俺たちを悪者みたいに言いやがって」
「通行人の邪魔だから、わざわざどかしてやろうってんのによ」
「おら、どけよ」
最後の男は足を振り上げ、花器を蹴りつけた。あとの二人は、柊二の手によって幽玄の美に昇華されたつるそけいや百合の花を掴み、花器から引き抜いた。
「だめっ……」
またさっきのように地面に叩き付けられる。そう思った絢はとっさに男の腕にしがみつき、花を奪い返した。しかし、その勇敢な行為の代償は大きかった。
「こいつっ……」
男たちは派手な舌打ちをして、絢の胸ぐらを掴み上げた。そして拳を振りかぶったが、途中でぴたりと止めた。
「……おい、こいつ男、だよなぁ?」
「ああ? なに言ってんだよお前……」
男の間抜けた問いに、残る二人は呆れたように返した。しかし、絢の顔を覗き込んで小さく喉を鳴らし、
「ちょっと確かめてみようぜ。なあ?」
そう言って絢を石碑の裏に引きずった。絢は花が折れないよう守るので精いっぱいで、抵抗すらできず大きな石碑の陰に連れ込まれる。気がついた時には、男たちの間に漂う空気が一変していた。
さっきまでの分かりやすい暴力一辺倒とは違う、生臭い何かが絢の皮膚を撫でる。その正体が分からぬながらも、絢は生理的な嫌悪を覚え小さくふるえた。
すると絢の怯えを察したのか、一人がにたりと笑ってぬっと手を伸ばしてきた。そして絢の胸を乱暴に揉んだ。
「あ、やっぱ男だ」
「マジか? うわ、男相手に初めて勃った」
「いいじゃん。男同士ならゴーカン罪にならないって聞いたことある」
「んじゃ、ヤッちまうか」
彼らが何を話しているのか分からないけれど、本能が早く逃げろと繰り返し警告していた。絢は震える下肢を急き立て、立ち上がろうとした。しかし、
「おおっと。逃がさないよ。お前、そっち押さえてろ」
「了解」
絢は後ろから羽交い絞めにされ、動きを封じられた。当然ながら抱いていた花は落ち、男たちの足に踏みにじられる。
「ああっ」
絢は悲愴な声をあげて、手を伸ばそうともがいた。すると男たちは一斉に笑い、
「花の心配してる場合じゃねえだろ」
馬鹿にしたようにそう言い放って、絢のセーターをたくし上げた。突然の冷たい夜気に、絢は小さな悲鳴を漏らす。すると男の大きな手に口を塞がれ、悲鳴はこもったような呻きに変わった。
「んぅっ、う、うぅっ……」
恐怖と混乱から涙腺が勝手に緩み、絢の瞳は涙に覆われた。それがさらなる加虐の欲求を呼び起こし、男たちを狂わせると知らぬまま。
「あんた、すげえいい、ヤバい……」
男たちの傍若無人な手が、絢の平らな胸や滑らかな下腹を撫でさする。さらにベルトが外され、下着ごとずり下ろされようとした時、
「ぐがっ、が、がッ」
背後から苦悶の声が聞こえ、絢の拘束はあっけなく解かれた。振り向いた視線の先では、太い腕に首を絞められた男が、泡を吹きそうな勢いでもがいていた。
「柊…二さん……」
失神寸前で男を解放した柊二は、残る二人に対峙した。闇を従えたその風格といい、ダウンジャケットの上からでも分かる精悍な身体つきといい、集団行動で個々の弱さをごまかして何とか生きている草食動物とは格が違う。
「な、なんだよてめえ」
男は一応吼えてはみたものの、完全に腰が引けている。すると柊二は、一人の手をがっしと掴んでその爪を引っ張り、
「花びらをむしられる痛みを教えてやろうか」
地を這うような低い声で告げた。男たちは暗闇でもはっきり分かるほど青ざめ、引きつった謝罪を繰り返しつつ一目散に逃げ去った。
呆然と座り込んだままだった絢は、慌てて涙を拭ってセーターを下ろすと、地面に散らばった花をそっと拾い上げた。
「……絢」
名を呼ばれて、絢は喜ぶどころか身体をびくりとふるわせた。柊二の声に、咎めるような響きを聞き取ったからだ。絢は深く頭を下げ、
「ごめんなさい、柊二さんの花、守れなくて……」
「そうじゃない」
苛立ちも露わな声で遮られ、絢はさらに小さくちぢこまる。すると打って変わって和らいだ声で、
「全然戻ってこないから捜しにきてみたら、あんなことに……。あまり心配させないでくれ」
「えっ? 僕が来てたの知ってたんですか? 隠れてこっそり覗いてたのに」
「あれは隠れているうちに入らん」
呆れたように言われ、絢は恥ずかしいやら情けないやらで、まさに穴があったら入りたい状態だった。肩をすぼめて項垂れていると、柊二が目の前に膝をつき、絢の手をそっと取った。
「無茶をするな。手を大事にしなさい」
言われて初めて、絢は手がちりちり痛むのに気づいた。石碑の裏に連れ込まれた時にすりむいてしまったのだろう。
「はい、ごめんなさい」
「痛むか?」
「少し、だけ……」
柊二は頷くと、絢の身体を抱えて立ち上がらせた。そして散らされた花を手早く拾い上げる。
「すぐに生け直せば助かるものもある。あと、君の手当てもしないとな」
そう言って、柊二は歩き出した。絢は慌ててその後を追う。すると柊二は歩調を緩め、
「……あの男たちに、何もされなかったか?」
その問いを受けてようやく、絢はあの男たちが何をしようとしていたのか疑問を抱いた。
「え、えと……口を塞がれて、胸とお腹を触られました」
「それだけ、なんだな?」
安堵と怒りの混じった不思議な声に、絢は「はい」と素直に返し、柊二の横に並んだ。柊二は前を向いたまま、
「今後は十分注意するように」
何に対して注意するのかよく分からないまま、柊二の真剣さに圧されるように絢は頷いた。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT