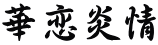
─KAREN ENJOU─
四、迷花の章
「こんな感じでいかがでしょうか?」
客の要望を聞きながら絢が作ったブーケは、どうやら気に入ってもらえたようだ。アマリリスを中心に据え、ポンポンマムとセルリア、コチアをラウンド形にまとめた白いブーケ。
客はまるで宝石でも受け取るかのように恭しく手を差し出し、「ありがとう」と言って心から嬉しそうに笑ってくれた。
不思議だった。これまで、花を生けてお礼を言われることなんてなかった。華道家なのだから、花を生けて当たり前。苑山ほどの大家になれば別だろうが、絢程度のひよっこがどれだけ心血注いで生けたところで、感謝どころかダメ出しされておしまいだ。
なのにここでは、簡単なブーケをこしらえただけで笑顔と感謝をもらえる。同じ花を扱う世界なのに、自分が身を置く厳しい世界とのあまりの落差に絢は眩暈すら覚えた。
「あの、私もいいですか? 予算は二千円ぐらいで、赤を基調にした可愛らしい感じで……」
「はいっ、お待ちください」
絢は勇んで頷き、赤いガーベラに千日紅、イタリアンベリーをコルダータの葉で包むようにまとめた。そしてベアグラスの細い葉をアクセントに。
客の女性は「可愛い!」と飛び上がって喜び、「ありがとうございます」と何度も頭を下げて帰っていった。
「コルダータで包んだのがよかったな。最近の若い女性は、パステルカラーのペーパーで包んでリボンをかけて、といったいかにも花束風なアレンジを嫌う傾向がある」
柊二に褒められたのが嬉しくて、絢は浮かれた口調で軽口を返した。
「最近の若い女性は、なんておじさんみたいですよ」
「悪かったな。俺はこれでもピチピチの三十三歳だ」
「僕は十九です!」
「ふん。若さなんてあっという間に弾けて消えるぞ。バブルみたいになっ」
柊二はそんな負け惜しみを言いつつ、店頭に置くミニブーケの制作に励んでいる。こうして見ていると本当に、ザ・熊の花屋さん、だ。
絵本の挿絵にぴったりな光景に、思わず心和む。ずっと眺めていたい。ずっとここにいたい。ずっと……この人の傍にいたい。でも、
「あ、もうこんな時間。帰らなくちゃ……」
遅くなると、また幹に問い詰められる。柊二と出会ってから二週間が経とうとしているが、絢はその間二日と空けず花屋を訪れ、こうしてアルバイトの真似事をしていたのだ。
柊二は給料を払うと言ってくれたが絢は固辞し、その代わり古くなった花をもらって帰った。それを自分の部屋で生けるのが、二番目に幸せな時間だった。もちろん一番は、こうして柊二と一緒に花屋にいる時間だ。
そんな絢の変化に、敏い幹が気づかぬはずはない。だから絢はなるべく普段通りを心がけ、幹が帰宅する時間には家にいるようにしていたのだ。
「それじゃ、また明日来ますね」
絢はそう言って、笑顔で手を振った。
「ん、ああ……」
それに対し柊二は、いつも何か言いたそうに口ごもる。気にならないと言えば嘘になるが、商店街を歩いているうちに忘れてしまう。また明日彼に会えるという喜びで薔薇色に染まった心に、不安や気がかりが入り込む隙はなかった。
そして翌日。絢はいつもの時間に家を出ようとした。しかし、
「兄さん、また出かけるのか。どこ行くんだよ」
玄関で、切れ長の目をさらに吊り上げた幹にきつい口調で呼び止められた。絢もつい喧嘩口調になる。
「幹には関係ない。それより、学校はどうしたんだ」
「今日から試験休み。ていうか、関係ないじゃないだろ。本部展が近いっていうのに、どこを遊び歩いてるんだよ。俺たちは、次代の紫月流を支えていく人間なんだ」
「この前も言っただろ。僕は本部展への出展を禁じられたんだ。家元候補は二人もいらない。一人で十分だ」
絢はぴしゃりと言い返すと、幹を顧みることなく家を出た。一刻も早くあの場所に行きたかった。今や、自分が心から笑って寛げる場所はあそこだけだった。
そんな想いに急き立てられていたせいで、絢は自分の後を幹がこっそり付けていることに、全く気づくことができなかった。
「おはようございます!」
絢は元気いっぱいの挨拶とともに、柊二の花屋に入っていった。まだ時間が早いせいで客はおらず、窓から射し込む日の光を浴びた花たちが気持ちよさそうに呼吸しているのが伝わってくる。
絢は、この時間が大好きだった。花に包まれ、柊二と二人で過ごす時間が。しかし、
「こんなとこで何やってんだよ、兄さん」
狭い入り口を塞ぐように、幹が立っていた。絢は呆然と見返し、
「か、幹……どうしてここに……」
「どうして、はこっちの台詞だ。一体どういうつもりなんだよ。まさか、こんなチンケな花屋でアルバイトしてるんじゃないよな? 紫月流の名を汚すつもりか?」
幹は怒りと苛立ちを隠さずそう言って、ディスプレーされている紫のカラーをぴんと指で弾いた。すると柊二はその手を掴み、
「紫月流は、そんなぞんざいに花を扱うのか? 兄弟喧嘩なら外でやってくれ。迷惑だ」
絢と幹をまとめて店の外に追い出した。幹は望むところとばかりに絢と向き合い、長年のうちに溜まった感情をぶつける。
「兄さんはいつもそうだ。どうせ自分なんかと卑屈になって背中を向けるばかりで、正面から挑もうとしない。本部展への出展を禁じられたのなら、じーさんの前で何度も何度も生けて許可をもぎ取ればいいじゃないか。俺ならそうする」
その口調は厳しいものだったが、不思議とこれまでのような刺々しさは感じられなかった。思いがけぬ真摯な訴えに絢は戸惑いつつも、きっぱりとはね付けた。
「そんな我を通して駄作を披露したところで、恥をかくだけ。それこそ、紫月流の名を汚すことになる。お祖父様もそう考えたからこそ、出展を禁じたに違いないよ」
「我を通して何が悪い。恥をかいて何が悪い。そこから掴み取れるものがあるはずだ。歴代の家元も、そうやって躓きながら己の技と心を磨いてきたんだ」
幹の言葉は、あまりに正論だった。ゆえに絢は耐えられず顔を背け、
「家元は幹が継ぐんだから……それでいいじゃないか」
「そういう問題じゃない! どっちが家元を継ぐとか、そんなことはどうでもいい。俺はただ、紫月流の伝統を守りながら華の道をたくさんの人に広めたい、それだけなんだ」
いつの間に、幹はこんなしっかりした考えを持つようになったのだろう。紫月流宗家としての責務を果たす覚悟を、彼はすでに固めていたのだ。でも、やはり、
「僕はもう……いい」
喉の奥から這い上がってくるのは、自分に見切りをつけたかのような呟きだった。幹はこみ上げる感情を抑え込むように拳をぎゅっと握り締め、
「努力もせず諦めるのは、潔さとは違う。兄さんは逃げてるだけだ」
痛烈に言い放って去っていった。絢は店先にぽつんと一人佇み、遠ざかる弟の背中を見送る。まるで今の自分たちを象徴するような光景だなと、他人事のように思ってしまう自分が、絢は可笑しくもあり哀しくもあった。
「……紫月流の跡取りか」
店の中から聞こえた問いに、絢は弱々しい声で「はい…」と答えた。そして店内に戻って柊二と向き合う。
「紫月流のこと、ご存知なんですね」
「花に携わっている者なら誰でも、紫月の名ぐらい知っている」
「そう、ですよね……」
絢は自嘲気味に微笑んでみせると、ぽつりぽつりと身の上語りを始めた。自分のことを話すのは苦手だったけれど、柊二の真剣な相槌に導かれるように言葉が溢れてきた。
「父が流派を去ったのは、僕が九歳、弟が八歳の時です。紫月流家元の祖父は、僕か弟のどちらかに流派を継がせると宣言して、それ以来ずっと僕たちに厳しい教育を施してきました。僕は怠けたつもりはないけど、祖父を満足させられるのはいつも弟の幹の方でした。たぶん、努力とかそういう次元の話ではないのでしょうね」
どうしても、自らを哀れむような口調になってしまう。兄さんはいつも卑屈になってる、という幹の言葉が脳裡をかすめたが、絢は改めようとはしなかった。
「小さいころ教え込まれた基本の『型』。そこから脱却しなければ、人を感動させるものを生み出すことはできない。それは分かっているけれど、どうしたらいいのか分からないんです」
お前が生けるのはただの花だ。華の道には程遠い───祖父から繰り返し浴びせられた叱責が、身体の中で行き場をなくしどろりと滞留している。
『華は詩的官能』
『華は美と醜の弁証法』
『花に情念が宿ってこそ華となる』
『華は人なり、人は情なり』
これらは全て苑山の言葉だ。流派に属する者はみな心に刻みつけ、ゴールのない華の道を歩み続ける。もちろん絢も心に留めてはいるが、それらを理解し自らの血肉とするには到っていない。
「僕にとって花は美しく、安らぎを与えてくれるもの。美の彼方にある情念など分かりません。でも、それじゃ駄目なんです。祖父からはついに、引導を渡されてしまいました。来月、年一回の最重要行事である本部展があるのですが、お前は出展しなくていいと宣告されました。そう、初めて柊二さんに会ったあの日にです」
絢はそう言って、力なく微笑んだ。自分のことなのに、まるで他人の話をしてるみたいだなとぼんやり思っていると、柊二も同じ感想を抱いたのか、「悔しくはないのか?」と訊かれた。絢は笑みを深め、
「正直……分かりません。僕はもともと、何に対しても執着というものが薄いようです。見捨てられた淋しさや、お祖父様の期待に添えず申し訳ないという思いはありますが、弟が優秀だから流派の存続には問題ないでしょうし。これでよかったのかなと」
そうだ、これでよかったんだ。自分は、流派や伝統を引き継ぐ精神力も才覚も持ち合わせていない。自分の限界を悟って身を引くことは、決して逃げではない。絢がそう納得しかけた時、柊二が静かに口を開いた。
「執着を持たないのは、失敗した時や認められなかった時に傷つかないための予防線としか思えない。逃げてるだけという弟の言い分は正しい」
「なっ……!」
あまりに容赦ない物言いに、普段めったに声を荒げることのない絢も思わずカッとなり、噛みつくように言い返した。
「あなたに何が分かるというんです! 小さいころからずっと弟と比べられて、周囲からは出来の悪い兄と言われて。かといって他の道を見つけることもできず、同じ場所でもがいてばかりでっ……」
絢は慌てて拳で口を押さえた。そして泣くな、泣くなと声に出さず唱える。そのまま深呼吸すると、激しい感情はすーっと引いていった。
しかしその後に残ったのは心の安寧ではなく、無味無臭のざらりとした虚無感。長い間感情を抑え続けたせいで、自分の心は死にかけているのかもしれないなと、絢は他人事のように思った。
そうして悄然とうなだれる絢に対し、柊二は再び口を開いた。その言葉は依然として厳しかったが、声の芯には包み込むような優しさが息づいていた。
「この場所は居心地がいいだろう? 厳しい祖父や芸事のことを考えず、家元候補という重圧からも解放されて花と触れ合うことができる。簡単なブーケを作っただけで、お客に喜んでもらえる。けれどこのぬるま湯に浸かって厳しい現実から目を背けるのは、やはり逃げていることになる」
柊二はいったん口を閉じ、なぜか毒々しい自嘲を浮かべた。しかしすぐにいつもの優しい表情に戻り、絢の頬を大きな手のひらで包み込むように撫で、
「もがきなさい、苦しみなさい。そうすれば必ず、何かが見えてくる。それが今の君に足りないものだ」
「僕に足りないもの……」
「そうだ。“それ”は闇の果てにある光のように美しいものとは限らない。直視が憚られるような醜いものかもしれん。けれど怖がることはない。君のお祖父様も、それ以前の偉大な家元たちもみな通ってきた道だ」
柊二が大切なことを伝えようとしていることは分かっていた。けれど絢の意識はどうしても、頬を優しく包む大きな手、そしてそこから伝わる温もりに引き寄せられてしまう。
温もりはあっという間に皮下に浸透し、身体じゅうを巡る。絢は全身が火照るのを感じつつ、柊二の手におそるおそる自分の手を重ねようとした。その時、
「分かったね? 絢」
「あ……」
初めて柊二が名前を呼んでくれた。それだけで、女の子みたいで嫌だなあと思っていた名前が、途端に唯一無二の輝きを帯び始める。さっきまでのしおれた気持ちが嘘のように、絢は胸を弾ませた。
もう一度、名前を呼んでほしい。そんなささやかな、それでいて切実な願いを口にしようとした時、絢は一気に奈落へ突き落とされた。
「君のいるべき場所はここではない。だからもう、ここへ来てはいけない。いいな?」
「…………」
直面した現実の冷たさと温もりの落差が激しすぎて感情が付いていけず、絢は呆然と固まった。やがて、凝固した心がゆっくりと溶け出すように、大きく見開いたままの双眸から涙がはらはらとこぼれた。
「僕……ぅっ、ぅ……」
人前で泣くのは本当に久しぶりだったが、そのことに思いが至らないほど絢の哀しみは深かった。涙で視界が霞み、柊二がどんな表情をしているのか分からないのが、絢にとって唯一の救いだった。
もし迷惑そうな顔をしているのを見てしまったら、一生立ち直れないだろう。
「今まで……ありがと…ございま…した……」
絢は息も切れ切れに感謝を述べると、小さくお辞儀をして店を飛び出し闇雲に走った。立ち止まったらきっと、柊二のもとに戻ってしまうと分かっていたから。
柊二は店先で、徐々に小さくなる絢の背中を見送った。思わず追いかけそうになる自分を何度も叱りつけ、ようやく絢の姿が見えなくなって、強張った肩をすとんと落とした。
「ちゃんと、真っ直ぐ家に帰るんだぞ」
届くはずのない言葉には、柊二の切実な願いが込められていた。まるで朝露滴る白百合のように可憐な泣き顔を、あんな無防備にさらした状態がどれほど危険か、男の邪な欲望を刺激するか、絢は一ミリも理解していないに違いない。
柊二は、絢の涙を受け止めた手をじっと見つめたが、すぐに頭を振って店の中に戻った。そして店内をぐるりと見渡す。狭いながらも居心地のいい我が城。絢がここに来たくなる気持ちも分かる。
「ぬるま湯に浸かって厳しい現実から目を背ける、か……ははっ」
苦い自嘲の毒で舌が灼けそうだ。まったく、よくもえらそうに言えたものだと思う。厳しい現実から十年にわたって逃げ続けている張本人のくせに。いや、だからこそ。
「絢、君は逃げてはいけない。俺のようになってはいけない」
柊二はぽつりと呟くと、丸く膨らみ開花の熱を秘めた椿の蕾に触れた。街の花屋で扱うには、椿は難しい花だ。しかし柊二は、季節になれば必ず仕入れた。“彼”が好きだった椿を、いつも身近に置いておきたかったのだ。
「お前が……引き合わせてくれたのか?」
柊二はまだ硬い蕾に問いかけたが、答えはどこからも、天からも返ってくることはなかった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT