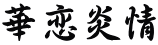
─KAREN ENJOU─
三、供花の章
絢がその店を再び訪れたのは、最初の出会いから三日後のことだった。
僕のこと覚えてるかな、覚えてなかったら普通に客として振る舞おう、でも名前言ったら思い出してくれるかも、そんなことをぐるぐると考えつつ商店街を歩く。
店に近づくにつれて、脈拍がどんどん上昇して顔が火照ってゆくのが分かる。絢はいったん立ち止まって深呼吸をした。それでも動悸は収まらない。
人前で何かをしたり祖父の前で花を生けたりする時など、緊張で震えることはよくあったが、そのドキドキ感とは全く違う。
どこがどう違うのか言葉で表すのは難しいけれど、ただの緊張では、こんな風に胸の奥がくすぐったくなるようなことはなかった。
これまで経験したことのない感情が生まれつつあるのを感じながら、絢は再び歩き出す。さっきより若干速めのスピードで。そして商店街の一番端、柊二の小さな花屋に着いた。
「こんにちは……」
絢はおそるおそる声をかけ、店の中を覗き込んだ。狭い店内には、客が三人。柊二は相変わらずのもっさりした髭づらで、客の注文に応えブーケを作っている。その手際たるや見事なものだったが、やはり一人で応対するのは大変そうだった。
絢がいったん出直してこようか迷っていると、柊二と目が合った。
「あ、あのっ、僕……」
あわあわしつつ名乗ろうとしたが、それに先んじて柊二が思いもかけないことを言った。
「ああ、いいところに来てくれた。ちょっと頼んでいいか?」
そして絢の返事も聞かず、大きな花束を差し出し、
「あの脇道を入って少し行ったところに、『ASTERAS』というカフェレストランがある。白とブルーが基調の、オープンテラスのある店だ。そこにこの花を届けてくれ。代金はもらっているから、渡すだけでいい」
「は、はい……」
勢いに圧される形で絢が受け取ると、柊二は「悪いな、助かる」と言って再びブーケ作りに精を出す。絢は言われた通り脇道を入り、白とブルーの日よけがお洒落なカフェにそおっと顔を出した。
「あの~、花を届けに参りました」
ランチタイムは終了しており、客はまばらだった。絢が声をかけると、フロアにいた店員が目を丸くして駆け寄ってきた。
「あらっ? いつもの花屋さんじゃないのね」
「あ、いえ。店主は接客で忙しいので、僕が代わりにお届けにきました」
「まあまあ、ご苦労さまです。あ、よかったらコーヒーでも召し上がっていきません? ね?」
いつの間にか他の店員も集まってきた。その瞳はきらきら輝き、みな客そっちのけで絢に熱烈な視線を送る。
絢はどうしてよいか分からず、「お店に戻らないと…」ともごもご言いつつ断ろうとしたその時、視界に鮮烈な色彩が飛び込んできた。
「ああ……」
絢は言葉を失い、その鬼気迫る紅の焔にただ溺れた。それは小道を隔てた店の向かい側に生けられた真紅のグロリオーサ。細長く波打ち、反り返って咲く花弁が特徴のこの花は、生け花でもよく使われる。もちろん絢にも馴染みの花だ。
けれど今、絢の眼前にあるそれは、未知の何かだった。
ただ美しいだけではない。激しいだけではない。狂気と紙一重の厳かな静寂すら感じられる造形に、絢は全身が粟立つのを抑えられなかった。
「綺麗でしょう? あれ、花屋さんが生けてくれたんですよ」
店員の言葉が、絢を一気に現実へ引き戻した。
「花屋って、あの、熊みたいな……」
「そうそう、あの人です。人は見かけによらないですよねえ」
店員は自分の言葉に頷いて、くすくす笑う。しかしすぐに真面目な顔つきになり、
「あそこに石碑があるでしょう? うんと昔の話ですけど、あそこには小さなお寺があって、自殺者の供養が行われていたそうで。そんな話を花屋さんにしたら、それ以来毎週ああして花を供えてくれるんです。あれ見たさに来店するお客さんも多いので、冬でもなるべくテラスを開放するようにしてるんですよ」
「そう、だったんですか……」
絢は驚きと感嘆を隠さず、溜め息混じりに呟く。そして「もう少し近くで見てもいいですか?」と訊ねると、店員がテラス席に案内してくれた。小道を挟んだ真正面に、柊二の花が咲き誇る。
「ごゆっくりどうぞ」
いつの間にか、テーブルにコーヒーが運ばれていた。絢は慌ててお礼を言うと、再び花に向かい合った。
「すごい……」
近くで見ると、より一層凄みが増して胸に迫ってくる。グロリオーサ一種だけでここまで豊かな表情を作り上げることができるのかと、驚きを超えた畏怖すらこみ上げてきた。さらに、
「花が……泣いてる?」
何をバカなことを言っているのかと自分に呆れつつ、この花なら笑ったり泣いたりしても不思議じゃないかもしれない、などと思う。
実際、耳を澄ますと聞こえるのだ。時に甲高く、時にすすり泣くような不可思議な音。それはまさに鬼哭。浮かばれない霊魂の泣く声に相応しい霊妙な響きだった。
「あっ、そうか」
風が吹くたびに聞こえる『声』の正体に、絢はようやく気づいた。花器だ。竹の筒を何本も重ねて作られた花器に、花は生けられている。竹筒の中を風が吹き抜けることで音が鳴るのだ。
発せられる音色は、筒の太さによって異なる。それらが重なり合って、この世のものとは思えぬ神秘的な響きを奏でているのだ。
気がつけば、絢の頬は濡れていた。この花は、柊二にとっての鎮魂歌(レクイエム)だ。自ら命を絶たざるを得なかった哀れな魂を慰めんがため、花を生ける。そういった強い念が花に宿り、見る者の心を揺さぶる。
そう、まさに花には、生けた人間のありのままが映し出されるのだ。
とはいえ、想いだけでこれほど見事に研ぎ澄まされた造形美を生み出せるはずがない。想いを形にするための技術が伴わなければならない。
「柊二さん、あなたは一体……」
絢は答えのない問いを呟くと、冷めたコーヒーに口をつけた。
絢がカフェから戻ると、柊二は狭いカウンターで黙々と帳簿に向かっていた。さっきまでの忙しさが嘘のように、店内は静寂に満たされている。
この空間だけ外の喧噪から切り離されているような、結晶のような静謐をなるべく乱さぬようにと絢はそっと声をかけた。
「あの……花届けてきました」
すると柊二はぱっとこちらを向き、もしゃもしゃの髭づらでにっこり笑った。
「ああ、ありがとう」
その瞬間、絢の心臓は跳ね上がり、顔がかあっと火照る。カウンターから出て近づいてきた柊二は、そんな絢の顔を見て、
「外、寒かったみたいだな。鼻の頭と頬が真っ赤だぞ」
「は、はい……ちょっと、寒かったです……」
顔が火照っているのは寒さのせいではないと分かってはいたが、では本当の理由は何なのか、絢にはまだちゃんと答えを出すことができない。だから取り敢えず同意して、鼻をすんと鳴らしてみせた。
「いきなり使い走りさせて悪かった。いま、温かいコーヒーでも淹れよう」
「あ、いえ。さっきカフェでいただいてきたので」
「花を届けたカフェか?」
「はい。店員さんがご馳走してくれました。みなさん、とても優しくていい方ばかりですね」
絢の言葉に、柊二は苦々しい表情を浮かべ、
「俺が届けに行った時は、早く帰れと言わんばかりに追い出すくせに。人によって態度を変えるなんて、客商売失格じゃないか」
「ま、まあまあ」
絢は半笑いで宥めた。確かに、あのお洒落なカフェに髭もじゃの熊男が出没したら、客も驚いてしまうだろう。
「……今、仕方ないって思ったな?」
柊二の鋭い指摘に、絢は素直に頷いた。柊二は頭をがりがり掻いて、
「どうせ俺は花泥棒の熊男だよ」
その不貞腐れた物言いがおかしくて、絢は声を上げて笑った。しかしすぐに顔を引き締め、
「柊二さんの生けた花、見ました。テラスの向かいにある石碑に供えられた花です」
「ああ、あれか」
絢の熱っぽい口調とは対照的に素っ気なく返すと、柊二はふっと後ろを向いてしまった。その強張った背中には、この話題に対する彼の消極的な気持ちが表れていた。絢は一瞬躊躇したが、自分の感動を伝えたいという想いがまさった。
「グロリオーサの花だけで、あんな豊かな表情が生み出せるなんてすごいです! それに、自殺者の魂を慰めようという柊二さんの想いがひしひしと伝わってきました」
「…………」
柊二は無言のままだったが、絢の方に向き直った。そしてじっと見下ろしてくる。髭づらには似合わぬ透徹した眼差しに射すくめられ、絢は小さく震えた。しかし臆することなく視線を重ね、
「柊二さんはあれを生けている時、自ら命を絶った人の痛みに思いを馳せ、心から哀しみ悼んでいたのでしょう?」
絢の問いかけに、柊二は目を見開いて驚きを露わにした。しかしすぐに無表情に戻り、
「なぜ、そう思うんだ」
「花には、生けた人間のありのままが映し出される───そう言ったのは他ならぬ柊二さんです。あの花を見れば誰だって分かります。生けた人の深い想いが。だからこそ、たくさんの人を感動させることができるんです。カフェの店員さんが言ってました。柊二さんの生けた花が見たくてお店に通う人もいるって」
自分の拙い言葉がもどかしい。柊二の花にどれほど胸打たれたか、惹きつけられたか伝えたいのに、言葉が感情に追いつかない。絢は顔を紅潮させて、さらに続けようと口をぱくぱくさせた。
すると、柊二の手がいきなりぬっと伸びてきて、絢の頬に触れた。絢は口を開けたまま固まり、次の瞬間ぼっと音が出そうなほど赤くなった。
柊二の手は温かくて、花屋という職業柄か指先はカサついていた。しかし頬を包み込むような触れ方はとても優しく、絢は恥ずかしさも忘れうっとりとなった。が、
「ふぁ? な、なにするんですか!」
頬をぶにっとつねられ、絢は思わず尖った声を上げた。柊二は悪びれることなく、にやりと笑い、
「いや、すまん。あまりにムチムチしてたんで、つい」
「ひ、ひどいですっ。人が真面目に話してるのに……」
「はは、そうだな」
柊二はいつものほんわかした笑顔を浮かべると、絢の頭をぽんぽんとあやすように撫でた。そして、
「ありがとう」
そのたったひと言で、絢は自分の言葉がちゃんと伝わっていたことを悟った。
「しゅ、柊二さん、あの……」
「ん? なんだ?」
「コーヒー、いただいてもいいですか?」
もう少しここにいたい、そんな思いを乗せた絢のお願いに柊二は笑顔で頷きを返し、ミルクがたっぷり入ったコーヒーを淹れてくれた。
明日も明後日もまたここに来てしまうに違いない。絢は胸が疼くような予感とともに、甘くてほろ苦い液体をすすったのだった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT