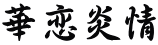
─KARENENJOU─
二、想花の章
「狭い店だろう?」
その言葉通り、男性の営む花屋は駅前商店街の一番端にある、八坪程度の小さな店だった。しかし、
「うわあ……すごい。珍しい花材がいっぱい……」
花はもちろん、いわゆる枝もの、実ものの充実ぶりに絢は目をみはった。紫もどきにシンフォリカルポス、桐の実、つる梅もどき、ペッパーベリーと、町の花屋ではそうそうお目にかかれないような花材が揃っていた。
だからといって、薔薇やガーベラ、カスミソウなどポピュラーな花材を疎かにしているわけではない。見慣れたものと斬新なものがうまく溶け合って、互いの魅力を引き出している。
また、ディスプレイや空間の使い方にも独特のセンスが溢れ、眺めているだけで感性が刺激される。絢は久しぶりに、花を生けたいという衝動がこみ上げるのを感じた。
「素敵なお店ですね」
「そうか? 言っておくが、花は盗んできたものではないぞ」
絢はちょんと肩をすくめ、
「ごめんなさい。花泥棒は言いすぎました。う~ん……熊男さん、かな」
すると男性は天を仰ぎ、
「近所の小学生にも、熊が花売ってるとよく言われる。ったく近ごろのガキどもは……」
彼が子供たちに囃される光景を思い浮かべ、絢はつい笑ってしまった。その流れで、自然と自己紹介する形に。
「僕は紫月絢といいます。あや、なんて女の子みたいな名前でしょう?」
しかし、彼が気にしたのは名前の方ではなかった。
「紫…月……」
「あ、はい。あの、何か?」
眉間に浅いしわを寄せて黙り込む彼に、絢は尋常ならざるものを感じた。しかし男性はすぐに「いや、何でもない」と答えて、さっきまでの気安い雰囲気に戻った。
「俺は……日向、日向柊二(ひむかい・しゅうじ)だ」
「柊二さんは、いつからこのお店を?」
「うん? そうだな、ここに店を開いたのは半年ほど前か」
「割と最近なんですね。それにしても、変わった品揃えですね。こういう実ものって、飾るの難しいんじゃないですか?」
絢自身、実ものを生けるのが苦手だったこともあり、ついそんな言葉が出てしまった。すると柊二はさらりと答えた。
「難しいと考えなければいい」
「え?」
「難しいと感じてしまうのは、自分の中に正解や理想の形があるからだ。しかし、花に正解も間違いもない。普遍の理想形もない」
絢は、意識せず背筋が伸びるのを感じた。まるで、身体が彼の言葉をひとつも聞き漏らすなと言っているかのようだ。
「花は、どう生けてもどんな素材と合わせても構わない。そもそも、土から生えている花や木を切って飾る時点で不自然なんだからな。重要なのは、死に向かいつつある切り花に対し真摯に向き合い、その美しさも怖ろしさも醜さも全て受け容れることだ」
柊二はそう言ってどこか自嘲めいた笑みを浮かべ、
「それはつまり、己の醜さを受け容れることでもある。生けた花には、自分のありのままが映し出されてしまうから」
絢はきゅっと唇を噛み締めた。そう、その通りだ。今日、祖父の前で生けた花には生気も躍動感も個性もなかった。まるで、今の自分そのものだ。
「どうした?」
「いっ、いえ、なんでもありません」
絢は慌てて首を振った。危うく涙をこぼしてしまうところだった。深呼吸をしてから柊二を見上げ、
「この花、ありがとうございます。大事に生けます」
すると柊二は嬉しそうに目を細めた。
「ああ、そうしてくれ」
その瞬間、絢の心臓は普段と違う鼓動を刻み始めた。トクトクと速いリズムで、全身に血液を送り出す。自分の身体に何が起きたのか分からぬまま、絢は柊二の店を出て商店街をひたすら歩いた。
その白い頬にはほんのり赤みが差していたが、そんな自分の変化に絢が気づくことはなかった。
自宅に戻った絢は、ガレージに車がないのを見てほっと安堵の息をついた。祖父はどうやら出かけているようだ。
しかしもう一人、厄介な人間がいた。
「兄さん、遅いじゃないか。どこ行ってたんだよ」
ひとつ違いの弟、幹(かん)。間違いなく血の繋がった弟なのに、どんなDNAのいたずらなのか全く似ていない。いや、似ていないどころか対照的だった。
同じなのは黒髪と黒瞳(こくどう)だけ。幹の方が背が高くて体格もいい。こうやって目の前に立たれると、圧倒されてしまう。
そう、どこか中性的で儚げな趣のある絢に対し、幹は男性的な美丈夫だった。兄の欲目を差し引いても、かなりの美形だと思う。
性格も、控え目な絢とは違い積極的でアグレッシブ。そして何より、紫月流宗家としての誇りを持っていた。
それゆえ傲慢な言動が見られることもあったが、家元候補という強大なプレッシャーを正面から受け止め、それに打ち克つため日々精進している彼に対し、絢が口を挟む理由などなかった。
自信とプライドに満ち、物怖じせず思ったことをずけずけ言ってのける弟が、絢は昔から苦手だった。幸い幹はまだ高校生だったから、昼間は顔を合わせなくて済む。それでも家にいる時はこうして、絢の行動にいちいち干渉してくるのだ。
自分のことなんて放っておいてくれればいいのにと思うのだが、それを面と向かって口にすることすらできず、曖昧な逃げ口上を並べてそそくさと自分の部屋に駆け込む。それがいつものパターンだった。
「こんな時間まで、一人でどこに行ってたんだよ」
苛立ちを隠そうともせず、幹が詰め寄ってきた。絢はふいと横を向き、
「ちょっと散歩のついでに本屋に寄ってきた」
なんで弟に行動を逐一報告しなければならないのかと苦々しく思いつつ、厳しく問い詰められるのが嫌で答えてしまう。幹はふんと鼻を鳴らし、こってりとした皮肉の混じった口調で、
「本部展前だってのに余裕だよな。よほど自信があるんだな」
「僕は出展しないから」
絢が投下した爆弾は、予想以上の効果を発揮したようだ。幹は珍しく言葉を失って固まる。年下なのにいつも堂々としている弟を驚かせてやることができたと、絢は自虐的な悦びにひたりながら言葉を続けた。
「今日、お祖父様に言われたんだ。お前は出さなくていいって」
「……兄さんは、それでいいのかよ」
「いいも悪いも、家元の言うことは絶対だ。僕の意志なんて関係ない」
絢はきっぱり言い置いて、幹の横を通り抜けようとした。するとその時初めて絢の抱えている花に気づいたのか、幹は「何だこれ」と馬鹿にしたような声を上げて、新聞紙ごとぐしゃりと掴み、
「ガーベラにスプレーマムなんて、どうしようっていうんだよ。まさか生けるつもりじゃないよな。こんな俗っぽい花──」
「は、放せっ」
絢は自分でも驚くほど険しい声で叫ぶと、幹の手を引き剥がした。そして、絢の剣幕にたじろぐ弟をキッと見返し、
「花に高貴とか俗っぽいとかあるのか? 花の命は全て平等だ!」
絢はそう喝破しつつも、本心は違うと自覚していた。あの人がくれたこの花は、自分にとって特別なもの。だから、いつもなら受け流す幹の嘲笑に過剰な反応をしてしまったのだ。
驚く幹をその場に残して、絢は自分の部屋に駆け込んだ。そして床にぺたりと座り込むと、幹に掴まれたせいで折れてしまったガーベラをそっと撫でる。すると胸の奥から熱い塊が湧き上がり、喉を内側から圧迫してきた
「ぅっ……」
絢は嗚咽が漏れぬよう、拳を唇に強く押し当てた。いつからだろう、こうして感情を表てに出さず、圧縮して閉じ込めるようになったのは。
不甲斐ない自分に対する苛立ち、花を折られてしまった哀しみ。しかしそういった負の感情だけではなかった。今、絢の心を最も大きく揺さぶっているのは──
──あの人に、逢いたい……。
手の中のガーベラが、その想いに応えるように小さく震えた。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT