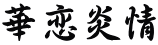
─KAREN ENJOU─
子供の頃、僕は花を生けるのが大好きだった。
子供向けの生け花教室で、お気に入りの器に好きな花を入れてみせるだけで、大人たちはみなこぞって褒めてくれた。さすがは家元のお孫さんねえ、と。
でも、僕が作っていたのは『きれいなもの』の寄せ集めにすぎなかった。そしてある時、気づいたのだ。きれいなだけでは駄目で、僕の花には決定的な“何か”が足りない、と。
花は人なり、人は情なり
花に情念が宿って『華』となる
幾度となく聞かされた言葉が虚しく脳裡をよぎる。そう、僕にとって花はきれいなもの、それ以上でもそれ以下でもないと思っていた。
あの人と出会うまでは───
一、逢花の章
行く当てなどなかった。ただ、やみくもに足を動かしているだけ。そうやって歩き続けていないと、ついさっき祖父から浴びせられた厳しい言葉に呑み込まれ、存在ごとぺしゃんこに潰れてしまうと分かっていたから。
『絢、お前はもういい。下がりなさい』
祖父の言葉には怒りの欠片もなかった。それは、冷ややかで無機質な命令だった。怒ったり叱ったりする価値もないということだろう。
絢は首を縮め、マフラーの中に顔をうずめて歩いた。冷たく厳しい祖父の存在そのものを思い出させる北風から、身を守るように。
紫月絢(しづき・あや)は、江戸中期から続く由緒ある華道の紫月流十一代家元、紫月苑山(えんざん)の孫で、ひとつ違いの弟である幹(かん)とともに、紫月流の次代家元候補として日々研鑽を積んでいる身だった。
現在十九歳。一年前に高校を卒業してからは、紫月流の文化事業部広報担当という肩書きのもとで、家元修行に勤しんできた。
けれど、祖父を満足させることができるのはいつも弟の方だった。絢の生ける花は祖父を苛立たせるばかり。そうして長年にわたって積み重なった劣等感が余計に絢を萎縮させ、自由な表現を妨げるという負のスパイラルに陥って久しかった。
子供の頃はまだよかった。しかし父が紫月流を去り、弟とともに次代家元候補となった時から全てが変わってしまった。
それまでは、祖父苑山は優しいおじいちゃんだった。やんちゃで粗暴なところのあった幹より、繊細で控え目な絢の方を特に目にかけてくれた。苑山は酔って上機嫌になると、よく冗談めかしてこう言った。
『いつか私も、絢を超える美を作り上げたいものだ』
それは血縁の欲目ではなく、実際のところ絢は、神秘の谷間にひっそりと咲く白百合のような無垢な美しさを湛えていたのだ。
他人からの不粋な視線にも、また『自分は美しい』という自意識にも汚されることなく、ただあるがままにある純粋な美。
おそらくそういった美への憧憬が苑山の中にもあって、それがあの冗談めかした言葉を口にさせたのだろう。『無作為の作為』は、紫月流が理想とする哲学でもあった。
上質な白磁を想わせる肌理細やかな肌に、艶やかな翠髪。大きく潤んだ黒瞳は伏せがちな長い睫毛の陰になっていることが多く、それゆえたまに真っ直ぐ見つめられると、何か胸奥にある秘めごとを今にも打ち明けられるのではないかと、老若男女問わず心拍数が上がってしまう。
また、左の目元にぽつりとともった小さな泣き黒子も、絢の容姿に雅致を添えた。白い肌との対比はあまりに艶めかしく、直視が憚られるほど。美青年というありきたりな形容で片づけるには、あまりに霊妙で繊細な個性の結晶だった。
しかし当の絢にそういった自覚は皆無。加えて生来の内気さ、華道の宗家という特殊な環境も相まって、これまで恋愛の経験はなく、性に関する知識も小学生並みだった。
とはいえそれは、絢のせいばかりではない。学生時代、男女問わず絢に憧れ恋心を抱いた者は多かったのだが、彼ら彼女らは絢の弟、幹によって一人残らず追い払われてしまったのだ。
幹は、兄の美しさや純真さを誰よりもよく知っていた。そして、それが理性を麻痺させ、本能的な所有欲や不穏な加虐欲を刺激する媚毒めいた魅力を孕んでいることも。
なのに当の絢ときたら自分の魅力には無頓着で、野に咲く花のようにそこかしこに甘い香りをふわふわ振りまいているのだから、幹としては文字通り悪い虫がつかぬよう、厳しく監視を続けぬわけにはいかない。
しかしそんなこととはつゆ知らぬ絢は、華やかな学園生活を送る級友たちを眩しそうに見つめるばかりだったのだ。
そんな純粋無垢な絢を祖父苑山はことさら可愛がったが、父親である紫月尭(ぎょう)が破門され流派を去ると同時に豹変した。絢が九歳、幹が八歳の時だ。
優しかった祖父は秋霜烈日たる師となり、少しでも怠けると叱責はもちろん、体罰も与えられた。
それでも二人は努力を続けた。いずれは自分たちが流派を導かねばならないのだと、幼いながらも分かっていたのだ。
そう、絢の努力が足りなかったわけではない。幹の方が特別優れていたわけでもない。けれど気がつけば、絢は弟の背中を追うようになっていた。
自分に何が足りないのか、どこがいけないのか分からないが、それは人から教えられるものではなく、自分で見つけねばならないことは理解している。
そうして出口の見えない迷路にはまり込んで、何年経つだろう。絢は迷路の先に、ほのかな光を見い出し始めていた。諦念という光を。
そして今日、その光が確実なものとなった。久しぶりに祖父の前で生けた花は、自分の目から見ても勢いも生気もない、幼いころ教え込まれた『型』をなぞっただけの代物だった。
祖父は怒りすら見せずただ退室を促し、項垂れる絢に「次の本部展にお前は出展しなくていい」と淡々と告げた。
絢はたまらず家を飛び出し、目的もないまま街中に向かった。静寂に支配された家に住んでいると、時に人恋しくなる。特に今は、人々の楽しげなざわめきの中にいたかった。たとえそれが、自分の孤独をさらに際立たせることになっても。
「僕には無理なんだ……。家元は幹が継げばいいさ」
乾いた冬の街。それ以上に乾いた声で自分に言い聞かせながら、絢は夕方の喧噪の中をひたすら歩いた。歩き続けた。そうしてどのくらい彷徨っていただろう、いつの間にかずいぶん遠くまで来てしまったようだ。
「そろそろ帰らないと……」
そうは言ってみたものの、足が動かない。このままどこか知らないところへ逃げることができたらどんなに幸せだろうと独りごち、すぐさま自己嫌悪に陥った。結局僕は、逃げることしか考えていないのかと。その時、
「あれ……?」
不思議な光景に、絢は思わず声を上げた。道行く人の多くが、新聞紙にくるまれた花束を抱えていたのだ。
男子高校生はちょっと恥ずかしそうに、母親に手を引かれた子供ははしゃぎながら、老齢の婦人は愛おしげに。共通しているのは、誰もが嬉しそうな顔をしていることだ。
近くに花屋があるのかなときょろきょろしていると、いきなり背後からぬっと花束を差し出された。
「あげる」
「え、えっ?」
赤いガーベラとミントグリーンのスプレーマム数本が、新聞紙に包まれている。絢は顔を上げ、花束を差し出している男性を見つめた。
男性は見上げるほど背が高く、厚手のジャケットを着ているにもかかわらず筋肉の厚みが感じられた。
顔の下半分、顎から頬にかけてはもっさりとした無精髭に覆われ、伸び放題の髪は後ろで無造作にまとめられている。
どう見てもちょっと小ぎれいなホームレスか山男だったが、その髭づらに似合わぬ邪気のない笑顔のせいか、絢が子供のころ大事にしていた熊のぬいぐるみ『ポン太』が真っ先に思い浮かんだ。
それゆえ、人見知りするところのある絢も臆することなく対応できた。
「これ、僕に?」
男性は頷いて笑みを深めた。絢は半ば勢いに押される形で受け取り、「ありがとうございます…」と一応お礼を述べた。すると男性は「どういたしまして」と答えて、また別の通行人に花を配り出した。
中には気味悪がって拒絶する者もいたが、彼は気にしていない様子で次々と花束を差し出す。そして全て配り終えた男性は、やれやれと言わんばかりに背伸びをして帰ろうとした。
「あ、あのっ……」
声を出してから、絢は自分に驚いた。こんな風に率先して他人に話しかけるなんて、最近はほとんどなかったのだ。
男性は振り向いて、「何か?」と質す。絢は自分を勇気づけるようにもらった花束をきゅっと抱き締め、
「あ、あなたはなぜ、花を配っているのですか?」
絢の問いかけに、男性は肩をすくめて答えた。
「売れ残りの古くなった花だ。明日は店の休業日だし、枯らすぐらいならあげてしまった方が花も喜ぶ」
「店って……もしかして花屋さん?」
「もしかしなくても、どこからどう見ても花屋だろう?」
「いえ、人のいい花泥棒にしか見えません」
絢の率直すぎる言葉に、男性は大仰な溜め息をついた。
「ひどい言われようだな」
その気落ちした熊のような仕草がおかしくて、絢は思わず吹き出してしまった。そして、こんな風に笑ったのは久しぶりだなと、嬉しいような哀しいような感慨に浸った。
「さてと。警察に通報されないうちに店に帰るか」
そう言って歩き出した男性の後を、絢は慌てて追いかけた。彼がどんな花屋を営んでいるのか知りたいという好奇心はもちろんだが、枯らすぐらいならタダであげるという行為に、花に対する純粋な愛情が感じられたからだ。
それは、花に苦しめられ花に縛られている自分にとって、懐かしくもあり新鮮でもある感情だった。
「あのっ、お店に伺ってもいいですか?」
彼の歩みに合わせるため小走りになりながら、絢は許可を求めた。男性は「好きにするといい」と言いつつも、歩調を緩めてくれた。
絢はすかさず横に並んで「ありがとうございます」と笑顔で返す。それを見た男性は眩しそうに目を細めてから困ったように頭を掻いたが、絢は気づかずにこにこ笑ったまま彼に付いていった。
NOVEL INDEX TOP 華恋炎情INDEX NEXT