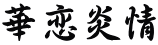
─KAREN ENJOU─
十六、誓花の章
目覚めが近いのか、時折まぶたがぴくぴく動く。それが可愛くてちゅっと口づけると、幸せそうに緩んでいた唇がかすかに歪み、うにうにと意味不明な寝言を呟いた。そしてもぞもぞと身体をくねらせ、顔をぺったり押しつけてくる。
片側の頬がつぶれて唇がぷっくり盛り上がったその顔は、お世辞にも整っているとは言えないが、全て預けきっていると言わんばかりの無防備さは信頼の証でもあるわけで、眺めていると胸が熱くなってしまう。腕の中にあるこの愛しい者を今度こそは守るのだと、柊二は決意を新たにした。
それにしても、とつくづく思う。こんなにも美しく清らかで、純粋無垢な生き物が現実に存在するとは。
果たして奇跡なのか、弟を初めとする周囲の努力の賜物なのか。どちらにしても、絢という稀有な存在へのある種畏怖にも似た驚きが薄れることはなかった。
ただし、純粋すぎることには弊害もある。絢が『他の人で練習する』と言い出した時には、柊二は本気で怒り呆れた。
けれどそれは、柊二に早く追いつきたいという絢なりの必死さの表れで、さらに言えば無知で幼い自分というコンプレックスの裏返しでもあるとすぐに察した。
好きな人にちゃんと愛してもらうため他の人で練習するという論理は、一見すると本末転倒で倒錯しているが、どこか胸を打つ一途さもあって、絢の危うい純真さをよく表しており、柊二はすっかり絆されてしまったのだ。
もちろん、他の男で“練習”などされてはたまらないという焦りも大いにあったが。
「俺がどれほど苦労して我慢していたか分かってるのか、全く……」
何も知らない絢の心と身体のことを考えて、少しずつ慣らしていくべきだと思っていた。だから、蜜をたっぷり含んだ花がとろりと綻ぶような媚態を見せられても、猛る下半身を理性で抑え込んで早く帰らせようとしたのだ。それがこのザマだ。
「作意なき媚態、作意なき美、か。ったくタチの悪い……」
花は人なり───紫月流の理念を表した苑山の言葉だが、これは絢のことを念頭に置いていたのかもしれないな、などと思う。
花に作意はない。誰かを喜ばせるためや、美しいと褒められるために咲くのではない。ただあるがままにある。だからこそ美しい。
そんな作意なき美という境地に、絢はすでに到達しているのだ。本人が全く意識せぬままに。
───問題はこれからだな。絢がどう変わっていくか。
今回のことで初めて、絢は己の内に潜む醜い感情を知った。これまで安穏と閉じこもっていた美しい檻の門を自ら開けて、一歩外に踏み出したのだ。
好むと好まざるとにかかわらず、絢は変わっていくだろう。そんな絢の変化を見守り、時には闇に迷い込まぬよう導くのが自分の務めなのだ。
───全く、空恐ろしいな。でも絢、君となら……。
変化を怖れず、現実から目を背けず前進する。それこそが、十年間逃げ続けていたことの罪滅ぼしと、そして乙耶の供養になるはずだ。
「ん、ん……しゅうじさ…ぁん……」
柊二の決意が眠りの国に届いたのか、絢が応えるように呼びかけてきた。柊二はそっと顔を近づけ、
「ん? なんだ? 絢」
すると絢は唇をぷくぷくと動かして、
「柊二さぁん……きもちいい……」
「こら。どんな夢を見てるんだ、君は」
柊二は苦笑混じりにぼやいて、絢のおでこをぴたん、と優しく叩いた。絢は眉をしかめ、うにうにぐずってからようやく目を開けた。
「おはよう、絢」
夢の続きを引きずっているのか、柊二の挨拶に絢はすぐ答えることができず、ぽわんと口を開けたままぼぅっと見返すばかり。が、ややあっていきなり火がついたように赤面し、蚊の鳴くような声で「おはようございます……」とようよう返した。
そんな挙動不審の理由は何となく察しがついたが、柊二は一応問い質す。
「どうした? 絢」
「あ、あの、僕っ……ゆうべ、い、いやらしいこといっぱいしちゃっ……」
要は、昨夜の乱れぶりを思い出したというわけだ。柊二はにやりと笑い、
「ああ、確かに。色々としたな」
わざと含みを持たせて言うと、絢は身の置き場もないと言わんばかりに縮こまって、柊二の胸にぎゅうぎゅうと顔を押しつけた。
「こら、痛いぞ」
あやすような咎めに、絢はおそるおそる顔を上げた。そして視線を重ね、
「僕、変じゃなかったですか? ちゃんと……できてましたか?」
この問いまでは予想できなかった。柊二は軽く瞠目したが、すぐに目を細めて頷いた。
「ああ、もちろん。初めてなのによく頑張ったな」
絢は顔を輝かせ、
「ほんと? よかったぁ」
頬を染めていた羞恥の赤が、喜びの薔薇色に変わった。その頭を柊二はふわふわと撫で、
「でも慌てることはないぞ。少しずつ教えるから。いいな?」
「はいっ」
あどけなさ全開でこっくり頷く絢に、柊二は苦い笑いを噛み殺した。やっぱりまだまだ絢は子供だな、と。しかし、
「じっくり時間をかけて、柊二さん好みの身体にしてください……」
潤んだ瞳で見上げつつの艶めかしい懇願に、柊二はまず硬直し、それから脱力し、そして呆気なく陥落した。
「ははっ、君には……負けた」
お泊りセットも持たずに外泊してしまったなと柊二に指摘され、初めてその事実に気づいた絢は、色々迷惑をかけてしまったに違いないと思い心から詫びた。が、柊二がにやにや笑っているのを見てようやく、からかわれているのだと察した。
「ひどいです! 真面目に謝ってるのに笑うなんてっ」
「真面目に謝ってるから可笑しいんだろうが。全く、君は……」
ほとんど定番となりつつある柊二の呆れ口調だったが、途中から諭すような色合いを帯びてきたため、絢は怒りを収めて耳を傾けた。
「そもそもお泊りセットは、友だちの家に泊めてもらう時に持参する必需品だろう?」
「は、はい」
「なら俺は、絢のお友だちか?」
「違います! 柊二さんは僕のこ、恋人……です、よね?」
「どうしてそこで疑問形になるんだ」
柊二は溜め息混じりにそう言って、絢の額をぴん、と小突いた。絢は「痛い」と言って額を押さえたが、本当はちっとも痛くはなく、ただ甘いばかりのじゃれ合いだった。
しかしその甘さに何も考えず浸ることができるほど、絢はまだ自分に自信が持てなかった。額を押さえていた手をだらりと下ろし、
「ほんとは……まだ信じられないんです。僕みたいな何にも知らない子供が、柊二さんのようなかっこいい大人の男のひとと……」
「かっこいい大人の男、か。髭を剃っただけでずいぶん変わるんだな。前は花泥棒だの熊男だの、さんざんな言われようだったのに」
「髭もじゃの柊二さんも、今に負けないくらいかっこいい大人の男性でした」
きっぱり言い返す絢に、柊二はややうろたえた様子で
「嘘つけ。熊のポン太に似てるって言ったのはどこの誰だ?」
「あはは、そうでした」
絢はからりと笑ったが、そのすぐ後を溜め息が追いかけてきた。
「僕もいつか……乙耶さんみたいになれるかな……」
そう言って前方に目を向けると、目的地である乙耶の墓が視界に入った。柊二の部屋を出た後、本部展の会場に行く前に寄ることにしたのだ。
紫月流に戻ることになったと乙耶に報告したいと言う柊二に、絢はもちろん同意した。絢も、乙耶に感謝と決意を伝えたかったのだ。
絢の自問ともつかぬ呟きに柊二はすぐに答えず、黙って歩みを進めた。その手には、見事な妙蓮寺椿が。
「……乙耶は早くに両親を亡くし、小さいころは親戚の家を転々としていた。いつもよそ者、居候で肩身の狭い思いをしていた彼が唯一心休まるのが、花に触れている時だった」
淡々と語る柊二の横顔を、絢はそっと窺った。そして乙耶の孤独に心を痛めたが、それと同時に少し安堵した。そうか、乙耶さんも花に安らぎを求めていたんだな、と。
「そして中学生になると、紫月が開いている学生対象の生け花教室に通い始めた。費用はアルバイトで稼いだらしい。そこで苑山先生と出会って心酔し、弟子入りを直訴したんだ。相手はあの苑山先生だ。もちろん一筋縄ではいかなかっただろうが、ともかく中学を卒業すると内弟子となることを許された」
「そういえば……かすかにですが記憶があります。僕と幹がお祖父様のいる紫月の本宅に移り住む前、まだ父が流派にいた頃です。お祖父様のところへ遊びに行くと、微笑みを浮かべて部屋の隅に控えている優しそうなお兄さんがいました。彼が……乙耶さんだったのですね」
当時はまだ祖父も優しいおじいちゃんだった。よく来てくれたと相好を崩し、二人の孫を散々甘やかした。そんな幸せそうな家族の団らんを、乙耶はどんな気持ちで眺めていたのだろうか。
「そうか、覚えていてくれたか。乙耶もさぞ喜ぶだろう」
柊二はそう言って、嬉しそうに目を細めた。そして、乙耶の墓の前に立った。絢も柊二の隣に立ったが、墓標を真っ直ぐ見つめることができない。
「乙耶さんはつらい境遇を乗り越え、誰の助けも借りず一人で努力してお祖父様に認められました。対して僕は、予め敷かれているレールの上に乗っかって、安穏とこれまで進んできました。そんな苦労知らずの子供が柊二さんの隣にこうして立っているなんて、なんだか乙耶さんに対して申し訳ないような気がしてしまいます……」
絢は正直な気持ちを言葉にして、深く項垂れた。すると隣から、厳しくもありまた包み込むような温かさにも満ちた声が。
「愛され守られて育ったことを恥じることはない。恵まれた環境にいることを恥じることはない。ただ、世の中には色んな境遇の人間がいて、みな各々が重いものを背負いつつ懸命に生きているのだということを、心に留めておきなさい」
柊二の言葉に、絢の背筋は自然と伸びた。乙耶の名が刻まれた墓標をしっかり見据えたまま、「はい」とたったひと言答えた。
「では、絢。これを」
柊二から椿の花を託され、絢は戸惑う。
「柊二さんが生けた方が、乙耶さんも喜ぶのでは……」
「いや、絢が生けた方が喜ぶだろう。当時はまだ洟垂れ小僧だった苑山先生の孫が、こんなに立派になったのかと」
「洟なんか垂らしてませんっ」
「分かった分かった」
笑いながら宥める柊二から花を受け取ると、絢は目を閉じてふっと息を吐いた。
───乙耶さん、あなたの好きだった妙蓮寺椿、僕が生けさせてもらいます。
そして二つの花挿しに生けた瞬間、それまでどんよりと曇っていた空が明るくなった。
「あっ、光が……」
厚い雲の間から射した清澄な光が、鈍色に沈んでいた墓石に降り注ぎ、きらきら輝き出した。
「ほら、見なさい。乙耶が喜んでいる」
柊二の勝ち誇ったような指摘に、絢は無言のまま何度も頷いた。込み上げる熱いものに喉が圧迫され、言葉がうまく出せない。ただ両手を合わせ、雲の上から自分たちを見守ってくれているであろう乙耶に誓った。
───紫月流の伝統を、必ず守り抜いてみせます。
そうして目を開けると、絢の誓いに応えるように妙蓮寺椿がそよそよと揺れた。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT