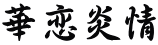
─KAREN ENJOU─
十五、艶花の章
「さて。ここもずいぶん柔らかくなってきたな」
柊二はそう言っていったん指を抜き、絢の脚を素早く抱え上げた。ほろりと緩んだ入り口に、ひんやりした外気が入り込む。これまで経験したことのない体感に、絢がぶるっとふるえた時だった。
「ひぅっ」
信じられないくらい熱くて信じられないくらい張り詰めたものが、ぐぅぅっとそこに押しつけられた。反射的にがちっと奥歯を噛み締め、全身を強張らせる。すると、まぶたや鼻、頬にあやすようなキスが降ってきた。
「絢、いい子だ。力を抜いて……」
絢は律儀に頷いて、まずは顎から力を抜いた。ぎりぎりと閉じていた唇がふわりと綻び、はふっ、はふっと緊張を吐き出すように浅い呼吸を繰り返す。そして腹部から力を抜くと、そのタイミングを見計らったかのように、柊二が腰を進めてきた。
「いっ、い……」
思わず痛いと言いそうになり、絢は慌てて口を閉じた。すると柊二はすまなそうに目をすがめ、
「我慢しなくていい。つらかったら正直に言いなさい」
「ぜ、ぜんぜん平気ですっ。だから、全部してください」
絢はきっぱり返して、柊二の眉間にうっすら刻まれた皺をそっと撫でた。柊二に気持ちよくなってほしいと思ってやったことなのに、こんな苦しそうな顔をさせてはいけない。早くこの皺を消し去りたい一心で。
そんな絢の想いが通じたのか、柊二はうっとりするほどきれいな笑みを浮かべた。そして浅いところでぬくぬくと出し入れしつつ、ゆっくり、巧みに、狭い器官を押し広げてゆく。
───あ、ああ……すご、い……入ってる……
痛みが全くなくなったわけではない。ただ、痛みは表層的なもので、その核には甘美な何かが潜んでいて、それこそがこの行為の唯一無二の目的であると絢は分かり始めていた。
「ふぁ、あ、あふっ、うぅ…ん……」
指で丹念にとろかされた粘膜が、柊二の形に広げられてゆく。さらに形だけでなく、柊二の鼓動を内側で感じた時、絢はこれが“ひとつになる”ということなのだと、心と身体で悟った。
「絢……入ったぞ」
深い感慨を噛み締めるような柊二の言葉に、絢は夢中で頷いた。
「柊二さんが……なかでどくんどくんってゆってます……」
すると柊二はフッと目を細め、
「君の中はとても気持ちがいい。柔らかくてとろりとして、温かくて」
「ほんと? ほんとに気持ちいい?」
「ああ。最高だ」
柊二に気持ちよくなってほしいという願望が叶い、絢は背中に回した手に力を込めて嬉しさを伝えた。するとそれに連動して身体の奥がきゅっと竦み、挿入された柊二自身の輪郭がよりリアルに感じられた。
絢は思わず赤面したが、それがどれほど柊二を刺激してしまうかまでは、分かっていなかった。
「絢……っ」
柊二には珍しい、切羽詰まった声で名を呼ばれた。しかしどうしたんだろうと考える余裕はなかった。柊二はいったん腰を引いて挿れたものを先端ぎりぎりまで抜くと、次の瞬間勢いよく腰を落として根元まで突き刺した。
「ああーーッ、ひ、ひっ、ぃぃ……!」
それがもたらす重量感や圧迫感は、先刻の比ではなかった。腹の奥にずしんと響き、一拍おいてびりびりした電流が全身を駆け巡る。
それが散るのを待つことなく、柊二は絢の柔肉に雄々しい律動を刻み込んでゆく。官能の波濤は途切れることなく、重なって大きなうねりとなり、絢の身体を呑み込んでいった。
「あっ、あ、やっ、もう……」
気がつけば絢は、柊二の腰に脚を絡みつけてくねらせ、自ら奥へ誘い込むように股間を跳ね上げていた。より深く密な結合の果てに訪れる快感はめくるめく陶酔を呼び、絢は霞み始めた意識のどこかで、自分の身体が変わってゆくのを感じていた。
「ああ……ん、んーー……いいっ、きもち、いい……」
ついさっきまでは恥ずかしくてたまらなかった、濡れた粘膜のこすれる音さえ、快感を深くする媚薬として享受している自分に気づく。身体の奥からヌチャヌチャとあからさまな音が聞こえるたびに、鼓膜に甘い痺れが走った。
思わず「あふぅ…ん」と喘ぐと、咎めるように唇を吸われた。
「絢、いつの間にそんな……色っぽい表情を覚えたんだ」
「し、知らなぁい……あっ、あん!」
「全く君はっ……」
呆れたような物言いも、なぜか今は気にならなかった。絢はうねうねと腰を揺らして、
「柊二さぁん……もっと、もっと奥ぅ……ぐちゅぐちゅってして……」
その瞬間、絢の中に収まっていたものがぐんと伸び上がり、さらに容積が増すのを感じた。絢は仔犬のように甲高く鳴いて、脳天まで突き抜ける快感に背中をがくがくと反らす。しかし、白旗を挙げたのは柊二の方だった。
「ああ、くそっ、だめだ。いくぞ、絢」
「え……?」
どこに行くの? と間抜けな問いを発しようとした唇は、甘い苦悩に満ちた嬌声に彩られた。膿み熱をもってずくずくと疼き、陵辱を待っていた奥の膨らみを、柊二の先端がぬるっとかすめたのだ。
「いやあーーーっ、あっ、ああっ、だめ、だめぇぇ……」
柊二の背中に爪立てて、襲いかかる高濃度の快感に耐えようとする。しかしそれは無駄な足掻きだと、本能は知っていた。
「あっ、出る、出るっ、出ちゃ…うっ……!」
びくびくと腰が跳ね、柊二にしがみついたまま絢は射精した。熱い液体が勢いよく飛び出すのに連動して、柊二を食い締めている部分が収縮と弛緩を繰り返す。
「くっ……」
柊二は熱っぽくかすれた声で呻くと、絢の中を好き放題に穿っていた楔をずるっと抜いて、絶頂感にひくひくと波打つ絢の腹の上に勢いよく放った。
粘液の白い触手はあっという間に絢の腹に広がり、胸の方までとろりと伝う。達ったばかりで敏感な乳首は、粘液の愛撫を受けてきゅっと尖った。
「ああ……柊二さ…ん……熱い……」
柊二が放ったものの熱さや量に欲望の激しさを感じた絢は、そこまで求めてくれてたんだと嬉しくなった。しかし、
「……すまない。気持ち悪いだろう。今すぐ拭くから待ってなさい」
そう言ってティッシュで拭ってくれる手つきは優しかったが、絢は眉間に皺が寄るのを抑えられなかった。
「気持ち悪くなんかないです」
「はは、そうか」
「でも、どうして外でしたんですか?」
本当は自分の中で達ってほしかったと言外に匂わせて訊ねると、柊二は肩をすくめ、
「まさかこんなことになるとは思わなかったから、避妊具を用意していなかった。だから外に出すしかなかった」
その理屈は、絢には理解不能だった。
「僕は、女の子じゃないです」
すると柊二は低く笑って絢の頬を撫で、
「分かっているさ。ただ、身体の中にあんなものを注がれたら気持ち悪いだろう? それに、絢への負担をなるべく小さくするために───」
柊二の言葉を遮るように絢は手を伸ばし、ぎゅっと抱き着いた。そして、
「もう一回、してください。それで今度は、僕の中に出して……」
柊二が小さく身じろぐのが伝わった。ややあって、
「そうやって、わけも分からず言うんじゃない」
怒りや咎めより、戸惑いの色合いが濃い声だった。絢は顔を上げてじっと見つめ、
「全部、教えてくれるって言いました」
「それは……」
「柊二さんで、この中をいっぱいに満たしてほしいんです。それに」
絢はいったん言葉を切ると、羞恥を抑え込んで自ら腰を押しつけた。射精の余韻を留めて熱く濡れる互いの器官が、くちゅっと秘めやかな音をたてて抱き合う。
「まだ、お尻の奥がうずうずしてます。もう一回挿れて、かき回してほしい……」
あけすけな物言いは、口にする人間によっては欲望を萎えさせてしまうだろう。しかしまだあどけなさの残る少年の身体を覚えたての快楽で火照らせ、大胆さと奥床しさのせめぎ合う仕草とともにおねだりする絢に、収まりかけていた柊二の情欲は一気に上昇した。
「絢はいつの間にそんないやらしい子になったんだ」
ねっとりとした低音で囁きつつ、絢の背中からするりと指を這わせ、谷間の奥へ滑らせてゆく。そしてついさっきまで柊二の猛るものを健気に呑み込んでいた場所を、慈しむように撫でた。
「あ、あっ……柊二さぁん……」
入り口を触られただけなのに、奥の方までくにゅくにゅと蠢くのが分かる。まるで、早くここをいじめてと催促するかのように。それに応じたわけではないだろうが、柊二は濡れた襞を掻き分けてぬるりと指を埋め込んだ。そして軽く揺すり、
「……すっかりとろけてる。これならすぐに挿れても大丈夫そうだ。絢、どうする?」
絢は尻の奥にともった甘痒い疼きに小さく喘ぎつつ、柊二の首に腕を回して腰を浮かせた。無言の誘いに、柊二は熱い溜め息で応じ、絢の双丘を両手で掴んで割り開いた。チュクッと音をたてて勝手に綻ぶそこが恥ずかしかったけれど、そんな羞恥はすぐに吹っ飛んだ。
「あ、あ……おっき…い……」
あてがわれたものの大きさや熱さに、背中がぞくりと総毛立つ。一度経験して知っているはずなのに、体勢や角度が違うだけで受ける感覚もこんなに変わるのかと驚きを反芻する。
「ふぁ、ぁ……すご…い……」
つい先刻までは頑なに閉じていた場所が、いともたやすく柊二の形に開く。それどころか、先端を舐めるようにひくひく動くのを感じ、絢は快楽に従順すぎる自分の身体に少し呆れ、と同時に誇らしくも思った。
「あぁん……もっと、柊二さぁん……」
甘えたおねだりが柊二の獣性に火をつけてしまったのか、それまでの慎重さから一転、柊二は掴んでいた尻をぐっと落とした。そのタイミングに合わせて腰を突き上げれば、不穏な熱を帯びた二つの器官は最も深いところで繋がった。
「ああっ! あ、いい、いいっ……」
絢は柊二の上でびくんびくんと二度跳ね、反り返った性器の先端から蜜状のものを撒き散らした。そのまま激しい抽挿になだれ込むかと思いきや、柊二は深く突き刺したままゆっくり腰を回す。
ねとり、ねとりと蜜壺の側面を絡め取るようにかき回されると、全身が甘い蜜の中に浸されそのまま溶けてしまうような錯覚に襲われる。
「きもちいいよぉ……柊二さ……ぁぁ、ん……」
「絢、頼むから……そんな声で名前を呼ばないでくれ」
切実な訴えに、絢はとろんとした目つきながらも真っ直ぐ見つめ返した。
「ど…して……?」
「おかしくなる」
答えの意味がよく分からず、絢はちょんと首を傾げた。すると柊二はふっと目を細めて軽く唇を合わせ、
「いや……いい。もうとうに俺はおかしくなってる。今さら、だな」
やっぱりよく分からなかったが、しっとりと汗ばんだ顔に浮かんだ微笑みは美しく、滴り落ちるような色気があった。ぼぅっとのぼせた絢は、無意識のうちに柊二の後頭部に触れた。するとその拍子に髪をまとめていた紐がほどけ、艶やかな髪が広がる。
汗で乱れた髪を無造作にかき上げる柊二には、これまで感じたことのない野性的な魅力があった。それは、顔半分に髭をたくわえた熊男とも、髪をきりっとひとつにまとめた天才華道家とも違う、狩野柊二という一人の美しい男性そのものの魅力だった。
「ああ、どうしよ……柊二さん、かっこいい……」
下腹の辺りに妖しい疼きを覚えた絢は、自然と腰が揺れるのを抑えることができなかった。
「すき、すきです、柊二さん……」
切ない声で想いを伝えつつも、性器を咥え込んだ尻をぬめぬめと揺らす。そんな純真さと妖艶さの両極を鮮やかに見せつけられて、柊二は今宵二度目の白旗を挙げた。
「君には……一生勝てないかもしれん」
そして「愛してるよ」と応え、絢の尻をがっしり掴み直した。そのまま上下に揺さぶり、頑丈な腹筋を使って突き上げる。
「あ、あうっ、ふっ、あふっ」
絢も拙いながら、それに合わせて腰を振る。二人の動きがぴったり合うと、まるでご褒美のように快感が突き抜け、そのすぐ後を追って甘いさざ波がざあっと全身を走る。
「絢……後ろを見てごらん」
「うし…ろ……?」
喘ぎの形に緩んだ口で問い返しつつ、絢は言われた通り後ろを振り返った。視界に飛び込んできたのは、柊二の上にまたがって甘えるように抱き着いている自分の背中。
「ひゃっ、やだ……」
窓ガラスに映ったその光景は直視に堪えないほど淫らだったが、それゆえ絢は目を離すことができなかった。
「ほら、しっかり繋がっている」
柊二はそう言って、絢の尻を少し持ち上げた。すると中に収まっていたものがぬるぬると引き出され、生々しい艶を見せつけた。絢の入り口はとろりとめくれ上がって、柊二のものにしっかりまとわりついている。
「入ってる……柊二さんの太いの……」
視覚と体感の一致に、絢は不思議な感動を覚えた。ひとつになっていることを目でも確認できて、さらに実感が湧き上がる。
「んあ、あっ」
柊二が再び腰を跳ね上げ、絢の奥を穿ち始めた。絢も合わせて腰を振り、一気に絶頂へと駆け上がってゆく。
「いい、いいっ! 柊二さぁん、奥、もっと奥、してぇ……」
「絢……ッ」
頭のてっぺんまでずぅんと重い痺れが走り、瞼裏にちかちかと星が瞬く。底の見えない快感の渦に今にも巻き込まれようとしながらも、絢は望みを伝えるのを忘れなかった。
「柊二さん、中にいっぱい出してっ……」
その瞬間、ぐっと強く腰を抱かれた。柊二の硬い腹に挟まれた性器がこすられ、その刺激に絢は呆気なく限界を迎えた。
「んっ! ふ、ふぅぅ…ん、んっ……」
息を詰めて射精を遂げていると、絢の中を押し広げていたものがぐぅっと反り返り、次の瞬間、熱いものがぱぁっと迸るのを感じた。
「ああ……柊二、さん……」
柊二は絢の腰を強く抱いて、小刻みに下半身を揺らしつつ絢の中に放っていた。温かいものに内側から満たされるという未知の体感は、絢に悦びと気恥ずかしさと、ふわふわした幸せをもたらした。
「んっ、すご…い……」
注がれたものが中でとろりとろりと対流し、収まりきらず隙間から溢れ出る。ようやく全て出し終わった時には、身体の繋がった部分は柊二のものにまみれていた。絢ははふぅ、と蜜状の甘い溜め息をこぼして下腹を撫で、
「柊二さんで、お腹いっぱいになりました」
幸福感と満足感を、素直な言葉で表現した。そこにどんな淫らな意味がこもっているか、当の本人は気づかぬまま。柊二は苦笑を漏らし、
「君には敵わないな」
そう言って唇を重ね、ゆったりと舌を吸ってきた。そのまましばらくの間、行為の余韻とともに甘いキスを愉しんでから、二人でバスルームへ。その頃には、今日一日の緊張と疲労のせいか絢はすでにうつらうつらしており、柊二に頭から身体まで洗ってもらった。
そして、シーツも取り替えられきれいに整えられたベッドで、四肢を絡ませるように抱き合って、絢はこれまでの人生で最も幸せな眠りに沈み込んでいった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT