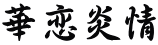
─KAREN ENJOU─
十四、萌花の章
「あ……僕、僕っ……」
フローリングの床に、白い飛沫がぽつぽつと散っている。それを見た瞬間、さっきまで全身を巡っていたのとは異なる種類の熱が、身体の芯にかあっとともるのを感じた。絢は慌てて脚を閉じ、シャツの裾を引っ張って、体液に濡れて淫らにぬめる股間を隠した。そして、
「ごめ…なさい……ごめんなさい……」
涙とともに謝罪を繰り返す。そんな絢を、柊二はあやすように揺らしながら、
「どうして謝るんだ?」
「だって、柊二さんのお部屋汚してしまって……それに、着物も……」
「部屋は掃除すればいい。着物は洗えばいい。それよりも、絢が気持ちよかったかどうかの方が大事だ。どうだ?」
恥ずかしかったけれど、正直に答える以外の選択は思いつかなかった。
「は、はい……気持ちよかった……です」
消え入りそうな声で答えて、膝をすり合わせもじもじしていると、柊二の逞しい腕に抱き締められた。
「それならいい。絢が気持ちよくなってくれるのが、何より嬉しい。だからほら、そんな下を向いてないでこちらを見なさい」
柊二の優しい促しに、絢はおそるおそる顔を上げた。そして衿元にきゅっとしがみつき、遠慮がちにだが身体を寄せた。すると腿に熱くて硬いものが当たり、絢は思わず息を詰める。
───これって……柊二さんの……。
着物越しでも激しい昂ぶりが伝わってくるそれを、絢は心から愛しいと思った。と同時に、柊二も自分に対してこういった欲望を持ってくれたことに純粋な喜びを覚えた。
「柊二さん、あの、これ……」
絢はそろそろと手を伸ばし、着物の上からその部分を撫でる。絢がこんな大胆なことをすると思っていなかったのか、柊二は驚いたように目を瞠った。しかし絢は構わず睫毛の奥から見上げ、
「柊二さんも、気持ちよくなってくれますか?」
しかし、驚きが去った後の柊二の顔に表れたのは、否定的な翳りだった。
「いや、君にはまだ無理だ」
「そんなっ、ちゃんとできます! だから柊二さんも───」
「馬鹿なことを言ってないで、服を着なさい。俺も着替えてくる」
絢の言葉を最後まで聞くことなくあっさり払い、柊二は立ち上がろうとした。絢は拒絶されたショックを抑えてしがみつく。
「ど、どうして? さっき柊二さんは、絢が気持ちよくなってくれるのが何より嬉しいと言いました。僕だって同じです。柊二さんが気持ちよくなってくれたら、すごくすごく嬉しい」
必死に言い募る絢に、柊二は上げかけた腰を戻した。しかし渋面は崩さず、
「絢は男のことや性のことについて無知すぎる。男同士の営みがどうやってなされるのか、俺のような男が欲望を満たすために何をするのか、絢は知っているのか?」
知らないものは知らない。それは仕方がない。絢は黙って首を振った。すると柊二は苦い溜め息をついて、絢の耳に口を寄せた。そして問いの答えを、ほのめかしや隠語を使わず具体的な器官の名前を使って、ごく散文的に説明した。
「…………」
それを聞いた絢は衝撃を隠せず、さあっと青ざめる。柊二は一瞬労わるような表情を見せたが、すぐに元の苦々しい顔つきに戻り、
「分かったろう? 絢には当分無理だ。さ、早く服を直して。遅くなったら弟君が心配する」
柊二には珍しくせかせかした口調でそう言うと、絢の身体を抱き上げて隣に座らせた。そして立ち上がり、部屋を出ていこうとする。その広い背中に、絢は呼びかけた。
「じゃあ、僕がお稽古してちゃんとできるようになったら、してくれますか?」
「稽古……だと?」
振り向いて反問する柊二の眉間には、これまで見たこともないような険しい縦皺が刻まれていた。しかし絢は臆することなく見返し、
「はい。一生懸命お稽古して、その……さっき柊二さんが教えてくれたことができるようになります。それまで待っててくれますか?」
「何を言ってるんだ君は。大体あれは、相手がいなくてはできんだろう。一体誰と“稽古”するというんだ」
荒っぽい歩みで近づき、上から睨めつけてくる柊二は、手を翳せば禍々しい不協和音が鳴り響きそうなほど不穏な空気をまとっていた。
絢はようやく、自分の言葉が柊二を怒らせてしまったことを悟ったが、ここで引き返すわけにはいかない。柊二の迫力に負けぬよう自分を鼓舞するため、シャツの裾をぎゅっと握って、
「ま、まだ分かりませんけど誰か探して、それで相手になってもらいます」
「探すだと? ふざけたことを。相手は誰でもいいと言っているようなものだ」
「はい。お稽古なんだから誰でもいいです。それで経験を積んでうまくできるようになったら、柊二さんと───」
「絢ッ、いいかげんにしなさい!」
自制のフィルターを通さず、怒りの感情からダイレクトに発せられた一喝は、絢の全身を竦ませるのに十分な威力を持っていた。けれど、
「だって! このままじゃ僕は何も知らない、何もできない子供のままです。いつまでたっても柊二さんを気持ちよくしてあげられない」
本能的な怯えより、気持ちを伝えたいという意志の方が勝った。絢は強張る舌を必死に駆り立て、訥々と訴える。
「ぼ、僕だってほんとは……柊二さん以外のひととそんなことしたくありません。でも、絢にはまだ無理だって言うから……だから早く柊二さんにしてもらえるように……が、がんばってれんしゅうし……て……ぅ、ぅっ……」
最後の方は涙混じりになってしまったが、何とか言葉にすることができた。想いはちゃんと伝わっただろうか。視界を覆う涙の靄を払うため、絢はぐいと目を拭って柊二を見つめた。すると柊二はいきなりその場にしゃがみ込み、
「全く君はっ……」
今まで何度も聞いた柊二のぼやきだったが、呆れ度は最上級だった。文字通り頭を抱え込み、綺麗にまとめられた髪をぐしゃぐしゃとかき回す。
ほつれて目元にかかった髪の隙間から、ちらと流し見るように見上げられ、その途轍もない色気に絢の鼓動は一気に速まった。吸い寄せられるように視線を重ね、
「柊二さん、僕、頑張ります。柊二さんにふさわしい大人になります。だから、あの、それまで待っ───」
「もういい」
ぴしゃりと遮られ、絢は一瞬目の前が真っ暗になった。ああ、やっぱり自分じゃ駄目なのか。乙耶みたいなしっかりした大人じゃないと、愛してもらえないのか……。
「ひゃっ? わ、わわっ」
柊二は立ち上がると素早く絢の身体を抱き上げた。そしてじっと見下ろす双眸は、相変わらず美しい黒青の輝きを宿していたが、これまでと何かが違っていた。
「柊二……さん……」
注がれる視線の、肌が灼かれるような熱さ。まるで、瞳の奥に熱源があるかのようだ。それがどんな感情に由来するのか絢には分からぬものの、なぜか全身に甘い戦慄が走る。もしかして、身体はすでに知っているのだろうか。この熱がもたらす悦びを。
「ここで帰したら、本当に他の男で練習されかねん。冗談じゃない」
柊二は己に言い聞かせるように呟いた。そして絢を抱いたまま隣の部屋へ。そこは寝室のようで、柊二の身体に合った大きなベッドが置かれていた。その上に絢を横たえると、ボタンを外すのももどかしいと言わんばかりに、シャツをするっと引き抜いて脱がせた。
「あっ……」
絢は反射的に身体を丸めてちぢこまったが、次の瞬間スプリングが大きく跳ねて思わず顔を上げた。すると、帯をほどき長着の前をはだけた柊二が、ゆっくり覆いかぶさってくるのが見えた。
───柊二さんの、裸……。
大柄で逞しい身体をしていることはもちろん分かっていたが、実際に目にした柊二の裸は想像以上に雄々しく優美で、絢はぼぅっと見とれてしまう。
実用的な筋肉が乗った胸や腹は、窓から射し込む月明かりを受けて蒼い陰翳を帯び、妖しい光沢を放っている。首から肩、二の腕へのラインは逞しくもあり滑らかでもあり、西洋の彫刻を想起させる。
絢は、男性の身体を初めて美しいと思った。と同時に、この胸にこれまで何度も抱き締められたのかと思うと、頬が赤らむのを抑えられなかった。
しかし柊二は、そんな絢の動揺に気づいているのかいないのか、薔薇色に染まった頬を弄ぶように撫で、
「いいか、絢。俺が一から十まで全て教えてやる。だから二度と、他の男と練習するなんて言うな」
「で、でもっ、柊二さんを練習相手にするなんて、そんな失礼なこと……」
まさか柊二が教えてくれるなんて思ってもいなかった絢は、驚きの声を上げた。するとほんの少し尖った声で、
「絢、返事はっ?」
「あ、はっ、はい!」
絢が慌てて答えると、待ち構えていたかのように唇を吸われた。
口の中から、クチュクチュとはしたない音が漏れ聞こえる。唾液でコーティングされた舌同士が、絡まり合いもつれ合って奏でられる音。しかしそれ以上に淫らな音が、絢の身体の奥で鳴っていた。
「ふぁ……あっ、ああっ、ん!」
節ばって骨太だけど、どこか繊細さの感じられる柊二の指。時には大胆に、時には優雅に花を生け、いともたやすく美を顕現させてしまうその指は、今は絢の秘処をまさぐっていた。
屈伸させたりぬるりとかき回したりするたびに、和らぎつつある粘膜がとぷん、たぷん、といやらしくこもった音を響かせる。
仰向けで大きく脚を開かされ、ここに指を入れられた時は、羞恥と異物感で恐慌状態に陥った絢だったが、奥処の過敏な膨らみを優しくつつかれた瞬間、甘い声を上げ強張っていた身体をくたりとさせた。
それからは、まだ羞恥はあるものの、徐々にこれを快感として受け入れられるようになっていった。
「絢……今、何本入っているか分かるか?」
濡れた唇を軽く触れ合わせたまま、柊二が揶揄めかした問いを仕掛ける。唇にかかる熱く湿った吐息にぞくりとしつつ、絢は小さく首を振った。
「わ、わかんない……」
「分からないのか? しょうのない子だ。ほら」
柊二はそう言って、絢の中で指を激しく揺り動かした。かすかな痛みとともにじゅわっと湧き上がる熱泉のような快感に、絢は腰を跳ね上げあられもなく悶えた。
「あっ、やだぁ、そんなにいっぱい動かしちゃ……」
「動かさないと、何本入ってるか分からないだろう?」
絢はひくひくと肩を上下させて嗚咽を呑み込み、
「に…二本……?」
「いや、三本だ」
柊二は答えると同時に、身体に教えるようにばらばらに動かしてみせた。そのうちの一本が、あの過敏な奥のしこりをかすめると、快感が火花のようにぱぁっと散る。
絢が甘ったれた悲鳴をあげて再び腰を揺らすと、粘液にまみれてぴちぴちに勃ち上がった性器がふるえ、ぴたぴたと下腹に当たった。
その感触に驚いて視線を下方へ滑らせた絢は、あまりに淫靡な光景に耐えられず顔を覆った。視界は遮られたが、脳裡に灼きついた光景は消えることなく、より生々しい光沢をもって浮かび上がってくる。
今にも弾けそうなほど真っ赤に膨れた胸の突起や、腹の上に溜まって浅い池のようになった愛液、悶えるように跳ねる桃色の性器、そして、M字に開いた脚の中心部をまさぐる柊二の手───
「顔を隠すな。こちらをちゃんと見なさい」
柊二の命令は、表層的な意識の深層に直接届いて、絢の身体を動かしてしまう。絢は意識する間もなく、のろのろと腕を下ろして言われた通りに柊二を見つめた。
「恥ずかしいか? 絢」
柊二のシンプルな問いに、絢はこくこくと何度も頷いた。すると柊二は、流麗な眉をついと吊り上げて、
「この恥ずかしいことを、絢は他の男としようとしていたんだぞ」
「あっ……」
「俺がどうしてあんなに怒ったか、分かったか? それとも、他の男とも練習したいか?」
「やっ、やです……柊二さんとじゃなくちゃいやぁぁ……」
身体の一番奥を委ねるということが、どれほどの信頼と愛情を要することなのか絢は身をもって分かった。と同時に、自分の無知さ加減も。
「ごめんなさい……僕、ほんとに子供でした……。でも、これからがんばるから、だから柊二さん、全部教えてください」
心からの謝罪と懇願に、柊二は満足げに頷いた。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT