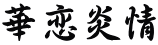
─KAREN ENJOU─
十三、悦花の章
「うっ……く、ぅ、ぅっ……」
絢はほとんど反射的に拳を握り締め、口元に押し当てた。嗚咽をこらえるための、いつもの癖だ。すると柊二の手が絢の拳をふわりと包み込み、口から引き剥がした。
「我慢しなくていい」
柊二はそう言って、絢の身体を腕の中に収めた。着物越しの温もりと、衿元から漂う成熟した男性の甘い匂いに、ここ数日ずっと緊張を強いられてきた絢の心がゆっくりほぐれてゆく。
「苦しかっ…た……すごく……。まだここに、胸の奥に粘ついたものがつかえているんです……」
「ならば吐き出してしまいなさい。今、ここで」
絢は柊二の胸元をぎゅっと掴み、決死の覚悟で吐き出した。
「乙耶さんではなく、僕を見てくださいっ……」
しかし柊二はわずかに眉をたわめ、
「それだけでいいのか?」
心の奥まで見透かすような問いかけに、絢はうろたえた。そうだ、これだけじゃない。
───乙耶さんでなく僕を、僕だけを愛してほしい。
けれどそんな生々しい執着を言葉にするのは、絢にはハードルが高すぎた。
「だ、だって……」
「どうした。何を怖がる必要がある? 自分に嘘はつけないと、さっき言ったばかりじゃないか」
厳しく問い詰められて、絢はついに泣き出した。
「だって言えないっ……僕みたいな子供が、柊二さんに……」
「なんだ? 言ってみなさい」
「僕だけを愛してほしいなんて、言えないっ」
絢は癇癪を起こした子供みたいに叫んで、柊二の胸をぽかぽか叩いた。すると両の手首を優しく掴まれ、そのまま引き寄せられた。絢は小さな悲鳴をあげ、柊二の胸に倒れ込む。そして温かな抱擁に迎えられた。
「ちゃんと言えたじゃないか、絢」
「え? ……あっ」
柊二に指摘されてようやく、言うつもりのなかった欲求を吐き出してしまったことに気づき、首まで真っ赤に染まる絢。柊二はその耳元に唇を寄せて、甘く囁く。
「今の、もう一度言ってごらん」
耳にかかる熱い吐息や、身体の芯に響く極上の低音にうっとりとなりつつも、絢はふるふると首を振って拒んだ。
「や、やです……」
柊二は「しょうのない子だ」と苦笑混じりに言うと、絢の目を真っ直ぐ見据えて告げた。
「愛してるよ、絢」
柊二の告白を受けた絢の正直な感想は、『信じられない』だった。あれほど望んでいたことなのに、いやだからこそ、実現を素直に喜べなかった。
「でもっ、柊二さんは乙耶さんのことを……」
すると柊二は神妙な顔つきで静かに頷き、
「俺は、乙耶が君に引き合わせてくれたと思っている」
「乙耶さんが?」
「ああ。君と初めて会ったあの日、売れ残りの花を配っていたのは、翌日が乙耶の命日で墓参りに行くため、店を臨時休業にしていたからだ」
もし翌日が命日でなかったら、店を休むことはしなかった。ということは、売れ残りの花を道行く人に配ることもなかった。つまり、絢と出会うこともなかったのだ。
「乙耶、さん……」
絢の頬を温かな涙が伝う。いつだったか、この世に偶然などないと祖父に教えられたことがあった。全ては必然が作用し合って起こった結果で、それに気づいた時、人は謙虚になれるのだ、と。
ようやく今、絢は乙耶への嫉妬を克服することができたような気がした。代わりに湧き上がるのは乙耶への深い感謝の念と、そして彼が命を懸けて守ろうとした紫月流を支えるんだという決意。
───見ていてください。僕と幹と柊二さんで力を合わせて、紫月流の伝統を守り抜いてみせます。
絢は胸の前で祈るように両手を組んで、乙耶へ誓いを捧げた。するとその様子を見守っていた柊二は、絢の顎に手を添えてそっと上を向かせた。
「さあ、絢。自分の気持ちを、もう一度はっきり言ってごらん」
「は、はい。柊二さん……僕だけを愛してください」
お世辞にも堂々と、とはいえないか細い声だったが、絢は何とか伝えた。柊二は優しく目を細めて頷き、ゆっくり顔を近づけてきた。
「まだ怖いか?」
互いの吐息が感じられるほどの近さで、柊二が訊ねる。絢は急激に速まる鼓動を意識しつつ、正直に答えた。
「怖いというより、どきどきします」
「ポン太とどっちがいい?」
絢はおそるおそる腕を伸ばして柊二の首に巻きつけ、
「こっちが……いいです」
答えると同時に、温かくて柔らかなものが目尻に触れた。泣き黒子にキスが落とされたのだと気づいた時には、唇と唇が触れ合っていた。
磨き抜かれた白刃のように冷ややかで鋭利な存在感を放つ柊二の身体に、こんな柔らかな部分があるなんてと、一度目のキスでは感じることのなかった嬉しい驚きを反芻していると、柊二が唇を軽く吸ってきた。
「んっ……」
キスの延長線上にある戯れに、絢の口が自然と開く。すると、熱くぬめったものが入り込んできて、唇の裏側をとろりと舐められた。キスの範疇を超えた未知の感覚に、絢はびくんと身じろいだが、逃げようとはしなかった。
むしろ、目覚め始めた官能に導かれるまま、さらに口を開いて奥へ誘い込む。そして自ら舌を伸ばすと、間髪いれずぬるりと搦め捕られた。
自分のものでない舌はひたすら甘く、染み込んでくる唾液は蜜のよう。絢は重ねられた唇の隙間から熱い吐息をこぼしつつ、含まされるもの全てを夢中で味わった。
「は……ぁっ……あ、んっ……」
もっともっと欲しい。もっともっと深いところで柊二と繋がりたい。それが具体的に何を意味するのか、絢にはまだ分からない。そんな輪郭は曖昧な、それでいて急速に激しさを増す欲求に煽られて、絢は最も熱を帯びている身体の部分を柊二にそっと押しつけた。
するとそれに応えて、それまで背中を支えてくれていた柊二の手が尻に下がってきた。そして緩やかな曲線と弾力を楽しむようにひとしきりやわやわ揉んでから、ぐっと力を入れて引き寄せた。
当然の結果として、絢の熱を帯びてかすかに隆起した部分が、柊二の逞しい腰にぎゅっと密着する。絢は思わず甘い声をあげ、気がつけば腰を淫らに揺すっていた。
「あ……あ、柊二さ…ん……また、身体が変です……」
身体の奥がじんわり濡れてゆくような感覚は、もう知っている。けれど、
「お、お腹から下が熱くて……熔けてなくなっちゃいそう。なのに……」
「なのに?」
「ここは……尖ってぴりぴりしてる……変、でしょう?」
絢はそう言って、自分の胸を指差した。すると柊二は絢の上着を脱がせ、シャツの下から手を滑り込ませてきた。何をする気だろうと考える間もなく、胸にちりっと甘いような痒いような痛みが走った。
「あっ! ん、や、やだっ、柊二さ…ん……」
「ここだろう? 絢」
乳首をつままれていると分かった時には、痛みの鍍金は剥げ落ちて、快感がじわりじわりと溢れ始めていた。
「こんなに硬くなって……」
柊二の低音で指摘されると、それが途轍もなくいやらしいことのように思えて、絢の顔は自然と赤くなる。そんな羞恥にも快感を増幅させる媚薬が含まれていることを、絢はまだ知らない。
「やっ、そんな……コリコリってしちゃいやです……」
舌足らずな懇願とは裏腹に、身体はもっとしてとねだるようにしなって胸を突き出す。柊二はもちろん身体の求めに従い、こんもりと盛り上がった乳暈ごと指で挟んで強めに揉みしだいた。
「あ、ふっ、ぅ……」
半開きになった唇の隙間から舌をちらちら閃かせつつはふはふ言っていると、舌先をぬるりと舐められた。その瞬間、絢は下着の奥がじゅわっと濡れるのを感じ、思わず腰を浮かせた。
「今度はここか?」
絢のちょっとした動きも見逃さず、柊二はいとも容易く快感の源泉を捉えてしまう。控え目な主張を見せる股間を指先でつい、となぞると、弾かれた弦のようにひくひく震える絢の身体を抱き上げて、膝の上に後ろ向きに座らせた。
「柊二……さん?」
腰を揺らめかせながら振り向いてようよう訊ねると、優しい口づけが落ちてきた。そしてその余韻を味わう間もなく、柊二の手によってするすると下穿きを脱がされた。
「…………」
あっという間に裸にされた下半身を、絢は呆然と見つめる。明るい照明の下で白い素肌をさらす脚が、自分のものだという実感がなかなか湧いてこない。
しかし股間を飾る薄紅色の性器が、上を向いたままふるんふるんと揺れるのを目にして、どっと恥ずかしさが湧いてきた。
「やッ……」
絢は顔を背けて脚を閉じたが、後ろからぬっと伸びてきた手に膝を掴まれ、ぐいと左右に開かれた。絢は半ば恐慌状態に陥って、膝を掴んでいる手を必死に剥がそうとした。しかしびくともしないと分かると、今度は上からぺちぺち叩き始めた。
「こら、絢。痛いぞ」
咎める柊二の声は笑み含んで、かすかに浮ついていた。対して絢は涙声で、
「だ、だってこんなっ……」
「恥ずかしいか?」
絢は熱烈に頷いた。その動きに合わせて、のぼせ上がった半身が誘うように揺れる。と同時に、先端の窪みに溜まった透明の液体がほろりとこぼれた。
「や、やだぁ……もぅ……」
一分の乱れもない端整な和装の柊二の前で、こんな醜態をさらしている自分が惨めで恥ずかしくて、絢は本格的に泣き出した。すると耳元で「よしよし、いい子だ」とあやすような甘い低音で囁かれ、膝を掴んでいた手が離れた。
絢はほっと安堵の息を吐いたがそれも束の間、すぐに呼吸が止まった。柊二の手が、股間のものをゆったり握って上下にしごき始めたからだ。
「やめっ……柊二さ……そんなの触っちゃだめですっ」
「ん? なんでだ?」
「だ、だって、汚いです」
「汚い? こんなに可愛いのに。まるで、ふっくらと綻んだ薔薇の蕾のようだ」
柊二はそう言って、芯に凝った熱を融かすように五指を波打たせつつしごく。時折親指の腹で先端を叩くと、ぷくぅと真珠色の液体が盛り上がってとろとろと滴った。
「絢の蜜はとても美味しそうだ」
揶揄めかした柊二の言葉だったが、その深層に生々しい飢えが潜んでいることを絢は肌で感じ取った。それは甘い戦慄となって四肢に伝播する。
「あ……あ……だめ……ぇ……」
口は相も変わらず拒絶の言葉を繰り返すが、身体が悦んでいることは明らかだった。腰は淫猥なリズムを刻み、白い太ももは艶めかしい震えを見せ、爪先は溜まった快感を放出するかのように丸まったり伸びたりする。
そして、柊二の手の中にある若茎は言わずもがな。しとどに濡れそぼって、手の動きに合わせてくちゅくちゅと水音をまき散らしている。
「んっ、は、はっ……ぁぁ……」
「絢、我慢しなくていい。気持ちよくなりなさい」
優しい誘導に応えるように、柊二の手に包まれた自身がぴくぴくと悶える。先端の割れ目からは薄く濁った液体が絶え間なく溢れ、絶頂が近いことを知らせていた。
「柊……二さ……ぼく、もぅ……」
官能の熱で今にも蒸発しそうなほどか細い声で訴えると、柊二はこめかみへの口づけで了承を伝え、手の動きを加速させた。
「あっ、あっ……違うっ……やだぁ……出ちゃうよぉ……」
腰の奥に溜まっていた粘ついた快感が一気に沸騰し、出口を求めて性器に凝集する。そこが痛いほど張り詰めるのを感じながらも、絢は首を振って必死に耐えた。
「構わないから、出しなさい」
「やだっ……こんなとこで……恥ずかし……です……」
絢が息も絶え絶えに答えると、荒い呼吸に膨らんだ胸の上で今にも弾けそうなほど勃ち上がった果実を、クリッと捏ねられた。
「ひぅ! ふ、ぅぅっ……」
二つの器官に同時に与えられた刺激は直結し、互いに干渉し合ってより大きな快感をもたらした。絢の中に残っていた羞恥心は一掃され、身体は素直に性の悦びを謳う。
「あっ、ああ……い、いい………!」
絢は大きく仰け反って腰をびくびくと跳ね上げた。と同時に、先端から熱く粘ついた塊がびゅっびゅっと飛び出す。
「あ、ふっ……ふぅ、ん……」
甘ったれた吐息を鼻や口からこぼしつつ、絢は秘めやかな放出を続けた。うっとりと中空を彷徨う瞳は涙の菲膜に覆われ、視界は妖しく霞む。しかし、放出を終えて意識がクリアになるにつれ、視界も輪郭を取り戻していった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT