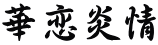
─KAREN ENJOU─
十二、情花の章
「ずいぶん遅くなったな。絢、帰るぞ」
病院を出ると、幹は硬い声でそう言って絢の手を有無を言わせず引っ張った。これまでにない弟の強引さに困惑しつつも、絢は首を振って抵抗し、
「ま、待って、幹。僕はあの、柊二さんと話を……」
「あそこに車を待たせてある。さ、早く行こう」
「だから待ってってば!」
絢は幹の手を振りほどいたが、そのまま背中を向けることなく正面から対峙した。
「柊二さんと、ちゃんと話がしたいんだ。だから一緒には帰らない」
「こんな遅い時間に男と二人きりになるなんて、何かあったらどうするんだよ!」
真剣そのものといった幹の叫びだったが、絢にはピンとこない。ちょんと首を傾げて、
「何か、って?」
絢の天然な問いかけに、幹は「うっ」と詰まる。続けて「いやだから……つまり……」ともごもご口ごもる幹に、柊二は冷ややかな視線を向けてぴしゃりと告げた。
「絢がこうなった原因は、君の過保護にもあるぞ」
「う、うるさいっ。分かったようなこと言うな!」
柊二はやれやれと言わんばかりに溜め息をつき、
「絢、今日は家に帰りなさい。話ならまた今度ゆっくり───」
「い、いやです! 柊二さんに大事なこと言わなくちゃいけないんですっ」
絢は必死に言い募り、真っ直ぐな瞳で柊二を見上げると震える声で訊ねた。
「それとも……ご迷惑ですか?」
すると柊二は流麗な眉をたわめ、ややぶっきらぼうな口調で「迷惑だなんて言っていない」と答えた。途端に絢はぱあっと顔を輝かせ、喜びと安堵を露わにする。そして幹にずいと身体を近づけ、
「お願い、幹。大事な大事な話なんだ。だから……」
「わ、分かったよ! 分かったから───」
幹は両手を挙げて『降参』の意思表示をしてから、柊二に勝るとも劣らぬ美しい切れ長の目をさらに尖らせた。そして柊二を睨みつけ、
「兄さんに変なことしたら承知しないからな!」
悲壮感漂う捨て台詞を残して、荒っぽい歩みで帰っていった。その強張った背中を見送った柊二は、苦笑いを隠そうともせず、
「やれやれ、大したブラコンだ。絢のことが好きでたまらないといった感じだな」
「え? 誰が、ですか?」
「もちろん絢の弟君だ。『兄さんLOVE』って顔に書いてあったぞ」
絢は思い切り眉をひそめ、ちょっと恨めしげに柊二を見上げた。
「冗談はやめてください。小さいころから顔が合えば尖った口調で命令ばかり。出来の悪い兄を持て余しているに違いありません」
「彼がああしろこうしろとうるさいのは、君が自分のことに無頓着すぎるからだ。心配でつい色々口出ししてしまうのだろう。まあ、君が無防備だから弟が過保護になったのか、弟が過保護だから君が純粋培養で育ってしまったのか、卵が先か鶏が先か、みたいなものだが」
絢は、眉間の皺が自然と深まるのを感じた。
「仰る意味がよく分かりません」
「はっきり言えば、君はまだ幼いということだ」
「あ……」
とうに自覚していることなのに、柊二の口から聞かされるとこうもショックを受けてしまうのか。絢は心に受けた傷をごまかすためキッと眦を決し、強い口調で言い返した。
「そんなの分かってます! 柊二さんのように人生経験が豊富な大人から見たら、僕なんてぬるま湯でばしゃばしゃやってる赤ちゃんみたいなものだって。でもっ───」
絢が言い終わらぬうちに、柊二の指先が顎に触れた。そしてくいっと上を向かせ、
「いいや、君は分かってない。ほら、またこんな風に瞳を潤ませて。この切なげに揺らいだ瞳が、男の卑しい欲望をどれだけ刺激すると思っているんだ?」
「卑しい欲望って……?」
絢の問いを、柊二は微笑でかわした。そして顎から手を離し、
「俺と初めて会った時のことを覚えているか?」
「は、はい。もちろんです」
もしゃもしゃの髭づらに笑顔を浮かべて、道行く人々に花を配っていた柊二。つい先月のことなのに、ずいぶん昔のことに思える。
「自分で言うのも何だが、あの時の俺はかなりの不審人物だったと思うぞ。なのに絢は、花をもらっただけで簡単に信じ、何の警戒もせず後についてきた。俺が悪い男だったら、あのまま絢を連れ去っていたかもしれない」
「そんなっ、柊二さんはそんなことしません!」
「ほら、そうやってすぐ人を信じる。なぜそう言い切れるんだ? 絢のそういうところに付け込んで、悪いことを企もうとする男が多いから、弟はあんな心配性になってしまったんだ」
「だ、だって……」
絢は必死に言葉を探した。他の男性のことなど知らない。ただ柊二だけは違うと分かっていたと、どうやって伝えればいいのか。
「あの時柊二さんは、売れ残った花を枯らすぐらいならあげてしまった方がいいと、その方が花も喜ぶと言いました。そういう人を疑うことが大人の証だというのなら、僕は一生幼いままでいいですっ」
絢は挑みかかるようにそう言って、こみ上げる嗚咽を閉じ込めるため唇を噛み締めた。でもどんなにこらえても、涙までコントロールすることはできない。目尻からぽろりと雫が転がったが、絢は拭いもせず柊二を見つめ続けた。
柊二は驚いたように目を見開いたが、すぐに溜め息をついて、
「全く君は……」
柊二のこういう呆れ口調を聞くのは何度目だろう。やっぱり想いは伝わらなかったのか。絢は自分が情けなくて、ぎゅっと目を閉じた。そしてくしゃくしゃの顔で、肩を上下させる。ずっと抑え込んでいた嗚咽が、ついに堰を切って溢れ出ようとしていた。その時、
「しょうのない子だ。でも、ありがとう」
跳ねる肩を優しく宥めるように、柊二の手が撫でてくれた。
「絢の気持ちは分かった。その代わり今後は、俺以外の男を簡単に信じたり、こんな風に涙を見せたりしないように。いいな?」
胸がいっぱいで言葉がうまく出せなかったから、絢は柊二の胸に顔を押しつけ何度も何度も頷いた。やがてか細く震える声で、
「柊二さんの……お部屋へ行ってもいいですか?」
問うと同時に、背中を撫でてくれていた柊二の手がぴたりと止まった。が、すぐに何事もなかったかのように再開する。絢はこわごわ顔を上げて視線を重ね、
「だめ?」
その時、いつも冷静に対象を射抜き、深遠な凪を湛えている柊二の瞳がわずかに揺らいだ。絢はそこに柊二の動揺と葛藤を見たがその理由が分からず、小さく首を傾げた。ややあって、
「……俺以外の男は信用するなと言ったばかりだからな。分かった、ともかく俺の家に行こう」
「はっ、はい!」
柊二の声にどことなく疲労感がにじんでいるのが気になったが、またあの部屋に行ける嬉しさの方がまさった。絢は笑顔全開で頷くと、柊二の隣にぴったり寄り添った。
散らかっているから足元に気をつけるようにと事前に言われていたが、部屋に入るとそれが実感できた。所狭しと床に積み上げられた書籍の山。それらが全て紫月流の資料や教本であることに気づいたのは、照明がともされてからだ。
「柊二さん、これは……」
「見ての通り、教本だ。どうしても捨てることができずに仕舞い込んでいたが、君からの手紙を読んで、あらためて紐解いた」
てきぱきと片付けながら答える柊二を、絢は驚きとともに見つめた。
「え? それじゃあ……」
「ああ。あの手紙を読んで、紫月流に戻る決意を固めた。花屋ではできない自己表現、己との対話に、俺ももう一度挑んでみたいと」
柊二はそう言って、フッと笑った。その瞬間、絢の心臓は身体ごと跳び上がりそうなほど大きく跳ねた。脈拍がどんどん上昇し、酸素たっぷりの熱い血が全身を巡る。
───ふわ……のぼせ…そ……
絢は今さらながら柊二の美貌にあてられ、リアルな眩暈に襲われた。本部展の会場や祖父の病室ではまだ緊張感があったし、幹と別れた後の会話は病院の外だから暗かった。つまり、熊男でない柊二と、明るいところでじっくり相対するのはこれが初めてなのだ。
「絢? どうした。具合でも悪いのか?」
柊二が心配そうに眉根を寄せて近づいてくる。絢は思わず後ずさり、その拍子に踵と本がぶつかってよろめいた。そしてその場にかくんと座り込む。
「絢っ」
柊二は慌てて駆け寄って手を伸ばし、絢の身体を支えた。
「大丈夫か? 怪我はないな?」
そう言って顔を覗き込んでくる柊二を、絢はじっと見つめ返す。するとさらに心臓がばくばく鳴って頭がぼぅっとし、自分でもどうしていいか分からなくなった。
すっと通った形のよい鼻梁、流麗な眉、深甚な知性と鋭利な感性がきらめく黒青(こくじょう)の瞳。ひとつにまとめた髪はわずかに乱れ、ほつれて頬にかかる長い前髪が落とす陰翳には、ぞっとするような色気があった。もしゃもしゃの髭があった場所は、すべらかな素肌で覆われている。
こんなに綺麗で、知的で、大人の色香漂う男性と、僕みたいな子供が釣り合うはずがない───絢の中に突如として頭をもたげたマイナス思考の怪物のせいで、気がつけばおかしなことを口走っていた。
「柊二さんの顔、こわい……」
「……は?」
「綺麗すぎて、こわいです」
それは絢の偽らざる本心だったが、あまりに唐突な言葉に柊二は怪訝な顔つきをした。
「何を馬鹿なことを」
「馬鹿なことじゃないです! だって、これまでずっと髭もじゃだったのに、いきなりこんなカッコよくなっちゃったら、どうしていいか分からなくなるし!」
「え? あ、ああ、これか……」
柊二は何となく合点がいったという風に呟いて、自分の顎をさらりと撫でた。そして、
「本部展にあの髭づらで行くわけにはいかないからな。取り敢えず剃ったんだが、絢は髭があった方がいいのか?」
困惑のにじんだ問いかけに、絢は慌てて首を振った。
「そ、そうじゃなくて……どっちがいいとかじゃないんです。どっちも柊二さんに変わりないんだし。ただ、えと、髭もじゃだとポン太に似てて安心するから───」
「ポン太?」
当然の疑問に、絢はあわあわしつつ答えた。
「はい、あの、僕が小さいころ大事にしてた熊のぬいぐるみです。こう、毛がもしゃもしゃしてて大好きだったのに、幹に壊されちゃって。で、最初柊二さんに会った時、ポン太に似てるなあって思って、それで……」
何とか筋道たてて説明しようと奮闘する絢をおいて、柊二は肩を震わせ笑う。
「ぶっ、くくくく……」
「ひ、ひどいですっ、笑うなんて」
「これが笑わずにいられるか。全く、君は……」
ああ、まただ。また呆れられてしまった。想いをちゃんと言葉にしようと焦れば焦るほど、柊二との距離が開いてゆくような気がする。必死に手を伸ばすと、その分だけ足元がずぶずぶ沈んでゆくのだ。
「分かってますっ。どうせ僕は子供です。カッコよくて大人な柊二さんにはきっと、乙耶さんみたいな人がお似合いなんだって……」
言ってしまってから、絢はハッと息を呑んだ。腹立ちまぎれに亡くなった恋人の名前を出すなんて、軽率で配慮に欠けたことをしてしまった。
「ご、ごめんなさい……」
絢は弱々しい声で謝罪して、深く項垂れた。怖くて柊二の顔を見ることができない。あの美しい瞳が怒りや軽蔑の色で染まっているのを見たら、きっと自分は一生立ち直れないだろう。しかし、
「絢、こちらを見なさい」
凛と通る声に命じられ、絢はおそるおそる顔を上げた。柊二の表情には怖れていたような感情の痕跡はなく、むしろ情愛に溢れて暈然と輝いているように見えた。絢がうっとり見上げていると、いきなりふわりと抱き上げられた。
「ひゃ? 柊二さん……」
そしてそのままソファへ移動し、絢の隣に腰を下ろすと、穏やかな口調で、
「乙耶のこと、苑山先生に聞いたのか」
「はい。十年前のお家騒動や、それに乙耶さんが巻き込まれてしまったことも。それから、柊二さんの客前装花の映像も……見ました」
亡き恋人を想って生けられた、血の滴る妙蓮寺椿。ちょっと思い出しただけで、胸の奥に凝るどす黒いものがうぞうぞと蠢き出す。
「カフェの前にある石碑に花を生けたのも、乙耶さんのことがあったからなんですね」
「ああ。雲の上で孤独を耐え忍んでいるかもしれない彼の、わずかでも慰めになればと」
柊二さんはまだ乙耶さんのことを想っているのですか?───喉元まで出かかった問いを、絢は急いで封じ込めた。答えを聞くのが怖かったのと、こんな質問が浮かぶ自分に卑しさを覚えたからだ。
沈黙する絢に、柊二はかすかに高ぶった声で、
「君の『華恋炎情』を見た。見事だった。あの真価は、情の炎に灼かれたことのある人間でなければ分からないだろう」
静かな、それでいて重みのある賛美を、絢はそのまま受け入れることはできなかった。小さく首を振り、
「僕があれに込めた感情は、決して美しいものではありません。血を流しながら一心不乱に生ける柊二さんを見た時初めて、深層に潜む醜い自己の存在に気づきました。乙耶さんに対し、僕は……同情するどころか激しく嫉妬したのです」
「…………」
柊二は無言のまま、不動の瞳を絢に向ける。彼の中にどんな感情が渦巻いているのか気にならないと言えば嘘になるが、絢は毅然と言葉を続けた。
「どんなきれいごとでも隠しきれない生の自分。そのおぞましさに慄え、一度は逃げようとしました。でもあなたの言葉を思い出し、これを花にぶつけてみようと思ったのです。そして、僕なりの『美と醜の弁証法』を完成させようと。つまりあの妙蓮寺椿は、嫉妬に苦しむ僕自身の姿なんです」
絢が口を閉じると、柊二は何も言わず目をつむった。瞼裏に灼きついた、燃え上がる椿の残像を鑑賞するかのように。
途端に絢は怖くなった。同じ花材を使って嫉妬という負の感情を表現したなんて、自分や亡き恋人を愚弄するような行為と思われてしまう可能性もある。
でも、それでも。
「自分に……嘘はつけなかった……」
絢の絞り出すような呟きが届いたのか、柊二はふっと目を開けた。そして、底知れぬ深みを湛えた双眸で真っ直ぐ絢を見据え、
「それでいい。醜さを怖れず剥き出しの自己を表現する、それこそが君に足りなかったものだ」
「あ……」
「つらかったろう、絢。よく頑張ったな」
優しい労わりの言葉に、張り詰めていた感情の糸がふぅっと緩むのを感じた。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT