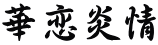
─KAREN ENJOU─
十一、賛花の章
舞台いっぱいに広がるのは、漆黒の闇。今から自分は、あそこに飛び込もうとしているのだ。
待ち受けるのは称賛の拍手か、失望の溜め息か。いずれにしても、やらなくてはならない。紫月流の未来を担う者の一人として、もう逃げるわけにはいかないのだ。
───柊二さん、あなたもこの景色を見たのですね。
十年前の本部展で披露した客前装花。恋人を想い、恋人のために生ける舞台に上がる寸前、柊二もこの濃密な闇を見たはずだ。
───あなたは闇の彼方に、何を見ていたのですか? 何を感じていたのですか……?
亡き恋人の面影だろうか、あるいは自分が流すことになる血の幻影だろうか。いや、きっと柊二のことだから、己の内に蠢くものをじっと見据えていたに違いない。ただ静かに感性を研ぎ澄ませ、揺らめく情念の炎に対峙し───
「さ、舞台へどうぞ」
背後から声を掛けられ、はっと顔を上げた。と同時に視界がハレーションを起こす。さっきまで闇に沈んでいた舞台は、複数の照明がもたらす光の洪水で溢れ返っていた。
絢は意志とは無関係の何かに押されるように舞台中央へ歩み出る。事前に説明がなされていたのか、会場が驚きや困惑でざわつくことはなかった。
しかし安堵などできるはずもない。むしろ静寂が重くのしかかって、絢は呼吸もままならぬほどの息苦しさに襲われた。会場から注がれる数多の視線。それは絢の一挙手一投足を見逃すまいと、皮膚にびりびり突き刺さる。
この時絢はようやく、自分がとんでもない場所に立ってしまったことを思い知った。家元が受ける重圧がどれほどのものか、宗家に生を受けながら全く分かっていなかった。だからこそ、僕がやるよなんて言えたのだろう。その意味ではやはり幹の方が、家元の何たるかを理解していたのだ。
が、今さら後悔しても遅い。絢は用意された花材におそるおそる視線を落とした。
石化柳が八本。そして黄色い実のフォックスフェイス。赤い実のついたサンキライの枝。
───ど、どうしよう……。
見た瞬間、絢の頭の中は真っ白になった。もともと、いわゆる実ものが苦手なのだ。それを客前で、しかも即興で生けるなんてとてもじゃないができる自信がない。
とはいえ、いやしくも家元候補である宗家の人間が、やっぱりできませんと言って頭を下げるわけにもいかない。やるしかないのだ。
絢は頭の中で形のイメージを描きつつ、石化柳の最も長い一本を手に取った。指先の震えが伝わり、伸びやかな柳の先端が小刻みに揺れる。しかし気にしている余裕はなかった。
石化柳の中央を慎重に握ってたわめ、緩やかな“く”の字に曲げる。これを中心となる『天』の枝としてまず生け、それに添う形で他の枝を生ければ、作品の基礎となる『線』ができる。
これさえうまくいけば、花材もフォックスフェイスという変り種なのだから、多少の冒険は許されるだろう。あとは自由な感性でのびのびと生ければいい……はずだった。しかし、
───どうしよう。うまく曲がらない……
選んだ枝が悪かったのか、力加減を誤ったのか、おかしな方向に曲がってしまった。中央は優雅な曲線を描き、枝先は上にぴんと跳ね上がるようにしたかったのに、くたりと下を向いて項垂れてしまった。
このまま生けたら、作品全体が絶望に打ちひしがれたかのような負のオーラをまとってしまうことは間違いない。本部展のオープニングに相応しいとは言えまい。絢は落ち着けと自分に言い聞かせ、石化柳の枝をもう一本取ろうと手を伸ばした。
すると会場から注がれる視線の束が、それに合わせて動いた。ほとんど暴力的な視線の力に、それまで何とか平静を保っていた絢の神経はついに悲鳴を上げた。視界は白く霞み、四肢から力が抜けふらりとよろめく。その時、
「考えてはいけない。感じなさい」
聞き慣れた声とともに、力強い腕が絢の背中を支えた。
「あなたは……」
絢は一瞬誰か分からずぼうっと見つめ、この突然現れた男性が柊二だとようやく気づいた。しかしそれも仕方ないだろう。彼を“熊男”たらしめていた顔半分を覆う髭はきれいに剃られ、髪は後ろできりっとまとめられている。
切れ長の瞳はかすかに青みを帯びた黒。舞台に降り注ぐ派手派手しい照明を一切寄せ付けぬ、冷ややかで鋭い輝きを宿していた。
韓藍の着物が、程よく引き締まった身体の輪郭を際立たせている。華やかな場に臆することなく凛然と立つ柊二に、絢は立場も状況も忘れ陶然と見とれた。
しかし柊二は気にする様子もなく、ごく自然な動作で絢の手から石化柳の枝を取った。まるで、最初から段取りが決められていたかのように。
そして下向きに曲がってしまった枝を軽くひねり、見事な『天』のラインを作り上げた。さらにそれに沿って数本の枝を生けると、あっという間に芸術的な『線』が出来上がった。
「さあ、絢」
柊二に促され、絢は躊躇することなくフォックスフェイスに手を伸ばした。個性的な形をした黄色い実を、柊二が生み出した美しい空間に配してゆく。迷う必要はなかった。柊二の生けた『線』に吸い寄せられるように、絢の手は自在に動く。
最後にサンキライの実を添えて全体に奥行きを持たせれば、和と洋、伝統と前衛、華と寂(さび)の二極を見事に捉えた作品が完成した。
柊二は絢の手を取って舞台の前方に歩み出て、深く頭を下げた。それを見た絢も慌てて倣う。すると一瞬のしじまを経て、割れんばかりの拍手が沸き起こった。
初めて味わう空気の振動に身を浸しながら、今になって緊張の糸が切れた絢は、溢れそうになる涙を必死にこらえた。
こうして、柊二と絢の合作による客前装花は大成功を収め、本部展初日に相応しい華々しさの中、オープニングセレモニーは無事終了したのだった。
病室の白い扉。一応ノックしたが、返事が待ちきれずすぐ開けて、部屋の中に飛び込んだ。
「お祖父様!」
絢と幹がばたばたとベッドに駆け寄ると、身体を起こして本を読んでいた苑山は眉をひそめ、「これ、病院では静かにしなさい」と言ってぱたんと本を閉じた。
病床の祖父は、家にいる時よりはやつれて見えるものの、控え室で倒れた時よりは顔色もよく、声にも張りがあった。
ただ、腕に刺さった透明の細い管が痛々しくて、絢はつい悲愴な顔つきで見つめてしまった。すると付き人の葉山が絢の心中を察したのか、穏やかに笑い、
「ご心配はいりませんよ。疲労が重なったところに、軽い風邪をお召しになったようです。脱水症状を起こしかけていたので、数日の入院と点滴が必要になりますが」
絢は、自分の顔がふにゃあと緩むのを感じた。
「よ、よかったぁ……」
自然と涙が溢れ、頬を濡らす。こうして、祖父や弟の前で泣くのは何年ぶりだろう。感情を抑え込むのが当然だった日常から、気がつけば遠く隔たっていた。
「泣くなよ、絢。みっともない」
幹は呆れたようにそう言いつつも、ハンカチをぬっと差し出した。絢は素直に受け取って涙を拭い、「ありがと」と礼を言ってまだ潤んでいる目で見上げる。幹はふいと横を向いてしまったが、その頬はなぜか赤く染まっていた。
「二人とも、心配かけてすまなかったな」
祖父からの謝罪に、絢も幹も首を振り、
「謝るのは僕たちの方です。本部展前で忙しいお祖父様のサポートもろくにできず……」
「いや。お前たちには自分のやるべきことがあった。それをおろそかにして儂の手助けなど、百年早い」
ぴしゃりと言われて、絢も幹も同時に首を縮めた。するとそれが可笑しかったのか、苑山は呵々と笑ったが、すぐに顔を引き締め、
「それより、装花はどうなった。絢がやったのか、幹がやったのか。それとも……」
その深刻な口調から、どんな事態を予測していたのか手に取るように分かる。客の前で生けるという未知の舞台に恐れをなして、二人とも背を向け逃げ出したのではないか、と。
「そのことですが、お祖父様に会っていただきたい人がいます」
絢はそう言って振り向き、扉の陰で静かに待っていた人影に微笑みを向けた。すると人影は小さく頷き、ゆっくりと歩み出た。
「柊二……来てくれたのか……」
苑山は目を細め、湧き上がる感慨を噛み締めるように呟いた。その枕元に控えた二人の付き人は、ぽかんと口を開けて見惚けるばかり。二人とも古参の紫月流会員だから、柊二のことはよく知っていた。だからこそ驚きが大きかったのだろう。
「深刻な病ではないと伺って安心いたしました。客前装花については、ご心配には及びません。絢さんが見事に務め上げてくれました」
柊二の言葉に、絢は慌てて付け足した。
「た、確かに僕は舞台に立ちましたが、装花が成功したのは柊二さんのお陰なんですっ。僕一人ではきっと、散々な結果に終わっていたはずです」
それは謙遜ではなく事実だ。もしあの時柊二が舞台に上がって支えてくれなかったら、これまで数々の傑作を生み出してきた本部展装花の歴史に泥を塗ることになっていただろう。想像しただけで、胃がきゅうっと竦み上がる。
「宗家としての務めを果たさねばという意気だけで、実力も伴わぬまま安易に大役を受けてしまいました。申し訳ありません」
すると絢の謝罪を遮るように、幹が一歩前に出た。
「兄は、自ら重責を担ってくれたのです。大舞台を前にして、僕はただ怯え震えるしかできませんでした。舞台に上がっていたらきっと、指一本動かすことができなかったでしょう」
「幹……」
「兄も同じ気持ちだったはずです。それでも舞台に穴を空けるわけにはいかないと、覚悟を決めて踏み出した。どちらが家元後継者としてより強い自覚を持っていたかは、言うまでもありません」
その言葉を聞いて、絢は悟った。あの舞台に立っていた間、幹も自分と同じくらい緊張して、客席からの視線に恐怖を感じていたに違いない、と。
そう、あの時自分は独りではなかったのだ。
「全く、お前たちは……」
呆れたと言わんばかりの口調に、咎めるような厳しさはなかった。その証拠に苑山はくくっと喉の奥で笑い、二人の孫に慈しむような視線を送った。そして柊二に向かい、
「見ての通り、絢も幹もまだまだ未熟。そして儂も、無理のきかない歳になった。今後は二人の後見人として、師として、道を間違えぬよう厳しく指導してくれんか。頼む、柊二」
病室が、緊張をはらんだ沈黙に満たされた。誰もが息を詰めて柊二の答えを待つ。ややあって、柊二はふっと口元を綻ばせた。
「私の方から、先生に頭を下げるべきでした。本当は、とうに分かっていたのです。華の道を捨てることなどできないと。なのに過去の因縁に縛られて、なかなか踏み出すことができなかった。そんな私の背中を、絢さんが押してくれたのです」
「えっ?」
絢は驚いて柊二の顔を見上げた。
「僕、が……?」
自分は何もしてないのに、と戸惑う絢に、柊二は優しい眼差しを向けた。そして苑山に向かって深く頭を下げ、
「華の道から長らく離れていた私に何ができるか分かりませんが、私を育ててくれた紫月流のため、そして花を愛する全ての人のため、身を粉にして働く所存です。どうぞ、よろしくお願いいたします」
重く真摯な誓いの言葉に、苑山は感無量の面持ちで大きく頷いた。
「頼んだぞ、柊二」
「はい」
そんな二人のやり取りを間近に見て胸が熱くなった絢は、気がつけば柊二の身体に飛びついて、ぎゅぅぅと抱き締めていた。
「こ、こらっ、絢。離しなさい」
「え? うわ、わわっ、ごめんなさいっ」
柊二に叱られて慌てて身体を離したが後の祭り。祖父や付き人たちには笑われ、幹からは突き刺すような険しい視線を浴びせられた。柊二はといえば、作ったような無表情で、大して乱れてもいない着物をせっせと直している。
「柊二が戻って一番喜んでいるのは絢だな」
祖父の言葉に、絢の頬はあっという間に色づいた。その薔薇色の頬が、何より雄弁な肯定の証だった。
BACK TOP 華恋炎情INDEX NEXT