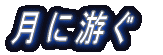
十四話<望月>
「がらくたばっかりでしょう?」
游月は博物館内を案内しながら、悪戯っぽく笑って言った。しかしその声に卑下するような暗い翳は微塵もなく、子供が宝物を見せる時のように浮かれた熱がこもっていた。透麻も楽しげに笑って、
「よく集めましたね。見事なコレクションですよ」
ここには、月に関するあらゆる物が展示されていた。月の写真や隕石(らしきもの)はもちろん、月を題材にした小説、詩集、絵本、漫画。さらには大きな月面地図、大小さまざまな月球儀、ガリレオの望遠鏡の複製。月を描いた絵画、版画などなど。
すると透麻は、月を題材にした小説のコーナーの前に立ち止まり、ケースの中をじっと見つめた。
「透麻さん、どうしたの?」
「いや……何でもないです。それよりも游月、あなたのお父さんにぜひ会わせていただきたいのですが」
游月はにっこり笑って頷いた。
「もう連絡してあります。あの、狭いですが実家へ来てもらえますか?」
「もちろん。光栄です」
そして透麻は、なぜか深呼吸をした。游月は不思議そうに首を傾げて見上げたが、閉館時間を知らせるチャイムが鳴るのを聞いて、慌てて閉館の準備を始めた。
「こちらです。どうぞ」
玄関から奥の部屋へ案内された透麻は、ぐるりと周囲を見回して「いいお家ですね」と微笑んだ。安易なお世辞を言うような人ではないと分かってはいたけれど、游月はぷるんと頭を振って「古い日本家屋です」と答える。
「確かに古いでしょうが、手入れも行き届いているし、建物自体が思索に耽っているような落ち着きが感じられます。ここで游月が生まれ育ったのが、分かるような気がします」
しみじみと感慨を述べる透麻に、游月は素直に「ありがとうございます」と伝えた。やがて戸が音もなくするすると開いて、游月の父、孝義(たかよし)が現れた。
と同時に、それまできっちり正座しながらもどこか寛いだ空気を漂わせていた透麻の様子が一変した。こんなに分かりやすい緊張をさらす彼は初めて見る。それとは対照的に、孝義は柔らかく笑い、
「遠いところをようこそ。さあ、そんな畏まらずに」
透麻は「恐れ入ります」と頭を下げたが、足を崩すことなく自己紹介した。そしてさらに深く頭を下げ、
「今日は、お願いがあって参りました。游月さんを私にください。必ず幸せにいたします」
孝義は半ば予想していたのか驚きも見せず、黙って腕を組んでいる。跳び上がるほど驚いたのは、游月の方だった。
「とっ、透麻さん! 何を言い出すのですか、そんな……」
しかしすぐに口を噤んだ。透麻も、そして申し出を受けた父も真剣だと気付いたのだ。不安や困惑は消せぬまま、成り行きを窺う。やがて、頭を下げたままの透麻に向かって孝義は厳かに口を開いた。
「ここへ戻ってきた時、この子はボロボロでした。傷付き、打ちひしがれて……」
透麻は畳に爪を立て、自らの非を暴く。
「申し訳ありません。全て私が犯した過ちの故です。一生かけて償いをいたします」
「一生というのは重い言葉ですよ。余り軽々しく使わない方がよろしい」
「分かっております。しかし、他に言葉が見つからないのです。私の気持ちをお伝えするには、これしか……」
游月はいつの間にか、胸の前で手を組んでいた。溢れる涙を拭おうともせず。孝義はそんな游月に温かい眼差しを送ると、
「僕は駄目な父親です。あなたに文句を付ける資格もない。どうか幸せにしてやって下さいと、頭を下げねばならないのは寧ろ僕の方だ。よろしくお願いします」
そう言って、畳に額をこすりつけた。透麻は畳に手を付いたまま慌てふためき、
「や、やめてください。どうか頭をお上げください」
「いやいや、そちらが先に上げてください」
「とんでもない、お父様が先に」
二人の男は、カエルのように畳の上に突っ伏したまま、延々と譲り合った。游月はその様子を眺めながら、濡れた瞳を輝かせ呆れたように笑った。
「やっぱり、游月の部屋はきれいですね」
「そう…ですか……?」
畳の上に一組だけ敷かれた布団。何だかベッドより生々しくて、思わず赤面してしまう。妙なところで気の利く父は、今日は徹夜で原稿書きだと言って、博物館の事務室へこもってしまった。つまり、この家にいるのは自分と透麻、二人だけ。
「游月」
「は、はいっ」
びくんと跳ね上がって、無駄に大きな声で返事をする。カチコチに緊張しているのがバレてしまった。恥ずかしくて、透麻の顔をまともに見ることができない。
俯いて固まっていると、後ろからふわりと抱き上げられた。そして布団の上にそっと横たえられる。
「游月、緊張しているのですね?」
「は、はい。変ですよね、今さら……」
「とんでもない。私も緊張していますよ。だって、初夜ですからね」
游月ははっと顔を上げて、透麻を見つめた。しっとりと優しく潤んだ黒瞳に、緊張した面持ちの自分が映り込んでいる。
「え? そんな、初夜だなんて」
「初夜ですよ。游月との仲を認めてもらい、将来を誓った後の初めての夜ですからね。だから緊張して当たり前なのです」
游月はそっと手を伸ばして、透麻の胸に手のひらを当てた。
「透麻さん、どきどきしてる?」
「はい。身体が地に着いていない感じです。ふわふわして……このまま舞い上がってしまいそうだ」
游月は、浴衣の裾を乱して透麻に抱きついた。
「だぁめ、まだ行かないで。一緒に天に昇るんだから。……ね?」
「游月……あんまり煽らないでください。本当に昇天してしまいそうだ」
透麻は熱い息と共に呟くと、游月の浴衣をするすると脱がせた。
「ぁ、ぁっ………ん……透麻さ……もぅ、きて……」
大きく広げられた脚の間で屹立するものを執拗に吸われ、游月はたまらず催促した。次から次へと溢れる蜜をじゅるじゅると吸い上げ、飲み干す透麻はまるで飢えた蜜蜂のよう。
早く早くと蠢く蕾に指を埋めて掻き回してはいるけれど、貪欲な蕾がそれで満足するはずもなく、呑み込んだ指をきゅうきゅうに締めつけては熱い楔をねだった。
「まだ……駄目です。もっとほぐしてあげないと。久しぶりなんでしょう? 傷付けてしまっては大変だ」
透麻の思い遣りは嬉しかったけれど、久しぶりだからこそ早く欲しい、早くひとつになりたい。欲求に駆り立てられるように游月が艶めかしく腰を振ると、指を咥え込んだ秘孔がちゅぷちゅぷと音をたてて喘いだ。
「ああ……游月。少しは手加減してください。私だって久しぶりなのですよ」
弱々しく訴える透麻に、游月は小さく口を尖らせ、
「嘘ばっかり。撮影でいっぱいしてたくせに…………ひゃうっ」
突然の灼けるような快感に、游月は腰を跳ね上げて悶えた。透麻は指を激しく屈伸させて奥を抉りながら、
「そういう意地悪なことを言う悪い子は、少し懲らしめてあげましょう」
「あっ、あっ、ごめ……ごめんなさ…い……………はぅっ、ん、んっ!」
勃ち上がって紅く張り詰めた先端から、くぷくぷと蜜が溢れ出る。透麻はそれを舌で舐め取ってから、
「あの仕事は辞めました。だから本当に久しぶりなのです」
「えっ、ほん…と……? ほんとに?」
「はい」
游月はこくりと喉を鳴らし、問いを重ねた。
「じゃあ、透麻さんはもう僕だけのもの?」
「游月……」
透麻はゆっくり指を抜いて、游月の身体に覆いかぶさる。そして、なよやかに潤んだ瞳を上から覗き込みながら、感動に震える声で「あなただけのものです」と答えた。游月は顔をくしゃりと歪めて微笑み、
「うれしい……」
頭では分かっているけど心が付いていかない――そう言って泣いたのはいつのことだったろうか。仕事だから、プロだからと言い聞かせて平気なふりをしていたけれど、それはただの自己欺瞞だった。ずっと押し隠していた本心。それは。
「もう、他のひととしないでね」
「游月……」
「ずっと言いたかった。でも言っちゃいけないって自分を戒めてたんだ。だから……あ、んっ……」
上から唇を塞がれ、舌ごと言葉を吸い上げられた。まるで、続きは言わなくても分かってますよ、と言わんばかりに。続けてとろとろと注がれた唾液を、游月は「ふぅん」と綿毛のような吐息を漏らしつつ飲み込んだ。
「しませんよ。私が游ぐのは、あなたの中でだけ……」
唇を離した透麻は、口づけの甘さをそのまま引きずったような声で答えた。そしてすでにとろけかかっている游月の身体をそっと掻き抱き、首筋に、肩に、胸の紅い実に舌を這わせて丹念に味わう。それから脚を持ち上げて大きく広げ、綻び始めた蕾を激しく脈打つもので艶やかに咲かせた。
「ふぁっ、あっ、ああっ、あ………と…うまさ………なか、きもち…いい………」
根元まで埋め込んでから、小刻みに揺らして奥にじれったい刺激を与える。すると、敏感な最奥と透麻の先端がぬるりとこすれ合って、骨が溶けてしまいそうなほどの快感が湧き上がった。
しかし、行き過ぎた快楽に囚われたのは游月だけではなかった。透麻は流麗な眉を歪め、
「ああ、すごい……。游月、あなたの熟れた肉が……絡みついてっ……」
その悩ましげな表情と声は、游月の官能をさらに深くする媚薬の効果をもたらした。甘えた声で透麻の名を呼びながら、逞しい腰に脚をぎゅっと巻きつける。それは離れたくない、もっと深く交わりたいという無意識の意思表示。これが游月の“本物の”愛情表現だと、透麻はもう知っている。
「游月っ」
透麻は何かに取り憑かれたように、腰のピストンを速めた。速さだけではない。より深く、より情熱的に。
「あんっ、ああっ、ああっ、もっと、もっとして……」
突き上げられるたびに尻の奥にずん、ずん、と灯る熱い刺激。それを追って、游月は自ら腰を跳ね上げた。二人の律動がぴったり重なった時、天国が降りてきた。
「ああ、游月、可愛い游月、あなたももう、私だけのものだ……」
透麻は愛情と執着で重くたわんだ声で囁くと、角度をつけて奥を犯した。
「あっ、あ……ァ…ァ………!」
張り詰めていた快楽の弦がビンッと弾かれ、その反動で全身にさざ波のような引きつりを走らせながら、游月は目くるめく放埓を遂げた。蒼い闇に白い飛沫が飛ぶ。それが平らな胸に掛かって滴るさまをぼうっと眺めていると、繋がった腰の奥で熱を感じた。
「透麻さ…ん、いっぱい出して……」
放たれたものが中でとろりと動くのが分かり、游月は思わず頬を染めた。そしてふと視線を上げると――
「あ……月が……見てる………」
窓の向こうに、皓々たる満月がぽっかり浮かんで夜空を照らしている。
「まだ、恥ずかしいですか?」
透麻の問いに首を振り、
「もう、恥ずかしくない。見せつけてやるんだ、僕たちの幸せを」
游月は答えると、月華も色褪せるほどの輝く微笑みを浮かべた。
BACK TOP NEXT