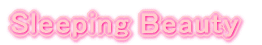
9.<最終話>
「やっぱり、来てねぇか……」
そりゃそうだよな、と自嘲するように呟いて、尭村は芝生の上に寝転がった。月曜の4限、純のクラスはフランス語だから、本当なら“課外授業”でここに来ているはずなのだ。
尭村は澄んだ空をぼーっと眺めながら、それとは対照的に罪悪感で曇りきった心を持て余していた。
純が帰った後、貴仁にぶっ飛ばされるに違いないと覚悟を決め、何発でも甘んじて受けようと思っていたのに、彼は何事もなかったかのように普段通り接してきた。
いや、普段より穏やかなほどだった。まるで、殴られた痛みによって罪悪感を軽減させようとした尭村の目論見を見透かしたかのように。
尭村はたまらず挑発した。「何だよ、あんだけブチ切れといて。やっぱりあいつのことなんてどうでもいいんだな」と言うと、貴仁は恐ろしく冷たい眼でこちらを一瞥し、
「自分なんかのことで喧嘩しないでと言われただけだ」
感情を抑えた声でそう答えると、アトリエにこもってしまった。
“自分なんかのこと”―――そう言った時の純の顔は、手に取るように分かる。怒り狂った貴仁を宥めるため、自分は平気、自分は傷ついていないという笑顔を必死にこしらえていたに違いない。幼い子が、痛みをこらえる時の顔だ。
尭村はがばっと起き上がると、校舎へ向かって走り出した。
昼休みの開始を告げるチャイムが鳴り、飢えた生徒が次々と廊下へ溢れてきたが、純が出てくる気配はない。尭村は柱の陰から顔を出して教室内の様子をうかがった。
すると、机に頬杖をついてぼーっとしている純の横顔が見えた。金色の陽光を浴びて暈然と輝く輪郭は、ぞっとするほど美しい。が、尭村は何故か不安に囚われた。このまま光に融けて、消えて、いなくなってしまうのではないか、と。
駄目だ、連れ戻さねば。意を決して一歩踏み出そうとしたその時、背後から声を掛けられた。
「うちのクラスに何か御用ですか?」
「あ、ああ沖秀か……いや……」
秀はにっこり笑って頭を下げた。
「あなたにはお礼を言わねばと思っていました。俺の頼みをちゃんと聞いて実行してくれたんですね。純のことをすっぱり切ってくれたようで。さすがです。ありがとうございました」
秀の口許は確かに笑っていた。が、尭村を見据える眼は微動だにせず、激しい怒りがもたらす熱でぎらぎらと険しく輝いていた。そして教室に入ると、尭村の目の前でぴしゃりと戸を閉めてしまった。
謝らなくちゃ、謝らなくちゃと、呪文のように胸の内で繰り返した。それでもなかなか実行に移せず、結局あれから一週間が経ってしまった。純は再び貴仁のアトリエにいる。
前回と違うのは、絵のモデルをしているということ。しかし貴仁が要求してきたのは、純が考えていた、というより一般的な“モデル”とはかけ離れたやり方だった。
貴仁は純に、好きなように寛いでいてくれと言った。お茶を飲んでも、本を読んでも構わない。寝てたっていい。純も最初は戸惑ったものの、次第にアトリエのゆったりとした空気に馴染んでいった。
貴仁がシャッシャッとパステルを滑らせる音は耳に心地よく、作品が創られる瞬間に立ち会っているんだという思いは、微かな興奮を呼び起こした。それでも、気持ちの大部分は尭村の方を向いていたのだが。
「失礼します。旦那様、名古屋の虹川様からお電話です。個展の最終打ち合わせがしたいと」
額賀が済まなそうに入ってきた。きっと、この後の貴仁の反応を知っているからだろう。
「くっそ、あのおっさん話長えんだよな。あーあ、ったく。悪りぃな、純。ちょっと待っててくれ。額賀、純に何か旨いもの持ってきてやってくれ」
「あっ、お構いなく。さっき美味しいスフレいただいたばかりですし。書棚の画集見てていいですか?」
「もちろん。ロクなもんねぇけどな」
貴仁はかったりぃ、などと言いながら出て行った。純は、後に続こうとした額賀を呼び止めて、
「あの、尭村さんは部屋にいますか?」
「はい。おられますよ」
先週の騒動について知っているはずなのに、額賀はそれ以上何も言わず、黙って頭を下げた。
扉の前で純は深呼吸をした。思わず掌に“人”という字を書こうとしたが、ピアノの発表会じゃないんだから、と呟いて止めた。
コン、コン、とノックすると、「茶も何も要らねぇよ」という不機嫌な声が聞こえた。額賀だと思ったのだろう。純はこくりと喉を鳴らして、「あの、純です」と告げた。
一瞬の沈黙の後、バタン、と勢いよく扉が開き、いかにも狼狽したという風に目を見開いた尭村が現れた。
「なっ、なんだよ」
彼らしくないあたふたとした対応に、純は悲しくなる。やっぱり来ちゃいけなかったのかな。でもちゃんと謝らなくては。
「ちょっといいですか? すぐに帰りますので」
思いのほかしっかりした声が出た。尭村も「ああ…」と答えて招き入れ、ソファに座れと勧める。すぐ帰るので結構ですと答えると、途端に険しい顔つきになって、「いいから座れ」と凄まれた。
いつもならここで恐くて震えてしまうのに、今日は平気だった。目の前で長い脚を優雅に組んで座る尭村は、何故か心細げに見えたのだ。
「尭村さん、先週は…いえ、今まで本当に済みませんでした。僕がロンドンにいた時の恋人、雅人、相楽雅人(さがら・まさと)っていうのですが、あなたによく似ていて、歳まで同じで、最初会った時は夢見てるんじゃないかと思った。でも、すぐに分かりました。あなたと雅人は違う、と――」
尭村はぐっと拳を固めた。ああそうかい、どうせ俺は………
「――違うって分かっていながら、あなたに惹かれるのを止めることができませんでした……」
―――えっ?
尭村は思わず純を見つめた。頬を赤く染めて、瞳を潤ませて、それでも泣くまいと必死にこらえている表情は、どうしようもなく扇情的だった。半開きの唇からこぼれるつたない言葉にすら、淡い色気が滲んでいる。
「……ごめんなさい。迷惑かけてごめんなさい、苛々させてごめんなさい、尭村さんの場所を汚してごめんなさい……でも、最後に………」
純は苦しげに呼吸を整えると、言葉を続けた。
「最後に、どうしても言いたかったんです。僕、あなたのことが―――」
尭村の視線を避けるように、純はいったん俯いた。そしておそるおそる上目使いで、再び視線を重ねようとする。その瞬間、尭村の中で抑え込んでいた感情が暴発した。
「っあ………」
純が声を上げた時には既にソファの上に押し倒されて、すごい力で手首を拘束されていた。乱れた前髪のせいで尭村の表情はよく見えない。しかし荒く熱い息遣いで、彼が今どんな状態にあるのかは分かった。
「あ、尭村さんっ、痛い…痛い……離してぇ………」
しかし哀しげな訴えも耳に届いていないのか、尭村は覆いかぶさって無理やり唇を奪おうとした。
「やっ、やめて……」
寸前で顔を背けて抵抗したが、そのせいで白くしなやかな首筋を晒すことになった。尭村は迷わずその首筋に吸い付いて、薄く滑らかな皮膚を味わった。そして片手を離し、すぐさまシャツの裾から差し入れて、ウエストのきゅっと締まった部分を指の腹で撫で始めた。
「いっ、いやぁ、やだぁ…尭村さん、やめてっっ!」
純は叫ぶと同時に、自由になった片手で尭村の胸を思い切り突いた。虚をつかれた尭村は後ろにのけぞり、呆然とした表情で純を、涙で濡れた頬を、首筋の痛々しい痕を一心に見つめる。自分が今何をやったのかを、自分に思い知らせるように。
「純……わ、悪かっ………」
「っぅ……う………」
純はいやいやをするように首を振って、部屋を飛び出した。
アトリエに戻った純は、必死で涙を拭った。涙だけでなく、泣いていた痕跡も消さなくてはならない。乱れた髪を直し、しわのできたシャツを伸ばして冷静を装った。そして飲みかけのお茶に手を伸ばしたが、指の震えがカップに伝わってカチャカチャ音をたてるので、諦めて戻した。
大丈夫、大丈夫と自分に言い聞かせて、貴仁が戻るのを待つ。やがて、
「純、悪りぃ。待たせたな。あのおっさん、1のこと話すのに10の手間をかけやがる。ったくこれだから………」
純はにっこり笑って貴仁を迎えた、つもりだった。が、
「純、どうした? お前様子が………っ、おい、これはなんだ! ああ!?」
貴仁は乱暴に純を抱き寄せると、シャツの襟を開いて首筋を露わにした。そこには、尭村に付けられたばかりの淫らな痕が。
「あっ、こ、これは……」
表情を繕うことばかりを考えて、これを隠すことをすっかり失念していた。虫に刺されて、などという間抜けな言い訳が一瞬浮かんだが、そんなもの貴仁に通じるはずがないとさすがに純も分かっていた。
「あんのクソガキィ………」
室内の空気を一気に凍結させる低音で呟くと、貴仁はゆっくりとアトリエを出て行った。
とうとうやった、やってしまった。いつかは暴走するだろうと恐れていたが、まさかこんな最悪のタイミングでやってしまうとは。
決意を固めて、自分の真摯な気持ちを伝えに来てくれた純。それに対する自分の答えが“アレ”とは、情けなくて泣けてくる。去り際の純は、裏切られたような哀しい眼をしていた。怒りとか非難を露わにしてくれたら、まだ救われたのに。
―――この期に及んでもまだ、自分が楽になることを考えているのか、俺は。本当に最悪だ
何を考えても落ち込んでしまう。いっそのこと土下座して謝ろうかと本気で腰を浮かせ立ち上がった時、部屋のドアが静かに開いた。
「親父っ」
ああ殴られるな、と思った瞬間には既に吹っ飛んでいた。尭村はすぐに身体を起こして口許を拭った。まさか一発じゃ終わらないだろうと思い、どこも庇おうとせず無防備なまま立ち上がった。
貴仁はゆっくり近づいて無言のまま胸倉を掴み上げる。その時、
「せんせいっ、やめてくださいっ」
純が飛び込んできて、貴仁の背中にしがみついた。しかし、
「離れてろ、純。こいつはお前を汚したんだ。許すわけにはいかねえ」
「ちっ、ちがいます! 僕が……僕が誘ったんです! だから尭村さんは悪くないっ」
貴仁は尭村から視線を外し、純をじっと見つめた。
「ほ、ほんとです……せんせい。それに、汚しただなんて、僕はそんな風に言ってもらえるような人間じゃありません。僕はそんな…きれいな人間じゃ―――」
言い終わらぬうちに貴仁は純を抱きしめ、
「分かった、分かったから、純……」
そのまま肩を抱いて、寄り添うように二人は出て行った。
額賀はいつになく浮かれていた。これまで真剣に誰かのことを想い、愛することのなかった尭村成仁が、変わろうとしているのだ。初めてのことだから、うまくいかずに苦しんだり戸惑ったりすることはあるだろう。しかしひとつずつ克服していけるに違いない。
相手が同性だとか、そんなのは全く気にならなかった。あんなに綺麗で可憐で優しい人には、それなりに人生経験豊富な額賀も出逢ったことがない。ともすれば弾みがちになる声を抑えて、額賀は尭村の部屋の扉を叩いた。そして、
「成仁様。秋原様が一人でお帰りになりましたが、よろしいのですか?」
案の定、すごい形相の尭村が部屋から飛び出してきた。
「なっ、なんで一人で帰すんだよ。もう暗くなってるじゃねえか。くそっ、親父は何考えてんだっ」
純の家までは徒歩だと20分はかかる。ずっと閑静な住宅街が続き、車も人も余り通らない。しかもいわゆる豪邸、大邸宅が多いから、道で何かあって叫んでも、家人には気付かれないだろう。
尭村は慌てて上着を引っ掛けて飛び出した。
一人で帰れます、と言い張った時の貴仁の心配そうな表情を思い出すと、胸がちくりと痛む。しかし純は一人になりたかった。一人で、尭村のあの行為の意味を考えたかった。
その時背後から突然声を掛けられて、純は「ひゃっ」と情けない悲鳴をあげた。
「あ、尭村さん……どうして?」
「どうして、じゃねぇ。危ないだろが。送ってく」
純が「ありがとうございます」と囁くようにお礼を言うと、それきり二人は黙りこくって歩き続けた。そして家が近くなったのを見計らって、純は「この辺で大丈夫です」と言った。すると、
「ちょっとあの公園に付き合え。お前に言いたいことがある」
そこは、背の低い金網で仕切られた狭くて暗い公園。人の気配すらない。植え込みの陰に純を連れてくると、尭村は頭を下げた。
「さっきは悪かった。何も弁解できないしするつもりもねえ。ただ、もう二度とあんなことはしない。くだらないプライドや嫉妬も捨てる。だから……」
尭村はそっと純を抱きしめた。そして、これまで聞いたことのない神妙かつ誠実な声で続ける。
「傍にいてくれ。昔の男の代わりで構わない。お前が好きだ」
純は黙って腕を尭村の腰に回した。そして顔を胸に押し付け、小さく頷く。懐かしい匂いに再び包まれ、嬉しくて眩暈がしそうだった。
尭村は、抱きしめる腕に力を込めた。純から言葉はなかったが、その気持ちはちゃんと伝わっていたのだろう。耳許で「キスしていいか?」と囁くと、純の頭が再び縦に揺れた。
「ん……」
始めは触れ合わせるだけ。それでもしっとりとした感触は心地いい。潤んだ瞳で見上げると、尭村は吸い込まれるように口づけを深くした。
「ぅん……ふっ………」
歯列を割ってねじ込まれた舌が、ねっとりと口腔をまさぐる。そして純の柔らかい舌を強引に絡め取ると、純はぴくんと腰を揺らして甘い息を漏らした。尭村は細い腰を引き寄せて、首筋に顔を埋める。
「あぁ……ん、あきむらさん、だめ……」
「分かってる……」
尭村は名残惜しそうに顔を上げると、唾液で濡れた唇を軽く吸って身体を離した。
「純、また明日。学校でな」
「いつもの場所で?」
「ああ。いつもの場所で」
純は笑って、大きく頷いた。尭村は目を細め、その笑顔を見つめる。この純の笑顔を、尭村は一生忘れないだろう。固かったつぼみが一気に綻んで、甘い芳香が溢れたような。
純が帰ってしまっても、その芳香に絡め取られた尭村は、暫しその場から動けずにいた。 (Fin)
BACK TOP INDEX