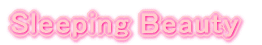
8.
帰宅した尭村が自室へ戻り、かばんを投げ出すのとほぼ同時にもの凄い勢いでドアが開けられた。そこには、眉間に禍々しい皺を刻んだ貴仁が仁王立ちしていた。
「成仁……」
「な、なんだよ、親父。勝手に開けんじゃねーよ」
「お前、純に何を言った? 留守電に、消え入りそうな声でメッセージが入ってたんだよ。個展前に何度もお邪魔してすみませんでした、ってな。俺はそんなこと言った覚えはねえ」
尭村は、後悔を覚られないように殊更冷たい表情で言った。
「なんだそのことかよ。個展を控えてんのは事実だろ。個展前はすげえ忙しくなるって言っただけだ」
「…ちっ、余計なこと言いやがって。個展なんて、現地のコーディネーターに丸投げしてあんだから、俺はオープニングパーティーでシャンパン片手に適当な芸術論と猥談かますだけでいいんだよ。どこが忙しいんだ」
「おまえなあ…。少しはこだわり持てよ。自分の作品への愛着とかねえわけ?」
「阿呆か。こだわりとか愛着なんてあったら、そもそも個展なんて開かねえよ。無人島に家建てて、壁じゅうに絵描きまくって、最後に火ぃつけて燃やしてやる」
尭村は話にならないという風に首を振って、
「もういいだろ、疲れてんだよ」と珍しく弱々しい声で言った。実際、彼は疲れていたのだ。
「はッ、なんでそんなにくたびれてんだか。ま、純のことは許してやるよ。さっき電話してちゃんと“誤解”も解けたしな。今日の埋め合わせでさっそく明日誘ったら、嬉しそうに“いいんですか”だってよ。可愛いったらないぜ、ありゃ」
だんだん目が釣り上がってゆく息子の顔をどこか愉快そうに眺めながら、貴仁はさらに畳みかける。
「明日は休みだからな。時間もあるしゆっくりできる。っつうことはそれだけチャンスも広がるってことだ」
「なんのチャンスだよ」
無視しようと決めていたのに、つい反応してしまう。
「エロいこと考えてんじゃねえよ。大人はちゃんと順序ってのを踏まえるものなんだ。誰かと違ってな。純に“好きだ”って告るんだよ」
「なっ…息子の後輩に告るだとぉ? ふざけんじゃねえ!」
「息子の後輩だろうが孫の後輩だろうが関係ねえだろ。まあすぐうまくいくとは思ってねーけど、うじうじ考えてるよりずーっとマシだからな」
冷静に、冷静に、こいつは俺を煽って、からかっているだけなんだから。そう自分に言い聞かせつつも尭村はブチ切れた。
「勝手にしろ! 俺には関係ねえ!」
咆えながらも、本当に関係なかったらどんなに楽だろうかと思わずにはいられなかった。
―――翌日
「あら? 純どこ行くの?」
「尭村さんのうちー」
幸せそうに微笑う純を見て、環(たまき)は言いようのない不安を感じた。当然といえば当然。環は一学年上とはいえ、中等部からずっと、尭村が犯した悪行の数々を目にしてきたのだ。
男に手を出して泣かせたことはなかったはずだが、相手が純なら分からない。大体、異性だ同性だと細かいことにこだわる男ではないのだ。これまで、自分の欲望を刺激するような男のコが現れなかっただけで。
それでも、嬉しそうに仕度している純に対して頭ごなしに行くなとは言えなかった。ただ、「尭村にヘンなことされたらすぐ私に言うのよ」としか。
「純ー、お迎えの方がいらしたわよー」
環の母で、純も母のように慕っている早紀(さき)が、のんびりした声で呼んだ。純が慌てて下りていくと、玄関ホールに額賀が立っていた。休日というのに一部の隙もないスーツ姿で。
「こんにちは秋原さま。お迎えにあがりました。昨日はお気を遣わせてしまい、まことに申し訳ありませんでした。さあ、旦那様がお待ちです。どうぞ」
「旦那様って、もしかして尭村の……」
環がおそるおそる尋ねた。
「うん。尭村さんのお父さんだよ」
「ゲッ、あのクレイジーなおやじ?」
「まあ、環。何てこと言うの」
早紀は叱っているつもりだろうが、子守唄でも歌っているようにしか聞こえない。
「だってあの親父、中学の進路面談の時、ごっつい鋲打ちしてある革の上下で来たのよ」
「申し訳ありません。おそらく正装のつもりだったのでしょう」
だとしたら余計にクレイジーなのだが、ともかく額賀は話を引き取って純を車へ促した。純は、今度その鋲打ち革スーツを見せてもらおう、とひそかに思った。
「じゅんー、会いたかったぜー」
着いた途端、抱擁とキスの嵐。純はくすぐったそうに身をよじりながらも、素直に受け入れた。
「あの、尭村さんは?」
「部屋でフテ寝。呼んでくるか?」
「いえ、いいんです。……あのぅ、尭村さんはもしかして、僕がここに来るのを余り良く思ってないんじゃないでしょうか」
「ああ、確かにそうかもな。…で、理由は何だと思う?」
肯定されて、やっぱりそうかと納得したのが半分、ショックを受けたのが半分。
「それは……先生のお仕事に差し障りがあると感じているからではないでしょうか」
「違うな。俺はそんなことひとっことも言ってねぇし、思ってもいない」
「じゃあ、自分の場所を他人に荒らされるのが嫌なんでしょう。僕にもそういう気持ち少し分かります」
俯いた純の頭を優しく撫でて、貴仁はアトリエへ誘った。
さすがに一日中ベッドの上でごろごろしているわけにはいかないと思い、尭村はのっそり起き出して、ぬるめのシャワーを浴びた。
よくよく頭を冷やして考えてみれば、あの親父が真剣に愛の告白などするはずがないのだ。しかも年下の、男相手に。いつだっていい加減で、来る者拒まずで、重たい付き合いが嫌いな天性の遊び人。
尭村はこれまで何人の女性から、「私があなたの新しいお母さんよ」と言われただろうか。平均一カ月の“新しい母親”。
そのうち息子の方に興味を示す女も出てきて、その中の一人と早々に童貞を捨てることになったのだが、今では顔も名前も覚えていない。
少し気分がさっぱりしたところで、離れの自室を出て本宅の方へ向かった。
「ようやくお目覚めですか、成仁様。何か召し上がりますか?」
「ん、いや、まだいい。それより親父は?」
「お二人ともアトリエでございます。ずっとこもりっきりなんですよ」
額賀は何か言い足そうとしたが、口を噤んでそっと頭を下げ、尭村の傍を離れた。
「……仕方ねえ、ちょっと顔出すか」
自分が出てこないのを純は気にしているだろうと思い、尭村はアトリエに向かった。
「…なあ、純。お前に頼みがあるんだ。絵のモデルをやってくれねえかな」
アトリエでお茶を飲んだり、新作を見せてもらったり、有名画家の画集を茶化しながら貴仁の毒舌に大笑いしたりと楽しい時間を過ごした後、急に真面目な口調になって貴仁は切り出した。
「えっ? 先生もモデルを使うのですか?」
「いや、学生ん時を除いて、これまでモデルを立てて描いたことは一度しかない」
純はすぐに分かった。尭村の部屋にあった母親の肖像画だ。
「でもお前を見てたら描きたくなったんだ。その美貌が云々というよりも、お前が抱えている不安や孤独や淋しさを引きずり出してみたい」
「せんせい……」
驚いたように見つめる純に、貴仁はにやりと笑って、
「俺の眼識をなめんなよ。お前は自分が綺麗だなんてこれっぽっちも思っちゃいない。……純、お前これまでどんな目に遭ってきた? 誰に捨てられた?」
純は全てをぶちまけたい誘惑に駆られた。しかし唇を噛み締めて、貴仁を見上げるに留まった。貴仁は、両手で純の顔を包み込むと、
「いや、いいんだ。無理して言うことはない。ただ、お前がどんな過去を背負ってたって、俺の気持ちは変わらない……純、愛してるよ」
「せっ、せんせい」
親指でそっと純の唇をなぞり、そのまま顔を近づけて唇を重ねようとした。が、寸前で止めて、
「ちょっと待ってな。扉んとこで立ち聞きしてる奴がいる。成仁!」
貴仁が叫ぶとほぼ同時に、扉がすごい勢いで開いた。そこには、物騒なオーラを発した尭村の姿が。
「面白れぇ真似すんな、お前は。親の濡れ場がそんなに見たいか?」
しかし尭村は無視して、純を睨みつける。
「…大したモンだよ、お前は。親父まで手玉にとって。昔の男に似てりゃ誰でもいいんだな」
「ちっ、ちがいます! 僕は……」
「うるせえっ! 親父も気をつけた方がいいぜ。俺はこいつがロンドンにいた時の恋人に似てるんだとよ。つうことは親父もそいつに似てるってことだ。ったく冗談じゃねえ。うぜえんだよ! 二度と顔見せんな!」
「ご……めんなさい………」
瞬きを忘れたように硬直した瞳から大粒の涙が溢れ、そのままぽたぽたとこぼれた。声をあげることも涙を拭うこともせず、ただじっと涙が流れるに任せるその姿は余りに無防備で、見る者の胸をしめつける。
もっと自分の悲しみとか苦しみを派手に見せつければ楽になるだろうに、こんな泣き方ではますます辛くなるだけ。しかし純はこういう泣き方しかできないのだ。
尭村もまた、初めて見た純の涙に心打たれて、その場に固まった。しかし、
「なるひと…てめえ、許さねぇぞ………」
父親のこんな声を聞いたのは久しぶりだった。こいつ、やっぱカタギじゃねえな、などと些か場違いな考えが浮かんだのは、動揺している証拠だろう。
しかし尭村をその場から逃げ出させたのは父親の憤怒の形相ではなく、苦しそうに嗚咽を呑み込んではすがるように自分を見つめる、純の紫色の瞳だった。
尭村が出て行ってから、どのくらい経っただろうか。その間貴仁はずっと、純の髪や背中を撫でてくれた。
「せんせい…もう大丈夫です。ありがとうございました」
「そうか。ったくあのバカ息子。どうやってぶちのめして欲しい?」
純は貴仁のシャツにすがり付いて、ふるふると頭を振り、
「だっ、だめです、先生。悪いのは僕なんですから。それに、僕なんかのことで喧嘩しないで下さい」
「お前のことだからこそ、許せねぇんだけどな。まあいい。約束する。その代わり、またここへ来てくれるよな?」
「で、でも、二度と顔見せるな、って………」
心の奥の、敏感で柔らかい部分に刻み込まれた痛烈な台詞。それがずくずくと、熱をもって疼き始めた。
「ここは俺の家、でもってお前は俺の大事な客。気にすんな。ついでに言っとくが、昔の恋人に似てるならそれで構わない。寧ろラッキーだな。ま、俺の方がずっといい男だっていずれ分からせてやるよ。さて」
貴仁は純の顎に手を添えて、上を向かせた。
「…まだ目が赤いな。ちゃんと送ってってやるから、もう少しここにいろ。
お前の姉ちゃん、お前を送り出す時すごく心配そうな顔してたって、額賀が言ってたからな。泣き顔で帰したら申し訳がたたない」
「せんせい……」
「純、愛されてるんだよ、お前は。だからもっと自分に自信を持てよ」
純は笑顔を返したつもりだった。しかし口許が引きつってしまい、涙をこらえるような表情にしかならなかった。
BACK TOP NEXT