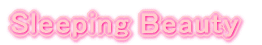
7.
「なあなあ森下ぁ、ちょっといい?」
「おお。いいけど藤崎、あんまり顔近づけんなよ。お前の旦那がこっち睨んでるんだって。こえー」
「ばぁっ、か。圭祐なんて放っときゃいいんだよっ。それよりさあ、尭村どうしたの? 最近ずっとご機嫌うるわしゅう、だったのに、またブリザードじゃん」
森下は頷くと、辺りをきょろきょろ見回して尭村が教室にいないことを確認した。そして、
「誰にも言うなよ。あいつ秋原を家に呼んだらしいんだ。そしたら運悪く親父さんがいてさ、秋原をすっげえ気に入って構いまくってるらしいんだ。勝手に家呼んだりしてさ。それでもう、不機嫌マックスよ」
「ほえー、家に呼んだってのもオドロキだけど、親父さんまでねえ。尭村の親父って、どんな人なの?」
「我がままで傲慢で自信家で女によくもてて……」
「あっ、俺そういう男一人知ってる。うちのクラスにいなかったけぇ?」
「偶然だな、俺も一人知ってるよ。っつーか、あの親子うんざりするほどそっくりなんだわ。恐るべし、尭村家の遺伝子」
二人は同時に、はーっと溜め息をついた。
旧図書館裏、いつもの場所。空は晴れ渡り晩春の日差しは暖かく、そよ風は心地よいのに、尭村はしぶーい顔で本を読んでいた。隣に座っている純が自分に話しかけたがっているのに気付いていたが、頑なに無視しつつ。
このままでは昼休みが終わってしまうと焦った純はそうっと、読書の邪魔にならないよう小声で、
「……あの、尭村さんは今日真っ直ぐ家に帰りますか?」
「知るか。…って、なんでだよ?」
「今日、先生から家に寄るよう誘われたんです。この前遊びに行った時には尭村さんいなくて淋しかったから……」
その日は別に用事があったわけではなかった。ただ純が来ると聞いて、また親密に語り合う二人を見るのは耐えられなかったから家を出ただけだ。
適当に外をぶらついて、その間3人に逆ナンパされて、そのうち1人とホテルで“休憩”して帰ってきた。ホテルを出る時女は泣いてたから、相当ひどいことをしたのだろう。よく覚えてないが。
「俺がいないと淋しい? はッ、なるほど、昔の男に似てる俺に傍にいて欲しいっていうわけか。いいぜ、優しく名前でも呼んでやるよ」
「違います! 僕はそんなことを言いたいんじゃなくて……」
「じゃあなんだよ。それになあ、親父は名古屋での個展を控えてて忙しいんだよ。そんなしょっちゅう来られたらこっちだって……」
「あ……」
純は驚いたように口を開けて固まってしまった。尭村は“しまった”と舌打ちしたがもう遅い。
「めいわく、だったんですね。僕、そういうのに気付けなくて…。どうしよう、先生に謝らなくちゃ。尭村さんにも。ごめんなさい。あと、言いにくいことをちゃんと教えてくれてありがとうございます。このままずるずると甘えてしまうところでした。僕……もう行きますね」
純は尭村を気遣うように微笑むと、一度も振り返ることなく去っていった。
尭村は今度は追おうともしなかった。追う気力さえなかった。また同じ失敗を繰り返してしまったと、己の学習能力の低さを呪うしかできなかった。
直は、一人で教室を出ようとする純を掴まえて声を掛けた。
「まだ帰んないの? また尭村さんのとこ?」
「ううん、違うよ。生徒会室。日向会長にお茶誘われたんだ」
貴仁には、留守電にメッセージを入れておいた。個展前のお忙しい時に何度もお邪魔してすみませんでした。今日は遠慮させていただきます。個展の成功をお祈り申し上げます――
そして、尭村から痛い事実を告げられて落ち込んでいるところに、日向からの伝言が届いたのだ。それを伝えに来た男は、にこにこ笑いながら「日向会長楽しみにしてるから行ってやってよ」と手を合わせた。
純は、真っ直ぐ家に帰っても余計落ち込みそうなので、喜んで誘いを受けることにしたのだ。
「そっかあ、あんまし遅くなるなよ。夜道の一人歩きはキケンです」
「はあーい」
純は直に手を振って、生徒会室へ向かった。
「あの…日向会長は?」
生徒会室は、この前来た時とかなり雰囲気が違っていた。見知った顔も一人もいなかったし、真ん中にあった大きなテーブルが片付けられていて、その代わりにベッドにもなりそうな大きなソファが置かれていた。
「顧問との打ち合わせが急に入ったらしくてさ。すぐに終わらせて来るから、これでも飲んでちょっと待っててくれって」
男が差し出したカップからは、香ばしいメープルシロップの馥りが。この前おいしいと言った銘柄を、勇人さんはちゃんと覚えててくれたんだ、と純は嬉しくなり、緊張を解いてお茶をこくりと飲んだ。
「おい、沖。純はもう帰ったのか?」
尭村は校門に続く並木道で直と秀を掴まえて、問い質した。
「あや、尭村さん。純は生徒会室ですよ。日向会長にお茶のお誘いを受けたって言ってました」
「ちっ、日向か……」
「はい。ねえ尭村さん、純と何かありました? あいつなんか元気ないみたいで……って、あっ、あれ?」
直が突然、脇道へ向かって走り出した。何がどうしたのか分からぬまま、尭村と秀もその後を追う。
「日向さん! 日向会長!」
「あっ、ああ沖くん。どうしたのですか? そんなに慌てて」
「純は? 純と一緒じゃないんですか? あいつあなたにお茶誘われたからって今生徒会室へ……」
日向は僅かに眉をたわめて、
「いえ。私はそんな約束は……」
「急げっ、生徒会室だ!」
叫んだのは秀だったが、尭村はそれより早く走り出していた。もちろん直もそれに従う。一人残された日向は、血管が浮き出るほど強く握り締めた拳をじっと見つめていた。
「か、鍵を何に使うんだ、尭村」
「つべこべ言わずさっさと貸せ」
背骨をざわざわと這い上がるような低音に怖気づいた教師は、慌てて鍵を手渡した。尭村はそれをひったくると、生徒会室へ向かった。扉の前には直と秀が厳しい顔つきで立っていた。
「やっぱり鍵がかかってます」
尭村は無言で鍵を開け、扉を脚で蹴り開けた。
「てめえら……」
半ば予想していた光景だった。いや、予想より被害は小さかったと言える。素早い行動が功を奏したのだろう。
とはいえ、ほとんど意識のない純のシャツははだけられ、目に痛いほど白い肌は複数のカメラレンズに晒されていた。微かに開いた唇からは、溜め息とも喘ぎともとれる熱い息がこぼれている。
直は、幼馴染の、これまで見たこともない官能的な姿態を目の当たりにして頬を赤らめた。
カメラを抱えた男は4人。何もせず、高みの見物とばかりに眺めている男は2人。計6人。全員新聞部の部員だった。
「あ、あああああきむら………」
6人が6人とも、同じ言葉を発してあとずさった。直と秀は、ここは尭村に任せた方がよいと判断し、黙って成り行きを見守った。
尭村は上着を脱いで純の上に掛けた。そしてひと言、
「出せ」
「はっ? あ、あの何を、でしょうか……」
「フィルムに決まってんだろ。そっちの2台はデジカメだな。データを全て消去しろ。今すぐだ」
「いえ、それはその……」
「なんだ? 二度とカメラ持てねえようにしてやろうか?」
この男の語彙に“はったり”という言葉はない。「肋骨折るぞ」と言えば本当に折るし、「鼓膜破るぞ」と言えば本当に破る。
「わわわわわかりましたっっ」
震える手を必死に動かしてフィルムを取り出すと、うやうやしく尭村に差し出した。受け取った尭村はバキバキと物騒な音をたててそれを握り潰すと、「人間の骨も折るとこういう音たてるんだぜ」と言って嗤った。
「申し訳ありません。うちの部員がとんでもないことを」
保健室のベッドで目を覚ました純が真っ先に見たのは、深くうな垂れた日向の姿だった。そのまま視線を巡らせて尭村の姿を探す。しかしどこにもいない。傍にいると錯覚したのは、羽織っている上着から仄かに香る、尭村の匂いのせいだった。
「いえ…勇人さんの……せいでは……」
喉がからからで上手く喋れない。日向は辛そうに微笑むと、
「よかった…まだ“勇人さん”と呼んでくれるのですね」
純は何と答えたらよいか分からず、上着をぎゅっと掴んで襟に顔をうずめた。その時、直が保健室に入ってきた。
「あっ、純。目が覚めたんだねー。良かったあ」
直はベッドの上にぽん、と乗って、布団の上から純をぎゅーっと抱きしめた。
「あ、直……えと、し、秀は?」
「ああ、秀のやつどっか行っちゃったんだよなあ。いいよ、我聞(がもん)に迎えに来てもらったからさ。一緒に帰ろ。じゃあ日向会長、俺たちはこれで」
「はい。お気をつけて。あと、あの部員たちは後日正式に処罰いたします。二度とこのような過ちは許さないと約束しますので」
純は曖昧に頷いた。頭の中には尭村のことしかなかった。
「よお、生徒会長。遅くまで熱心なことだな」
「…尭村。どうしたのですか、こんなところに」
人気のない会長室で二人は対峙した。尭村は腕を組んで壁に寄りかかり、日向は顔を上げただけで立ち上がろうともしない。
「日向、これ以上ふざけた真似すんじゃねえぞ。あれが部員の勝手な暴走だって? 笑わせんな」
「では、私が仕組んだとでも?」
「当たり前だ。お前の許可なしに、ヒラの部員があんなことするものか。日向、そんなにあいつの裸を売りたいのか? 新聞部はそんなに金が欲しいのか? なら俺に言え。4、500万なら融通してやる」
日向は陰気な笑いを漏らして、
「その程度の金、あなたに頼むまでもないですね」
尭村の表情はより険しさを増した。
「金じゃない……そうか、お前、あいつに惚れたな? だから、自分に頼らざるを得ないような状況を作ろうとしてる。日向さん助けてと、泣きついてくるのを待ってるんだ」
日向は何も答えない。
「…まあいい。どうせお前は、誰かと愛し合うことはできねえんだからな。せいぜい小細工してろよ」
日向は思わず尭村を睨み、口を開こうとした。が、その時音もなく扉が開いて―――
「沖秀じゃねえか。はん…お前も日向に文句言いに来たんだな」
「そうです」
「ほらな、分かる奴には分かるんだよ。まあ純は素直な奴だから気付いてねえけど。沖秀、帰るぞ。言うべきことは俺が言った」
音もなく出て行った二人を無言で見送ると、日向はキャビネットの鍵を開けて中から写真を取り出した。どれも純を映したものだ。そのうち、更衣室でシャツを脱いだ瞬間を捉えた1枚を摘み上げ、艶やかな肌の温もりを味わうかのようにそっと指先を這わせた。
「俺は、あなたにも文句を言いたいです」
「何をだ?」
尭村は秀を睨みつけて、不愉快そうに舌を鳴らした。
「いい加減はっきりさせて下さい。あいつのことをどう思っているのか。純はあなたのせいで、一部の女子生徒から恨みを買い始めています。この前も、靴箱にひどい中傷の手紙が入ってました。俺が先に見つけて破り捨てたから良かったものの、あいつがもし読んでいたら……」
「……俺にどうしろって言うんだ」
「純のことを愛しているなら、はっきりそう伝えて掴まえといて下さい。もし、ちょっと可愛い後輩、可愛いペットぐらいに考えているのなら、きっぱり関係を断って二度と近づかないで下さい」
「お前に指図される筋合いは―――」
「あります。俺と直にはその権利がある。だから言ってるんだ。俺はあなたのことが嫌いじゃない。日向会長なんかよりずっとマシだし、信頼できると思っている。でも純のことを他の女と同じように面白半分で傷つけたりしたら、俺はあなたを許さない」
激情に流されず、寧ろ淡々とした口調だったが、それが余計に凄みを感じさせた。尭村は足を止めて秀を見据え、
「お前、ずいぶん変わったな」
「いえ、俺はもともとこういう人間です。あなたの前で猫かぶる必要もないでしょう」
秀はにやりと笑うと、俺はこっちなんでと呟いて、さっさと行ってしまった。
―――日向よりマシか、言ってくれるじゃねえか
尭村はくぐもった笑いをこぼした。中等部の時は何考えてるか分からなかった秀が、急に身近に感じられた。
BACK TOP NEXT