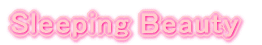
6.
「あ、秋原、君が尭村のオンナだって本当なのか?」
「え、えっ?」
「悪いことは言わない。あの男はやめた方がいい。っていうかあの男だけは駄目だっ。女癖は最悪だし野蛮だし自己中だし。君があいつに泣かされると思うと…」
「ちっ、違います! 変な思い込みやめてくださいっ」
「はーっ」
純は机の上にぺたん、と突っ伏して長い溜め息をついた。それを目ざとく見つけた直が駆け寄って、
「どしたどした、純? おにーさんに話してごらん」
「さっきの人でちょうど10人目だよぅ。尭村先輩と付き合うのやめろ、って。そんなんじゃないのに〜」
「ううむ。あのさあ、純。いっそのこと付き合ってることにしちゃえば? そしたらさ、変なの寄り付かなくなると思うよ。尭村先輩こえーし。なあ、秀?」
いつの間にか傍に来ていた秀に同意を求めたが、秀は首を振って、
「いや、もちろん諦める奴もいるだろうが、逆に執着心とか闘争心が煽られる奴も出るだろう。そういう連中の方が危険なんだ」
直はそっかなー、と首を傾げている。純は慌てて、
「どっちにしたって、これ以上尭村さんに迷惑かけらんないよ。大丈夫。えと、僕のことをそういう対象として見る人がこの学校にもいるんだってこと分かってきたし。ちゃんと気をつけるから」
純の決意に水を差すようなことはしたくなかったので、二人は素直に頷いた。その時、教室内にカン高いざわめきが起こった。その原因は一目瞭然。尭村が戸口に立っていた。
「純、まだか」
「あっ、はい。今行きます」
純はわたわたと焦ってノートをかばんに詰めた。直がつんつんと肩をつついて、「どこ行くの?」と訊いてきた。
「尭村さんちだよ。お父さんの絵を見せてくれるって。じゃあね、またあしたー」
遠ざかる二人の背中を見送りながら、直は「尭村さん、もしかしてマジ?」と呟いた。
「約束したのに、なかなか招べなくて悪かったな」
「いえ、そんな」
「親父の奴、ずっと家にいやがるから……」
え? と訊き返す純になんでもねえよと答えて、尭村は肩をそっと抱いた。
「あれが迎えの車だ。帰りもちゃんと送るから心配すんな」
尭村の視線の先には、黒塗りのリムジンが留まっている。純は車種やブランドについては疎かったが、とっても高級で、カタギの車ではないことは何となく分かる。
「尭村さん…これって防弾ガラス?」
「おう、よく分かったな。まあ狙われることはねえけど一応、な。あと、これはうちの運転手兼執事」
尭村は、車の傍らに直立していた男性を紹介した。歳はおそらく50代後半、美しい銀髪をうねらせた上品な紳士が、穏やかな笑みを浮かべている。
「あ、秋原と申します。尭村先輩には大変お世話になっております」
「額賀(ぬかが)と申します。成仁様から少しは伺っておりましたが、まさかこれほどお美しい方とは…」
「おら、純、早く乗れ」
強引に腕を掴んで車に押し込めた尭村を、額賀は目を細めて見つめた。
尭村の家はある意味予想通りだった。広大な敷地、聞けば千二百坪あるらしい。と言われても純にはそれがどのくらい広いのか分からないのだが。東京ドーム何個分(そこまで広くはない)の方がピンとくる現代っ子だ。
広い玄関ホールに通されて家の中に上がると、この屋敷は現代には珍しい平屋建てだということが分かった。天井が高いため、外から見ると二階建てに見えるのだ。
純のイギリスの実家も、それこそお城と呼べそうなほど無駄に広くて無駄に豪華だったから、尭村家の広さや立派さに驚きはしなかった。
しかしごてごてと飾り立てた実家に比べると、ここはとても禁欲的で無駄がない。かといって殺風景というわけではなく、さりげなく置かれた花瓶やランプは現代彫刻のように洗練された機能美を持っていて、優美且つ芸術的な空間を演出していた。
「素敵なおうちですね。とても落ち着くし、清潔だし。何ていうか、人が何かをじっと考えたり創ったりするのに最適な場所ですね」
「…ありがとう」
尭村は少し照れ臭そうにお礼を言った。純が素直な感想を言ってくれたので、自分も素直に応えるべきだと思ったのだろう。
「どうする? 先に俺の部屋に行くか? それとも――」
「成仁、帰ったのか?」
奥の部屋から声がした。そこから出てきたのは……
「おっ、親父! なんでいるんだよっ。今日は夜まで……」
「んあ? ああ、あれは行くのやめた。めんどくせえ」
「あんだとぉ? てめえ、額賀っ、なんで教えなかったんだっ」
「申し訳ありません。忘れておりました」
「忘れてた、だとぉ〜(怒)」
こめかみに青筋たてて額賀を睨みつける尭村の脇をすり抜けて、父親で画家の尭村貴仁(たかひと)は純の正面に立った。
「あ、はじめまして。後輩の秋原です。えっと…」
思わず見入ってしまったせいで、後が続かない。目の前の男性は尭村によく似た物騒な美貌を持っているが、余りにも若い。父親と言って信じる人がどれくらいいるだろうか。せいぜい兄弟ではないだろうか。
しかしぼおっと見入ってしまったのは寧ろ貴仁の方だった。何の挨拶もせずにいきなり純の腕を掴んで引き寄せ、
「おい、成仁なんかやめて、俺のものになれよ。こいつはタチ悪いぜ〜。見かけほど大人じゃねえし。ただの我がままなガキだ。お前苦労するぜ」
「てめえっ、何フザケたこと言ってやがんだっ」
「俺は真剣だ。お前が後輩を家に連れてくるっつうからわざわざ出てきたんじゃねえか。そしたらこんな綺麗で素直なコが。お前にはもったいねえな。俺がもらう」
言いながら貴仁は片手で純の腰を優しく抱き、空いた手を顎に添えてそっと上を向かせた。
「名前は?」
「…純、です。尭村せんせい……」
「先生なんて柄じゃねえよ。お前、綺麗なだけじゃねえ、妙な色気があるな。保護欲と嗜虐心の両方を煽る。男と相当寝てるだろ。でも俺は気にしないぜ。処女だなんだと下らねえことわめくのは、こいつみたいなガキだけだ」
「いいかげんにしろっ、このクソエロ親父! 純、行くぞっ」
貴仁の腕が絡められた腰を強引に奪い取って、尭村は引き摺るように純を連れて行った。「額賀っ、後で茶ぁ持って来いっ!」と叫ぶ尭村はいつもより少し子供っぽくて、純は思わず「可愛い…」などと呟いてしまった。
陽光に燦々と照らされたテラスのような渡り廊下を、二人は並んで歩いていた。尭村の部屋はこの廊下の先、離れにあるらしい。
「びっくりしたあ。尭村先生、すっごく若いんだもん。兄弟にしか見えないですよ」
「俺はあいつが18ん時の子供なんだよ。しかも絵描きなんかやってるせいで、社会人としての常識とか自覚が皆無なんだ。だから年相応の落ち着きっつうものがねえ」
お前がそれを言うか、尭村よ。純も一瞬、何か突っ込みを入れたい衝動に駆られたが、敢えて黙っていた。
ちなみに尭村には腹違いの兄(!)がいる。彼が登場するのはまだ先のことになるが……。
「ここが俺の部屋だ。まあ上がれよ」
「うわぁ」
黒い絨毯にベージュの皮張りのソファ。曲線が美しいメタリック製のフロアランプ。木目が重厚なスピーカー。目につくインテリアはどれもセンスがいい。テレビがないのが彼らしいな、と純は思った。
「何だか散らかってるな、悪い」
確かにCDが数枚投げ出してあるし、上着も丸めてソファに放ってあるものの、乱雑な感じは全くなかった。寧ろ、この空間を愛しいものにしていた。
「何やってんだ?」
純が隣で鼻をくんくんいわせているのを見て、尭村は尋ねた。
「いえ、尭村さんの匂いがするなあって……」
答えると同時に純はぼっと赤くなった。彼の胸に顔をうずめた時にほのかに香った、少し甘めのアンバームスク。あの時の嬉しいような切ないような気持ちを思い出して、鼓動が速まるのを感じた。
尭村は、隣で真っ赤になっている純を見つめながら、
「こういうシチュエーションでこういうこと言うか…」
「え? 尭村さん、なんですか?」
「何でもねえよ」
純はちょんと首を傾げたが、窓辺に飾ってある一枚の絵を見つけると、目を輝かせて駆け寄った。
「あっ、あの絵は?」
明るい色彩のパステルで描かれた女性の半身像。少し恥ずかしそうな笑みをこちらに向けて、寛いだ姿勢で座っている。
「10年前に死んだ俺の母親だ。あんまり似てねえだろ」
「いえ。確かに尭村さんはお父さん似でしょうけど、凛とした美しさみたいなものはお母さんから受け継いでいるんですね。きっと素敵な女性だったんだろうなあ……」
ふわふわした口調で感想を述べると、尭村の手に肩を抱かれた。
「どうしてお前の言葉は……」
「え?」
「胸ん中に沁み込んでいくんだろうな。何か特別なことを行ってるわけでもない、素直な感想をそのまま言葉にしているだけなのに」
自分に問いかけるような尭村の声はかすれて、いつもの覇気が感じられない。どうやら、本気で戸惑っているようだ。
「純、俺は……」
「あきむら、さん?」
純は顔を上げて、今度は一心に尭村の顔を見つめる。媚びも恐れもない、真っ直ぐで深い紫色の瞳。
「俺はお前が……」
―――コン、コン、
尭村は強張った肩をすとんと落とし、はーっと息を吐いて「入れよ」と答えた。額賀の奴も、何とも絶妙なタイミングで来たものだ。
「よっ、純。成仁に襲われてないか?」
入ってきたのは額賀ではなく貴仁だった。尭村は、父親の言葉は無視して冷たく言い放った。
「だから何しに来たんだよ」
「いや、茶飲むんなら俺んとこでどうだ?ってな。純は絵に興味ねえか?」
「うわっ、興味あります! 見たいです見たいです。いいんですか?」
「もっちろん。来いよ。あ、成仁は俺の絵なんか興味ねえだろ。来なくていいぜ」
にやにや笑いながら、さっきまで尭村の手が乗っていた肩をしっかり抱いて部屋を出て行った。振り向いて「尭村さんも行きましょう、ね?」と笑いかける純を、尭村は苦い顔で睨みつけるしかできなかった。
「あっ、この絵、冬に京橋のギャラリーで見ました」
「なに? 個展に来てくれたのか? いつ来たんだよ。ちっくしょう、そん時いりゃあよかった」
「これってパステルなんですか?」
「いや、これは木炭と墨を使ってる。墨の流動性によって画面の平板さを回避するためだ」
画架を前に肩を寄せ合って話している二人を、尭村は苦々しい思いをポーカーフェイスで隠しながら眺めていた。
なんだよ、親父。いつもはへこへこと頭を下げて絵を見に来る奴らを眼殺しそうな勢いで睨んでは、「金の勘定なら外でやってくれ」とあっという間に追い出すくせに。純も純だ。「先生、お砂糖いくつ入れますか?」ってにこにこ笑いかけて。俺にも聞けよ!って俺はブラックなんだけど。そもそも、お前は何しにここへ来たんだよっ―――
どうやら尭村は、親父の絵を見せると言って純を呼んだのを忘れているようだ。
「そうだ、純。お前に謝んないといけねえな。さっきは舞い上がってたとはいえ、失礼なことを言っちまった」
「え? 先生何か言いましたっけ?……っあ」
“男と相当寝てるだろ”
「……そんな、気にしてませんから」
純は小さく首を振ってにっこりと笑った。そしてぽつりと呟く。
「それに、本当のことだし……」
「ん? どうした? やっぱり気にしてるんじゃねえのか?」
「いえ…そうだ、尭村さんの部屋にあったお母さんの肖像、あれって先生が描かれたんですよね」
「ああ、あれか。うんと若い頃描いたやつだからな。ひでえ出来だろ」
「僕は…タッチがどうとかデッサンがどうとか専門的なことは分かりませんが、あの絵は大好きです。尭村さんが羨ましい」
「俺が?」
このアトリエに来て初めて口を開いた尭村に、純は「はい」と言って微笑みかけた。
「僕の母も僕が幼い頃死んだのですが、写真もほとんど残ってなくて。だから母の記憶がだんだん薄れてきて、そのうち消えてしまうんじゃないかって。あんな素敵な肖像画があったら、毎日眺めていられるのに。そしたら母のこと忘れなくて済むのに」
尭村は声を掛けようとした。大丈夫だ、お前の母親はお前の中で生き続けると、励まそうとした。が、先に口を開いたのは貴仁だった。
「そいつはちと違うな、純。冷たく聞こえるかもしれねえが、死んだ人間はさっさと忘れるべきだ。いつまでもうじうじ執着してても何にもならねえ。大体、死ぬより生き続けることの方がずっと大変なんだぜ。だから純、過去とか思い出に縛られんな。お前は真っ直ぐ前を見て行けよ」
貴仁は、愛しさと優しさをこめて純の頭を抱き、髪にそっと口づけた。尭村はこれ以上、二人を見ているのに耐えられなかった。
BACK TOP NEXT