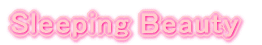
5.
俺はどうやら相当に機嫌が悪いらしいと尭村は思った。クラス中の人間が自分を腫れ物のように扱っているのだ。なるべく話しかけないように、目を合わせないようにと気を遣っているせいで、教室内に張り詰めた冷気が漂っている。
いつもは何だかんだと話題を持ち出してじゃれついてくる薫も、近寄ろうとしない。1年の時からの付き合いだから、みんな尭村の扱い方を心得ているのだ。
扱い方とは言っても、機嫌の悪い時には傍へ寄らない、というだけのことなのだが、それでも知らないよりはまし。
「成仁ぅ、最近冷たいんだからぁ」と、背中に胸をぐいぐい押し付けて絡んできた3年の女など、もの凄い眼で睨まれた挙句、多少でもスタイルを気にしている女性には死刑宣告にも等しいような悪罵を投げつけられて泣きながら出て行った。
しかし森下だけはさすが付き合いが長いとあって、不機嫌の底にいつもとは違う何かを感じ取っていた。もともと倣岸不遜で沸点の低い男だから、ちょっとしたことにイラつくのは珍しくもない。が、今の尭村は何だか自分に腹を立てているようなのだ。
―――おいおい、あの尭村が後悔とかしちゃってるわけ? ひえ〜
その通り。後悔とかしちゃってるのだ。
純が涙をこらえて走り去った後、尭村は追いかけようと何度も腰を浮かせたが、結局その場に留まった。
“昔の恋人に似てる”と言われたことは確かにショックではあったが、下らない嫉妬で純を傷つけてしまったことの方がずっと痛かった。最後、震えながらもきちんと目を見て謝ってきた純。謝ることなんか何もないのに。
「くっそ」
尭村は低くうなって自分の腿を殴った。すると、教室内のざわめきがさっと引いた。そおっと席を立って、教室を出て行く者までいる。“こりゃ重傷だな”と森下は嘆息した。
「日向部長、すみません。生徒会がお忙しいのに」
「いえ、私の方こそ部長らしいことは何もできずに。ところでいいのは撮れましたか?」
「ダメですねえ…。沖兄弟のガードが固くて」
「ずいぶん弱気ですね。ハイエナの異名が泣きますよ」
「ひと昔前のブンヤみたいな呼び方、やめて下さいよ〜」
日向は苦笑しながら、広げられた写真の吟味を始めた。どの写真にも純が写っていることは写っているのだが、ピンボケとか体半分とか後頭部だけとかで、ハイエナが弱気になるのも頷ける。秀が、純の肩越しにこちらを睨んでいるものまである。日向はくっ、と笑って、
「相変わらず食えない男だ。姫のナイト気取りなんでしょうね」
「沖ですか? あいつ2、3年から恨まれまくってますよ。それに、聞けば尭村までもが……」
日向の指先がコツ、と机を叩いた。ハイエナ君こと下条(しもじょう)はびくりと身体をふるわせて、
「あ、す、すみません。俺余計なことを。はははは………」
日向は冷ややかな沈黙を保ったまま、一枚の写真をつまみ上げた。フォークに刺さったいちごを、嬉しそうに口に入れる瞬間。色気は皆無だが、見てるとこちらまで幸せな気持ちになってくる、そんな写真。
「あ、それ気に入りましたか? どうぞどうぞお持ち下さい」
ハイエナは助かったとばかりに、へこへこと頭を下げた。
はー、と溜め息をつく尭村を、森下は珍獣でも観察するような目つきで眺めた。朝からそわそわして落ち着きがなく、昼休みのチャイムが鳴るとほぼ同時にがばと立ち上がり、教室を出て行った。
「なあ…尭村なんか変なモン食った? それとも自律神経失調症とか」
「さあな、更年期障害かもしれねえな」
森下と薫は、冗談を言い合っているようには見えない真剣さで頷き合った。
尭村は1−Cの教室へ急いでいた。手には、この前純が買ってきてくれたLe Rostandのパンがある。
尭村は、自分が買いに行って初めて、このパン屋が学校からけっこう遠くにあることを、そして純がおいしいからと言って勧めてくれたパンが人気商品で、朝早くに行かなければ売り切れで買えないことを知った。
純が学食に行く前に掴まえなければ、とさらに足を速めたその時、尭村はものすごく嫌なものを見た。純が背の高い男に連れられて体育館の方へ歩いていたのだ。廊下の窓から一瞬ちらと見ただけだったが、間違いない。
尭村は考えるより先に身体を動かしていた。
「あの……お話って?」
昼休み、体育館倉庫の裏で二人きり。このシチュエーションで何を言われるか分かりそうなものだが、学園の“真の姿”をまだ知らない純にとっては想像すらできなかった。
男は、純を一人で連れ出すことに成功しただけで舞い上がってしまったのか、その華奢な肩を両手で掴んで引き寄せ、
「好きだ好きだっ、お、俺と付き合ってくれ。何度も手紙書いたのに沖の野郎に握り潰されて……。お願いだ、もうたまらないんだ。見てるだけでおかしくなりそうで……」
生臭い激情、とでも言おうか、純はそれを間近に浴びせられて思わず後退った。が、男はそれを許さず、肩を掴んだ手に力を込めてさらに引き寄せる。
「い、痛っ、やめてくださ……」
「秋原…秋原……」
うわ言のように呟きながら、腰に腕を回して抱こうとした。純は必死に押し返していやいやと首を振る。その仕草が逆に男を煽ってしまったようだ。それなりに整った顔をいやらしく歪めて、シャツの下から手を入れようとしてきた。
いきなり素肌を触られて、純はびくんと震える。
「敏感なんだな…可愛い……」
そのまま手をすべらせようとしたその時、もの凄い力で後方へ引っ張られ、わけが分からないまま吹っ飛ばされた。
たった一発でのびてしまった男と、目の前で仁王立ちしている尭村を、純は微かに潤んだ目で見比べた。余りの出来事に驚いて、助けてもらったにもかかわらずお礼の言葉も出てこない。
「あ、あの……あきむらさん……」
「純、来い」
自分が殴り倒した男になど目もくれず、純の手を取ってぐいぐい引っ張ってゆく。強引ではあるが、冷たさは感じられなかった。
そのまま黙ってついて行くと、いつの間にかあの場所、旧図書館の裏に来ていた。
「助けていただいて、ありがとうございました」
純は深々と頭を下げた。
「座れ」
「…またご迷惑をおかけして、本当にすみません」
「いいから座れっ」
純は弾かれたように顔を上げると、おそるおそる腰を下ろした。まるでこれからお仕置きを受ける子供のように縮こまって、曲げた膝を抱える。尭村はそのすぐ近くにどさりと腰を落とした。
「純、こっち向け」
「は、はい…」
純は怯えながらも素直に従った。真っ直ぐ見上げると、尭村の美しい黒瞳に搦め捕られる。純は目を逸らすことなく、ゆっくり瞬きをした。
「この前は悪かった。許してくれ」
突然の謝罪に、純は口を“え?”の形に開いたまま固まった。
「お前はひとつも悪くない。俺がお前の思い出に傷を付けただけで」
「そんな……僕はあなたにすごく失礼なことを」
純は思わず、尭村の腕を掴んですり寄った。尭村もそれに応えるように身体を寄せて、純の腰を抱く。
「この前のフラ語、お前の訳文完璧だったぜ。また頼んでもいいか?」
「はいっ、もちろんです。……っあ」
優しく引き寄せられると、純の華奢な身体は尭村の腕の中にすっぽりと収まった。そのまま頬を胸に押し付けて尭村の体温を感じていると、嬉しいような切ないようなどうしようもない気持ちに襲われて、純は泣きたくなった。
涙の湧出を抑えるため、唇をぎゅっと噛み締めてさらに顔を強く押し付ける。すると、背中に回された手があやすように撫でてくれた。
―――尭村さん、もうこれ以上優しくしないで……
そんな想いとは裏腹に、純はしがみついた手を離そうとはしなかった。僕はまた誰かに依存しようとしてる、こんなんじゃ駄目だ、と自分を叱咤しながらも、この温もりに融かされたいと願うもう一人の自分の存在も無視できない。
「……純」
頭の上から、甘くかすれた声が降ってきた。純はそっと顔を上げて尭村の顔を見る。
「今度、うちに来いよ。親父の絵好きなんだろ? アトリエには未発表の作品がごろごろしてるし」
「えっ? いいんですか? アトリエって、画家の聖域じゃ……」
「ただの汚ねえ仕事場だよ。っつーか、親父ってそういうタイプじゃねえの。無頓着っていうか大雑把っていうかいい加減っていうか。ゲージュツカっていうよりただのヤクザだな」
「ぷっ」
純は尭村の胸に顔をうずめて笑った。
「あんだよ、 知ってんだろ? 俺の実家のこと」
「はい…いえ、なんていうか、先生の作品とのギャップが……」
腕の中でくすくすと笑う純が可愛くて、力を込めて抱き締める。
「あの、アトリエももちろん見たいんですけど、尭村さんの部屋も見てみたいなあ」
「え?」
一瞬固まった尭村から顔を離して、慌てて頭を下げる。
「ご、ごめんなさい。図々しいこと言って。僕……」
「ああ、いや、構わねえよ。別に面白いものなんてねえけどな」
嬉しそうに眼を輝かせて見上げてくる純の頭を撫でる尭村の顔には、複雑そうな苦笑が浮かんでいた。
さてその後、二人はいつもの場所でよく会うようになった。それを知っているのは取り敢えず沖兄弟だけだったのだが―――
「あのー、すみません」
2−Aの教室に突然現れた噂の姫に、室内のざわめきはぴたりと止んだ。
「なになにー? 誰か呼ぶ?」
固まったクラスメートを押しのけて、薫がぱたぱたと駆け寄った。
「あ、はい。尭村さんを」
「おおっと、尭村ね。ちょっと待っててー」
“うっわー、すっげー、近くで見ちゃったー”と心の中ではしゃぎながら、教室の奥、一番後ろの特等席で机に突っ伏して寝ている尭村を起こしに行った。
「尭村、尭村、あーきーむーらーっ。お客さんだよお。とびっきりのっ」
「……ぅるせえんだよ、藤崎は」
「ああもうっ、寝てる場合じゃないって。ほらほらっ」
薫のテンションに負けた尭村は、のっそりと起きて廊下の方を見た。そしてにこにこ笑って小さく手を振る純の姿を認めるや否や、がばっと立ち上がって慌てた様子で駆け寄り、
「お前っ、なんでこんなとこに来んだよ」
それまで笑顔だった純は急にしゅん、としぼんで、
「借りてた本を返そうと思って……。ごめんなさい、迷惑だっ――」
「あああ〜っ、そうじゃなくてっっ」
尭村は頭をばりばりと掻いて、
「一人で2年の教室に来たりしたら危ないだろがっ。ったく、ちょっと待ってろ」
席に戻って上着を取り、まだ下を向いている純の肩を抱いて優しい声で、
「いつもの場所に行くぞ」
そして呆然としているクラスメートを置き去りにして、出て行った。
―――それから一拍おいて、
「ぎゃぁ〜っっ」
「なになになにぃ? 今のぉ」
「あ、あんなあたふたした尭村くんはじめて見たっ。感動!」
「あの二人、どうゆう関係なのっ? ちょっとちょっと、森下っ」
腐女子隊、大爆発。問い詰められた森下は「知らね〜よ」と肩を竦めながらも、心の中では納得していた。ああ、あいつの最近の情緒不安定は秋原のせいだったのか、と。
BACK TOP NEXT