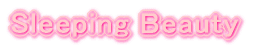
4.
直の言うことは正しい、それは秀にも分かっていた。
新聞部の裏の顔に象徴される学園の“暗部”を知り尽くしている直と秀には、今、純がどれだけ危険な状態にあるかも、そして当の本人はその一割も危機感を持っていないことも分かっていた。
純の“艶写真”への需要は高まる一方で衰える気配を見せないというのに、直と秀がきっちりガードしているせいで供給は驚くほど少ない。というかほとんど出回っていない。さっきの激写だって、窓の外からだから大したものは撮れていないだろう。
そのせいか、入学式からまだ一週間しか経っていないのに、純に対するなまぐさい欲望は沸点を迎えつつあったのだ。
すれ違いざまに「うゎ、やりてー」というねっとりした呟きを、秀は何度か耳にした。そのたびに横つらを張り倒してやりたいという衝動に駆られたが、持ち前の自制心で何とかこらえたのだ。
嫌な兆候はまだまだあった。数々のふざけた武勇伝を持つ3年生、明石(あかし)とか桜小路(さくらこうじ)とかが、純を必ずモノにすると公言しているらしい。
ちなみにこの明石という男、2年の時に当時1年生の薫に横恋慕し、挙句の果てに強姦しようとしたことがある。
薬でぐったりとした薫の上にのしかかってその白い脚を広げ、血管の浮き出た己れのモノをこれからゆっくり挿れるぞという時に片瀬に見つかり、ぶちのめされた。
その後、「散々注意してたのにのこのこ付いていくお前も悪い」と鬼畜ギレした片瀬にその場でお仕置きを受けた薫は、二日間学校を休むという微笑ましい(?)後日談も付いてたりする。
それはさておき。
二人の不安はそれから数日後に現実のものとなった。昼休みの学食、特に混雑している日替わりランチのコーナーに並んでいた直と秀は、純が傍にいないことに気付いた。
「あ、あれっ? 純どこー?」
「こっちー。席取ってるからねー」
純の朗らかな声が後方から聞こえてきた。前も後ろもぎゅうぎゅうに挟まれて身動きがとれない二人は、仕方なくそのまま並んで順番を待つことにしたのだ。
「うっわー、珍しいね。一人?」
後ろから声を掛けられて、純は振り返った。そこには、質の良さそうな服をだらしなく着崩した長身の男が3人。親しげに声をかけられたので知り合いかなと思い、3人をじっと見つめた。すると3人は途端に口許をいやらしく緩めて、
「マジすげぇわ……」
あからさまにごくりと喉を鳴らすやつまでいる。最初に我に返った一人が純の腕を掴んで、
「なあ、一緒にランチしねぇ? 俺たちさ、お姫さまとオトモダチになりたいんだよね〜。いいだろ、ほら」
口調に反して、強引に連れて行こうとする。純は驚いて「いえ、友だちが…」と抵抗するが、相手は全く動じない。気がつけば、3人に囲まれて身動きのとれない状態で。しかも、首筋とかお尻とかをさわさわと触ってくる。
思わず見上げると、口は笑っているけど目はぎらぎらとぬめってほとんど瞬きしていないという、夜道では絶対にお目にかかりたくない物騒な表情に出くわした。
―――ええっと、こ、これはどうしたらいいんだろ……
純の無抵抗を承諾と見なしたのか、
「そんじゃ、裏庭へ行こう。あ、屋上の方がいいかな?」
などと、この学園ではほとんど「エッチしよう」と言っているも同然の言葉をしゃあしゃあと掛けながら、今度は強く純の腕を掴んで連れて行こうとした。が……
「ぅぐっ……ったたたぁ、いてえっ! だれだっ?」
肩を背後から掴まれ、あまりの痛さにうめきながら振り向いた男の目に、明らかに不機嫌マックスと分かる尭村の、ぞっとするほど整った顔が映った。
「ぅわっ、あ、尭村…な、なんだよ……」
「手ぇ離せ」
男は、一学年下である尭村の命令に従順だった。舌打ちと、はっきり聞こえない程度の悪態は吐いたけれど、それは悪あがき以外の何ものでもなく、物欲しそうに純をねっとりと見つめると、あっさり引き下がった。
「純っ、大丈夫かっ?」
秀が珍しく声を荒げて駆け寄ってきた。手ぶらのところを見ると、結局何も買わずに慌てて駆けつけたようだ。答えるより早く尭村が純の腕を取り、
「ほら。沖秀、こいつを一人にすんじゃねえよ。何があっても知らねぇぞ」
秀は神妙な顔で頷く。
「純、お前もだ。自分でちゃんと気をつけろ」
「は、はい。ありがとうございました……」
何に気をつけるのか今いち分からないながらも、純は丁寧にお礼を言った。
「なあなあ、純はいつ尭村先輩と知り合ったの?」
好奇心が抑えられないらしく、直はテーブルにつくなり身を乗り出して訊いてきた。直が食べ物を後回しにするなんて、滅多にあることじゃない。
「うん、この前フラ語サボッた時にね、グラウンドの向こうの芝生の所で」
「って、もしかして旧図書館の裏?」
「そうそう。うとうとしてたら、いつの間にか隣にいたんだ」
「うっわー、あそこって、尭村さんのシマなんだよ。怒られなかった?」
直が“シマ”なんて言葉を使うのには、それなりの理由があるのだ。
「ううん、全然。お昼買い損ねちゃったらパン半分くれたし。いつでも来ていいからって。優しい先輩だね」
にこにこ笑いながら、ショートケーキのてっぺんに乗ってたいちごを頬張る純を、二人は複雑な表情で見つめた。
「…あのね、純。尭村さんっていうのは、むっちゃくちゃ恐い人なんだよ。それこそ伝説は数え切れないほどあるし。環(たまき)姉ちゃんに訊いてみなよ。色々教えてくれると思うよ」
“環姉ちゃん”とは、純が現在居候している弓月(ゆみづき)家の一人娘である。蒼薇学園高等部の3年生。沖兄弟とは幼馴染で、純のことを弟のように可愛がっている。
が、純が納得いかないような顔をしたので、直はさらに尭村情報を教えた。
「そ、れ、に、あの人の実家って極道なんだよ。それも、その辺のチンピラやくざとかじゃなくって、政財界とか大物右翼とか右派の思想家なんかとの繋がりも深い超大物。特にお祖父さんがすごいらしい」
「尭村先輩って、やくざなの?」
「違う違う。本人は違うし、お父さんも違うよ。お父さんは画家になるって言って早くに家を出たんだ。尭村なんとかって、けっこう有名な洋画家らしいけど…」
「えっ、もしかして尭村貴仁(たかひと)? うわー、僕あの人の絵大好きっ」
純はすごい、すごいを連発しながら、ショートケーキを平らげた。先にデザートを食べてはいけません、という環の注意もすっかり忘れて。
「今度尭村さんに訊いてみよぅっと。いつあそこで会えるかなあ……」
うっとりと笑いながら、唇についたクリームをちろと舐める仕草は法に触れそうなほど可愛らしい。直はそんな純を眺めながら、“尭村さんてお父さんのこと言われるの嫌いなんだよ”という忠告を呑み込んだ。
「よっ、日向、西園寺(さいおんじ)。がんばってるか?」
「おや、佐倉(さくら)先輩。珍しいですね。受験勉強からの逃避ですか?」
「相変わらずキレイな顔でイヤなこと言うよなあ…。去年の副会長としては、今の副会長の働きぶりが気になるんだ、と言いたいところだが、まあ俺より優秀なことは間違いないからな。たまには頼ってほしいけど」
西園寺は切れ長の目をすっと細めて微笑ったが、それは“あなたのアドバイスなんて要りませんよ”という拒絶以外の何ものでもなかった。佐倉も思わず苦笑い。
「それよりよ〜、瑞樹ちゃん最近すっげえ不機嫌なのな。日向、何かあったのか?」
「いえ、心当たりはありませんが」
「心当たりはない、か。あっ、そういやさ、俺昼休みに面白いもの見たぜ。食堂でさ、あの秋原が桜小路とか柴田とか、あのへんのヤバめな連中に囲まれたのよ。あいつら傍から見ても分かるくらい欲情しててよ、あのまま連れてかれてたら、完全にマワされてたぜ」
「それで?」
先を促す日向の声は幾分強張っていた。佐倉はにやりと笑うと、
「そう、そんな絶体絶命のお姫さまを救ったのは誰だと思う? 沖じゃないぜ。尭村だよ、尭村」
「尭村って、あの尭村ですか?」
西園寺も少なからず驚いたようだ。初めて書類から顔を上げて佐倉を見た。
「おうよ。あの尭村成仁だ。すんげえ形相で肩掴んで引きはがしてよ。あいつのああいう顔、久々に見たな。おっと、俺そろそろ行くわ。予備校の時間だ。じゃな」
佐倉が出て行った後、二人きりの生徒会室にはしばし沈黙が残った。しかし、
「尭村ですか…。日向会長、厄介なライバルが出てきましたね」
どこか愉しげな西園寺を、日向は氷の視線で突き刺した。
今日は寝ないで待っていようと思ったのに、春の日差しの催眠力は強力で、やっぱり純は眠ってしまった。それからどのくらい経ったのか、近くに気配を感じて目を覚ますと、すぐ隣に尭村が座っていた。
―――すごく…綺麗なひとだなあ……
日向の“キレイ”とは違う。違うどころか全く対極にある。
日向の微笑みは相手を安心させるし、尭村の微笑みは緊張を強いる。声も、二人とも少し甘めのテノールなのだが、日向の声は相手をふわりと包み込むし、尭村の声は皮膚にぴりぴりと電流が走ったような刺激を生む。
共通しているのは、二人共とても魅力的だということ。きっと女のひとにすっごくもてるんだろうなあ。
「何見てる」
急に声を掛けられて、純は慌てて起き上がった。
「あっ、すみません。おはようございます、じゃなくて、あの、これを」
がさごそと紙の袋を取り出して、尭村に渡した。
「Le Rostandっていうすごくおいしいパン屋があって、そこで買ってきました」
「わざわざ買ってきたのか……確かに旨そうだな。じゃあ遠慮なく。ほら、お前も。一人じゃこんなに食えない」
言いながら尭村は、二人分のパンが入った袋をそっと隠した。
「あの、尭村さん」
「なんだ?」
食べ終わった二人は、くつろいだ格好で寝転がっている。
「尭村さんのお父さんって、洋画家の尭村貴仁なんですよね?」
「……ああ」
あからさまに不機嫌な返事も、純は気にならなかったようだ。ぱっと表情を輝かせて、
「うわあ! あの、僕尭村先生の絵大好きなんです。特にパステルで描かれた静物画が。そこらへんにあるただの瓶とか手袋とかが、神秘性を帯びて迫ってくるっていうか。“具象も抽象も関係ない、その間で揺れ動く鮮烈なイメージを捉えたい”っていう言葉にもすごく共感して」
純は頬を薔薇色に染めて、嬉しそうに話している。しかし尭村は、複雑な感情に囚われていた。
これまで父親のことを言ってきた奴らはみな、“有名な画家”とか“作品が高値で取り引きされる”といった事実にしか興味を示さず、実際にどんな絵を描いているのかなんて知りもしなかったし知ろうともしなかった。だから、こういう風にきちんと作品を知った上で評価してくれるのは嬉しいこと、のはずだった。
しかし尭村は不愉快だった。純が紫色の瞳を潤ませて父親のことを話すのを聞いていると、胸がムカムカして、苛ついて仕方なかった。だからつい、目の前の純に剥き出しの感情をぶつけてしまった。
「親父のことは言うな。ムカつく」
地の底を這うような声。純ははっと顔を上げて尭村を見ると、哀れなほどうろたえてすみません…と囁いた。そして俯いてしまった。
尭村もバカではない。自分が嫉妬しているのはちゃんと自覚していた。それを純にぶつけるのは理不尽だということも。しかし醜い感情はぐんぐんと膨らんでいった。純の心を捉えた父親に対する嫉妬だけではなく、もうひとつの嫉妬にも気付いてしまったから。
「…お前、最初俺を誰と間違えた?」
「え、えっ?」
「まさと」
尭村が口にしたたったひとつの名前に、純は凍りついた。
「お前、俺をそいつと間違えただろ。なんだ、昔の男か? 捨てられたけど忘れられないとか、そんな下らねえことなんだろ。俺をそいつの代わりにするつもりか? ふざけんな」
純はいつの間にか正座していた。腿の上に乗せた手が、ふるふると震えている。それでも純は顔を上げ、しっかりと尭村の目を見据えて言った。
「ロンドンにいた時の恋人です。すごく好きでした。初めてあなたを見た時、似てるなあって思って……。き、気持ち悪いですよね、こんなの。本当にごめんなさい。もう…ここには来ませんから………っ」
純は泣いてはいなかった。しかしそれは涙を流していないというだけで、その瞳は悲しみに溢れていた。
純は深く頭を下げると、肩を丸めて走り去った。
BACK TOP NEXT