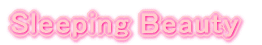
3.
「へー、あの日向会長が頭下げたんだ。ちょっとオドロキ」
「うん、思ったとおり、ちゃんと話せる人だったし。楽しかったよ」
純は、昨日の生徒会室での一部始終を二人に話して聞かせた。
「そっかあ…自分の言うことなら何でもはいはい頷く人ばっかしってことは、逆に言えばまともに話を聞いてくれる人がいないってことだもんな。うん、だから日向会長と秀は仲いいんだな」
「誰が仲いいんだよ」
秀にしては珍しく、嫌悪感を露骨に表して抗議した。しかし「はいはい」と軽くいなされる。
「そうそう、僕も思った。なんか、お互いの能力を認め合ってるってカンジ。よきライバルっていうのかな」
「お前なかなかやるな、お前こそ見直したぜ、わっはっはっは……。みたいな?」
「うわー、さむーい」
きゃらきゃらと笑い合う直と純。
「…お前ら、人で遊ぶな」
秀は呆れながらも、口許を緩めて二人を見つめた。その時、折りよく授業開始のチャイムが鳴った。
「あ、次フラ語だよ。純はどうする?」
「わ、そうだった。課外授業、行ってきまーす」
蒼薇学園高等部では、第二外国語としてフランス語が必修だった。しかし純は英語もフランス語も堪能で、今さらアー、ベー、セー、デーとかJe suis
Japonais、なんてやってられない。ということで、レッスンごとの節目に皆の前で全文を朗読するという条件付きで、課外授業、つまりサボりが容認されていたのだ。
大体がこの学園は放任主義に近いものがあり、他人の邪魔になることさえしなければ、授業中の態度は個人の裁量に任されていた。もともと優秀な生徒が集まっているので、がつがつしなくても皆それなりの成績がとれてしまうのだ。
純は読みかけの本とジャケットを持って、教室を出て行った。
学食で買ったばかりのパンとウーロン茶、そして次の授業で使うテキストを持って、尭村(あきむら)はいつもの場所に向かっていた。
そこは、現在は書庫として使われている旧図書館の裏。寝転がるのにちょうどいい程度の傾斜と、柔らかな芝生と、涼しい木陰。しかも校舎から離れているため、昼休みの喧騒も届かない。ここは彼だけの場所だった。
もちろん札が立ったり柵が設けてあるわけではないが、彼がここは俺の場所だ、と言うだけで充分なのだ。それに異を唱えたり勝手に入ろうとするようなバカな(もとい、勇敢な)者がいるはずもなく……いた。
「ちっ、誰だよ」
尭村はあからさまに不機嫌な声で呟いて、ずかずかと近寄った。たぶん1年生だろう。よおく言い聞かせてやらねばならない。どうやら熟睡しているらしい侵入者に足音をたてて近づき、立ったまま上から見下ろした。
「ぅ…わ……」
おい、起きろ、と怒鳴ろうとしたのに、出てきたのは情けない溜め息だった。そしてしばし見惚れる。何かにうっとりと見惚れるなんて、彼の生涯では初めてのことで。
尭村はそのままゆっくりと腰を落としてひざを着いた。そして誘われるように指先を伸ばしてつややかな頬に触れる。
「ぅうん……」
いやいやと首を振ってぐずる仕草はあどけないのに、どこか艶かしくて情事の後の気だるい朝を思わせる。そのまま指を首筋の方へすべらせると、「やぁん…」と鳴いて熱い息を吐いた。
―――これはちょっと……堪んねぇな
指が肌に吸い付いて離れない。このまま鎖骨の方へさらにもっと下へとすべらせるのはさすがにヤバイだろう。そんなことを考えているうちに、不法侵入の眠り姫はゆっくり目を開けた。
尭村は、その瞳の色にも驚いたが、それ以上に、自分に注がれる甘えるような視線に蕩かされた。姫は、夢とうつつの境にいるのか、抱擁をねだるように白い手を伸ばしてくる。そして、
「…ま……さ、と………」
―――え?
次の瞬間、がばっと起きて辺りを見回した。
「うわわっ、すみませんっ。えと、えと…。あれ? ここどこ? って、ぅわっ尭村先輩!」
さっきまでの色気はどこへやら、くるくると変わる表情は無邪気で幼い。尭村は苦笑しつつ、
「どこ? はねえだろ。人んとこ勝手に占領しといて。お前、1−Cの秋原だろ。俺のこと知ってんのか?」
「はい。先輩が教室の前通るたびに、女子がきゃ〜、尭村先輩よ〜って」
純の素直な物言いに、尭村は思わず吹き出した。誰だよ、こんだけ綺麗だったら性格も歪んでるはず、なんつったのは。
「それよりお前、いつからここにいるんだ? 昼めしは?」
「え、僕四限をサボッて……って、もうこんな時間? わー、寝過ごしたっ」
慌てて立ち上がろうとする純を制して、
「今から学食行ったって無駄だと思うぞ。ロクなもん残ってねえよ」
「う〜」
タイミングよく純のお腹がくるくると鳴った。うらやましそうに尭村のパンを眺めている。
「わぁった。半分やるから。ほら」
純は何度もお礼を言って、差し出されたエビコロッケパンをほおばった。
「旨いか?」
「ふぁい」
「そうかそうか」
尭村は、自分でも驚くほどの穏やかな微笑みを浮かべた。たぶん薫がいたら、「尭村、鼻の下伸びてる」と指摘するところだろう。
「…ん、どうした?」
さっきまで食べるのに必死だった純が、じっとこちらを見ている。その健気ともいえる視線に何か心打たれるものを感じて、尭村は戸惑った。が、純はそれ以上に戸惑った様子で、
「あ…いえ、なんでもありません。これおいしいですね」
そう言うと、何故か淋しそうに微笑った。しかしすぐに朗らかさを取り戻して、
「あれ、先輩。フランス語の予習ですか?」
「ん? ああ。フラ語だけはどうしても駄目なんだよ。馴染めねぇっていうか。名詞に性別があるのが意味分からねえ。なんで木が男性で葉が女性なんだよ。なんで車が女性で電車が男性なんだよ。乗り物なんだから女でいいじゃねえか」
などと下品なことを言いながら、本気でムカついているようだ。純はけらけらと笑って、
「ドイツ語じゃなくて良かったですね。中性名詞まであるんだから。あの、もしよかったら、僕フランス語話せるんで」
「マジで? そりゃ助かるな。ここからここまで、訳してくれるか?」
「はい、もちろん。お昼ごちそうになったお礼と、勝手に場所取っちゃったお詫びです」
「ん? あ、ああ、そうだな……」
そうだった。ここは尭村だけの場所。一人で過ごす有意義な時間、のはずだったが…。
「んと……」
テキストにかりかりと訳文を書いている純を、じっと見つめる。時折指先で下唇をなぞるのは、無意識の仕草のようだ。癖なのだろう。何とも艶っぽい癖だ。他の男には見せたくない。
「できました、尭村せんぱ……」
純がぱっと上を向いた瞬間、上気した頬と僅かに開いた唇の薔薇色に、尭村の胸は妖しく騒いだ。顔をそっと近づけても、純は逃げる気配を見せない。不思議そうに尭村を見上げているだけ。
このままここで…と彼本来の獣性が頭をもたげてくるが、ひとつどうしても気になることがあった。結局、それが欲望の暴発を抑えることになったのだ。
「ああ、さすがに早いな。助かった」
「いえ、そんな……あ、僕つぎ体育だった。着替えなくちゃ」
「そうか。じゃあもう行った方がいいな。じゃな、純」
名前を呼ばれて、純は嬉しそうにふわりと微笑んだ。
「あ、それから……お前、好きな時にここ来ていいんだからな」
純は笑顔全開でこくんと頷くと、緩い傾斜を駆け上がっていった。尭村はその後ろ姿を見送りながら、指先で自分の唇をそっと撫でた。
体育用のジャージを抱えて更衣室へ急ぐと、すでに着替えた直と秀が待っていた。
「おっそーいよ、純! 何やってたんだあ? 急げ急げ」
「ごめんごめん、ちょっと待ってて。今すぐ……」
言うが早いか、純はシャツのボタンを二つほど外しただけでするすると器用に脱ぎ始めた。
「あっ、先にカーテン閉めろっ」
直が慌てて叫んだが、時すでに遅し。窓の外で二度ほど何かが光り、秀が駆けつけた時には逃げ去る後ろ姿しか見えなかった。
「何人だっ? 秀」
「二人、だな」
「くっそおー、新聞部だな。気をつけてたのに。よおしっ、あとで怒鳴り込んでやるっ」
怒り心頭の直。対して純はぽかんと口を開けている。真っ白でたおやかな上半身をさらしたままで。何が起きたのかよく分かっていないようだ。
「待て、直。新聞部とは限らないぞ。あの手際の悪さはもぐりの可能性が高い」
「でもっ、どうせ新聞部に売るんだろ? だったら……」
「っくしょん!」
二人の切羽詰った会話は、小さなくしゃみに断ち切られた。
「純、お前何やってんだよ〜、風邪ひくぞ。早く着替えて着替えて」
「うん…ね、ね、直。今のなあに?」
「今のはなあ、純のハダカ……っんぐ」
「純、早く着替えろ。授業に遅れるぞ。俺たちは外で待ってるから」
秀は逞しい腕で直の口を塞いで、そのままずるずると引きずって出ていった。
「なぁにすんだよっ、バカ秀!」
「お前が余計なこと言うからだ」
「余計なこと? ってホントのことじゃねぇかっ」
「自分の写真が売り買いされて、しかも男どもがそういうコトに使ってるって知ったら、純はどんなショックを受けるか」
「ショックだとしても事実だろ? そろそろ純も、自分が男にどういう目で見られているかちゃんと自覚する必要があると思う。秀だって気付いてるはずだ。もう俺たちの力だけで守りきるのは難しくなってきてるって」
秀は否定も肯定もしなかった。ただ黙って、純がいつもの笑顔で更衣室から出てくるのを待った。
ここで新聞部について説明しなければなるまい。
蒼薇学園新聞部は、学園内において強大な権力を握っていた。表の権力者が生徒会なら、裏の権力者は新聞部。
とはいえ、部長は代々生徒会長が務めることになっていたから、二つの権力には密接なつながりがあった。そう、今の部長はあの日向勇人なのだ。
新聞部は週に2回ニュース紙を発行し、週に1回昼休みにワイドショーを放映する。何か校内で事件が起きた時には号外も出すし、記者会見のセッティングも行う。
容姿、頭脳、性格ともに優れた生徒に“姫”の称号を認定するのも、新聞部の仕事。つまり学園内のマスメディアを一手に引き受けているのだ。しかしこれらはいわば、新聞部の“表の顔”だった。
彼らの“裏の顔”、それは人気の高い生徒の生写真(通称「裏写真」「艶写真」)を売りさばくこと。
生写真といっても、さっき純が撮られたような着替え写真などはまだまだかわいい方で、裏庭や今は使われていない旧校舎でヤッているところを撮影した「本番写真」や、そのものずばり「レイプ写真」「輪姦写真」などは、信じられないほどの高値で売買されていた。
さらに現場を撮影したビデオテープも出回っているらしいというのはまだ噂の域を出ていないが、口は堅く財布のひもは緩い上客相手にはすでに予約承り中だとか。
もちろん、これらを学外へ転売することは固く禁じられていた。この暗黙の掟を破った者はこれまで3人ほどいたが、みな新聞部に恐ろしい噂をでっち上げられて学園にいられなくなり、自主退学して海外に留学する羽目になった。
こういった裏メディアの売買で新聞部が得る金は、中堅サラリーマンの年収に匹敵するといわれている。
これを元手に高性能カメラや編集機械を買い、余った分は予算不足のクラブに提供する。もちろんただでというわけにはいかず、資金援助を受けたクラブはその代わりに、一番人気の部員を差し出さなくてはならないのだ。
期間限定の人身御供とはいえ、とんでもない姿態のとんでもない写真を撮られまくり(軽い薬物が使われるという噂も)、それを学内市場に流すことによって新聞部がますます潤う、という仕組みだった。
ちなみに、こんな暴挙を教師たちが許しているのかといえば、触らぬ神に何とかで、完全黙認状態だった。
むかし、正義感あふれる一人の教師が学生にあるまじき行為を取り締まろうとしたが、生徒へのセクハラをスクープされて教職を退いたということがあったのだ。それが事実だと信じている生徒は少ないが。
まさに向かうところ敵なしの独裁者といえるが、そんな新聞部が唯一恐れている男がいた。傍若無人、唯我独尊。小ざかしい術策を「うぜえ」の一言で難なく蹴散らしてしまう孤高の猛獣、尭村成仁だった。
BACK TOP NEXT