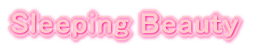
2.
入学式から3日経って、蒼薇学園では通常授業が始まった。つまり、昼休みの学食にもいつもの賑わいが戻ってきたというわけだ。
「あ、純のプリンうまそー。あとでひと口ちょうだい」
「直のひと口って3分の1なんだよね。この前のレアチーズだって……」
「ちょっとすくったら3分の1とれちゃっただけじゃんかー。純のけちー」
などとじゃれ合っている二人を、鼻の下をだらしなく伸ばして見つめる男たち。なんとも微笑ましい(?)光景だ。
その時、ちょっと色彩の違うざわめきが食堂の入口辺りで沸きあがった。
「うわ、日向会長じゃん。めずらしー」
あちこちで囁きが交わされる。確かに、飢えた生徒でごった返す昼の学食に日向が現れることなどめったにない。昼食は生徒会室の会長専用個室で、ファンやシンパらが作ってきた弁当を食べるのがいつもの習慣なのだ。
日向は、席をお取りしましょうかと寄ってくる後輩たちを優雅に制して、きょろきょろと辺りを見回している。誰かを探しているようだ。
秀はいやな予感がした。予感というより確信に近い。ほとんど条件反射的に純の腕を引いて自分の後ろにやり、日向の視界から隠そうとした。しかし間に合わなかった。
こちらに気付いた日向は嬉しそうに微笑んで、真っ直ぐ近づいてくる。進行方向にいた生徒らは慌ててよけて道を作る。まさにモーゼ状態。
「やあ、沖くんたち。久しぶりですね」
「日向会長も相変わらずですねー。でもどうしたんですか? こんな人がわさわさいる所に来るなんて」
「いえ、あの沖兄弟が大事に大事にしている人がいると聞きまして。ぜひ紹介していただきたいのですが」
日向は胡散臭いほど美しい笑みを浮かべて、直に詰め寄った。ちなみに日向は誰にでも、後輩相手にも敬語を使う。これを謙遜などという旧時代の美徳と考えるおめでたい奴などいるはずもないが。
ともかく、生徒会長にここまで言われて隠し続けるわけにもいかない。秀は仕方なく脇へよけて、純を紹介した。
「同じクラスの…秋原純だ」
日向はゆっくり息を吐いて呼吸を整えた。前回のような不様な真似を繰り返さぬように。この美貌に呑まれぬように。
しかし間近で見る彼は日向の想像をはるかに超えていた。近くで見ればそれだけあらも目立つというのが人間というもの。なのにこうして対面して分かったのは、本当に美しいものは遠くから見ようが近くで見ようがびくともしないということだった。
まつ毛の1本1本まで、神さまが特別な愛情を込めて作りあげたに違いない。このまつ毛がもし涙に濡れたなら、そしてそれが快楽に耐え切れず流した涙だったらと、淫らな妄想に日向は襲われた。が、もちろんそんな野獣な感情などおくびにも出さず、日向は優雅に腰を折った。
「はじめまして。生徒会長の日向勇人と申します。沖くんたちには、中等部で大変お世話になって」
「こ、こちらこそはじめまして。秋原です。日向…先輩」
媚びるでもなく怯えるでもない、無邪気な視線を向けられて、日向はくすぐったいような喜びを感じた。
「あなたは内部生ですよね? でも中等部でお会いした記憶がないのですが」
「あ、僕は3年から編入してきたんです。それまでは…イギリスにいました」
「ああそうでしたか、道理で…。今度ぜひゆっくりお話ししたいですね。よろしければ生徒会室に遊びにいらして下さい。おいしいお茶をごちそうしますよ。では、また」
日向は秀を横目でちらと見ると、意味深な笑いで口許を歪め、そのまま去った。その時背後から「すっごいキレイな人だね〜」という純の朗らかな声が聞こえて、一瞬日向は足を止めた。
――なるほど、美しいのは顔だけではないようですね。沖兄弟があれだけ大事にするわけだ
日向は、自分がいつになく浮かれていることに気付いていた。
「でもねー純、日向会長って見かけほど優しい人じゃないんだよお」
チキンのトマト煮をむぐむぐと口に押し込めながら、直は力説した。
「あの人はあ、未来の理事長でぇ…うぐ。んで、日向家が学園のけーえー権を握ってるわけだからあ…」
「…直、食うか喋るかどっちかにしろ。口はひとつだ」
「じゃあ食う」
言うが早いか皿の上のものをがつがつと平らげて、再びトークモードオン。
「気に入らない教師辞めさせたり反抗的な生徒追い出したり。生徒会は自分の信奉者で固めちゃうし。ま、顔と頭だけは抜群なんだけどね。性格はどーかなー。あ、あと人間アレルギーだし」
「人間アレルギー…?」
純はきょとんとした顔で訊き返す。
「うーんと、正式名称は対人性接触不全なんたら症とかいうらしいけど、とにかく人に触ったり触られたりしたら、呼吸困難を起こしてぶったおれちゃうんだ」
「うっそ…そんな病気があるの?」
「そーそ、最初はみんな驚くんだけどね。ホントなんだよ。肩がちょっと触れるくらいならセーフらしいけど、握手はダメ。もちろん抱き合うのもキスするのもそれ以上もぜーんぶNG」
「なんでそんな……」
純は、日向の穏やかな笑顔を思い出した。そういえば、その奥に諦めのようなものがゆらめいていたように思えるのは、今こんな話を聞いたからだろうか。
「うーん、あの人もなんていうか複雑な家庭環境でね。子供のころはけっこう嫌な思いしたらしいよ。そのせいかどうかは分かんないけど、異常なほど潔癖症だし、他人の肌なんて汚くて触れない、って感じじゃねえの?」
「そう、なのかなあ……」
純は納得いかないという顔つきで、フォークに刺したエビフライをぱくり、とかじる。
「まあ人の心の中なんて分かんないけどさ、俺中等部んときに一度、日向会長が手ぇ洗ってるとこ見たことあるんだよね。真っ剣な顔して何度も何度もごしごしこすってて、鬼気迫るって感じですっごいこわかったよー。あと、例の発作も一度だけ見たことあるけど、あれも忘れられない。苦しそうに胸かきむしってさ……」
直は、はーと溜め息をつくと、純のフォークに刺さったままのエビフライにかぶりついた。
「ん、んまい。でもさ、本人はあんまり気にしてないみたいで、ひょうひょうとしてるんだよな。俺なんか、もし純にぎゅーっとしたりちゅーってできなくなったら、もう淋しくて悲しくて生きていけないっ」
叫ぶと同時に純の頬にすりすりと頬ずりした。周りでぎゃーっ、とかうおー、という声が沸いたが、直は気にせず抱きついたままでえへへと笑う。
「食堂でいちゃつくなよ。ほら、お前が変な話するから、純が暗くなっちまったじゃねえか」
秀が心配そうに純の顔を覗き込む。
「ううん、大丈夫。でもホントにそうだね。僕も二人にさわれなくなったらきっと、淋しくておかしくなっちゃうよ……」
そう言って純は、プリンを目一杯すくって直の口に運んであげた。
その2日後―――
純は立ち止まって、はーっ、と溜め息をついた。この奥に生徒会室があるのは分かっている。直と秀をなんとか宥めすかして先に帰しここまで来たのだが、急に気後れしてきたのだ。
遊びに来てくれとは言われたけれど、新入生に気を遣って言ってくれた社交辞令かもしれないし。それに、生徒会室には日向以外の役員たちもいるわけで、全く面識のない先輩たちに囲まれるのは、想像しただけで気詰まりだった。
それでも純は引き返そうとしなかった。どうしても日向のことが気になるのだ。他人なんて汚くて触れないのだろうと直は言ったが、真実はその逆ではないかと思えて仕方なかったのだ。
理由は? と訊かれたら、直感でと答えるしかない。あとは自分の経験。純にも、人に触ったり人から見られたりするのが怖くてどうしようもない時があったから。こんな汚くて醜い自分を見ないで、と。
「ど、どうしよう…かな」
生徒会室の扉の前。中からは話し声や笑い声が聞こえてくる。改めて日向の教室に会いに行った方がいいかも。いや、その方が変に目立ってしまうかなあ……
「そこは自動ドアではありませんよ」
「ひゃっ!」
慌てて振り返ると、そこには涼やかな美貌が。
「さっそく来て下さったんですね。口では絶対遊びに行きます、なんてしおらしいこと言いながら、実際には足を運ぼうともしない人間ばかりなのに。とても嬉しいです」
「あの…でもお邪魔ではないですか? 生徒会のお仕事は?」
「うちの副会長は非常に有能なんですよ。会長なんてふんぞり返って書類にサインするだけ。さあどうぞ。遠慮なさらずに」
日向はうやうやしく一礼して扉を開けた。
「いやーあれは凄い」
「凄いですね」
「日向会長を見慣れてる我々でもよろめきますね」
生徒会の面々がこそこそと囁きを交わす中、日向は一人うきうきとお茶の仕度をしている。そして、最近お気に入りのメープルはちみつティーの芳香とともに奥の会長専用室へ入っていった。
「うーん、日向会長浮かれてるなあ」
「瑞樹がいなくてよかったな」
うんうんとうなずき合うと同時に、その当人、書記を務める瑞樹央(みずき・おう)が扉を開けた。
「僕が、なに?」
「ああ、いやあ〜、はははー」
どうか奥の部屋に秋原がいることに気付きませんように、って無理か。嵐の予感。
いただきます、と軽くお辞儀をしてカップを手に取り、ふうふうと吹く。そしてふちに唇をそっと付けてひと口飲むと、おいしいと呟いてにっこり笑った。
そんな一連の仕草を、日向はうっとりと目を細めて眺めている。彼の周りには、自分をこう見せたい、ああ見られたいと自我を剥き出しにしている人間ばかりだったので、こういう自然で飾らない振る舞いは新鮮だった。一緒にいると、まるで自分まで澄んでいくような気がする。
どのくらいそうしてお茶を楽しんでいただろうか。窓から流れ込んできた風で紙ナプキンがふわりと飛んだ。純と日向はそれを拾おうと同時に手を伸ばし、その拍子に指先が触れ合った。
「あっ、す、すみません。あの……」
純は慌てて手を引っ込め、心配そうに日向を見つめた。
「いえいえ、この程度なら平気なんですよ。…直くんに聞いたのかな?」
「はい、そうです。あの、日向会長、」
日向は不機嫌そうにちょっと眉をたわめて、
「名前で呼んでくれませんか? 勇人、日向勇人です」
「は、はい。…勇人さん、あの、辛くはないんですか?」
真っ直ぐな口調、真っ直ぐな視線。日向も正面から視線を返した。
「辛くはないですね。むしろ楽です。親に強制されて訳の分からないパーティーに駆り出されても、差し出された脂っぽい手を握らなくて済みますし。なれなれしい態度を取られることもない。私の領域を清浄に保つことができるのです。発作自体は確かに辛いですが、時間が経てば治まりますから」
「そうですか…済みません、僕余計なことを」
本当にそうだろうか。この先愛する人が現れても、この人はそう言えるのだろうか。愛する人と抱き合って、ひとつになりたいとは思わないのだろうか。
もちろん純はそんなことは訊かなかった。自分の価値観を人に押し付けるなんて傲慢が過ぎる。
「いいんですよ。それよりも、私について他に何か言ってませんでしたか? 特に沖秀なんかが」
純はあれ? と思った。秀のことを沖秀(オキシュウ、“キ”にアクセントをつける)と呼ぶのは、親しい人間だけだったから。
「いえ、何も」
「そうですか。いえ、あれはなかなか一筋縄ではいかない厄介な男でしてね。切れ者で寡黙だという噂を耳にしたので、中等部の時に生徒会に誘ったことがあるんですよ。ところが詳しい話をするまでもなくあっさり断られまして。
私もつい意地になって色々裏工作したのですが、まあ見事に玉砕で。だから私のことはきっと毛虫のように嫌っているでしょうね」
「勇人さん。たとえそうだとしても、秀は悪口を言いふらすような奴じゃありません」
日向は一瞬、微笑うのをやめた。厳しい表情で純を見つめる。こちらがこの男の本性なのかもしれない。そしてゆっくり頭を下げた。
「申し訳ありません。あなたの友人に大変失礼なことを」
もしこれが他の人間だったら、ふざけた振る舞いに見えたかもしれない。しかし日向の真情はきちんと伝わってきた。やっぱりこの人は、権力で学園をおもちゃ扱いしているただのわがまま坊ちゃんではない、純はそう確信した。
奥の部屋から響いてくる笑い声に、瑞樹は苦々しい思いで耳を傾けていた。
日向は純のことをかなり気にかけている、生徒会役員でそれを知らない者はいなかったが、まさかこんなに早くこんなに親密になるとは思っていなかった。
「瑞樹、こえー顔」
「うるさいっ」
その時、ようやく二人が会長室から出てきた。
「すみません。あの、カップは」
「ああ、そのままでいいですよ。僕が洗っておきますから」
切れ長の黒い瞳に深い知性を湛えた男が、書類から顔を上げてにっこり笑った。おそらく彼が、日向言うところの“有能な副会長”なのだろう。
「では、帰りましょうか。途中までお送りしますよ」
「ええっ、勇人さん、いいですよお。一人で平気です」
「駄目です。あなたに何かあったら沖兄弟に埋められる」
冗談とも本気ともつかない口調でそう言うと、日向は上着を羽織って外へ出た。純も慌ててそれに続いたが、もちろん扉のところでくるっと回れ右をして、お邪魔しましたっ、と挨拶するのも忘れなかった。
「…ふーん、なかなか。にしても“勇人さん”とはねぇ……」
しかしその言葉に答える者は誰もいなかった。瑞樹が発する冷たいオーラを、肩を丸めてやり過ごすので精一杯だったから。
BACK TOP NEXT