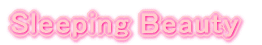
1.
都内有数の偏差値を誇る蒼薇(そうび)学園高等部の入学式は、散りゆく桜が舞う淡い色彩の中で粛々と進行していた。
瀟洒な講堂の中で背筋をぴん、と伸ばして座る新入生。その後ろには、そんな彼らを面白そうに眺めてはにやにや笑う上級生の面々。
私服通学が基本なので、季節に合わせた桜色やレモンイエローのスーツで軽やかに装った生徒の姿もちらほらと見える。
高校の入学式とは思えない華やかさ。浮き立った空気。それは、祝辞を贈るため生徒会長が壇上に現れると、さらに熱を帯びて講堂全体を包んだ。
蒼薇学園高等部生徒会長、日向勇人(ひゅうが・はやと)。
マイクを何気なく直すだけの仕草に、優雅な香気を感じさせてしまう男。肩に付く長さの茶色いストレートヘアを指で梳いて、柔らかに笑う。
涼やかな目許が印象的な透き通った美貌に、新入生の目は釘付けになった。長身痩躯ではあるが、しなやかな筋肉がスーツの上からでも窺える。
しかし“聖母のような”、“慈愛に満ちた”などと形容される微笑みを、緊張している新入生の上へ降り注いでいるものの、微笑みの奥に結晶しているものは限りなく冷たいということは、それなりの観察眼を持つ者なら誰でも知っていた。
「新入生の皆さん、ようこそわが蒼薇学園へ。私たちは心より皆さんを歓迎いたします」
その声もまた、上質のベルベットのような光沢と艶を持つテノールだった。思わず胸を押さえる女子生徒の姿もちらほらと。日向はそれに気付いていたが、もちろん素知らぬ顔で言葉を続ける。
「こうして皆さんの希望に満ちた顔を見ておりますと、一年前の同じ日を思いだ………」
その時、日向はこの世ならぬものを見た。見てしまった。
天井の明り取りから差し込む光がまるで天然のスポットライトのように照らす中、新入生席に座る彼はじっと壇上の日向を見つめている。その余りの美しさに、冷徹な生徒会長は言葉を失ってしまった。
大体、この学園に美少年美青年の類いは珍しくない。もちろん日向も含めて。
正真正銘男女比率5対5の共学にもかかわらず、男子生徒同士のカップルがやたらと多いのはそのせいで、彼女なんて作ろうものなら「お前女なんかと付き合ってんの〜?」と皮肉られる始末。
近くの男子校までその影響を受けて、蒼薇学園の“姫様”(もちろんオトコのコ)たちをゲットしようと毎朝毎夕校門辺りに群がっては手紙アンドプレゼント攻撃。
そんな学園のトップに君臨する、泣く子も黙る美人生徒会長を凍らせるほどの美貌が存在するとは、まさに奇跡だった。
真っ白な肌は陶器のようにすべらかなのに、しっとりとした輝きと頬に灯るほのかな薔薇色のせいで冷たい感じはしない。
耳が隠れる長さの髪はごくごく緩くうねって輪郭を優しく包み、少し長めの後ろ髪が首筋を這うさまはどこか官能的で男の本能を刺激する。色はつややかなティーブラウン。
生徒会長の話に真剣に耳を傾けているせいか、僅かに開いた唇はふんわりと柔らかそうで甘そうで、食欲さえ起こさせる。
そしてその瞳! 日向は家の事情により様々な人種の人間に会うことが多かったが、こんな深く美しい紫色の瞳の持ち主に出逢ったことはなかった。鳥肌がたつ。眩暈すら覚える。もちろん、肝心の祝辞の方はひどい有様で。
「あ………、えー……」
会場がざわつき始めた。教師たちは訝しげに日向を見やり、彼の腰巾着、生徒会の面々も心配そうだ。それもそのはず、彼が言葉を失ってうろたえるなんて前代未聞の珍事、あるはずがないあってはならないことなのだから。
それでもさすがは日向勇人。鋼鉄の神経を持つ男。湧き上がる動揺を抑えてゆったりと微笑み、「新米生徒会長なものでつい緊張してしまいました」と心にもない言葉で繕って何とか祝辞を再開した。
しかしその目は決して新入生席の方を見ようとしなかったが。
「やったーい、うっれっしっいなっっ」
沖直(おき・なお)は、本日5度目の“喜びのおたけび”をあげた。
「…直、分かったから」
直の双子の弟、沖秀(おき・しゅう)は、やつれた声で答えた。
「なあんだよ、秀! またまた3人同じクラスになれたんだぜ、嬉しいじゃねーかっ」
直は顔の3分の1はあろうかというほど大きな黒瞳(こくどう)をくりくりと動かして、仏頂面の弟を睨みつけた。
睨んだとはいっても、卒業と新加入を繰り返す某アイドルグループのセンターパートにいても遜色ないほど可愛い顔をしているせいで、何の効果もない。ただ可愛いだけ。
ところが本人は、「可愛い、キレイ」と言われることを極端に嫌がっていた。しかも、同じ遺伝子を持ち同じ顔をしているはずの弟は自分より10センチ以上も背が高く、男前、かっこいい、渋い、男っぽい…と、憧れの形容詞を独り占めしているのだから面白くない。
今だって、下から見上げる目線のせいで、睨むというより縋るといった感じになってしまった。
しかし可愛いのは外見だけではないのだ。「俺は可愛いんじゃない、かっこいーのっ!」というのが直の口癖なのだが、こんなこと叫ぶこと自体かわいさ爆発、ということに本人は気付いていない。
もちろん、すぐに“姫”の称号が与えられ、陰で“直姫”と呼ばれることになろうなんて分かるはずもなく。
「クラス替えとかもないから、これで卒業までずぅっと一緒にいられるんだからな、純」
「うん、ホントにうれしーね」
秋原純(あきはら・じゅん)は直に向かってにっこりと微笑みかけた。すると直の後ろにいたクラスメートたちは、真っ赤になってふにゃふにゃとその場に座り込む。
直たちのような中等部からの内部進学組にはまだ免疫があるからいいものの、受験組には初体験の純の笑顔。慣れるまでにはまだまだ時間がかかりそうだ。
沖直と沖秀の兄弟は、この綺麗で、繊細で、脆くて、優しい幼馴染を大切に守り、慈しんできた。
離れていた時間の方がずっと長いし、苛酷な家庭環境に抑圧されていたせいで心を閉ざしていたこともあったが、それでも兄弟は純のためにできることはなんでもした。惜しみない友情と愛情を注いだのだ。
そして何より、度を超えた美貌は様々な危険を呼び込んでしまう。だから二人は楯となり防波堤となって、淫らな触手から純を守ってきたのだ。
しかし高校に入学して、沖兄弟は不安を感じていた。今までのようにちゃんと守りきれるだろうか。この高校に浸透する“悪癖”を知っているだけに、不安はいよいよ増すばかり。
現に今だって、教室の外には2年3年の先輩方が群がって、ぎらぎらした視線を恥ずかしげもなく送りつけている。
直と秀はその視線から純を守るように立っているのだが、野卑な観客はいっこうに諦める気配をみせないのだ。
その不穏な空気に気付いているのかいないのか、純は無邪気に笑って、
「でも3人同じなんてすごい確率だよね。今年の運使い切ったって感じ」
などとのんきなことを言っている。もちろん運がいいとか悪いとか、そんなことではないのだ。純も直も知らないことだが、秀がちゃんと裏で手を回していたのだ。
家の力とか名前を振りかざすことに昔はあれだけ抵抗があったのに、純のことになるとこんなにあっさり使えてしまうんだなと、思わずこぼれる苦笑いすら愛しく感じられてしまう。
秀は「そうだな、運に感謝しよう」と言って、純の頭を優しく撫でた。二人にしか見せない柔らかい微笑みを浮かべて。
「なーなーなー、見た? あの1年」
椅子の背もたれをまたいで後ろ向きに座り、好奇心旺盛な小動物のように大きな瞳を輝かせて訊いてくるのは藤崎薫(ふじさき・かおる)。通称“薫姫”。
その後ろで興味ないと言わんばかりに分厚い推理小説を読んでいるのは、薫の恋人片瀬圭祐(かたせ・けいすけ)だ。
「おう、見たぞ。C組の秋原だろ?」
クラスメートの森下貴志(もりした・たかし)は、精悍な顔に人懐っこい笑みを浮かべて頷いた。どうやら2−Aの教室内でも、純の噂で沸き返っているようだ。
「俺はまだ遠目でしか見てねぇけど、すっごいよな。オーラっていうかさ、そこだけ別世界」
森下の言葉にうんうんと熱烈に頷いて、薫も続けた。
「俺もびっくりしたあ〜。日向とか麻生(あそう)とかさ、美人は見慣れてるけどあそこまでってのはねぇ」
頬を紅潮させてしきりに感心する薫も間違いなく美人なのだが、本人にそんな自覚はないらしい。森下は苦笑しつつも、こいつのこんな所に片瀬は弱いのかねえと、勝手な分析をしてしまう。
「なあなあ、尭村はもう見た? なあ、なあってば」
盛り上がっているすぐ隣の席で、机に突っ伏して寝ている長身の逞しい肩を、薫は容赦なくわしわし揺らす。この男にこんな乱暴な振る舞いができるのは、学園内でも片手に余るほどしかいないはずだ。
「……あんだよ、ぅるせえなあ」
身体を起こす動作はいかにも寝起きでのったりとしているのに、起きた瞬間周囲の空気がぴりりと凍結したように感じられるのは、この男の物騒で剣呑な美貌のゆえだろう。
尭村成仁(あきむら・なるひと)はうざったそうに長めの前髪をかき上げると、小さい息をひとつ吐いた。それだけで眠りの甘い余韻は一掃され、いつもの彼、近寄りがたい空気をまとった、獰猛で冷酷で美しい獣じみた男に戻った。
「お前な、しょっぱなから遅刻して、爆睡はねえだろ」
森下の揶揄にも眉ひとつ動かさず、ちらと冷たい一瞥を投げつけるだけ。
他の男ならその一瞥だけで真っ青になって震え上がり、女なら下腹部あたりにアヤシイ疼きを覚えるだろう。しかし尭村とは小学校からの腐れ縁という森下は、この傲慢を絵に描いたような旧友の不機嫌を笑い飛ばすことができた。
「…で、何の話だよ、藤崎」
「ベリー美人な1年の話っ。尭村はまだ見てねえの? すっごいんだって、日向も真っ青の恐るべき美貌」
「ふ…ん」
尭村の冷淡な反応に、薫はしごく不満げだ。
「おお、そういや日向で思い出したけど、あれは面白かったな」
森下はにやにや笑いながら続けた。
「日向の野郎、式の祝辞思いっきり飛んじまったんだぜ。“えー”なんつってうろたえてよ。あれって壇上から秋原を見たからなんだろ? そのベリー美人な1年だよ。あれは見物だったぜぇ」
「ほー、うろたえる日向か。そいつは見たかったな。惜しいことした。早起きする価値はある」
「だろ? 生徒会の奴らなんて真っ青な顔しておろおろしてよ」
「うん、確かにー。でもさあ、一部の生徒会役員とか日向のシンパとか、あれで秋原に怨み持っちゃってるらしいぜー。僕たちの日向会長に恥をかかせて許せないっ、とか言っちゃって」
「ひでえな、それ。まるで逆恨みじゃねえか」
尭村は眉をひそめた。こんな僅かな表情の変化でさえ、女性の心を捉えるには充分なのだろう。数人のクラスメートが、眼をうるうると潤ませて彼を眺めている。
「ま、秋原の方もさ、あんだけキレイなんだからきっと性格もとんがってるってゆうか、高飛車で俺サマな奴なんだろうけどなっ」
と、薫は勝手に決め付けて、勝手に納得している。
「ミもフタもない言い方すんなあ、藤崎は。でもまあ尭村もよ、見たらきっとビビるぜ。あれだけ綺麗で―――」
「な、る、ひ、とっ。一緒に帰ろうよぅ」
べたべたに甘く作り込んだ声が教室中に響き渡った。尭村はちっ、と舌打ちすると、
「あのクソ女、名前で呼ぶなっつってんのに……」
地を這うような低い声で呟いて荒々しく立ち上がると、さっさと教室を出て行った。残された二人は顔を見合わせて、
「うわー、今のひと、3年だよね。相変わらず根強い年上人気。わざと名前を呼ぶことで、あたしはこぉんなに成仁と親しいのよ、あたしは特別なのよと知らせようとしたわけだ。健気だね、なんとも。でもなんで尭村は名前で呼ばせないんだろ?」
「ああ、あいつ自分の名前嫌いなんだよ。“ナルシスト”みたいでいやなんだとさ」
「なんだ、ぴったりじゃんか」
薫はけらけらと屈託のない笑いをまき散らした。そして、
「そうだよな、尭村はオトコに全く興味なし、だもんなあ……」
BACK TOP NEXT