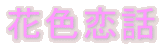
―小さな花屋の物語―
第9話
「ありすがわ…さん……?」
ソファに押し倒され、上から押さえ付けられても優里は怯える素振りも見せず、きょとんとした無防備な眼差しで、徐々に近付いてくる有栖川の顔をじっと見つめた。有栖川はいったん顔を止めると淡く笑い、
「優しくて可愛くていつも一生懸命で、透き通った強さを持っている……。優里さん、今こんなことを言うのは卑怯だと、あなたの苦しい状況を利用していると思われるのを覚悟の上で言います。僕はあなたを愛している」
「…………」
有栖川の告白は、優里の処理能力の範囲を超えていた。その意味を理解し、消化するのに暫く時間がかかると思われたが、その前に有栖川は行動に出た。優里の背中に腕を回して僅かに持ち上げ、そして上から唇を重ねる。
優里は目を閉じるのも呼吸をするのも忘れ、有栖川の温かな唇と心地よい整髪料の香りが感覚に刻み込まれるのを、ただ黙って受け入れた。
「んっ……ふ………」
優里が呼吸も忘れるほど驚いているのは分かっていたから、舌を挿し込んで口腔を味わいたい欲求を抑えてそのまま唇を離した。
もちろん、軽く触れ合わせただけで優里の唇の甘さを十分に堪能することはできたのだが。
有栖川は持ち上げていた優里の身体をソファに戻し、恍惚と呟く。
「なんて柔らかくて甘い……。それに、綺麗な脚……」
押し倒された時の勢いで、フレアスカートの裾が捲り上がって白い太ももまで露わになっていた。有栖川はその無防備すぎる美しさを目を細めて賞翫する。
手のひらを這わせて温もりを写し取りたかったが、さすがにそこまでしたら抑え切れなくなると分かっていた。思わずぽつりと本音を吐く。
「優里さん、あなたは自分がどれほど魅力的か、男を惑わせるか分かっていない……」
「ぁ……ぁ………」
ようやく我を取り戻し始めた優里。とはいえ頭の中は収拾がつかないほどぐちゃぐちゃに乱れ、泣いていいのか怒るべきなのか分からない。分からないまま正直な涙腺は、はらはらと涙を溢れさせた。
「ぅっ……ぅっ………ぇぇっ…………」
有栖川は素早く優里の上からおりて、その身体を抱き起こした。が、
「わっ、優里さん大丈夫ですか? 身体が熱い………」
優里の身体はちょっと触れただけで分かるほど火照っていた。有栖川は慌てて立ち上がり、冷たい飲み物と濡らしたタオルを用意しようとした。その時、
「優里ッ、優里、ここなのっ?」
ドアの向こうから叫ぶ声が。有栖川はすかさず扉を開けて、駆け付けた美咲を中へ招き入れる。
「優里っ、あんたどうしたのっ?」
赤い顔をして泣きじゃくる優里に飛び付き、頭を撫でたり背中をさすったりして宥める。そして傍らに立ち尽くす有栖川をぎっと睨み付け、
「あんた、優里に何したのよッ」
「申し訳ありません。実は―――」
有栖川は正直に告げようとした。しかしその前に優里が力なく首を振り、
「だ、だいじょうぶ。何でもないの………。ごめんね、びっくりさせて……」
そしてひくっひくっと肩を上下させながら美咲にすがり付き、
「も、帰る……。お化粧も、女の子の格好ももう嫌ぁ………早くお父さんのところに帰りたい………」
「分かったわ。着替えもメイク落としも持ってきたからね」
美咲は厳しい表情を向けて、有栖川に命令する。
「あちらへ行っててください。着替えさせますので。それから洗面所はありますか?」
「はい。ご案内します」
有栖川は洗面所の場所を教えると、部屋の外に出た。それから暫くして、いつもの細身ジーンズにシンプルなセーター姿の優里が、美咲に手を引かれて覚束ない歩みで出てきた。
「では、失礼します」
美咲は硬い声で短い挨拶をすると、優里の肩に手を回して寄り添いつつ去っていった。
二人の後ろ姿が見えなくなっても、有栖川はその場に留まって二人の消失点をじっと見つめ続けた。唇に付着したグロスの甘さを反芻しながら。
「優里、もうすぐ家だからね。ほら、しっかり掴まって」
「う、うん……ごめんね、お姉ちゃん………」
優里のこの落ち込みよう。ホストクラブで隆矢と、そして有栖川とも何かあったことは確かだ。だから美咲は敢えて明るくとぼけた声で、
「ホントよぉ。あんた男でしょっ。あたしに頼りきってどうすんのよ」
「ふぇぇ……ほんとにそうだね………ごめんなさぁい………」
ふわふわした声で、それでも真摯に謝る。そして苦しそうに大きく肩で息をした。絡ませた腕からだけで、体温が上昇していることが分かる。
「何が……あったの?」
人間関係のストレスや激しい感情の起伏、環境の変化などに弱い優里は、そういった波に襲われるといつも熱を出してしまうのだ。美咲もそれをよく知っていたから、訊かずにはいられなかった。
優里は俯いてはらはらと涙を流した挙句、
「ぼく……ファーストキス………ぅぅっ………」
「え、ええっ? あの男とっ?」
うんうん頷いて目をこする優里を横目に、美咲は軽い眩暈を覚えた。有栖川に対する怒りももちろんあったが、それよりも想像以上の優里のオクテぶりに対する驚きの方が勝っていた。
―――ああ、優里……あんた可愛いすぎるっ。でも、あんたに惚れた男は苦労するわね……
そんな複雑な感慨を持て余しつつ、ようやく優里の家に着いた。
「ほら、涙拭いて。お父っつぁんが心配するわよ」
「うん…」
言われた通り涙をこしこし拭うと、美咲の手がにゅっと伸びてきて頬をくにくにされた。
「よしよし、いいわね。では、ごめんくださぁーーい、父っつぁん、優里を送ってきましたぁ」
美咲が言い終わらぬうちにどたどたと騒々しい足音が聞こえ、3分の1開いていたシャッターから顔を真っ赤にした司が飛び出してきた。
「優里っ、おまえ〜〜、こんなに遅くなるなんて聞いてなかったぞッ」
すかさず美咲が間に入り、まあまあと宥める。
「あたし達が引き止めちゃったの。優里だってたまには若者とカラオケしたりしないと。いつまでもハコ入りじゃだめ。渡る世間は鬼ばかりなんだから」
「なに訳の分からねえこと言ってやがんだっ。美咲、うちの優坊にヘンなこと教えるんじゃねえぞっ」
美咲は心の中で“だめだこりゃ”と呟いて、はあと溜め息をついた。もしかしたら優里には、1から10まで優しく手ほどきしてくれる、有栖川のような大人の男が必要なのかもしれない。
「じゃね、優里。今日はもう何も考えないで、ゆっくり休みなさい」
「うん、お姉ちゃん。色々ありがと……」
くすんと鼻をすすり上げて、潤んだ目で見つめてくる。いくら男だからって、この可愛さを前にして平静でいられた隆矢も大したものだわ、と美咲は独りごちて、手を振って帰っていった。
「ほら優里、中に入るぞ」
司に肩を抱かれて家の中に入る。ちゃぶ台の上には、優里が用意していった夕食がほとんど手付かずのまま並んでいた。きっと、心配で食べられなかったのだろう。
優里は謝罪の思いも込めて、もう一度温め直そうとした。すると司がぽつりと遠慮がちに、
「優坊、隆矢の奴はどうだった? 元気にしてたか?」
「あ………」
司は今夜、優里がどこで何をしてきたか勘付いていた。しかし敢えて黙って行かせたのだ。そんな父の思い遣りは、今の優里には苦しかった。その場にかくんと膝をつき、
「うん……元気だったよ。とっても……楽しそうで……お店にも溶け込んでて……。ほんと、よかった………」
辛うじて支えていた最後の神経の糸が切れ、優里はそのまま畳の上にふわりと崩れ落ちた。
「すみません、あの……優里さんはまだ………」
「ああ、あんたか。まだ寝込んでるぜ」
司は店先に現れた有栖川にちらと視線を送って、肩を竦めてみせる。諸手を挙げて歓迎するというわけではなかったが、それでも追い返そうとはせず、律儀に優里の様子を教えてやる。
「相変わらず微熱が下がらねえ。飯もロクに食わねえし」
「そうですか……」
司も息子を溺愛しているとはいえ、人の気持ちが分からぬ頑固者ではない。有栖川が心底優里のことを想い、優里の体調を心配するがゆえ、足繁く通ってくるのだとちゃんと分かっていた。
「これを優里さんに。よろしければお父さんもどうぞ。フルーツゼリーです」
「ああ、いつもすまねえな」
有栖川は苦しげに首を振り、店の奥に視線を送る。優里の体調不良は、自分のせいもあるのだ。隆矢のことで混乱し、弱っている状況に付け込んで告白した。しかも―――
―――初めて、だったんですねえ……
唇を重ねた後の優里の反応で分かった。きっと初めてのキスだったのだろう。それを知って嬉しさが込み上げてくるのも確かだったが、それ以上に、優里が受けたショックのことを考えると胸が痛むのも事実だった。
―――大事に大事にされてきたんですね。お父さんや二人のお兄ちゃん、商店街の人たちに守られて………
人々の優しさで温かく潤った土壌。そこに根を張り、ひっそりと秘めやかに、美しい花を咲かせてきた。それを今、自分は、根こそぎ引き抜いて手に入れたいと望んでいる――――
「なああんた。優里に惚れてるのか?」
何の前置きもなく核心を衝く問いを投げかけられて、さすがの有栖川も激しく戸惑った。しかしその問いを突き付けた司は真剣そのもの。有栖川はいったん呼吸を整えて、「はい」と力強く頷いた。
「そうか……。あんた、噂ほど悪い人じゃなさそうだな」
「噂、ですか…。計画に反対する店を追い出したり、店舗の権利書を騙し取ったり、ですか?」
「はは、分かってるじゃねえか」
司はもらったゼリーをしまってくると、有栖川を促して店の外に出た。そして、
「優里はご覧の通り、余り身体が丈夫じゃねえ。いや、弱いのは身体だけじゃない。ちょっとしたストレス、環境の変化にうまく対応できず、すぐに寝込んじまうんだ。
母ちゃんを早くに亡くしてるから、不憫さも手伝って大事にしすぎた部分もある。それは俺の責任だ。分かっちゃいるんだけどな……」
「確かに優里さんは繊細で、身体も丈夫ではないかもしれません。でも確固たる自分というものを持っていて、それを貫こうとする強さがある。
それは、お父さんやこの商店街の人たちの愛情があってこそ、育まれたものだと僕は思います」
「ははっ、カッコいいこと言うな、あんたは………」
司は乾いた笑いを漏らした。しかしすぐに表情を引き締めて、
「なんつうか、うまく言えねえけど優里のことを頼む。俺もいつまで働けるか分からん。いや、あと10年20年は大丈夫と高を括っていたんだが―――」
「どこかお悪いのですか?」
「ここが痛い、あそこが苦しいってわけじゃねえんだが、何だか最近調子が狂っててな。朝起きたら眩暈はするし。なんか右手は痺れるし。まあ、それだけのことなんだが」
有栖川は眉根を寄せて、
「一度、検査を受けられてはいかがですか。よろしければ病院を紹介しますよ」
「ま、まあそんな大袈裟に騒ぐほどのことでもないんだが。でも近いうちに検査は受けるよ。それよりこのことは優里には―――」
有栖川が「もちろん、言いませんよ」と返すと、司はほっとした様子で小さく頷いた。有栖川はふっと息を吐き、
「本当は……隆矢さんにお願いするつもりだったのでしょう?」
「ん……まあな。でも駄目だ、あいつは。まだ柾矢の影を引きずってやがる。それから逃れようと必死にもがいているんだ」
司の意外な指摘を、有栖川は息を詰めて聞き入る。
「あいつはな、店を継ぐのが嫌なんじゃない。継いだ上でやっぱりお前じゃ駄目だ、柾矢の方が良かったと言われるのが恐いんだ。バカな奴だ、誰がそんなこと言うもんか。柾矢は柾矢、隆矢は隆矢だ。どっちがいいとか悪いとか、そんなもんじゃねえ。誰も、誰かの代わりになんてなれねえのによ」
「……お父さんの仰る通りです」
そう、自分は隆矢の代わりにはなれない―――
「だからな、俺にもしものことがあったらあいつを支えてやってくれよ。ま、当分くたばる予定はねえけどよ」
有栖川は笑って頷いた。でも検査はちゃんと受けてくださいよ、と念押しは忘れずに。
「ちっ、お節介な野郎だ。医者は嫌いなんだよ。人の顔見りゃすぐ酒をやめろ酒をやめろってな」
「お医者さまのアドバイスをないがしろにしてはいけません」
「へえへえ分かりました」
司は肩を竦めて背中を向け、店の中に戻っていった。その精悍な後ろ姿は、説明会の会場で見た時より幾分縮んで見えた。
「優里、優坊、どうだ調子は」
「あ、うん……だいぶいいよ。明日からはお店に出られそう」
「そうか。無理するなよ。ほれ、差し入れ」
父の無骨な手には不似合いな、パステルカラーの包み。優里はちょっと首を傾げて見つめる。
「あの代理店の男からだ。フルーツゼリーだとよ。食うか?」
途端に優里の胸は早打ちを始める。起き上がって震える手で包みを受け取り、
「有栖川さん……来てたの?」
「おお。お前がぶっ倒れてからこれで3度目だ。心配そうにしてたぞ」
優里はかさこそと音をたてて包みを解き、箱の中からゼリーを取り出す。オレンジの皮が入れ物になっており、中身をくり抜いた中にオレンジゼリーが入っている。
「何とまあ洒落たもんだな。俺にも残しておいてくれよ。じゃ、店に戻るからな」
父の言葉に耳を傾けつつ、スプーンですくって口に運ぶ。
「ん……あまずっぱい………」
爽やかなオレンジの甘さと共に、有栖川の笑顔が浮かぶ。
―――僕はあなたを愛している
優里は慌てて頭を振って、耳の奥で反響する有栖川の言葉を消そうとした。しかし消そうとすればするほど、整髪料の匂いや唇の温かさを伴ってより鮮烈に蘇ってくる。
―――そんな…ことあるはずないもん。僕みたいな子供で、何の取り柄もなくて、暗くて、しかも男で………
「ふふっ……しょっぱい………」
スプーンですくったゼリーの上に、ぱらぱらと涙が降りかかる。何で涙が出るのか……
「こわ…い………」
そう、恐かった。有栖川の優しさが。そして、その優しさによろめいてしまいそうになる弱い自分の存在が。
それは、これまで大事に大事に慈しんできた隆矢への恋心に付いた、小さな瑕だった。
BACK TOP NEXT