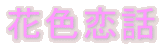
―小さな花屋の物語―
第10話
「あ……」
その時、心は嫌な音をたてて軋んだけれど、優里は何とか笑顔を拵えていつも通り明るく「お兄ちゃんっ」と駆け寄った。対して隆矢は視線を泳がせつつ、「久しぶりだな」と曖昧な笑みを浮かべる。
二人の間で何かが変わってしまったことを如実に知らしめる、重苦しい空気が漂う。
「あの……お兄ちゃん、この前はごめんね。ホストクラブってどんなとこなのかなあって単純に興味があったから、ちょっと行ってみただけなんだ」
「あ、ああ。俺も悪かった。あんな道の真ん中で怒鳴ったりして」
それきり二人は俯いてしまう。言いたいのはこんなことじゃない、けれどそれが何なのかよく分からない、言葉にできない。そんなもどかしさに叫び出したくなる。
「あ、優里……お前具合悪かったのか?」
「え、なんで…?」
「い、いや、何度か店の前を通りかかったんだけど、お前の姿が見えなかったから」
「ん…大丈夫。いつもの知恵熱だから。今回はちょっと長引いちゃったけど」
隆矢は苦しそうに眉根を寄せて、「俺のせいか…」と力なく呟く。優里は慌てて首を振って、
「ち、ちがうよ、えと、あの、あ、有栖川さんが―――」
途中まで言いかけてはたと口を噤む。もちろんこの先なんて言えるはずがない。しかし隆矢は、額に険しい翳を落として優里に詰め寄る。
「有栖川だって!? あの男に何かされたのかっ?」
「あ、あの………」
愛してるって言われて、そしてキスされたの―――もしそう告げたら、隆矢はどんな反応を見せるだろうか。
なんだその程度のことかと笑うか、嘘つけと額を小突くか、気持ち悪いと嫌悪を滲ませるか、それとも、それとも少しは怒ってくれるだろうか。俺の優里に何てことするんだ、と―――
「何でも、何でもないよ。それよりお兄ちゃん、今度はどんな人なの?」
「えっ?」
「ブーケ、頼みに来たんでしょ?」
「あ、ああ……よく分かったな」
優里はにっこり笑って、明るい声でおどけてみせる。
「そりゃ分かるよぉ。だってお兄ちゃんがわざわざ僕に会いに来てくれるのは、ブーケを頼む時だけだもん」
分かりきった事実をそのまま口にしただけなのに、どうしてこんなに胸が痛むのだろう、瞳の奥が熱くなってくるのだろう。それでも優里は笑顔を崩さず、「今度こそうまくいくといいね」とお決まりの台詞を言う。
「ああ、頼むよ優里。お前の力を貸してくれ」
「うんっ」
その瞬間、隆矢はあの音を聞いた。自分にしか察知できない小さな小さな音。優里の心が壊れる音―――
「ねえねえ、今度はどんな人? 予算は?」
そんなはずはない。だって、目の前の優里はこうしてにこやかに笑っているじゃ―――
「笑って……ない………」
「え?」
「お前、笑ってねえよ」
それは確かに“笑顔”の形をしていた。いつも見慣れている優里の顔。なのに今やっと気付いた。これは笑顔ではない。これは、これは―――
―――泣くまいと必死にこらえている子供の顔だ……
「おにい…ちゃ………」
隆矢は両手を伸ばして優里の頬をそっと手のひらで包み込み、指先で目尻を撫でる。するとこれまで頑なに不動を維持していた黒瞳が、ふるふると揺れ始めた。
「や…だ……お兄ちゃん……そんな………」
慈しむような優しい目で見ないでっ―――優里は喉の奥で叫び、隆矢の手を振り払おうとした。その時、隆矢のポケットから軽薄な電子音が。
二人ははっと我に返る。優里はあたふたと目をこすり、隆矢は急いで携帯を取り出す。
「はい………あっ、ああ、もちろんだよ………えっ? 今? でも………わ、分かった、行くよ。必ず行くから待っててくれよ―――」
隆矢は電話を切ると、優里に向かって頭を下げた。
「悪い、優里っ。ブーケ大至急頼む。俺のお客さんなんだけど、その、俺がヘマして怒らせちまったんだ。上客だったから店にとってもすげえ損失だし、何とか許してもらって、もう一度来てもらえるようにしなくちゃならない」
「その…お客さんとこれから会うの?」
「ああ、待ち合わせて一緒に店に行くはずだった。なのに今すぐ会いに来いって。俺の本気を確かめたいんだとさ。だから―――」
優里は「そっか…」と疲れたように答えて、それでも自分の務めを果たそうと「で、どんな人なの?」と訊ねた。が、
「いや、もう時間がないから、とにかく派手なやつ作ってくれ。金は幾らかかってもいいから」
「あ、うん……分かった」
「なるべく急いでくれな。ごめんな、無理なこと言って」
「ううん、いいよお。お兄ちゃんの頼みだもん」
優里はそう言いながらも花の選定を始める。しかしどんなイメージも湧かず、ケースに向かって伸びた手は宙で止まってしまう。これまでは、花束を贈られる人についてあれこれ想像を巡らし、受け取った時の笑顔を思い浮かべて作っていたから。
「派手で……豪華な花束………」
優里はぶつぶつ呟きながら、ともかく薔薇や百合などの大振りで高価な花を引き抜いて、手際よくまとめていった。
それは確かに豪華で美しいブーケだった。けれど、何の個性もない社交辞令の贈り物。取り敢えず花でも贈っておこう―――そんな囁きが聞こえてきそうな。
優里は一瞬、こんな花束を贈られる人が不憫に思えたが、それは自分の価値観の押し付けだと気付いて慌てて頭を振って払った。
「お待たせしました………こんな感じでいい?」
隆矢は出来上がった花束をじっと見つめ、
「すげえ。さすがだな。無駄に派手で豪華で……イメージ通りだ。………優里、こんなブーケをお前に作らせちまってごめん」
「お兄…ちゃん……」
隆矢は恥じ入るように俯いたまま1万円札2枚をそっと置いて、短い挨拶を残して店を飛び出した。
「あっ、待っ―――」
お金を半分返そうと、1万円をポケットに突っ込んで隆矢の後を追う。しかし花束を抱えた長身を追っているうちに、本当の目的はお金を返すことではなく、隆矢が女性に花束を捧げる姿を目に灼き付けることなんだと気付いた。
そうすることで、今度こそ本当に隆矢のことを諦める。長く不毛な恋に決着を付けるために―――
―――もっと早く、こうすべきだったんだ
分かっていた。自分が拵えたブーケを笑顔と共に恭しく捧げる隆矢の姿を網膜に刻み込んで、自分を傷付けることでしか隆矢への想いを断つことはできないだろうと。
でも、分かっていたけど恐かった。できることなら、このささやかな宝物をずっと胸にしまって大事に慈しんでいたかった。たとえ成就することはなくても。
これが、これだけが、幼い頃から自分を支え導いてくれた光明だったのだから―――
―――でも、もうおしまい……
隆矢は、小さな橋のたもとで止まった。辺りはすでに暗く、人影もない。花束を抱えたままきょろきょろしていると、カツカツと鋭い靴音を響かせて背の高い女性が近付いてきた。
街路樹の陰に隠れて、優里は二人の様子を窺う。風がそよぐと、彼女のものと思しき香水の匂いが優里のもとまで漂ってきた。
「先週はごめんな。言い訳はしないよ。でも、君が来てくれないと淋しくて、店に出る気も失せるんだ。だから―――」
隆矢は彼女に近付いて、抱えていた花束を彼女の胸に押し当てる。
「また来てくれよ。待ってるからさ」
優里の場所からだと、彼女の表情までは見えない。しかし黙って手を伸ばして、渡された花束を受け取ったのは分かった。が、次の瞬間―――
「なっ、何を……」
隆矢は驚いて絶句する。彼女は花束を逆さにして乱暴に振り出したのだ。そしてきっと顔を上げて、嘲るような歪んだ笑みを浮かべ、
「なによ、花だけなの? 中に宝石でも入ってるかと思った。この程度で呼び戻そうだなんてバカにしてるわっ」
甲高い声でそう叫ぶと、花束を振り上げて隆矢の足下に叩き付けた。
「じゃあね。あたしこれから約束があるから」
刺々しい捨て台詞を投げ付けて、振り向きもせずその場を去っていった。隆矢は苦い溜め息を吐き、足下の花束を拾おうとする。が、背後から近付く人影に気付き振り返ると、
「優里……お前なんでここに………」
しかし優里はその問いに答えず、ゆっくり近付きながら、
「ごめんね……ごめんねぇ………」
苦しげな謝罪を繰り返す。そして隆矢の前にぺたんと座り込んだ。
「ごめんね……」
隆矢は始め、自分に謝っているのかと思った。しかし優里は、足下に散らばる花たちに謝っていたのだ。
「ひどい……こんな、こんな………」
叩き付けられた衝撃でもげた蕾や散った花びらを、ひとつひとつ摘まんでエプロンの上に乗せる。ぽつぽつと涙が降りかかるが、それを拭おうともせず丁寧に拾い集め、最後にぐしゃぐしゃになった花束を拾い上げてそっと頬を寄せる。
可哀想な花たち。本当なら、笑顔で贈られ、笑顔で受け取られ、朽ちて散るまで「きれいだねえ」と愛でられるはずだったのに―――
「も、いや……もう、お兄ちゃんにはブーケ作らないっ………」
「優里……」
隆矢は返す言葉もなく、その場に呆然と立ち尽くす。優里は花がこぼれないようにエプロンの裾を持って立ち上がり、そのままくるりと踵を返して隆矢の前から去っていった。
そして小さな後ろ姿が完全に闇に融けてしまって、隆矢はようやく気付いた。たった今、大事なものが失われてしまったのだということに。
店に戻った優里は、持ち帰った花束を取り敢えず大きな花瓶に移した。落ちたスプレーバラの蕾は水を張ったボウルに浮かべたけれど、散った花びらはもうどうしようもない。
「んっ、く………ぇ、ぇぇっ…………」
路上に叩き付けられ散った花。無意味な感傷に過ぎないと分かってはいるけれど、決して受け入れられず散る運命にある自分の想いと重なって見えてしまう。
「ごめんね……」
花びらを処分してぎゅっと涙を拭い、いつもの閉店業務に取り掛かった。レジ閉めをして売上計算をし、簡単な掃き掃除をしてシャッターを下ろす。そして夕食の仕度をしている父の手伝いをしようと台所へ。しかし父の姿は見えない。
「お父さん? どこ?」
台所を出て居間に行こうとした時、階段に手を付いて額を押さえている父の姿が目に入った。
「お、お父さんっ。どうしたの? どこが具合が―――」
司はぎこちない動きで優里の方を向いて、
「おお、優坊……ちょっと眩暈がな………はは、大丈夫だ………」
「待ってて。今すぐお布団敷くから。暫く横になって―――」
優里が言い終わらぬうちに、ドサリと鈍い音をたてて司が倒れた。
「お父さんっ、お父さんしっかりしてっ」
駆け寄って肩を揺さぶり必死に呼びかけるが、完全に意識を失してしまったのか全く反応がない。
「や、やだ……やだよおおぉぉぉ………」
優里はがくがくと震える膝を叱咤して電話まで辿り着き、泣きながら救急車を呼んだ。
―――お父さん、お父さん、ごめんね……
―――血栓が脳の血管に詰まっています。脳梗塞です
―――僕、自分のことばっかりで……
―――半身の痺れや眩暈などはありませんでしたか? もう少し早く診察を受けてもらえたら……
―――気付いてあげられなかった。お父さんにもしものことがあったら……僕の責任だ………
「ん………」
誰かが頭を撫でている。優しくて温かくて大きな手。
「まぶし……」
優里はゆるゆると目を開けて、顔を上げた。真っ白なベッド、消毒薬の臭い、朝日、小鳥の囀り、そして―――
「お…父さん………」
うっすら目を開けて、温かい眼差しでこちらを見つめる父―――
「お父さんっ」
優里は慌てて手を握り、父の顔を覗き込む。司は言葉を返す代わりに淡く笑い、優里の手を握り返した。
いつもの彼からは想像もつかないほど弱々しい力だったが、込められた想いの強さは何ものにも勝る。
「ごめんね、僕……何もかもお父さんに頼りきりで、何にも力になれなかった……。具合が悪いのにも気付かないで、自分のことばっかり………」
司の手が微かに震えた。優里が手を離すと、無骨な指先が伸びて溢れる涙を拭ってくれた。ぎこちない手付き。でも、温かい指先。
「ぅぇっ……ぇっ、ぇっ………お父さぁん………」
すると指先は優里の頬から離れ、ぶるぶる震えながらも親指をにゅっと突き上げた。
―――だぁいじょうぶだ、優坊。心配すんな
優里は天を衝く親指をじっと見つめると、涙に濡れた顔を笑顔に変えて頷いた。
「ナースステーションに知らせるね」
意識が回復したらすぐ知らせてくださいと言われていたのだ。ナースコールを押して伝えると、ほどなく医師と看護師が現れた。
暫し専門用語が飛び交う会話がなされたのち、カーテンを引いて出てきた医師は「もう大丈夫ですよ」とにっこり笑った。
「あ……ありがとうございます」
「では、後で構いませんので入院手続をお願いします。それから、今後の治療法について主治医から説明がありますので、ご家族の方よろしくお願いしますね」
「はい……」
家族は自分一人。全てが自分の背中にかかっている―――
優里はもう一度医師に礼を言うと、電話をするため部屋の外に出た。と同時に、複数の声に名前を呼ばれる。
「徹矢おじさん………相太にいちゃん、美咲お姉ちゃんも………」
「父っつぁんはどうしたっ?」
「うん、意識は回復したよ。もう大丈夫だって先生が」
「そうか、意識が戻ったか……よかった、ひとまず安心だ」
みな、一斉にへなへなと座り込む。優里は再び涙が出そうになるのをこらえて、
「ありがと……ほんとにありがと………」
先の見えない不安やのしかかる責任に押し潰されそうだった心が、少し軽くなるのを感じた。そうだ、僕はひとりじゃない―――
「優里さんっ、ああ、よかった、すぐに見つかって……」
「あ、有栖川さん……どうしてここに………」
有栖川は珍しく髪を乱し、息を切らせて優里たちのもとへ駆け寄る。徹矢は思い切り険しい皺を眉間に刻んで、
「何であんたがここに来るんだ」
しかし有栖川は気にせず、淡々と説明する。
「今朝お店の方に伺ったら、シャッターが閉まったままだったのです。もしや何かあったのかと思って商店街の方に訊ねたら、美園さんが………」
有栖川は喉を詰まらせ、悲愴な顔付きで押し黙る。
「有栖川さん、心配しないで。意識も回復しましたし、先生ももう大丈夫だ、って」
「本当に?………ああ、よかった………」
そしてさっきの徹矢たち同様、へなへなと座り込む。徹矢は仏頂面で近付くと、ぬっと手を差し伸べて、
「大の男がみっともねえな。おら、掴まれ」
「自分だってさっき腰抜かしたくせに」
「うるせえな、美咲は。そういう細かいこと言ってっから嫁に行けねえんだ」
「余計なお世話よっ………って、ゆ、優里大丈夫? ごめん、こんなとこで騒いじゃって……」
優里は両手で顔を覆ったまま、何度も首を振った。
「みんな……ありがと………」
大丈夫、僕はひとりじゃないと分かったからひとりでも頑張れる。でも、今一番傍にいて支えて欲しい人は―――ここにはいない。
BACK TOP NEXT