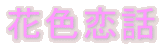
―小さな花屋の物語―
第8話
目を閉じると、暗闇の中に二本の道が浮かび上がる。優里の道と隆矢の道。それはこれまで交わることはなかったけれど、ずっと平行線のままだったけれど、それでも常に最も近くに寄り添って、真っ直ぐ続いていた。
でも―――
「道が……離れてゆく………」
二本の道は角度を変え、ゆっくりと離れようとしていた。もう、修正はきかない。
―――もしかしたら、もう二度と会えないかも………
そんなことあるはずない、お兄ちゃんはお兄ちゃんなんだしと必死に打ち消そうとするけれど、たった今見せつけられた世界の断絶は余りに強烈な印象を刻んで、優里の胸をこれでもかと痛め付けた。
「ぅっ……ぇぇっ………お兄…ちゃ…………」
ほとんど人通りのない商店街。その敷石の上に涙の雫がぽたぽた降りかかる。優里は履き慣れぬ華奢な靴の底でその跡をそっとこすり、再びとぼとぼと歩き出した。
これで良かったんだ。やっと諦められる。余りに長く、そして不毛な恋。誰の目に留まることなく、もちろん愛でられることもなく、日の当たらぬ冷たい場所で秘めやかに咲き続けるだけの花。もう、摘み取ってやる時が来たのかもしれない。
このまま花が色褪せて、醜く朽ちて腐ってゆくだけなら、潔く根元から切り落としてしまった方が―――
「でもっ……でも…………」
そんなことできないと、誰よりもよく分かっているのは他ならぬ自分。結局こうして想いを引きずったまま、べそべそ泣き暮らすしかできないのだ。
「ふぇっ……ぇっ、ぇっ…………」
再び溢れ始めた涙を手でぐいっと拭うと、黒いものが付着した。一瞬、悲しみが涙まで黒く染め上げてしまったのかと思ったが、すぐにはたと気付いた。目をこすっちゃだめよ、という美咲の言葉を思い出したのだ。
「ど、どうしよう………も、やだ…………」
きっと今自分は、お化けみたいな顔をしているに違いない。何て惨めで滑稽な姿。優里は顔を上げることができず、俯いたまま歩いた。
駅の中を通り抜ければ早いけれど、この顔と格好を人目に晒すのはもう耐えられない。少し遠回りになるけれど、駅をぐるりと迂回して帰ることにした。
駅の横を通り、高架線の下をくぐって向こう口に出る。右手には小さな公園。隆矢に「もうお前のお守りはごめんだ」という言葉を投げ付けられた場所。優里はそちらを見ることができず、顔を背けて足を速めた。その時、
「優里ッ、優里、待て!」
背後から聞き慣れた声が呼び止める。大好きな人の声は、怒りと苛立ちで尖っていた。
「おにい…ちゃん………」
優里はその場で足を止めたが、振り向くことができない。咄嗟に両手で顔を覆い、激しく首を振る。
「優里っ、何であんなところに来たんだ。俺が分からないとでも思ったか?」
隆矢は怒りを隠そうとせず、厳しく問い詰めながら優里の背中に近付く。
「こんな遅い時間に………しかもあんな空気の悪いところ。それにお前、まだ未成年だろが」
優里は顔を覆ったまま「来ないでッ」と鋭く叫ぶと、そのまま逃げるように駆け出した。もちろん隆矢は慌てて追い駆ける。
「待てッ、優里―――」
二人の距離はすぐに縮まった。隆矢は手を伸ばして優里の肩を掴もうとする。しかしその時、物陰から突然人影が現れて優里の身体を抱き取った。
「あ、あんたは………」
有栖川は渡さないという意志を込めて、腕の中の優里をぎゅぅっと抱き締める。隆矢は、普段の彼からは想像できぬ、険のある翳を刻んだ視線で睨み付け、「優里を返せ」と詰め寄った。しかし、
「いや……見ないで、見ないで…………」
尚も顔を覆って必死に訴える優里の背中を、有栖川は安心させるようにぽんぽんと叩き、
「返せ、ですか? もともと君のものでもないのに」
「なん……だと………」
「それに今は仕事中でしょう? 途中で抜け出して、優里さんを掴まえて、どうするおつもりですか。結局、何もかも中途半端なんだ、君は」
口調は柔らかいが、隆矢に向けて発した言葉、単語のひとつひとつは明確な怒りを孕んで、ざわざわと漣(なみう)っていた。有栖川は、自分の胸元で小さく震える優里の頭にそっとキスを落とし、
「優里さんは渡しません。あなたにも、他の誰にも」
静かに告げて、その告白の重みで目の前の隆矢を圧倒した。隆矢は何か言い返そうとしたが、自分には有栖川に対抗できるだけのどんな言葉も持ち合わせていないことを今さらながらに覚り、唇を噛み締めて見返すことしかできなかった。
隆矢は改めて痛感した。自分という人間は、本当に空っぽなのだということを。
「………優里を頼む。ちゃんと送ってやってくれ」
こんなことを言えた義理ではないが、と自嘲しつつ有栖川を見つめると、真剣な表情で力強い頷きを返してくれた。そう、これでいいんだ。この人になら任せられる。これでいいんだよな、柾兄…………
隆矢は潔く背中を向けると、その場から走り去った。
「………優里さん、もう大丈夫ですよ。あの人は行ってしまいました。さあ、顔を上げてご覧なさい」
優しい促しを受けて、優里は両手で隠したままそっと顔を上げた。
「み、見ないでください……僕、すごく変な顔してるの………」
有栖川はふわりと綿毛のような笑みを浮かべて優里の手を包み込むように掴み、ゆっくりと顔から引き剥がしていった。
「優里さん、こちらを向いて。僕の前でそんな俯く必要はありません」
嗚咽を押し込めるように唇を噛んで、ゆるゆると顔を上げる優里。確かにアイラインが涙のせいか少し滲んでいたが、濡れた瞳と相俟って妖しく懶惰な色気を醸していた。普段の楚々とした魅力とは対照的な、淫靡とさえいえる危うい美しさ。
ああやはり。やはりこの人はまだまだ蕾なのだ。こうして時折、蕾が孕む濃厚で甘美な馥りをちらと垣間見せて男の理性を蕩かす。
有栖川は、滅多に騒ぎ出すことのない雄の脈動が早打ちを始めたのを明瞭に意識しつつ、ゆったりと笑みを深めて優里の髪を、頬を撫で、
「変な顔だなんて、とんでもない。このふわふわにカールした髪も、薔薇色の唇も、白いジャケットもとてもよく似合っています。でも…僕はいつものあなたが、細身のジーンズの上にエプロンをして、楽しそうに花々と対話しているあなたの方が好きです」
「有栖川……さん………」
「だからまた、いつもの笑顔を見せてくださいね」
瞬きもせず大きく見開かれた瞳が震えたと思ったら、目尻から涙の珠がひとつ、またひとつと生まれこぼれ落ちた。苦しそうにしゃくり上げる優里の背中をさすり、
「優里さん、今は泣いてもいいのですよ」
その言葉に弾かれるように有栖川の胸に飛び込み、ジャケットの襟を掴んでわんわん泣いた。
「そう、泣いて、泣いて………そして全てを流して…………」
空っぽになった心を、僕が満たしてあげるから――――
自分以外の腕に抱かれ、小さく震える華奢な肩―――
「これで……いいんだ………これで…………」
そう、これで自分をあの場所に縛り付けるものはなくなった。柾矢に託されたものを全て捨て、やっと自分らしい生き方ができるはず。なのに―――
「なんで……涙が出そうになるんだ………」
本当は分かっていた。あらゆるしがらみから解放された自由なんて美しくも楽しくもなく、ただ侘しくて虚しくて、途轍もない孤独の重みに耐えねばならないことを。
隆矢は、先刻優里が泣きながら歩いて涙の痕跡を刻んだ道を、俯いたままとぼとぼと戻っていた。すると、前方から険しい怒鳴り声が。
「隆矢ッ、貴様どこで何してたんだっ!」
店のオーナーが怒りの形相で駆け寄り、隆矢の胸倉を掴んで激しく揺さぶる。
「あ、いえ、ちょっと客を送りに………」
「お前はバカか! 自分の客を放っておいて他の客送りに行く奴があるかッ。しかも、お前をあんなに気に入ってくれてるふっとい客をっ。怒って帰っちまったぞ!」
「えっ? あ、やべ………」
「やべえどころじゃねえぞ、どうしてくれるんだッ。こんな田舎のホストクラブで、あれだけ落としてくれる客はそういねえんだ。いいか、すぐに死ぬ気でフォローしろ。分かったなっ」
結局、君は何もかもが中途半端なんだ―――有栖川の言葉を噛み締めながら、隆矢は膝に手を付いてがっくりと項垂れた。
「さあ、どうぞ。あ、足もと気をつけて―――」
有栖川に手を引かれるまま連れてこられたのは、駅前にあるビルの最上階。優里は泣き腫らした目で辺りをぐるりと見回し、
「あの、ここは………」
「はい、僕の仮事務所です。もうじきここは畳んで、本社の方に戻ることになると思いますが」
仮の事務所の割りには、デスクやキャビネット、来客用のソファも洗練されたデザインのものを使っていた。現代彫刻のように優雅なフォルムのフロアランプを灯すと、琥珀色の微妙な陰翳が室内を彩る。神秘的でありながら温かみのある、寛ぎの空間へと変じた。
「先に、連絡をした方が良さそうですね」
有栖川の促しを受けて、優里は美咲に電話した。ごく簡単に事情を話すと、すぐに着替えとメイク落としを持ってきてくれるという。有栖川に教えられた通りビルの名前と場所を告げて、電話を切った。
「どうでした?」
「すぐに来てくれるって……」
「そうですか。それは良かった」
優里はこくんと頷いて、ふぅっと息を吐く。そして改めて有栖川にお礼を言おうと顔を上げると、スーツの襟が汚れていることに気付いた。「あっ」と小さく声を上げ、
「ごめんなさいっ………あの、スーツの襟……僕が顔を付けちゃったから……どうしよう、どうしよう………」
有栖川は襟をつまんで「ああ」と笑い、
「気にしないで。僕が望んだのですから。優里さんの涙を拭うハンカチになりたいって。そのくらいしか、してあげられることはないですから……」
少し淋しそうにそう言いながら手を引き、奥のソファに座るよう勧める。優里は申し訳なさそうに項垂れたまま大人しく従う。その時、甘くふくよかな芳香が鼻を掠めた。
思わずふっと顔を上げ、香りの源を探す。それはすぐに見つかった。キャビネットの上のガラス瓶に、大輪のカサブランカ。たった一輪なのに、この空間を艶やかに華やかに染め上げている。
「ああ……なんて綺麗。それにこの馥り………」
カサブランカの美しさも芳しさも、よく知っているつもりだった。しかしたった一輪のカサブランカがこれほどの存在感を放つものだと、今改めて思い知った。
いつも溢れんばかりの花々に囲まれて、それが当たり前になっていたから気付くことができなかった。優里の深い感慨に同調するように、有栖川もゆったり頷き、
「本当に美しい。優雅でいて、尚且つ無駄がない。この事務所のインテリアはね、全てイタリアの有名デザイナーのものなんです。しかしこの空間を支配しているのは紛れもなく、このたった一輪のカサブランカ………」
琥珀色の秘めやかな空間を乱さぬよう、静かに移動して優里の隣に腰を下ろす。
「キリストは、栄華を極めたソロモン王でさえ、野に咲く花ほどにも着飾っていなかったと言ったそうです。僕は無神論者ですが、この美しいフォルムを眺めていると、神というものの存在を信じてしまいそうになる。でも………」
有栖川は優里の腰にふわりと腕を回す。その余りの細さが胸を締め付けるが、敢えて淡々と言葉を続けた。
「でも、一輪の花の美しさを僕に教えてくれたのは、優里さん、あなたなんですよ」
「有栖川さん……ぼく、ぼくは………」
再び顔を覆って泣こうとする優里の手を掴んで、自分の背中に回す。しかし優里は遠慮がちに身体を強張らせて、有栖川の寛い胸に凭れようとはしない。そのまま顔を上げて濡れた瞳でじっと見つめ、
「有栖川さんの言った通りでした。ホストクラブは騒々しくて空気が悪くて、ちっとも楽しくなんかない。豪華な花瓶に作り物の花を活けるような、そんな所でした。
でも、でも、お兄ちゃんはそこで生き生きと、楽しそうに働いてた。商店街では見つけられなかった自分の場所を、ちゃんと確保していたのです。
だから―――」
喉がひりひりして苦しかったけれど、痞えている苦い言葉たちを吐き出そうとお腹に力を入れる。そして再び口を開いた。
「だからよかった、って………これで……よかったの………おにいちゃんが……幸せになってくれれば………ぼく…………」
「好き…なんだね?」
有栖川の静かな問いに、たった一度頷きを返す。そして震える唇から、迸る想いを乗せた言葉を紡ぎ出す。
「この想いが……実ることはないと分かっていました……それでも、傍にいて、あの優しい笑顔に触れていられれば……僕はそれだけで幸せだったの………できることならこのままずっと、ずっと一緒に、って。でも……もうおしまい。これで………」
優里はもうこれ以上、自分の力で自分を支えていることができなかった。目の前の寛い胸に身体を預け、浅い呼吸を繰り返す。
このまますーっと呼吸が止まって、そして腕の中でふっと消えてしまうのではないかという悪夢めいた妄想に襲われた有栖川が、抱き締める腕に力を込めようとした時、
「大人になんか……なりたくなかった……ずっと、ずっと子供のままでいたかった……そうしたら―――」
この華奢な腕のどこにそれほどの力が眠っていたのかと思うほど、強く激しく有栖川の身体に縋りつき、そして喉を嗄らして叫んだ。
「こんな痛みを味わわずに済んだのにッ!」
「優里っ―――」
有栖川もまた、切迫した声で優里の名を叫び、胸が潰れて息が止まるほどの激しい抱擁を与えた。
そのままどれくらいの時間が経過しただろう。有栖川の背中に爪を立ててしがみ付いていた優里の腕が、だらりと弛緩した。
有栖川はゆっくりと身体を離し、そして―――優里の身体をその場に押し倒して覆いかぶさり、ゆっくり顔を近付けていった――――
BACK TOP NEXT