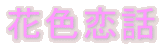
―小さな花屋の物語―
第7話
隆矢が商店街を出て行ってからどのくらい経っただろう。もう何年も会っていないような淋しさもあるし、ほんの昨日のことのようにも思える。実際には、二週間が経とうとしていた。
その間、有栖川は幾度となく店を訪れては、売れ残りそうなサービス用花束を買っていった。少し古いものですからお値引きしますと優里が言っても、頑なに首に振ってそのままの値段で買い、大事そうに抱えて帰ってゆく。
そして時にはささやかな贈り物を持ってきた。ジャスミンの馥りのルームキャンドル、バラのジャム、イルカの小さなフォトブック、さらに――――
「はい、プレゼント。これ、何だか分かりますか?」
優里は渡された小さな花束をじっと見つめた。色鮮やかな、ガラス細工の薔薇のような…………
「あ、もしかして………キャンディ?」
「当たりです。飴細工。綺麗でしょう?」
優里は鼻を近付けてくんくんと嗅いでみた。しかしビニール包装されているためか期待したような甘い匂いはせず、ちょっと首を傾げてみせる。その無邪気な仕草を、有栖川は目を細めて愛でる。
「とってもきれい……食べるのがもったいないです」
「それはいけません。ちゃんと食べてくださいね。それとも、甘いものはお嫌いですか?」
優里はふるふると首を振って、「だいすきです」と答える。そしてにっこり笑ってお礼を言う。しかしその笑顔は、有栖川の記憶の最良の部分に刻まれた笑顔とはかけ離れたものだった。
有栖川は胸の痛みをこらえて、この二週間でやつれてしまった頬をそっと撫でる。大好きな人の温もりをを思い出してしまったのか、優里は切なげに眉根を寄せて力なく項垂れた。と思ったらぱっと顔を上げて、
「あの……有栖川さん、ホストクラブって、その、どんなところなんですか?」
「ホストクラブ、ですか?」
有栖川は驚いたように反問したものの、もちろん優里が何故そんなことを気に掛けるのか分かっていた。
しかし、今目の前にいる有栖川が隆矢をホストに引き抜いた張本人だとは夢にも思わぬ優里は、身を乗り出して問いを重ねた。
「あ、あの……えと……い、いやらしいこととかするところなんですか……?」
有栖川は思わず吹き出しそうになるが、何とかこらえて真面目な表情を守った。見れば、優里は不安を押し隠した真剣な眼差しで、有栖川の答えを待っている。
「残念ながら詳しくは知りませんが、そういうことをするお店ではないと思います。まあ女性に奉仕するのですから、肩を抱いたり手を握ったり、その程度の触れ合いはあるでしょうが」
優里はきゅっと唇を噛んで、再び俯いてしまう。その肩にそっと手を置いて、
「ホストクラブに、興味があるのですか?」
「いえ、そういうわけでは……」
「お止めなさい。あなたが行くような場所ではありませんよ。騒々しくて、下品で……」
優里は苦しげに息を吐いて、
「そんなに……嫌な場所なんですか?」
「まあ、あれが楽しいという人もいるでしょう。僕は否定はしませんが、人間のあらゆる欲望の集大成のように思えてしまうことも確かです。それゆえ、一度はまってしまったら抜け出すのは容易ではないでしょうね。客も、そしてホストも」
今にも泣き出しそうな顔で、手の中の飴細工を見つめる優里。有栖川にはその心中が手に取るように分かったが、敢えて何も言わず優しく肩を撫で続けた。
「あの……美咲(みさき)お姉ちゃんいますか?」
商店街唯一の化粧品店、『ビューティーショップ桜井』の店内に、優里がおずおずと入ってきた。閉店間際とあって客は誰もおらず、店主の咲子おばさん自称42歳が真剣な表情で売上計算をしているところだった。
「あらあら優里じゃない。美咲は奥にいるわよ。どうぞ」
「あ、はい。お邪魔します」
靴を脱いで奥の住居スペースに上がり、テレビの音がする方へ。美咲は面白くもなさそうに騒々しいバラエティ番組を眺めていたが、優里の姿を見とめるや否や嬉しそうに笑顔を咲かせて、
「優里じゃない。どうしたのよこんな時間に。ほらほら、コロッケ食べる? まだあったかいわよ」
優里は「お腹いっぱいだから…」と断って美咲の前に座り、真剣な表情で
「ね、僕……その……お化粧したら女の子に見えるかな?」
このひと言で美咲は、優里が何をしにどこへ行こうとしているか察した。優里をあんなところへは行かせたくない。行ったら行ったで傷付いて帰ってくるに違いないのだから。
「優里、あんなバカ隆矢のことなんかもう忘れなさい」
優里は驚いて瞬きも忘れ、「どうして分かったの…?」と呆然と訊ねる。美咲はそれには直接答えず、ただ優里の頬を軽く叩いて、
「こんなに痩せて……。あたしたちみんな心配してるのよ。優里は楓町商店街のマドンナなんだから。今すぐには無理でも、早くいつもの笑顔を取り戻して欲しいの」
優里は淋しそうに笑って、「ありがとう、お姉ちゃん」と掠れた声でお礼を言った。しかし続けて頭を下げ、
「お願いです。僕、一度でいいからお兄ちゃんがどんなところで働いているのか見てみたいの。な、なんかお酒とかいっぱい飲んで、夜遅くまで騒いでなくちゃいけないんでしょ? 身体を壊したりしてないか心配で………」
「大丈夫よ、あいつは。ていうか、少し身体を壊した方がいいくらいだわ」
苛立たしげに吐き棄てる美咲。途端に優里の瞳は潤み始める。
「そんなこと言わないで……ぼく、ぼく………」
両手で顔を覆ったと思ったら、肩がびくびく震え出した。美咲は慌てて謝る。
「ご、ごめん。ちょっと言い過ぎた。ねえ優里、あんたそんなに隆矢のことが―――」
好きなの? と訊こうとして呑み込んだ。今さら訊くまでもないことだし。その代わりに苦い溜め息をついて、
「分かった。じゃああたしの部屋に来て。服と化粧品を貸してあげる。ただし、必ず12時前には帰ってくること。でないとお父さんに言い付けてやるんだから。いいわね?」
優里はしゃくり上げながらうんうん頷いて、美咲の後に付いていった。
何だか睫毛が重くて変な感じだ。唇もべたべたしてるし、それに何より、初めてはいたスカートがすーすーして落ち着かない。
優里はおそるおそる駅の改札にある鏡を覗き込んでみた。そこには、髪にふわふわのウェーブをかけ、ローズピンクのグロスで唇を光らせ、白いニットジャケットを羽織った自分でない自分が、不安げな眼差しでこちらを見ていた。
どこからどう見ても萌え心をくすぐる超絶美少女だと美咲は太鼓判を押してくれたけど、もちろん優里の不安が解消されるはずもない。
いったん俯いてからふぅっと息を吐き、気持ちを落ち着かせる。そして再び顔を上げると、複数の男性と鏡越しに目が合った。みんな、じっと優里のことを見ていたのだ。
優里は一瞬、このまま回れ右して帰りたい衝動に駆られた。どうしよう、もうバレたんだ、僕が男だって―――
しかし優里は自分を奮い立たせ、そのまま真っ直ぐ進んで駅の反対側、桜町商店街がある北口に出た。駅の改札は明るかったからバレたんだ、暗いところならきっと大丈夫、必死にそう言い聞かせて。
久しぶりに歩く桜町商店街は、様子が一変していた。再生計画は確実に進められているらしい。
もちろん見知った店もあったが、その多くはすでに閉店時間を迎えており、新装オープンした飲食店やカラオケなどの遊戯施設が放つ輝きに埋もれて、静かに沈黙していた。
ホストクラブは商店街の最も奥まった場所にあるらしい。きょろきょろしながら歩いていると、いかにもホストらしき二人の男性が所在なげに立っているのが見えた。店は地下にあるらしく、階段の入口で客を迎えているようだ。
優里はその二人を遠くから眺めて、隆矢ではないことを確認する。ほっと安堵の息をついてゆっくり近付いてゆくと、すかさず一人が駆け寄ってきた。
優里は怯えつつも初めての来店であることを告げ、そして男に導かれて階段を下り、店内に入った。
「す…ごい……」
壁は一面鏡張り、毛足の長いワインレッドの絨毯、ゴールドのシャンデリア。もっと暗くてアンダーグラウンドな世界を想像していた優里は、目の前のきらびやかな空間に眩暈を覚えた。
案内されてソファにこわごわ腰を下ろすと、すかさず隣に男が座り、「流星(りゅうせい)です」と名前を告げてにっこり笑った。優里は大きく瞬きをして名前を反復し、
「綺麗なお名前ですね。流れ星ですか?」
流星と名乗ったホストは嬉しそうに頷いて、
「そう。僕に願いをかけたらきっと叶うよ」
そして優里の背中にさりげなく腕を回し、
「何飲む? ええと、今日はボトル何が入ってたかな……」
優里は慌てて手を振った。
「いえ、僕はお酒は―――」
じっと見つめられて、自分の失策に気付く。「僕」だなんて言ってしまった。男だとバレてしまったかもしれない。どうしよう………
しかし流星は眩しそうに目を細めて、
「可愛いな。ちょっとドキッとしたよ。名前教えてもらってもいいかな」
「え、はい……えと……美園………」
「みそのちゃんか。素敵な名前だ。君にぴったり」
そう言いながら薄めの水割りを作り、優里の前に差し出す。断りきれなくなった優里は仕方なく口を付けた。
ほろ苦くて冷たい液体が喉を通ると、鳩尾がかあっと熱くなる。やっぱりこれ以上飲むのはやめようと自分に言い聞かせて、隆矢の姿を探すため顔を上げた。
すると、金蒔絵風の大きな花瓶に活けられたカサブランカや胡蝶蘭が目に飛び込んできた。そのボリュームに圧倒され、思わず身を乗り出して眺めたが、
「あ……造花かあ………」
「ん? あれ? そう、造花だよ」
「そっか。よかったぁ……」
何故? と不思議そうに訊ねる流星を見上げて、
「だって、あんなに照明に近付けていたら、花が灼けてすぐ萎れてしまいます。可哀想でしょう?」
彼は感じ入ったように深い声で「なるほど」と返すと、改めて優里の顔をじっと見た。
「あの、何か……?」
「ん? いや、何でもないよ。あ、煙草は吸う?」
「いえ、吸いません」
「だろうね。大丈夫? ここ空気悪いけど」
優里は「はい」と答えて、改めて隆矢を探した。その姿はすぐに見つかった。優里の対角線上、端の席に足を組んで深く座り、客の肩を抱いて楽しそうに話している。
優里は咄嗟に目を伏せた。胃がキリキリと痛み始める。
「どうしたの? もう酔っちゃった?」
「いえ……あの………」
顔が上げられない。顔を上げたら、どうしたってあの二人を目で追ってしまう。ひと目見ただけで、彼女が隆矢のことを凄く気に入っていることが分かる。甘えるように身体を寄せ、手を隆矢の腿の上に乗せて話に耳を傾けている。
「お兄ちゃん………」
分かっていた。たぶんこういう光景を見ることになるだろうと。それなりの覚悟はして来たつもりだったけれど、実際に間近で見た時のショックが和らぐことはなかった。
しかし優里は意を決して、再び二人の方を窺う。相変わらず楽しそうに、親密な空気を隠そうともせずじゃれ合っている。
女性が何か言うと、隆矢は嬉しそうに頷いて得意気に叫んだ。どうやら女性が高価な酒を注文したようだ。店全体でお礼の決まり文句を唱和すると、店内の温度が一気に高まった。
―――これで……良かったんだ、きっと…………
商店街に自分の居場所を見つけられず、ずっともがき続けてきた隆矢。ここではこんなに生き生きと、楽しそうに働いている。
―――お兄ちゃん、よかったね。これからも……がんばって…………
その時、膝の上の手をきゅっと握られた。びくんと小さく跳ね上がって隣を見ると、流星が申し訳なさそうに鼻の頭を掻いて、
「驚かせてごめん。何か……震えてたから寒いのかなと思って」
「あ、あの……ありがとう」
流星はほっと息をついて、優里の指先を温めるように優しくマッサージする。さらに、カサカサに荒れた手の甲をそっと撫で、
「可哀想に。手が荒れてるよ。ひりひりしない?」
「あ、大丈夫です。慣れましたから」
「そお? 何でこんなに荒れちゃったのかな」
「家の仕事を手伝ってるんです。水仕事が多いから、それで」
流星は神妙に頷いて、優里の手を撫で続ける。他のテーブルが騒々しくなってきたため、優里の耳許に唇を寄せて、
「お酒、進んでないね。もしかして飲めない?」
「あ、はい。あんまり……」
流星は「分かった」と言って席を立ち、暫くして真っ赤なグラスを持って戻ってきた。
「はい。グァバジュース。おいしいよ」
フルーツや花が盛り付けられた美しいグラス。優里は「わあ」と瞳を輝かせて、ひと口飲んだ。
「ん……すごく美味しいです。ありがとう」
すると流星は「ああ〜〜」と声を上げて背もたれにどさっと倒れ込み、
「よかったぁ。やっと笑ってくれた。ホント、どうしようかと思ったよ」
ずっと気にしてくれていたんだと思ったら申し訳なくて、思わず「ごめんなさい」と謝ってしまう。流星はぴょんと跳ね起き、
「ほら、またそんな暗い顔して謝る。いいからいいから、そのジュースをゆっくり飲みなさい。それで飲み終わったら帰るんだよ。駅まで送っていってあげるから」
優里はこくんと頷いて、甘い果実のジュースで乾いた喉と心を潤した。
きっとお金をたくさん請求されるのだろうと思って予め貯金を下ろしておいたけれど、実際はそうでもなかった。もちろん、ほんの1時間ちょっといてジュースを1杯飲んだだけにしては、びっくりするような値段だったけれど。
階段を上って地上に出ると、優里はゆっくり深呼吸した。地下はやはり空気が悪く、煙草と香水の匂いで軽い頭痛も起きていた。
「ね、もうこんな所に来ちゃだめだよ、美園さん」
優里は驚いて、送るため一緒に店を出てきた流星を見上げた。彼はにっこりと屈託ない笑みを向けて、
「僕はね、君からブーケを買ったことがあるんだ。と言っても、オリジナルのを注文する金がなかったから、店頭のサービス用ブーケだったけど。でも君はとても綺麗なリボンをかけてくれた。嬉しかった」
「あ……ぼく………」
驚いたのと恥ずかしいのがごっちゃになって、瞳がじんわり潤み始める。流星は肩を優しく抱いて、
「何があったのかは訊かないよ。でも君はとても、とても辛そうな顔をしていた。もうここに来ては駄目だ。こんな、偽物の花を恥ずかしげもなく飾っているようなところには」
優里は両手で顔を覆い、指の隙間から「もう来ません…」と呟いた。
「うん、それがいい。じゃあ、駅まで送っていくよ」
「いえ……一人で大丈夫です。流星さん、ありがとう。もうお店に戻ってください」
「……本当に、大丈夫?」
「はい」
優里が一人になりたがっていることを察したのか、「それじゃ、気をつけて」と返して手を振り、暫く見送った。そして優里の後ろ姿が見えなくなると、くるりと振り向いて階段を下り、店に戻ろうとした。その時、凄い勢いで階段を駆け上がる隆矢とすれ違った。
「なるほど。そういうことか」
流星は誰にともなく呟いて、ちらと肩を竦めた。
BACK TOP NEXT