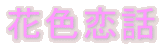
―小さな花屋の物語―
第6話
「はい、美園花店で………おう、なんだ、徹ちゃんか。どうしたんだ?」
優里は電話をとった父の傍で聞き耳をたてる。徹ちゃんというのは他でもない、隆矢の父親で沢村酒店の店主、徹矢だった。
何だか胸騒ぎがする。こんな時間に電話をしてくるなんて、滅多にないことだ。もしかしたら、隆矢に何かあったのか……?
優里の不安を裏付けるように、司の眉間が徐々に険しく寄り、深い皺が刻まれていった。
「はあ? 勘当? 隆矢をか? うん、うん………なに? ホストぉ?」
優里はこくりと喉を鳴らした。父の口から聞き慣れない言葉が飛び出して、思わず身を乗り出す。すると司は受話器を握ったまま、深刻な表情で二度三度頷いてみせた。
「そうか……分かった。ともかく少し様子を見ようかじゃねえか、なあ? 気持ちは分かるが、徹ちゃんも余り熱くなるな。血圧高いんだろ? おう、じゃあ今夜にでも。それじゃ」
司は太い溜め息をついて、受話器を戻そうとする。しかし手からつるりと滑らせて、落としてしまった。
「お、お父さん大丈夫?」
「ん? ああ、最近ちょっと右手が痺れるんだよな。まあ大したことねえよ。それより優里、沢村さんとこ大変だぜ。隆矢の馬鹿がまたやらかした」
「な、なにを……」
さっと血の気がひいた優里の白い顔を痛ましげに見据えてから、司は口を開いた。
「桜町商店街のホストクラブで、ホストをやるんだとさ」
「ホ……スト………」
「そう。もちろん徹ちゃんは許さねえ。そんなもんやるんだったら勘当だ、家を出てけと言ったら、最初から出るつもりだったとさ。若い新人ホストのために、格安でアパートを提供してくれるから、そこに行くって荷物まとめて出ていったそうだ―――」
優里は最後まで聞くことなく、すごい勢いで店を飛び出した。その後ろ姿を見送りながら、
「まったく、優坊も厄介な男に惚れたもんだ」
司は静かに言い置いて、配達リストの整理に戻った。
「徹矢おじさんっ、あの、お兄ちゃんはっ?」
「おう、優里。あの馬鹿のことは放っておけ。たった今家を出ていった。もう二度とうちの敷居は跨がせねえ」
優里はすぐに後を追おうと店先から飛び出した。が、何を思ったかくるりと振り向き、
「おじさん、ヤケになっちゃだめだよ。柾矢お兄ちゃんのためにも。僕は、僕は絶対にこんなの嫌だからねっ」
そして今度こそ店を飛び出して隆矢の後を追った。駅に通じているメインストリートは1本だから、急げば途中で掴まえることができるはず。
と思っていたら予想通り、大きな荷物を持った長身が前を歩いているのを見つけた。
「お兄ちゃん、隆矢お兄ちゃんっ」
声を嗄らして叫び、背中に飛び付く。隆矢は前につんのめりつつも「お、優里じゃないか」といつもの笑顔を向けてくれた。
優里は何か言おうとしたが、走ったせいでけほけほ咳き込んでしまい、苦しそうに肩を上下させて隆矢にぎゅっとしがみ付いた。隆矢は慌てて荷物を置いて背中をさすってやり、
「バカ、落ち着け。お前は気管が弱いんだから、こんな無理しちゃ駄目だ」
しかし優里は呼吸が落ち着くのを待つことなく、シャツにしがみ付いたまま訴えた。
「どう…して……お兄ちゃん………。そんなに……ここが嫌……?」
「ゆうり……」
「そんなに………ふぇっ……楓町の商店街が…………嫌いなの?
…………ぇ、ぇぇっ…………」
涙の珠を実らせた長い睫毛が、ふるふると揺れている。しっとりと濡れた瞳は一途な輝きを湛え、真っ直ぐな想いを訴えていた。
―――あれほど純粋で真っ直ぐで、美しい人はそういない
有栖川の言葉が頭をよぎる。隆矢は今初めて、幼馴染みのフィルターを外して、美園優里という一人の人間を見たのだ。まだ泣きじゃくる優里の腕を掴み、
「こんなところで泣くな。取り敢えず公園に行くぞ」
少し乱暴にぐいぐい引っ張っていった。もう笑顔は浮かべていない。それは優しいお兄ちゃんの顔ではなく、一人の“男”の顔だった。
メインストリートから外れた小さな公園。幸いにも誰もおらず、二人はベンチに並んで座った。優里はまだ、隆矢のシャツを掴んでいる。
隆矢ははあ、と少し作為的な溜め息をついて、
「いきなり泣くなよ。驚いたぞ」
「ごめんなさい……」
「で、お前は俺にどうして欲しいんだよ」
優里は顔を上げて、潤んだ瞳を一心に向ける。言いたいことはただひとつ。僕をおいて行かないで、傍にいて、と―――
お兄ちゃんにはお兄ちゃんの人生が、お兄ちゃんの幸せがある、商店街を出て行きたいのなら仕方がない、ずっと自分にそう言い聞かせてきた。
でも実際にこうして出て行く姿を目の当たりして、ようやく分かったのだ。それが想像していたよりずっと、辛くて痛くて悲しいということを。自分を押し殺して好きな人の幸せだけを願うことが、どれほど難しいことなのかを。
「行かないで……お願い………」
色々な想いが凄い勢いで頭の中を駆け巡る。うまく整理できず頭がぼぅっとしながらも、優里は今最も伝えたいことを何とか口にした。
これまでの隆矢だったら、「バカだな、いつだって会えるだろ」と笑い飛ばし、優里の頭をわしわし撫でて終わっただろう。しかし今、隆矢は苦しそうに顔を歪めて、優里の濡れた瞳から目を逸らす。
「何でだよ……別に、俺がいなくなったって何も変わらねえだろ………」
そうだ、自分は柾矢とは違うのだ。柾矢がいなくなって、全てが変わってしまった。誰も柾矢の代わりにはなれない。しかし自分は―――
「店だって、親戚の誰かに継いでもらえばいい。俺みたいに何にもできない若造が継ぐより、ずっと安心のはずだ」
「そんなことないっ」
「それにお前だって、あの男がいるしな。あの代理店のスカした野郎」
優里は驚きの余りぽかんと口を開けて、「有栖川さん…?」と訊ねる。隆矢は鼻先で嗤って、
「ふぅん、そういう名前なのか。お前、あいつと食事に行ったんだろ? 大人で落ち着いてて等身大の自信に満ち溢れてて………そう、あいつは柾兄に似てる。どうだ?」
優里は正直に「僕も似てると思った」と言って頷く。すると、隆矢の顔に険しい翳が差した。苛立ちを隠そうともせず、
「やっぱりな。あいつ、お前のことかなり気に入ってたみたいだぜ。ちょうどいいじゃねえか」
隆矢が何を言わんとしているのか、優里にはさっぱり分からない。何故ここで有栖川の名前が出てくるのか、何故隆矢がこんなにも苛立っているのか―――
「ああ、とんだ道草食っちまった。もう行くぞ。じゃあな」
隆矢は鞄を持って立ち上がり、優里にあっさり背を向けた。優里も慌てて立ち上がり、
「や、やだっ、行かないで、行かないでぇ………」
隆矢は背を向けたまま、初めて優里に拒絶の言葉を叩き付けた。
「もうお前のお守りはごめんだ。俺には俺の人生があるんだからな」
「おに……ちゃ………」
それは小さな小さな音だった。けれど背中越しに確実に聞こえた。ぱりん、という儚い音。これまで大事に守り続けてきた繊細な心が壊れた音。
隆矢は振り向いて謝りたい欲求を押し殺して、そのまま去っていった。この短い間に、何かが決定的に変わってしまったという痛い自覚を反芻しながら。
「んっ、ぇっ………ぇぇっ………っく……………」
ここはどこだろう。訳も分からず悲しみの勢いに促されるまま歩き続けている。もしかしたら、知らない街に迷い込んでしまったのかもしれない。涙で白く霞む視界はよそよそしく、道行く人の顔ものっぺりとした無表情に見える。
「ぼく……ぼくぅ………」
どうしたらいいのか分からない。好きで好きで大好きな人に突き放されて、存在の支えを失ってしまった。立ち止まったらきっと倒れてしまう。だから歩き続けなければならない。行くあてなどないのに。
そんな優里の痛々しい歩みを、楓町商店街の面々はハラハラしながら見守っていた。そう、結局優里は帰巣本能に導かれて、ふらふら彷徨いつつも楓町商店街に戻ってきていたのだ。
手を差し伸べてやりたいが、何と声を掛けてよいのか分からない。もちろん優里の涙の理由は、みな察していた。だからこそ、声を掛けるのがためらわれたのだ。隆矢はきっと戻ってくるよ、そんな気休めを言ったところで、余計に辛くさせてしまうだけだ。
そして有栖川もまた、心を痛めながら優里の歩みを見守っている一人だった。こうなることは分かっていた。というより、分かっていたからこそやったのだ。優里から、隆矢を引き離すために。
しかし有栖川はすでに後悔していた。「お兄ちゃん」と甘えた声で呼びかけながら微笑む優里と、今の涙に溺れた優里との痛ましいほどの落差を見せられて、罪悪感が込み上げる。
こんな、こんな姿は見たくなかった。光を失った虚ろな瞳からとめどなく涙を溢れさせ、壊れた機械人形のようにふらふら歩く優里なんて――――
「んっ、んく………ぅっ、ぅっ…………」
涙に翻弄され、儚くよろめく。もう駄目だ。見ていられない。商店街の人間に睨まれるのを覚悟で、有栖川は飛び出して手を差し伸べようとした。が、僅かに先んじて―――
「優里っ」
恐らく誰かが知らせに行ったのだろう、司がふうふうと息を切らせて駆け寄り、優里の身体を抱き取った。心配の余り張り詰めていた周囲の空気が、ふっと緩むのが肌に伝わる。
お客そっちのけで店先に出て見守っていた人たちが、みな良かった良かったと頷いて店内に戻っていた。
「お父さぁん………ぼく………だめだった……がんばったけど、お兄ちゃん引き止められなかったよ…………」
「優坊……」
「お兄ちゃん、行っちゃった………行っちゃったの…………」
司は何も言わず、泣きじゃくる優里の背中をさすりながら、ゆっくりと来た道を戻っていった。
あの音が耳から離れない。ごく微かな、恐らく自分にしか察知できない音。優里の心が壊れる音。
あれを聞いたのはこれで二度目だ。最初は、柾矢の死を知らされた時。身体中に包帯を巻かれていても、必死の呼びかけに全く反応を示さなくても、優里は信じ続けた。
絶対に柾矢お兄ちゃんは助かる、いつか目を開けてくれる、と。決して絶望はしない、諦めない。真っ先に絶望して泣き崩れてしまうと思われた優里の悲壮なまでの強さに、隆矢は驚きと敬虔な感動を覚えた。
しかし事故から二日後、柾矢の死を知らされた優里の心は呆気なく砕けた。それまでの強さが幻であったかのように。
そしてたったひと言、「どうしてお兄ちゃんがっ……」と呻くように叫んで、その場に昏倒した。
どうして? どうしてお兄ちゃんが………どうして柾矢が………どうして隆矢ではなく柾矢なんだ…………
お前が死ねばよかった―――はっきりそう言われたことなどない。けれどみんなそう思っているに決まってる。早くから家業を継ぐことを決意し、店のため商店街の発展のためをいつも考えて働いていた柾矢。
三代目の中でもリーダー的存在で、皆に慕われ、親身になって相談に乗る。沢村さんとこが羨ましい、あそこの酒屋は安泰だ、そんな言葉が頭上を飛び交う中、隆矢は自分がしたいことも見つけられず、兄が与えてくれた自由の檻の中でもがいていたのだ。
隆矢は好きなことをやっていいんだぞ―――そう言って笑いかける柾矢の顔は、いつも何故か淋しそうだった。家業を継ぎたい、それが柾矢の本心だったのか、今となってはもう分からない。
確かなのは、柾矢は車のスリップ事故に巻き込まれて死んでしまったこと、後のことを託された自分はその重みから逃げ回っていること、誰も柾矢の代わりになんかなれないこと、そして、心から自分を必要としてくれる人などいないこと――――
―――行かないで……お願い………
「なんで……あんな目で見るんだよ…………」
涙で濡れた瞳は、これまでにない激しい感情に沸いていた。優里の涙を見たのは、もちろんこれが初めてではない。
隆矢が驚いたのは、涙が蒸発しそうなほどの熱い眼差し。他の誰にもあんな目で見られたことはない。思い出しただけで、鳩尾の奥がカッと火照ってしまう。
「優里……俺を惑わすな………」
小さいころからずっと守ってくれた人がいなくなってしまうのが、きっと不安なのだろう。でも優里には有栖川がいる。柾矢のように、包み込むような大人の優しさを感じさせる有栖川が傍にいてくれれば、いずれ不安も淋しさも解消されるだろう。
そう、自分の代わりならいくらでもいる。だからこれで良かったのだ。
「柾兄ごめん………約束、何ひとつ守れそうにねえや………」
がらんとした部屋の真ん中で、荷物を枕に横たわって目を閉じると、静かに涙を流す優里の白い顔が浮かんできた。その瞬間、隆矢の身体に甘い電流が走る。それに弾かれるように起き上がって、思わず頭を抱え込んだ。
信じられない、が、紛れもない事実。自分は今、優里に対してはっきりと、劣情を催したのだった。
BACK TOP NEXT