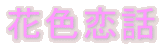
―小さな花屋の物語―
第5話
「簡単に説明しますと、大手フラワースクールが資本参加しているショップで、花を売る、飾る、学ぶの3つのコンセプトを基本に据えた―――」
「ちょ、ちょっと待ってくださいっ」
大きな声を出してしまった優里は、はっと気付いて「すみません…」と謝った。しかしすぐに顔を上げ、
「僕には美園花店があります。将来的にはあの店を継ぐつもりです。ですから―――」
「お言葉ですが、それは余り現実的な未来ではありませんね」
有栖川の言葉に思わず息を呑む。優里は自分で意識せぬまま、すがるような眼差しを向けた。有栖川はふぅっと溜め息をついて、
「少し厳しいことを言わせていただきます。優里さん、あなたは余り体が丈夫ではないようですね。でも、花屋というのは体力を要する仕事です。今、あの店を続けていられるのは、お父さんのサポートがあってこそではないのですか?」
「それ…は………」
「いずれお父さんも体力が衰え、今のように働くことができなくなります。そうなった時あなたは、ちゃんと仕事を引き継ぐことができますか? 或いは、親身になって助けてくれる人がいますか?」
一瞬、隆矢の顔が脳裡に浮かんだ。しかし慌てて首を振って消す。彼を当てにするなんて、そんな甘えは許されない。隆矢には隆矢の人生があるのだし、何より彼はこの商店街から一日も早く出たがっているのだ――――
その時、有栖川の瞳が微かに光った。これまで、優里に対しては決して見せることのなかった作為的な笑みを浮かべて、
「昨日の彼ですか?」
「えっ?」
「あなたの王子様、なのでしょう?」
驚きの余り瞳孔が小さく引き絞られた黒瞳を厳しく見据えて、有栖川は優里の小さな望みを打ち砕く。
「昨日の彼、沢村酒店の一応は跡継ぎということになるのかな。あなたの大事な大事な王子様ですね。でも彼はどうやら、この商店街に愛着を持っていないようだ。違いますか?」
「どう…して……お兄ちゃんは関係ないでしょう……?」
有栖川はくくっと笑って首を振る。僕が気付いていないとでも思っているのですか、とでも言いたげに。
「いずれ彼は商店街から出ていきます。あなたの傍から離れていきます。親を捨て、家業を捨て、あなたを捨て、自分勝手な生き方を―――」
「お兄ちゃんのこと悪く言わないでくださいッ」
声自体は大きくなかったが、その言葉に込められた強い思いは、周囲の人間を黙らせるだけの力があった。しかし優里はさっきのように謝ることはせず、強い眼差しを有栖川に向けて、
「お兄ちゃんにはお兄ちゃんの考えがあるんですっ。それに僕は誰かに頼ろうなんて思っていません。確かにあなたの仰る通り、不安要素はたくさんあります。でも、やってもみないで無理だと決め付けるのは卑怯だと思うんです。がんばってがんばって、倒れるまでがんばってみればいい。本当に倒れてしまったら、それはその時です」
優里の決意表明を、有栖川は苦しそうに目を細めて聞いた。やがて柔らかな溜め息をつき、
「やはりあなたは僕が思っていた通りの人だ。一見脆そうで、人の意見に流されそうだけれど、実は頑固で一途で………」
自分が発した言葉を改めて味わうように目を閉じる。やがてゆっくり目を開けて僅かに身を乗り出し、意外な問いを発した。
「ね、魔法のブーケを自分のために作ったことはあるのですか?」
「え? いえ、それは……ないです」
有栖川はくすりと笑って「なぜ?」と問いを重ねる。
「魔法使いは……自分のために魔法を使ってはいけないのです」
「なるほど。ストイックな魔法使いさんだ」
彼のように社会的な地位のある大人の男性が、<魔法>なんて本当に信じているのだろうか。もしかしたらからかわれているのかも………優里は急に恥ずかしくなって俯いてしまった。しかし、
「いつか……僕もあなたに魔法のブーケをお願いする時が来るかもしれませんね。その時は、作っていただけますか?」
「え? はい、それはもちろん………」
「ああ、良かった」
心底嬉しそうに微笑んで、「よろしくお願いします」と深く頭を下げる。あんなきついことを言われたすぐ後なのに、優里の口許には笑みが戻っていた。不思議な人だな、とつくづく思う。
「店長の件は、保留とさせていただきます。もし気が変わったらいつでも連絡ください」
有栖川はそう言って、名刺を差し出した。優里はテーブルの上の名刺をじっと見つめて、「気が変わることはないと思います」とはっきり告げた。
「……分かりました。でも、この名刺は受け取ってくれませんか? そして美味しいランチが食べたいなと思った時には、連絡してください。すぐに駆けつけますから」
優里は迷いつつも、名刺を自分の方へ引き寄せようと手を伸ばした。すると有栖川も手を伸ばし、優里の上に重ねて指をぎゅっと握った。
「あ、有栖川さん………」
水仕事のせいでお世辞にも綺麗とは言えないカサカサの指を、有栖川はうっとりと目を細めて撫でる。
優里は驚いて手を引こうとしたが、彼の手の意外なほどの温かさ、柔らかさに酔わされて、そのささやかな愛撫に委ねた。
「この小さな手が、人を幸せにする魔法を紡ぎ出すのですね………」
有栖川は熱っぽい感慨を込めて囁いて、そのまま暫く手を離そうとはしなかった。
―――この小さな手が、人を幸せにする魔法を……
優里は有栖川の言葉を思い出しながら、傷だらけの手をじっと見つめた。
ランチの後、自分と一緒にいるところを見られたら外聞が悪いだろうという気遣いから、有栖川は駅の反対側で優里を降ろした。そしてまたお客として伺いますねと言って去っていった。
それから店に戻っても、夜、家に戻っても、有栖川の言葉が耳から離れない。
「魔法のブーケ、かあ……」
こんな風に言われるようになったのは、いつ頃からだろうか。フラワースクールを辞めてから無我夢中で仕事を覚え、何とか店番ができるようになった。その頃にはすでに、噂を聞いて来ましたという人が訪れるようになっていたのだ。
「魔法なんて……あるはずないのに………」
優里は分かっていた。告白が成就するのはブーケの力ではなく、贈る人間の想いの強さ、花に託して伝えたいと願うその気持ちが相手に伝わるからだろうと。
優里にブーケを依頼する人はみな、贈る相手の趣味や好きな色、性格まで細かく優里に教えたうえで、お願いしますと頭を下げる。そこまで相手のことを思い、理解しようとする努力が幸せを呼ぶに違いない。
でももし、本当に、自分が作るブーケに不思議な力が備わっているとしたら―――
―――お兄ちゃんにあげたら………もしかしたら………
余りに虚しい空想。優里は頭を振って必死に払う。自分はただの幼馴染み。おまけに男なのだ。もし自分が女だったら……と、またも虚しい妄想に囚われそうになるが、今度は笑って打ち消した。
女に生まれてきたとしても、きっと性格はこのままだ。こんな暗くて、話下手で、花を介してしか他人とまともにコミュニケーションできないような子は、隆矢の好みではないだろう。明るくて華やかで、誰とでも打ち解ける太陽みたいな可愛い女の子が、隆矢にはふさわしい。
そう考えれば、神様は優しい配慮をしてくださったのだ。男に生まれたお陰で、もしかしたらという希望に惑わされることなく、最初から諦めることができるのだから。
優里にとって希望を持つことは、苦しみ以外の何ものでもなかった。
―――僕ができるのは、お兄ちゃんの幸せを願うことだけ。これからもがんばってお兄ちゃんのためにブーケを作って、うまくいきますようにって祈って、それで、それで………
いつかは本当に諦めることができるように………なるのだろうか………
ふと気が付けば、デスクの上に飾った一輪の花に触れている。無意識の行動なのだから大して深い意味はないと自分に言い聞かせるものの、そんな誤魔化しの奥にある本心から目を背けることはできなかった。今のところ、この花だけが唯一、彼との繋がりを感じさせてくれるものなのだ。
「あら? その花もう駄目なのではありませんか? 新しい花を買ってきましょうか」
部下の五十嵐女史に言われて初めて、一輪挿しの青いデルフィニウムが萎れ始めていることに気付く。
しかし有栖川は「いえ、けっこうです」と答えて、椅子の上で大きく伸びをして目を閉じた。
―――お兄ちゃんのこと悪く言わないでくださいっ
「はは、参ったな………」
ちょっと目を閉じただけで、暗がりの中から浮かび上がってくる。
頬を真っ赤にして瞳を潤ませ、大好きな人を必死に弁護しようとする彼の面差しが――――
有栖川は、ファイルを開いて書類をぱらぱらとめくった。楓町商店街で営業している店のデータ。店舗面積や創業年月日、月間売上、推定純利益などはもちろん、従業員数や家族構成まで記載されている。
有栖川はその中で、沢村酒店に目を留めた。備考として、長男の柾矢が2年前に不慮の事故で亡くなったこと、次男の隆矢が現在大学3年で、家業を継ぐのに難色を示していることが記されていた。
「お出かけですか? 主任」
「ええ。今日はこのまま直帰です。君もたまには早く帰宅したらどうですか? 新婚なのにご主人が淋しがりますよ」
「主任、それってセクハラになるんですよ」
有栖川は「それは失礼しました。以後気を付けます」と軽く頭を下げて上着を引っ掛け、颯爽と事務所を出ていった。
日も落ち始めた黄昏どき、隆矢は肩を落としてとぼとぼと家路を辿っていた。
本当なら今ごろは、東京湾クルーズの真っ最中。お台場のイルミネーションを眺めながら、誕生日の計画を彼女と一緒に練っているはずだった。
なのに―――
「他に好きな奴ができたって? しかもフランス人……ったくよぉ………」
待ち合わせ場所に現れた彼女は悪びれもせず、申し訳なさそうな素振りも見せず、淡々とした口調で「あなたとは終わりにしたいの」と言って、呆然とする隆矢を置き去りにして人ごみの中に消えていった。
今まで何度も踏襲したパターンではあったが、だからといって慣れたというものでもない。失恋の痛みはいつも、嫌というほど鮮やかだった。
「あーあ、またフラレたぁ」
わざと明るく言って空を仰いでみたものの、余計に虚しさが増してずっしりとのしかかってくる。隆矢は「ははっ」と乾いた笑いを漏らして、再び歩き出した。
柾矢が死んでからの自分は、色々な意味で最悪だった。しかし、全ての原因は自分にあることを、隆矢は痛いほど自覚していた。柾矢の最期の言葉から、耳を塞いで逃げ回っている自分に。
事故に遭って救急病院に運び込まれ、集中治療を受けた柾矢。しかしその甲斐もなく、二日後に息を引き取った。
死ぬ前日、奇跡的に意識が回復した柾矢は、隆矢の手を取って信じられないほど強い力で握り、店を、父と母を、そして優里を頼むと告げたのだ。
そして、まるでそれを伝えるためだけに“こちら側”に戻ってきたかのように、その後すぐ再び昏睡状態に陥り、そのまま二度と目を開けることはなかった。
「俺は……最悪だ………」
分かってる、でもどうしたらいいのかが分からない。柾矢の代わりになんて到底なれないのに、周りはみんなそれを求めてくる。
家業を継ぎたくないのではなく、継いだ挙句やっぱり隆矢では駄目だと言われるのが恐い、そう、恐いのだ――――
「やあ、こんばんは」
いきなり背後から声を掛けられ、飛び上がって慌てて振り向く。情けない悲鳴を上げずに済んだのは幸いだった。そこに立っていたのは―――
「あ、あんたは確か代理店の………」
「はい。優里さんのところで一度お会いしましたね。有栖川と申します」
有栖川は足音をたてずに近付いて、「沢村隆矢さんですね?」と笑顔で念押しした。隆矢は胡乱げに目を細めて、
「言っとくが、俺を丸め込んでも無駄だぜ。俺は酒屋を継ぐ気はねえし」
「そんなつもりはありません。というより、楓町商店街の再生計画は諦めました。皆さんの頑固さには脱帽です。もちろん残念ではありますが………」
でも、本当に欲しいものは諦めませんよと、胸の裡で付け足す。
「それよりも、本当にご家業を継ぐつもりはないのですか? あなたが継がなければ、沢村酒店は一体どうなるのか―――」
「あんたには関係ないだろ」
苛立たしげに遮る隆矢に、有栖川はいかにも同意するように深く頷いて、
「確かに。でも、きっと何かお考えがあるのでしょうね。優里さんも、お兄ちゃんにはお兄ちゃんの考えがちゃんとあるのだと仰ってましたし」
「優里が、そんなことを……」
「はい。先日一緒に食事をさせていただいた時にそう仰ってました。それにしても……あれほど純粋で真っ直ぐで、美しい人はそういない」
隆矢はちらと肩を竦めて、「惚れたんじゃねえの?」とからかった。しかし有栖川は至極真面目な顔で頷き、
「どうやら、そのようです」
隆矢は瞠目して口をぱくぱくさせたが、やがて掠れた声で「あいつは……あれでも男だぞ」と呻くように言った。
「ええ、存じ上げておりますよ。仕事熱心で、優しくて、一見儚げだけれど芯の強い、美しい青年。僕の周りにいるどんな女性より、輝いて見える」
有栖川ははっきりそう言い置くと、返す言葉を失って呆然とするばかりの隆矢に笑いかけ、
「これからゆっくりと距離を縮めて、いずれは恋人にしたい。よろしいでしょうか?」
そして隆矢の返答を聞く前に「ああ」と声を上げ、
「あなたに許可をもらう必要などありませんでしたね。失礼しました」
「あ、あんた……本気、なのか?」
「もちろん本気です」
何を今さら、と言わんばかりに即答して、不敵な笑みを浮かべる。隆矢は「勝手にしろ、俺には関係ねえ」と吐き棄てて、背中を向けた。
「あ、お待ちください。もうひとつ、あなたに大事なお話があるのです」
有栖川の呼びかけに、隆矢は不快な表情を隠そうともせず、渋々振り返る。
「なんだよ」
「沢村さん、ホストに興味はありませんか?」
「……は?」
ぽかんと口を開けて聞き返す隆矢に、すらすらと説明を始める。
「桜町商店街を再生するに当たって、歓楽施設、特に大人の社交場の充実をひとつの課題として取り組んできました。桜町商店街にホストクラブがオープンしたのをご存知ですか?」
「は、初めて聞いた……」
「そうですか。まあ、オーナーはまだ20代の若造なのですが、そこそこ売上を出しています。ただ人材不足で、肝心のホストが足りない。面接をしても碌なのが来ないと嘆いていましてね。そこで、沢村さんをお誘いした次第で」
隆矢はようやく驚きから脱した様子で、真剣に耳を傾けている。有栖川は満足そうに頷いて、
「いかがですか? まだ大学生ということでバイト扱いになりますが、時給は破格ですよ。それに、固定客が付けばその分上乗せされます。失礼な言い方かもしれませんが、あなたのその容姿ならすぐにお客が付くと思いますが」
隆矢は考えた。自分に全てを託して死んでいった柾矢の顔が頭をよぎる。と思ったら、何故か優里の泣きそうな顔が浮かんできた。無言のうちにお兄ちゃん行かないでと訴えるような、悲愴な表情。
しかし隆矢は目を逸らした。恐らくこれは転機だ。これまでの、何もかもがうまくいかない毎日をリセットするための―――
「やります。やらせてください」
有栖川は「よかった」と笑顔で応えつつ、胸の奥で優里に詫びた。
ごめんね、これで君の大事なお兄ちゃんは、もっと遠いところへ行ってしまうに違いないよ、と。
BACK TOP NEXT