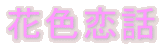
―小さな花屋の物語―
第4話
説明会は双方の腹を探り合うような疑念に満ちた空気で始まり、そして見事なまでの決裂で終わった。
新しく生まれ変わろうとしている桜町商店街を引き合いに出して、最近の都市再開発のムーブメントに乗り遅れないよう、楓町の皆さんも一緒に生まれ変わりましょうと口舌巧みに誘う有栖川に対し、楓会のメンバーらはこれ以上話し合うことはないと言って、一方的に散会を宣言した。
もちろん司も怒り心頭で立ち上がり、優里の腕を掴んで連れ出そうとする。尤も司の場合、二重、三重の怒りがあったのだが。
「あの男……最初っからなんか怪しいと思ってたんだッ」
何度も店を訪れては、優里に馴れ馴れしく話しかけ、花を一輪だけ買っていく。恐らく、ああやって店を偵察していたのだろう。何故美園花店が評判になっているのか、その秘密を探ろうとしたに違いない。
優里は父の怒りに翻弄されるまま、席を立って引きずられてゆく。会場を去る間際に振り返ると、一輪さん――有栖川は諦めたような淋しげな笑みを浮かべて、優里が去るのを見送っていた。
寄合所から家に帰る途中、色々な噂が耳に飛び込んできた。みんな不安なのだろう。自分が持っている情報を吐き出して、周りと交換しては不安を鎮めているのだ。
その中でも、特に多いのは有栖川に関する噂だった。優里は思わず聞き耳を立てる。
「商店街再生のエキスパート、魔術師なんて言われてるらしいぞ。これまでも、全滅寸前の商店街をいくつも建て直してきたとか」
「はん、胡散臭い肩書きだな。名前も胡散臭いし、あの妙な男前ぶりも胡散臭い」
「全くだ。結局は、空き店舗をぶっ潰してパチンコとかカラオケ屋を作っただけだろ? そんなの俺でも考え付くさ」
「それだけならいいけどな。採算の取れない店を無理やり追い出したり、計画に反対する人間を容赦なく排除したり。物腰の柔らかさに騙されちゃ駄目だ」
「高齢の店主を言いくるめて、店舗の権利書を騙し取ったって話も聞いたぞ。ただの悪党じゃねえか」
優里はそれ以上聞いていることができなかった。真剣に噂に耳を傾ける父をその場に残して、ひとり家路を急いだ。
その翌日。昨日までのことは全て忘れて仕事に専念した。花の世話をして、お客の相手をしていれば胸の内のもやもやを意識せずにいられた。
優里は改めて花の魔力を実感し、花屋という仕事を与えてくれた神様に感謝した。
しかし、心安らかな時間は長くは続かなかった。お昼、配達に出ていった司がそろそろ戻ってくるかなという頃合。店先から聞き慣れた声の「すみません」が届いた。
優里は驚いて店頭に出ると、思った通りそこには“一輪さん”が、今までと何ら変わらぬ美しい微笑みを浮かべて立っていた。
「な、何のご用ですか?………有栖川さん」
有栖川はぺこりと頭を下げて、
「昨夜は驚かれたでしょう? 失礼しました。それで、そのお詫びというわけでもないのですが、これから一緒にお昼をしませんか? ご馳走しますよ」
「い、いえ、けっこうです。僕は仕事がありますから……」
有栖川は足音をたてずに一歩、二歩と近付いて、優しげに微笑みを深める。
「ああ、まだお父様が配達から戻られないのですね。いいですよ、お戻りになるまで待っていますから」
そして怯えも露わに見上げる優里の肩にそっと手を置き、
「ここから車で10分くらいのところに、僕が以前プロデュースを手がけたカジュアルなフレンチレストランがあるんです。庭がきれいな、とても落ち着く店です。ぜひあなたをお連れしたい。いかがですか?」
「い、いや……」
掠れて震える声でささやかな拒絶を呈すると、肩に置かれた手に僅かに力が入った。逃がさないぞという意志表示だろうか。
もともと優里は、人からの誘いを断るのが苦手だった。そのせいで学生時代、カラオケやゲームセンターへの誘いを断り切れずに付いて行き、空気の悪さ、うるささに必死に耐えた結果、翌日熱を出して寝込んでしまうことがたびたびあったのだ。
「いいでしょう? ね?」
相変わらず美しい微笑みで、しかし強引に誘い出そうとする有栖川。優里はどうしてよいか分からず、頭の中がぐちゃぐちゃになって今にも泣き出してしまいそうになった。その時、
「おおーーい、優里ぃ。昼飯まだかぁ? 玉ちゃんラーメン奢ったるぞ」
明るくて、ほんわかして、懐かしい太陽の匂いすら感じる声で優里の名を呼びつつ駆け寄ってくるのは―――
「あ、悪い。お客さんだったのか―――」
済まなそうに頭を掻く隆矢に、優里は勢いよく抱き付いた。
「お兄ちゃんっ」
「わ、わわっ、どうした優里」
隆矢は戸惑いつつも華奢な身体を受け止めて、背中に腕を回してよしよしとさすってやる。そして顎に手をかけてそっと上を向かせる。
優里の瞳が微かに潤んでいるのを見とめると、有栖川をぎっと睨み、
「どうした。こいつに虐められたのかっ?」
優里は慌てて首を振って否定するが、怯えと混乱に加えて、隆矢が来てくれて気が緩んだのかじわじわと涙が溢れてしまう。
「ごめ、ごめんね………なんかほっとしちゃって………」
そう言って隆矢の胸に顔をうずめる優里の細い肩をじっと見つめていた有栖川は、ふぅっと息を吐いて肩を落とし、
「そんなに怯えさせるつもりはなかったのですが……。また出直してきますね」
心なしか萎れた声でそう告げると、二人に背中を向けて去っていった。
「なんだあのスカした野郎は。優里、優里、もう大丈夫だ。ほら、顔上げて」
「う、うん………」
鼻をぐじゅぐじゅいわせながら顔を上げる優里。隆矢は「しょうがねえなあ」と笑いながらポケットを探り、駅前でもらったキャバクラの広告入りティッシュを取り出す。
「ほら、鼻かんで。鼻が詰まってたら、ラーメンの味が判らないぜ」
「ふぇぇ……ありがと………」
尚も鼻をくしゅくしゅさせる優里の頭をぽんぽんと叩いて、
「ほら、おやっさんが戻ってきたぞ。ちょうど良かった。ラーメン食いに行こう」
優里は涙の痕が残る頬を赤く染めて、「うんっ」と元気いっぱい答えた。
「なるほど、あいつが代理店の……」
カウンターでラーメンをすすりながら、優里は有栖川について簡単に説明した。そして最後に、有栖川を弁護する。
「別に嫌なこと言われたり、されたりしたわけじゃないんだ。でも、ああいう大人の人ってなんか恐くて。それに、えと、何ていうか………」
「悲しかったんだろ?」
隆矢はさらりと言って、そして優里に向かって優しく笑いかけた。
「純粋に花を楽しみたくて、花を買うために来てくれてると思っていたのに、実際は違った。花はただの口実に過ぎなかった……」
優里は何度も頷く。隆矢はその頭をよしよしと撫で、
「たった一輪の花に安らぎを見つけて、それを大事に飾ってくれる……お前、本当に嬉しかったんだな」
ああ、やっぱりお兄ちゃんはすごい。口に出さなくても、それどころか自分でもよく把握できていない感情のもやもやを、ちゃんと理解して解きほぐしてくれるのだから。
優里は、心の底に重く淀んでいたものがふぅっと消えてゆくのを感じた。
「優里、もうそんな奴のことは気にするな。お前はこれまで通り、花を愛し、お前のブーケを愛してくれる人のためにがんばればいいんだ。そうだろう?」
「うん、がんばるっ」
「おう。ただし、がんばり過ぎないようにな」
優里はきゅっと唇を噛み締めて頷いた。気を抜いたらきっと、泣き出してしまうと分かっていたから。
「お、そうだそうだ。お前にちゃんと報告しねえと。告白したんだ、あのブーケ渡して」
優里はお腹に力を入れて、ふぅっと息を吐いた。大丈夫、大丈夫。そしてにっこり笑い、
「聞いたよ。うまくいったんだってね。よかったね」
「おうっ。お陰でもう超ラブラブ。いやあ、やっぱすげえな、お前のブーケは」
「そんな……ことないよ」
「いやいや。彼女が言ってたんだけどさ、本当は花とか贈ってくる男って嫌いだったって。女には取り敢えず花贈っときゃいいみたいな考え方が、バカにされてるようでムカつくから。でもあのブーケには、自分の趣味や嗜好への理解が込められているのが分かって感動したって」
隆矢はスープをずるずると飲んでほう、と息をつき、
「彼女、すげえ喜んでた。こんな不思議な、それでいて懐かしい色合いのブーケをもらったのは初めてだって」
「そっか……僕も嬉しいよ。喜んでもらえて」
「来月は彼女の誕生日なんだ。だからまた頼むよ。幸せを呼ぶ魔法のブーケを」
優里はにっこり笑って頷いた。
「うん、任せて。いつでも言って。お兄ちゃんにはね、絶対幸せになって欲しいから」
「優里………」
隆矢は、自分のどんぶりに浮いている味付け卵を優里の方に入れてやり、
「ほら、食え食え。お前の大好きな味玉だぞ。俺のやるから」
優里はもうお腹が、いや、胸がいっぱいで何も食べたくなかったが、隆矢がくれた卵を丸々そのまま口に入れた。
「おおっ、豪快だなあ。旨いか?」
「ふぅん、ふぉいしぃ」
お兄ちゃんのくれるものなら何でも嬉しいし、何でも美味しいんだよと心の中で呟いて、口の中の卵を必死に呑み込んだ。
「こんにちは。昨日はいきなり誘ってしまってすみませんでした」
「あ、いえ……あの………」
店番は父とバイトの子に任せて、お昼は大塚ベーカリーの店内カフェでコロッケパンを食べようか、それとも多聞庵でデザート付きそばランチセットを食べようか迷いつつ歩いていたら、後ろから呼び止められた。
優里はびくんと震えて立ち止まり、おそるおそる振り向く。すると、相変わらず一分の隙もないビジネススーツ姿の有栖川が、一分の隙もない笑顔で立っていた。
「あの……有栖川さん、あまり商店街を歩かない方がいいと思いますよ。何て言いますか……こういう言い方は嫌ですが、あなたにいい感情を持っていない人が多いので」
有栖川はほんの少し笑顔を曇らせて、
「仕方ありませんね。僕の不徳の致すところです。甘んじて受けましょう。ただ、もしあなたにも同様に悪い感情を持たれているとしたら……かなりショックですが」
「い、いえ……そんな…ことは………」
有栖川の言葉に覆いきれぬ真情のようなものを感じて、優里は戸惑いを隠せない。有栖川はそれを敏感に察したのか、声を引き締めて本心を打ち明ける。
「昨日、あなたに背中を向けられて、本当に悲しかった。もちろん原因はこちらにあるのですが、せめて弁明をさせていただきたいのです。お昼休みはどのくらいですか?」
「あの、特に決まってはいません。今日はバイトさんもいますし……」
有栖川は、恐がらせないよう配慮しているのが手に取るように分かる慎重な歩みでそっと近付いて、そして頭を下げた。
「ランチ、付き合っていただけませんか? あなたにぜひお見せしたいものもあるので」
不思議と昨日のような恐怖が湧き上がることはなく、優里はこっくりと頷いて彼の後に付いていった。
有栖川がプロデュースしたというフレンチレストランはこじんまりした一軒家の佇まいで、店内もフランス料理イコール堅苦しいという既成概念を鮮やかに裏切る寛いだ空気に満たされていた。
明るくて天井が高い開放的な空間。通された窓際の席からは中庭が眺められる。コスモスや萩の花が満開だった。
優里はテーブルの上に飾られた花、白いラナンキュラスとアスパラの葉を目を細めて愛でつつ、
「素敵な一輪挿し………テーブルに飾られているの全部、少しずつ形が違うのですね」
「はい。と言ってもこれは全て、調味料の空き瓶なんですよ」
メニューを運んできた女性は、少し得意そうに種明かしをする。そして有栖川に視線を向け、
「有栖川さん、お忙しいのは分かりますが、もっとお店に足を運んでください。自分が手がけた店は子供みたいなものだと仰ってたじゃありませんか。親失格ですよ」
「ああ、仰る通りですね。申し訳ありません。でも、こんなに地元の皆さんに愛されて、僕の子供は本当に幸せだ」
有栖川の言葉通り、平日だというのに子供連れの家族や年配女性のグループなどで、ほぼ満席状態だった。
女性は「親孝行の子供でしょ?」と微笑んで、「ランチのコースでよろしいですね」と念を押す。有栖川は頷いて、
「すみませんが、ちょっと急いでもらえますか? お昼休み中の彼を無理やり連れてきてしまったので」
「まあ。分かりました。鋭意努力いたします」
有栖川の無理な注文にも嫌な顔せず、女性は悪戯っぽく返して厨房に告げに行った。
「いかがですか? お店の雰囲気は」
「はい、何だかお友だちの家に遊びに来たみたいな感じがします」
優里の返答に有栖川は相好を崩し、
「ありがとう、そう言ってもらえると、僕もあれこれ頭をひねった甲斐があります。まさにそんなお店にしたかったのです。
コンセプト先にありきだと、頭の中のイメージばかりが一人歩きしてしまって、お客さまに伝わらない危険性もあるのです。僕もこれまで、そういう苦い経験を幾度も味わってきました」
「はい、それは僕にも分かります。イメージが余りはっきりし過ぎていると、なかなかうまくいかないものです。特に花は生き物ですから、こちらの思う通りにはならないことが多くて。
……あ、でも有栖川さんのお仕事とはスケールが違いますね」
調子に乗ってえらそうなことを喋ってしまったと、優里は肩をすぼめて恐縮する。有栖川は調味料の瓶に活けられた花にそっと触れて、
「たった一輪の花があるだけで、空間の色彩が変わり、人の気持ちが和む。確かに扱うものの大きさは違いますが、お客さまに少しでも喜んでもらいたいという思いの強さは同じです。僕はそれを、あなたのお店に通うことで再認識しました」
こんなことを言われるとは思ってもいなかった優里は、ぱちぱちと大きく瞬きをして正面にある有栖川の顔を見つめる。
驚きを隠そうともしない無邪気な振る舞いに、有栖川はこぼれる笑みを抑え切れない。しかし、まずきちんと言うべきことが先だと表情を引き締め、
「恐らくあなたは、僕を桜町商店街のスパイと思っているのでしょう。美園花店の人気の秘密を探り、それを盗んでやろうとしたに違いないと」
「そんな、スパイだなんて………」
「いえいえ。そう思われるのも仕方ありません。確かに一番最初に伺った時は、偵察してやろうという気持ちでした。でも二度目、三度目からは違う。本当に花が欲しくて、そしてあなたとお話がしたかった。信じてください」
そう言って、有栖川は携帯を取り出した。そして素早く操作して自分が撮ったらしい写真を映し出し、優里に見せる。不審を覚えつつも覗き込んだ優里は、一転、ぱぁっと顔を輝かせて、
「うわぁ、素敵……」
そこには、有栖川が買っていった一輪の花が、色々な器に活けられているさまが映っていた。
優里のアドバイス通り、カーラーはワインの空き瓶に。スプレーバラは短く切り分けて、籐で編んだ籠の編目に1本ずつ挿して。
「籐の籠の中にガラスの器を入れて、水を張ったのですね。そして編目から挿し込んで……」
「はい、そうです。この方法を思い付いた時は本当に嬉しかった」
有栖川は得意気に胸を張って説明する。優里もつられて楽しくなってきた。次の写真を指さして、
「このチョコレートコスモスを活けた茶色の瓶はなんですか?」
「ああ、これは健康ドリンクの空き瓶ですよ」
優里はくすくす笑いながら頷いて、「素敵なアイデアです」と返した。有栖川は嬉しそうに笑って携帯をしまった。
「花を買うことはもちろん、あなたとお話するのがとても楽しかった。ね、よろしければ名前を教えていただけませんか?」
隠す必要もあるまい。優里は頷いて、
「美園優里です。やさしいさと、と書きます」
「優里さん……ああ、あなたにぴったりだ。では改めて優里さんに提案があります。今度、桜町商店街に僕がプロデュースする花屋がオープンするのですが―――」
有栖川の瞳が、すっと澄み渡ってゆく。二人の間を流れる空気の質感が、明らかに変化した。
「優里さん、そこの店長になる気はありませんか?」
その瞬間、優里は彼の誘いに応じてしまったことを心から後悔した。
BACK TOP NEXT