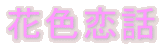
―小さな花屋の物語―
第3話
入荷品のチェックや開店業務もひと段落つき、落ち着いた頃合だった。店先から「すみません」と声がかかる。
優里は柔らかく押し付けがましくない「いらっしゃいませ」を口にしつつ、ぱたぱたと声のする方へ向かった。
そこには、背の高いスーツ姿の男性がひとり。厳しく尊大な印象を与えてしまいがちな切れ長の目を優しく細め、男女問わず見惚れてしまいそうなほど美しい造形の笑みを優里に向けて、「お店はもう開いてますか?」と深みのある声で訊ねてきた。
朝の清涼な空気を通ってちかちか瞬く陽光に目を細めつつ、優里は「はい、開いております」と答える。すると男性は「ああよかった」と言ってにっこりと笑った。
―――わ、いかにもできるビジネスマン、みたいな人でもこんな風に笑うんだ
自分の発見に優里は楽しくなって、男性にも劣らぬほどの無邪気な微笑みを返す。
「あの、その花をいただきたいのですが」
男性の指の先には、淡いピンクのガーベラが。優里は「はい」と頷いて、「何本ですか?」と訊ねた。
「1本でけっこうです」
男性は申し訳なさそうに答え、そして「1本では駄目ですか?」とおそるおそる伺う。優里はぷるぷると首を振って、
「もちろん大丈夫ですよ。ご自宅用ですか?」
「いえ、贈り物です」
優里は頷いて桶から1本抜き取り、店の中のカウンターへ。そこで茎を少し短くして濡らしたティッシュペーパーを切り口に当て、その上からアルミで包む。
そして少し考えてから、真っ白で皺加工が施されているラッピングペーパーを選び、たった1本のガーベラをふんわりと包む。そしてリボンではなく、<天使のひも>と呼ばれるフィルフィーコードで縛った。
「お待たせいたしました。このような感じでいかがでしょうか」
優里が差し出したガーベラを見た男性客はまず驚き、そして嬉しそうに切れ長の目を細めた。
「すごい。まるで………天使のようだ」
彼の喜びが優里にも伝播したのか、心なしかうきうきした声で、
「はいっ。まさにこのひもは<天使のひも>と呼ばれているものなんです」
「初めて見たなあ。リボンや麻紐ならよく使われるけれど」
フィルフィーコードはワイヤー入りでカラーバリエーションの豊富なナイロン製のひもで、約3センチおきにふわふわのモール糸が飛び出ている。それがまるで天使の羽根のように見えるのだ。
これをインターネットで見つけた優里はすぐに注文し、ラッピングに使い始めた。大きな花束には向かないが、今回のように一輪の場合やミニブーケに使うと華やかで愛らしくて、評判も上々だった。
「お気に召したでしょうか?」
「ええ、とても。おいくらでしょうか?」
「200円です」
男性は少し驚いたように瞬きをして、言われた金額を差し出しつつ、
「1本だとラッピングしてくれないところや、その分お金を取るお店もありますよね。ここは無料でやってくれるのですね」
今度は優里が驚く番。ちょっと首を傾げて見上げると、
「はい、もちろんです。大事な花をお嫁に出すのですから、ちゃんとおめかししてあげないと」
「なるほど。この店からお嫁に行く花は幸せですね」
男性の言葉に嬉しさの余り頬を染め、優里は「またお越しくださいませ」と囁くように告げた。男性は受け取った花を大事そうに抱えて「はい、また来ます」と答え、軽く頭を下げて帰っていった。
そしてその翌日。前日同様、開店業務が終わった頃に彼はやって来た。前日と同じ、溜め息の出るような美しい微笑みと共に。そして白いカーラーを指差し、
「これを1本ください」
優里は頷いて1本抜き取り、「贈り物ですか?」と訊く。
「いいえ。これは僕の部屋に飾ろうと思いまして。恥ずかしい話ですが、僕はこれまで花というものの良さがよく分からなかった。なんで女性はあんなに花が好きで、嬉々として飾るのだろう、と。でも昨日、こちらで花を買って、少しだけ分かったような気がするのです」
優里はぱあっと笑顔を咲かせて、男性の言葉に聞き入った。
「あなたが綺麗にラッピングしてくれたあの花を持っているだけで、心が華やぐような、豊かな気持ちになれました。だから今度は、自分のために買って飾ってみようと思ったのです。でも……」
「どうされたのですか…?」
眉間に微かな皺を寄せて俯く男性の顔を、心配そうに下から覗き込む優里。
「花を飾ったことなどないもので、家に花瓶もないし。どうやって飾ったらよいものか……」
優里はぱちぱちと瞬きをしてからにこっと笑い、
「花瓶なんて改めて買う必要ありません。ワインの空き瓶で十分です」
「ああそうか…。あれなら深さもちょうどいい」
「でしょう? カーラーがきっとよく映えますよ。それに、もっと小さな花だったら例えばコーヒーカップとか、ピッチャーとか食器を使ってもいいですし、ジョウロに挿しても素敵だと思います」
男性は真剣に耳を傾けて何度も頷き、優里に渡されたカーラーの花を大事そうに持って帰っていった。
そしてその後も、彼はたびたび訪れた。買っていく花は相変わらず1本だったけれど、そのたびに優里にアレンジ法を聞き、感心したように頷いては嬉しそうに花を抱えて帰ってゆく。優里もいつしか、“一輪さん”の来訪を心待ちにするようになった。
ある時、彼は不思議そうに店頭のミニブーケを眺めていた。確かにそれはちょっと変わったブーケだった。茎の長さが異常に短いのだ。これでは花瓶に活けるのも無理だろう。優里はくすりと笑って、
「そのブーケは、店に搬送する途中や水揚げしている最中に落ちてしまった花を集めて作ったものです。だから茎が短いの」
「なるほど。確かに捨ててしまうのは忍びないですね。こんなに綺麗に咲くのだから」
「はい。こうしてまとめて括って、少し深めのお皿やボウルに水を張って浮かべます。枯れ始めたら紐を解いてばらばらにして、まだ綺麗な花は水を張ったガラスの器に散らすんです」
男性は「あ、」と声を上げて、
「そういえば、家に使っていない金魚鉢があったな」
「うわあ、素敵。底にガラス玉を敷いて花を浮かべたら、涼しげなインテリアにもなりますね」
こんな話をしている間にも、このミニブーケは次々売れてゆく。
「やあ。大したものだなあ。アイデア勝利だね」
しかし優里は得意気になるどころか、申し訳なさそうに肩をすぼめて、
「本当は、落ちた花を掻き集めて作ったものを売るなんて失礼ではないかなと。最初は売るつもりではなく、ただ店頭に飾っていただけなんです。それを見たお客さまから、ぜひこういうブーケも売り物として作ってほしいと言われて……」
男性は「うーん」とうなった挙句、
「その考え方はあなたらしくないですね。落ちた花、折れた花はゴミではないでしょう? こうしてあなたにおめかししてもらい、お客さまのもとへお嫁に行く。素晴らしいことではないですか」
まさかこんな風に言ってもらえると思っていなかった優里は、返す言葉を失ってただ彼を見上げる。すると馴染みのお客さんが陳列棚に近付いて、件のブーケをひとつ手に取り、
「よかった。まだちびブーケ残ってた。これすぐ売れちゃうのよねえ」
優里ははっと我に返って「いらっしゃませ…」と声を掛け、
「ちびブーケ、ですか?」
「そうよお。ミニブーケとも違う、ちびブーケ。可愛いでしょ?」
優里は胸が熱くなった。折れて、捨てられる運命にあった花たちが、こんなに愛されて………
「可愛がっていただいて、本当にありがとうございます」
優里は心からお礼を言って、深々と頭を下げた。
「ね? 僕の言った通りでしょう? ちびブーケ大人気だ」
目元に微かな皺を刻んで、悪戯っぽく笑う。その笑顔を見た優里は、はっと息を呑んだ。ようやく分かった、この人は―――
―――柾矢お兄ちゃんに似てるんだ………
穏やかで口数は少ないけれど、包み込むような優しさでいつも自分と隆矢を見守ってくれた。もう二度と会うことのできない、大事な人――――
「どう…しましたか?」
「い、いえ。何でもないです……なんだか嬉しくてぼーっとしちゃって」
男性は目を細めて優里の頬を手のひらで包み、
「可愛い人だ」
深みのある低音でひとこと囁くと、帰っていった。彼の後ろ姿が見えなくなっても、手の温もりはずっと頬にとどまり続けた。
会場となっている寄合所は、すでに人がいっぱいだった。もちろん見知った顔ばかりだったけれど、いつもの楓会の会合とは明らかに異なる険しく張り詰めた空気。
景気はどうだいと笑いながら肩を叩き合う者もいない。これから始まる話し合いに、誰もが警戒心を抱いているのが分かる。
優里は父の後に付いて会場に入った。今日の話し合いは商店街の未来を決める大事なものだからお前も来い、父にそう言われて来たのだ。会場内を見れば、確かに普段は会合に出席しない若旦那衆の顔も多数見受けられた。しかし、
―――お兄ちゃんは……やっぱり来てないんだ………
沢村酒店の店主で隆矢の父親である徹矢(てつや)は、前方の真ん中に陣取って、難しい顔をして腕を組んでいる。その隣に三代目であるはずの隆矢の姿はなかった。
久しぶりに顔が見れるかもと期待していた優里は、しょぼんと項垂れる。すると「おおーい」と明るく優里の名を呼ぶ声が。
「優里っ、来てたんだな」
「あ、相ちゃん。わあ、健ちゃんも」
せんべい屋の三代目相太と、魚屋の三代目健三が、会場の重苦しい空気を払うかのような朗らかな笑顔を浮かべて駆け寄ってくる。
「優里、見たぜ新聞記事。けっこう大きく出てたじゃねえか」
「う、うん。なんか恥ずかしーけど」
「優里の写真も、笑顔はちょっと引きつってたけど可愛く写ってたぜ」
そして二人は、さすが俺たちの優里だと頷き合う。そこへすかさず司が割り込み、
「おいこら。うちの可愛い優坊にちょっかい出すんじゃねえぞ。こいつはハコ入り息子なんだからな」
「ハコに入れてんのは父っつぁんだろ。たまには若者同士で話させてくれよ」
若者から弾き出された司はぶつぶつ言いつつも、飲み仲間でもある徹矢のもとへ。一人ぽつんと座っていた徹矢は、嬉しそうに相好を崩して隣の椅子を勧めた。
「………隆矢のヤツは来てねえのか。こんな大事な時に」
相太は怒りを隠そうともせず、低い声で言い置く。優里は慌てて、
「きっと、大学が忙しいんじゃないかな。就職のこともあるし……」
しかし健三は肩を竦めて、
「いんや、きっと女のとこだぜ。合コンで知り合った女とうまくいきそうだって言ってたし――――痛ッ」
相太に脛を蹴られて、ようやく失言に気付く。目の前の優里は震える声で「そっかぁ、うまくいったんだ……」と呟いて、儚げに笑った。
相太に余計なこと言いやがってという目で睨まれた健三は、掠れた声で「すまん…」と謝った。
「それじゃ、僕もそろそろ席に着くね。相ちゃん、この前のかぶき揚げすごくおいしかったよ。ありがと」
優里は淋しそうな笑顔を保ったまま、二人に手を振って司の方へ駆けていった。残された二人ははあ、と複雑な溜め息をつき、
「なんか優里のやつ、だんだん綺麗になっていくのは一体どういう道理なんだ」
「そりゃあ、お前。恋をしてるからだろ」
「恋をしたら綺麗になるのは女だけで、男はマヌケになるだけだと思ってたけどなあ」
そうして再び同時に溜め息をつき、
「隆矢の野郎………いい加減に気付いてやれよな…………」
同じ言葉を呟いた。
「えー、あと5分ほどで代理店の担当者が来るそうなんで、それまでこの概要にひと通り目を通しておいてください」
楓会の現会長、寿司屋の亮さんの言葉に従って、みな席に着き始めた。用意された資料の表紙には、『楓町商店街の皆様へ ― 駅前の発展と新しい町づくりに向けて』と仰々しい書体で書かれていた。そして下方には、<野々村エージェンシー 担当 有栖川・五十嵐>とある。
中をぱらぱらとめくると、商店街の現状、問題点、メリット、デメリットなどがもっともらしく箇条書きになっており、桜町商店街で現在進行中のプロジェクトについて説明がなされていた。優里は“これが悪魔の正体かあ”と心の中で呟く。
「なんだよこの分かりにくい文章は。カタカナ使えば俺らがビビるとでも思ってんのかっ」
司が咆えると、それに同調するようにみんなうんうん頷いた。さっと一読したところでは、桜町商店街の再生計画は急ピッチで進められており、すでに新装開店した店も。これまでにない専門店と娯楽施設の融合が実現するのも間近だということだった。
「ねえ、お父さん……桜町の人たちは、本当に全員一致でこの計画に賛成したのかな」
「んなわけねえだろ。阿呆な若い連中が、これからはコンセプトとトータルプロデュースの時代だとか何とか黄色いクチバシで喚きたてて、これに乗っからなかったら店は継がねえとか脅したに違えねえ。それに―――」
会場の空気がざわ、と波打った。司は思わず口を閉じる。つられて優里も顔を上げた。
「楓町商店街の皆さん、初めまして。今日はわざわざお集まりいただいて恐縮です。私は野々村エージェンシーの有栖川(ありすがわ)と申します。桜町商店街再生計画のチーフプロデューサーを務めさせて頂き―――」
優里は驚きの余り、一瞬耳が遠くなった。彼の声が、聞き慣れた声が二重三重になって頭の中で反響する。
「一輪さん………」
有栖川と名乗った男は、何度も優里のもとに足を運んでは一輪の花を買い、大事そうに抱えて帰っていった、あの男性客だったのだ。
BACK TOP NEXT