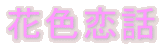
―小さな花屋の物語―
第2話
「なんだ? 隆矢のヤツはまた新しい女か」
「うん、そうみたい……」
優里は力ない声で答えながらも、何とか笑顔を拵えて「うまくいくといいね」と加える。司はがっちりした肩を気障な仕草で竦めてみせて、
「そりゃ、告白自体はうまくいくだろう。お前のブーケがあるんだからな。でもどうせ、すぐに振られるさ。いつもみたいに」
「そんな……ことは…………」
優里の弱々しい反論は、最後まで口から出ることなく立ち消えてしまう。実際、父の言う通りだったから。
商店街の三代目衆の中でも飛び抜けて男前の隆矢。すらりと優雅な長身、整い過ぎた顔立ちに浮かぶ人懐こい笑顔、誰とでもすぐに打ち解ける快活な性格―――女性にモテるあらゆる要素が備わっているにもかかわらず、何故か隆矢の恋はいつも呆気なく散ってしまうのだ。
優里のブーケの魔力が効いているからなのか、告白すれば必ず受け入れられる。しかし有頂天になって付き合い始めたのも束の間、他に好きな人ができたとか仕事や勉強に専念したいからなどという理由で、一方的に別れを告げられてしまうのだ。
そのたびに優里は、またきっといい人が見つかるよと口では慰めつつも心の中では喜んで、そんな自分への嫌悪と罪悪感に苛まれるのだ。
「あいつもいつまでフラフラしている気なんだか。大学3年にもなって、家業について何も学ぼうとしねえで合コンだバイトだと。まったく、沢村さんとこも気の毒でしょうがねえや」
「そんなことないっ。お兄ちゃんはいつだって一生懸命なんだよ。一生懸命自分のやりたいことを探して―――」
必死に擁護する優里に言い聞かせるように、司は声を低めて、
「そりゃあな、柾矢(まさや)がああなっちまって戸惑うのも分かる。家業を継ぐなんて考えてもいなかったんだろう。
けどなあ優里。やっぱり人生では、やらなきゃならねえことを優先させるべきなんだよ。自分のやりたい仕事を選んで、進みたい道を歩む。それは幸せなことには違いねえが、みんながみんなそうやって自分を主張し始めたらどうなる?」
優里は何も言い返せない。父の言うこともよく分かる。隆矢が継がなければ、実家の沢村酒店は現在の二代目で潰れてしまうことになるのだ。
「人様の境遇と比べたらキリがねえ。与えられた領分の中で努力し、幸せを見つけるのが真っ当な人間の生き方じゃねえかな」
「うん……」
父の言葉を噛み締めて、優里はこくんと頷いた。たったひとつだけはっきり言えること、それは―――
「やらなきゃならないこととやりたいことが一致している僕は、本当に幸せ者だね」
司は日に焼けた精悍な顔をほんの少し緩めて、優里の頭をぐりぐり撫でる。そのまま目を細めてふっと息を吐き、
「柾矢が逝っちまってからもう2年か………」
普段はめったに見せぬ淋しげな表情で、感傷的な言葉をぽつりと口にした。
―――お兄ちゃん、うまくいったかなあ……
窓を開けて求愛する虫たちの大合唱に身を浸しつつ、秋特有の冴えた夜空を見上げる。
夜空こそが、“空”の本来の姿なんだと言って譲らなかったのは、隆矢お兄ちゃんだったろうか、それとも柾矢お兄ちゃんだったろうか。
昼間は、まるで青空に蓋をされているようで息苦しくてキライだ―――こんな子供みたいなことを言うのは隆矢のようにも思えるし、悠久のロマンを感じさせる星空を好む感性は、柾矢にこそ相応しいようにも思える。
いずれにせよ、柾矢は空の星になって久しく、隆矢は今きっと、この空の下のどこかで恋人と抱き合っているに違いない。優里が拵えたブーケを傍に置いて。
―――どんな顔で、どんな言葉を添えて渡したのだろう
考えれば悲しくなるだけなのに、つい思い描いてしまう。きっと照れ臭そうに微笑んで、隆矢らしいストレートな言葉と共に手渡したのだろう。優里が作った花束に対する絶対の信頼感に支えられて。
もしこの恋が壊れてしまっても、隆矢はまた新たな恋を見つけるに違いない。そして優里の許を訪れて、ブーケを頼み、玉ちゃんラーメン奢ってやるぞと笑う。
優里はそのたびに、隆矢が好きになった女性の好みに合わせたブーケを作り、お兄ちゃんがんばってねと嘘をつき、そして決して届かない「だいすき」を捧げる。ずっと、ずっと―――
―――きっと一生、諦められないんだろうなあ……
誰にも打ち明けることなく、誰に知られることもなく、自分の胸の中で秘めやかに芽吹き、花開いたこの想い。実りが訪れることはなく、いずれは萎れて朽ちてゆくだけなのだろう。
悲しくないと言えば嘘になるけれど、それでも仕方ない。今さら告白したところで隆矢を困らせるだけだし、下手をすれば疎まれてしまうかもしれない。あの優しい笑顔を失ってしまうのは、この世界から花が消えてしまうことと同じくらい辛いことだ。
それに、隆矢からは色々な思い出を、幸せをもらった。感謝してもしきれないほど。これまで何度救われただろうか。
幼い頃の思い出を数え上げたらきりがない。隆矢の兄である柾矢も優里のことを大事にしてくれたけれど、年が離れていたこともあって、いつも身近にいて守ってくれたのはやはり隆矢だった。
名前だけでなく外見も女の子みたいで、身体も弱かった優里をいじめっ子から守ってくれた。友達と野球やサッカーがしたかっただろうに、優里の植物採集に根気よく付き合い、二人で図鑑と照らし合わせて名前の覚えっこをした。
優里が忘れ物をした時には、休み時間に全速力で家に取りに行ってくれたし、苦手なマラソン大会では、ずっと傍について一緒に走りながら励ましてくれた。
優里の母親が病気で入院した時には、線路脇の原っぱで花を摘み、二人で病室に届けに行った。母はそのまま帰らぬ人となり、父は店で忙しくて一緒にいる時間が短かったけれど、淋しさを余り感じずに済んだのは全て隆矢お兄ちゃんのお陰だったのだ。
柾矢が突然の事故で死んでしまってからは、確かに隆矢は少し変わった。親に反発心を見せ始め、家業を嫌い、次々と女性に手を出すようになった。
優里に対しても以前のようにあれこれ世話を焼こうとはせず、自分から距離をおくようになった。
しかし根底にある優しさ、温かさは変わることなく、人間関係のストレスや環境の変化にすぐ負けそうになる優里を時には励まし、時には労わって正しい道へ導いてくれたのだ。
優里が今、自分らしいスタイルで楽しく働くことができているのは、実は隆矢のお陰でもあった。高校を卒業後、優里は自分から志願してフラワースクールに通い始めた。いずれは実家の花屋を継ぐことになるのだから、その前に色々勉強しておこうと考えたのだ。
しかし入学早々、自分が誤った選択をしたことを思い知らされた。スクールには、“生き物の臭い”が全くなかったのだ。花に関する知識は分かりやすくテキストにまとめられ、実践では先生が選んだ花材を、毎回テーマに沿ってアレンジする。
奇抜なデザインで作り上げた生徒が“創造的”といって褒めそやされ、なるべく自然のままの姿を残そうとする優里は“創造性に欠ける”と見做された。
もちろん、花を切って束にすること自体反自然的な行為なのだから、なるべく自然の姿を残そうとするのは自己矛盾に過ぎないのかもしれない。しかしだからこそ、優里は自然の花々に対する敬意を失いたくないと常々思っていたのだ。
花に色インクを吸わせて色を変え、茎にワイヤーを通して好きな形に曲げるという行為には、自然を思いのままに操れるとう人間の驕りが感じられてならなかった。
それでも優里は何とかがんばって授業に付いていった。本当は疾うに限界だったのだが、入学金を出してくれた父に対して不満をこぼすこともできず、ひたすら耐えていた。
もともと精神的な不調が身体に出やすく、食欲も落ちて、学校に通い出してからあっという間に4キロも体重が落ちた。
そんな時、久しぶりに会った隆矢は、黙って優里を例の玉ちゃんラーメンに誘った。汗をかきながらはふはふとラーメンをすすりつつ、お互いの近況報告をする。
そして隆矢に「フラワースクールは楽しいか?」と訊かれた瞬間、何かが優里の中で弾けてしまった。箸をぎゅっと握ったままわんわん泣き出し、顔なじみの主人に「それじゃ塩ラーメンになっちまうよ」とからかわれる始末。
隆矢は驚きも宥めせず、ただ優しい眼差しで見守りつつ、泣きじゃくる優里の頭を撫で続けた。
ようやく落ち着いた優里から全てを聞き出した隆矢は、「お前は間違っていない」と言ってぎゅっと抱き締めた。その言葉に勇気を得た優里は父に全てを話し、スクールを辞めさせて欲しいと頭を下げた。
黙って耳を傾けていた司は悔しそうに頭をがりがりと掻き、「何でもっと早く言わなかったんだ」と不貞腐れた。「隆矢に一本取られた。俺が先に気付いてやるべきだったのに」と。
そうして優里はすぐに退学し、美園花店で働くことになったのだ。それからの彼の活躍については、今さら説明するまでもないだろう。
「………お兄ちゃんの恋が、うまくいきますように」
ちかちか瞬く星に向かって、優里は祈りを捧げた。偽善者という痛い言葉が脳裡に浮かび上がってきたが、それでも優里は祈ることをやめなかった。
大好きな人に幸せになってもらいたいという願いに、嘘はないと信じていたから。
「おう、今帰ったぞ」
「あ、お帰りなさいー」
優里は玄関まで司を迎えに出て、「お風呂沸いてるよ」とにっこり笑う。司は心なしか疲れた様子で笑顔を返し、
「優坊はちゃんとめし食ったか?」
「はいはい。食べました。それより今日はどんな話だったの?」
楓町商店街互助組合連合会、略して楓会のメンバーは、月に1回寄合所に集まって商店街の発展や防犯対策、その他の様々な案件について協議する。とはいえ、本当の目的はその後の打ち上げにあるのだが。
さらに今日のように、重要な議題が上がった時には緊急の召集がかかることもある。とはいえ、乾物屋のみよし婆さんが転んで腰を打ったとか、寿司屋の三代目が婚約者に逃げられたとか、そんな話で呼び出されることがほとんどだったのだが。
しかし、今回ばかりは違った。司は太い眉を寄せて苦々しいと言わんばかりの表情で、
「桜町のへなちょこめ、悪魔に魂を売ったらしい」
「あ、悪魔?」
「ああ。商店街再生計画とかいう悪魔だ。広告代理店の口車にまんまと乗せられた。商店街を整備し、ゲームセンターやパチンコ店、カラオケなんかが入ったビルを中心に据えて、買い物と遊びを同時に楽しめる一大歓楽街を作り上げるそうだ。はッ、大層なご計画で」
優里には、父の苛立ちがよく分かった。
「そんなことをしたら……桜町の商店街じゃなくなっちゃう………」
「まったくだ。計画の華やかさ、目先の利益に囚われやがって」
司は心底腹立たしげに吐き棄てて、優里が運んできたお茶を一気に飲み干す。
「おい優坊、酒だ酒。ビールが冷えてるはずだ」
「だめです。これからお風呂入るんでしょ? ビールはお風呂上がり」
司はチッと舌打ちして「母ちゃんみたいなこと言いやがって」とぶつぶつ言う。
「それにしても、何で桜町の人たちはそんなことを……」
「焦ってるのさ。隣の駅前にどでかいスーパーができただろう? 500台収納できる駐車場付きの。それで奴ら泡食って、もう楓の連中と張り合ってる場合じゃねえって」
駅南口の楓町商店街、北口の桜町商店街は昔から犬猿の仲。言葉を変えればよきライバルということだろうが、ともかく仲が悪かった。
楓町が秋祭りで二段の御輿を担げば、桜町は三段の御輿を造る。歳末セールで桜町がもれなく二百円のお買い物券を配れば、楓町は三百円の券を配るという有様。
たまたま駅で顔を合わせればたちまち小競り合いが始まり、お前んとこの寿司屋は粉わさび使ってるだの、てめえんとこの弁当食ったら下痢が止まらなくなっただの、ほとんど子供の喧嘩レベルの罵り合いに発展する。
優里も昔は、桜町んとこのガキとは仲良くするなっ、と父によく言われたものだった。
今のところ、二つの商店街の売り上げ、実力は拮抗していた。しかしたった一つ、例外がある。それは言うまでもない、花屋の売り上げ。
優里が店を手伝うようになってからは、桜町の花屋は閑古鳥。桜町の人間ですら、変装してまで優里のブーケを買いに来るのだからたまったものではない。噂によれば、切り花から鉢物に変えて何とか営業を続けているとか。
そのお陰で、司は楓会ではほとんど英雄扱い。初代楓会のご長老たちにまで、手を合わせて拝まれるほどだった。
それはさておき。
優里は納得したように頷き、
「そういえば、すごくおっきなチラシが入ってたなあ。何でも揃ってるんだなあって感心しちゃったけど」
「確かに便利ではあるがな。でも商店街には独自の買い物文化ちゅうもんがある。それを捨てて大型店に対抗しようとしたってな、無理な話だ」
「そうだね。桜町さんには桜町さんの色があったのに。淋しくなるな……」
司は「バカな奴らだ」と吐き棄てて、よっこらしょと立ち上がった。が、ぐらりとよろめいて傍らの柱に手を付く。
「お父さんっ? 大丈夫―――」
司は手をひらひらと振って“大丈夫”をアピールする。しかしまだ足下が覚束ないようだ。優里は駆け寄って手を貸そうとしたが、
「気にすんなって。ただの軽い眩暈だよ。風呂入ってくるからな」
そう言ってふらふらと風呂場へ向かった。
BACK TOP NEXT