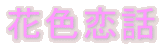
―小さな花屋の物語―
第1話
駅南口から歩いて3分。昔ながらの人情味溢れる商店街、楓町(かえでまち)商店街に、ちょっと変わった花屋さんがあります。
店舗と呼ぶには余りに小さく、ささやかなスペース。しかし道行く買い物客が見落とすことはありません。小さなスペースを埋め尽くす花たちが贈る季節の彩り、甘くふくよかな芳香に、心を奪われない人がいるはずもないからです。
そしてもうひとつ、この花屋の若き店主。小さな花の王国の主は、潤みがちな大きな瞳、絹糸のようにすべらかな黒髪、すぐにぽっと色づく柔らかそうな頬など、その全てが無造作に触れたら壊れてしまいそうなほど華奢な造形で、花たちが見ている夢の結晶ではないかと錯覚しそうなほど現実離れした愛らしさに溢れておりました。
そしてどんなに忙しい時でも、花も色褪せるほどの美しく優しい微笑みで客をもてなし、たったひとつのブーケをその繊細な指先で愛情込めて作る。
一度彼のブーケを買った人は、他の店で売られているどんな高価な花束にも満足できなくなり、再びここを訪れることになるのです。
これからご披露するのは、彼、美園優里(みその・ゆうり)がここにささやかなフラワーショップを開くまでのお話。
それは今から三カ月ほど前に遡ります。その頃はまだ彼も、同じ商店街に実家が開いている花屋『美園花店』で充実した、けれど少し切ない毎日を送っていたのでした――――
「いらっしゃいませ…………あ、こんにちはぁ」
条件反射的に口にしたマニュアル言語は、しかしすぐに融けて親しい響きに変わっていった。
優里は嬉しそうに口許を綻ばせて、店に入ってきた女性の傍へ近付いてゆく。女性も同じように嬉しそうに微笑んで、
「私のこと、覚えていてくれたのですか?」
「もちろんです。確か……2週間前でしたっけ?」
女性はぱあっと顔を輝かせ、ぱちんと手を合わせて喜びを表す。
「すごい。感激です。それならお話もしやすいわ。今日はね、お礼を言いに来たんです。あの………」
ここで女性は少し赤くなり、照れ臭そうに笑った。が、くるりと後ろを向いて手招きすると、それに応えて店に入ってきた男性を紹介した。
「あの、例の彼です。お陰でもう一度やり直すことができました」
優里は「うわぁ」と声を上げ、瞳をきらめかせて「良かったですねっ」と祝福した。女性はこくんと頷いて、
「美園さんのブーケのお陰です。本当にありがとうございました」
すると隣に立っていた男性も同意するように頷いて、「ありがとうございました」と頭を下げた。女性は胸に手を置いて「はぁ」と感慨のこもった溜め息をつき、
「噂は本当だったんですねぇ。美園花店の手作りブーケは、幸せを呼ぶ<魔法のブーケ>だ、って」
しみじみ言い置いて恋人の顔を見上げる。優里は慌てて手を振り、
「そんな……僕はただ、自分の思うがままに作らせてもらっただけで……」
しかし今度は男性の方がぐいと身を乗り出し、
「いや、僕ももらった花束が普通の薔薇とか百合とか、いかにもありがちな花束だったら、彼女ともう一度がんばってみようとは思わなかったに違いありません」
熱い口調で断言した。
ことの始まりは2週間前。今、幸せそうに微笑んでいる彼女が、噂を聞いたんですと言ってこの美園花店を訪れたのだ。
彼女によれば、3年間付き合い結婚まで考えていた彼が地方に転勤になり、遠距離恋愛を続ける自信がないから別れようと切り出された。自分にもプライドがあるし、半ばヤケになっていたこともあり、その時はあっさり「いいわよ」と答えた。
しかし家に帰ってひとりアルバムを紐解き、思い出を反芻しているうちにどうしようもなく悲しくなり、自分が本当は彼と別れたくないと望んでいるということに気付かされた。
そこで以前噂に聞いた美園花店を訪れることにしたのだ。
楓町商店街にある美園花店のブーケは<魔法のブーケ>。これを添えて告白やプロポーズをすれば、必ず成就する―――そんな噂がインターネットの掲示板やブログなどで少しずつ広まっており、それを目にした彼女は半信半疑ながらも救いを求めて訪れたのだった。
恋人は少し恥ずかしそうに鼻の頭を掻いて、
「これで最後だからと、駅まで見送りに来てくれた彼女が持っていた純白のブーケ。それを見た瞬間……恥ずかしい話ですが涙が出そうになりました」
彼女の話を聞いた優里は、白い花だけで純白のブーケを作ったのだ。仄かに甘い香りを漂わせる白い薔薇。小さくてまぁるいポンポン菊。乳白色の粒が愛らしいライスフラワー。そして――――
男性はその時の情景を透かし見るように目を細め、まだ鼻孔の奥に香りが留まっているのか、うっとりとした声で歌うように語る。
「真っ白で、丸くて、仄かに甘かったなぁ。それに―――」
そう、優里はさらに、コットンフラワーを混ぜた。白くてふんわりした綿の暖かさを添えたのだ。
これからの未来を二人で作り上げていきたいという彼女の決意。それと共に、苦しい時も彼を包み込んで暖めてあげたいという彼女の優しい想いも、何とか伝えたかったから。
「それに、あの白くてあったかな綿の花。あんな花があるなんて僕は知りませんでした。でも、あの花束を贈ってくれた彼女の気持ちは痛いほどよく解ったのです。だから、離れた場所でもう一度がんばってみることにしました」
優里は首をちょっと傾げてにこっと笑い、
「あなたはきっと、彼女の気持ちに疾うに気付いていたのではないでしょうか。あのブーケが教えたというよりも、あなたの中にもともとあった想いを掘り起こしたに過ぎないと僕は思います………なんて、えらそうなこと言っちゃった」
3人は顔を見合わせて微笑みを交わす。名前も知らない、ただの花屋とその客に過ぎないのに、肌で感じ取ることができるほどの親密な空気が生まれた。
「あ、なんかお仕事中なのにごめんなさい。でも、どうしても二人でお礼を言いに来たかったから」
「いいえ、とても嬉しいです。休日なのにわざわざ寄ってくださって」
二人は顔を見合わせて照れ臭そうに笑い、
「これから二人で横浜にでも行こうかなあって。その前に寄らせてもらったんです」
「そうですか。お天気もいいし、きっと気持ちいいでしょうね。楽しんできてくださいね」
「はいっ」
二人同時に唱和して、そして手を繋いで帰っていった。優里はその後ろ姿をじっと見送る。すると、
「まったくなあ、最近の男は情けないっ。もっとどーんと、俺についてこいっ、とか言えねえのかよぉ」
「そういうのは、最近の女性には敬遠されるんだよ、お父さん」
優里は笑いながら、店の中へ戻った。そして水揚げと桶の清掃を手伝おうとする。しかし店主であり父親である司(つかさ)に止められた。
「お前はいいから。こっちは俺がやっておく。ミニブーケ用のペーパー切りでもしててくれよ」
「でも……」
「風が少し冷たくなってきた。また風邪でも引かれちゃたまらんからな。お前さんはこの店の大黒柱なんだから」
司はよほどのことがない限り、力仕事を全て自分でやろうとする。優里は小さい頃から身体が余り丈夫ではなく、疲れるとすぐに気管支の炎症を起したりお腹を壊したりして寝込んでしまうのだ。
「ごめんね、お父さん……」
しかも車酔いしやすいため、花の配達や市場での仕入れに出向くこともできない。もともと花屋の仕事は、華やかで楽しそうという一般の見方とは裏腹に、体力勝負の仕事なのだ。
大好きな花たちに囲まれての仕事は、優里にとって天職には違いなかったが、それは父のサポートがあって初めて成り立つものだった。
「ほらほら、どーした、優坊」
父の大きな手に、頭をわしわしと撫でられる。まるで子供扱いだったけれど、こうされるとほっとするのも事実だった。
父の手から、ユーカリのつんと刺激的な匂いが漂う。そう、父の手には色んな植物の匂いが染み込んでいた。優里もいつか、こんな手になりたいと心から思う。
「お父さん、ありがと………」
でも今は自分のできることをやろう、そう言い聞かせて店頭ディスプレイの直しや、ワックスペーパーの整理に専念する。もちろん合間に接客をこなしつつ。すると通りから優里の名を呼ぶ大きな声が。
「おおーい、優里! がんばってるかぁ」
「あ、相ちゃんだ。長塚のおばあちゃんのとこに配達?」
「おお。これからなんだ。その前に、ほら、お前の好きなかぶき揚げ。できたてだぞぉ」
せんべい店の三代目、相太(そうた)が自転車から下りて優里のもとに駆け寄り、紙袋を手渡す。すると別方向からも優里の名を叫ぶ声が。
「優里ぃ、揚げたてのカレーコロッケだ。親父さんと食えよ」
今度は肉屋の三代目、敦彦(あつひこ)。優里は右手にかぶき揚げ、左手にカレーコロッケをぶら下げてにっこり笑う。
「相ちゃん、敦っちゃん、いつもありがと」
すると二人の大男はその体格に似合わず頬を染め、へにょへにょに顔を緩めてうんうん頷く。
「ああ〜、やっぱ優里の笑顔は万能薬だなあ。さすがわが楓町商店街のマドンナ」
「もお。その呼び方やめてっていつも言ってるでしょっ。男なのにマドンナだなんて……」
「はは。じゃあプリンスだ」
相太も敦彦も大真面目なのだが、からかわれたと思い込んだ優里は顔をほんのり赤らめて二人を怨めしげに見上げる。
「おお、それより優里、聞いたぞ。新聞社の取材を受けたんだって?」
「そうそう、うちの婆さまがはしゃいでた。新聞の取材なんて、20年前に大塚ベーカリーの看板猫が子供を生んだ時以来だ、って」
優里は真っ赤になって手をぶんぶん振り、
「そんな、取材なんて大層なものじゃないよ。記事だってきっと、紙面の隅っこにちっちゃく載る程度だと思うし」
「いやいや、<魔法のブーケ>の噂はけっこう広まってるっていうからな。これで記事が掲載されれば、ますます噂に拍車がかかるだろう」
「さすが、俺たちの優里だ」
二人が我がことのように喜んでくれているのが分かったから、優里もこれ以上否定的なことを言うのはやめた。そして、昏く波立つ本心を隠してできるだけ元気な声を拵え、
「うん、そうだね。商店街のためにもがんばるよ」
「おうっ、がんばれ。俺たちも応援するからな」
そして二人は自分たちの仕事に戻っていった。
「………そうだよね、がんばらないと」
見送った優里は、店先でぽつりと呟く。自分を鼓舞するには余りに弱々しい声で。
取材の時のことを思い出すだけで、今でも胃がきゅぅっと締め付けられる。取材前日から不安と緊張で食事も喉を通らず、どんなことを聞かれるのだろうか、そして何と答えれば相手を満足させられるだろうかと考えすぎて、頭がパンクしてしまった。
結局、店は父とバイトのなずなちゃんに任せて寝込んでしまう始末だった。
もともと優里は人見知りが激しく、初対面の人と世間話をしながらお互いの接点を見つけてゆくという社会的行動が大の苦手だった。
一生懸命話そうとするのだけど、こんな話じゃ相手が詰まらないかもしれないとか、そんなことばかり考えて何も言えなくなり、でも何か話さなきゃと焦って自滅してしまうのだ。
ただ唯一の例外は、店に出て客と応対している時だった。その時だけはすらすらと言葉が出てくる。初対面とは思えないほど自然に、コミュニケーションを楽しむことができるのだ。
取材に訪れた記者は、決して嫌な人物ではなかった。しかし仕事柄なのか生来の性分なのか非常な早口で、質問の内容がうまく聞き取れない。何度か聞き直していたら、「ああ、じゃあ次の質問にいきます」と言われ、申し訳なくて泣きそうになってしまった。
さらに取材後、「これが掲載されればかなりの集客効果があると思いますよ」と言われると、喜ぶどころか不安の黒い影に押し潰されそうになった。
お客が増えるのは嬉しいことではある。でも、そのせいでこの平穏な生活が乱され、騒々しい変化に巻き込まれていくかもしれないという考えは、優里にとって脅威そのものだったのだ。でも―――
―――でも、変化が恐いなんて言ってはいられないんだ。がんばらなくちゃ。お母さんの分まで
重苦しい不安は消えてくれなかったけれど、それでも「よしっ」と気合を入れて明日発注する花材について頭を巡らせる。とにかく花のことを考えていれば、嫌なことを意識の表層から払うことができたから。その時、
「優里っ、また頼む!」
切羽詰った声を上げて店内に飛び込んできたのは―――
「あっ、お兄ちゃんっ」
優里はぱあっと笑顔を咲かせ、純粋な喜びに駆られてその胸に飛び付く。が、はっと我に返って慌てて手を離し、
「い、いらっしゃいませ、隆矢(たかや)お兄ちゃん」
しかし隆矢はそんな優里の行動になど構うことなく、両手を合わせてへこへこ頭を下げる。
「優里ぃ、ブーケを頼むよ。予算は…3千円、いや……奮発して5千円!」
優里は軋む胸に手を置いて宥めつつ、何とか笑顔を保って応じる。
「いいよ、3千円で。それで、どんな人なの?」
隆矢は伸びかけの前髪に無造作に手を突っ込んで「うーん」とうなり、
「合コンで知り合ったコなんだけどな、ちょっと変わってて、映画はフランス映画しか観ないとか、美術館巡りとヨーロッパに一人旅に行くのが趣味だとか………」
「なるほど。そういう人には、余り可愛い感じの花束にしない方がいいね。人とはちょっと違う、変わった花材を盛り込んでシックにまとめた方が良さそう」
優里はそう分析しながらも、てきぱきと花を選んでゆく。
メインはスプレーバラ。しかし赤やピンクは選ばず、くすんだアンティーク調の色彩が特徴のジプシーキュリオサという種類にした。
それに秋色アジサイとニゲラの実を合わせ、敢えて和風の紙でラッピングし、リボンは使わずラフィアで縛る。まるで古いフランス名画のようなブーケが出来上がった。
「おお、すげえ。こんな花束見たことねえぞ。これならきっと彼女も喜ぶはずだ」
「うん………うまくいくように願ってるね………」
隆矢から受け取った代金をレジに仕舞いながら、優里はふぅっと息を吐く。大丈夫、大丈夫、辛くなんかない。悲しくなんか……ない。
「いつもありがとな、優里」
隆矢はそう言って、昔から変わらぬ“隆矢おにいちゃん”の顔で無邪気に笑う。優里の心をあっという間に不可視の花で埋め尽くす、大好きな大好きな笑顔。
「今度、お前の好きな玉ちゃんラーメン奢ったる。焦がしネギのトッピング付きで」
「うんっ。ありがとぉ。お兄ちゃん、だいすきっ」
「おおっ、出たな。奢ってもらう時限定の“大好き”が」
優里はへへっと笑ってみせる。隆矢は知らない。この“大好き”に込められた優里の本当の想いを。お兄ちゃん奢ってとせがむのは、それが堂々と口に出して「だいすき」と言える唯一の機会を与えてくれるからなのだ。
「それじゃそろそろ行くな。待ち合わせに遅れちまう」
「あ、うん………じゃあ………」
店の外まで送りに出て、小さく手を振る。すると隆矢は「あ、」と小さく声を上げ、
「そういや、お前取材受けたんだって? 相太んとこが大騒ぎしてた」
「うん、そんな大した記事にはならないと思うけど……。少しでも商店街の宣伝になればいいな、って」
「そうか……」
隆矢は黙って優里の頭をふわふわと撫でた。
「お兄ちゃん……」
「確かに宣伝にはなるだろうけど、そういうのがプレッシャーになるからな、お前は」
そして優しく目を細め、
「がんばり過ぎるんじゃないぞ」
がんばらなくちゃと張り詰めていた優里の心を見透かすかのような言葉を残して、商店街を駆けていった。
優里は唇をきゅっと噛み締めて乱暴に目をこすり、とぼとぼと店の中に戻った。
INDEX TOP NEXT